ステビアの育て方

育てる環境について
パラグアイ、ブラジル原産で毎年花を咲かせる多年草で、現在では多くの場所を生息地としています。見た目は何の変哲もない草の一種のようですが、根・茎・葉に強い甘みがありますが、その甘みの成分はステビオサイドという配糖体で、砂糖の300倍の甘みがあると言われています。ステビア農法という言葉があります。
これはステビアに強い抗酸化作用があって、土壌を改良する力を持っていることから、土壌改良に植えられることがあり、そこから土壌改良法のひとつとして知られるようになりました。土壌改良に使われるくらいの頑健でよく育つ植物ですので、基本的に育てるのは簡単です。
ちなみに原産国の南米の栽培地は、その後、日本が栽培のための研究を進めて行く過程において、決して最適地ではないということがわかっています。基本的には、乾燥が苦手であり、水はけが良く、少し湿った状態の土を好みます。土には酸性とアルカリ性があるのですが、中性または弱アルカリ性の土が向いていると言われます。
地植えにする場合は、あらかじめ庭の土を調べて、酸性であった場合は石灰を購入して中和させた方が良いでしょう。石灰を撒くのであれば、事前に土と混ぜ合わせてしばらく置いてから植えつけるようにしましょう。
地植えにする際は地面を掘り、堆肥と腐葉土などを混ぜて苗を植えると良いでしょう。最近ではホームセンターで、培養土など、自分で一から土作りをしなくても、あらかじめ肥料の混ざった土が売られていますので、こうしたものを利用するのも良いでしょう。鉢植えなどはこうした培養土が便利です。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては種子から育てることもできます。発芽適温は22℃前後とされています。適湿な土壌環境を好み、乾燥がやや苦手です。生育期の間は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えまるようにします。湿度が必要とは言え、まだ乾かないうちに水を与えてしまうと土の中が過湿状態になってしまいます。
このような状況が続いてしまうと、根が腐って株がダメになることがありますので気を付けてください。水やりの意味としては、土中の酸素交換の働きもあります。酸素が効率よく交換されるようにするためには、一旦は土が乾燥する必要があります。そのため土が乾くのを待ってから水を与える必要があるというわけです。
また冬場は休眠しているため、水やりそのもの回数を少なくし、乾かし気味にするようにします。肥料については、最初植え付けるときに、あらかじめ遅効性の粒状肥料を土に混ぜ込んでおきます。その後の追肥は、春から秋の間は2~3ヶ月に1度、追加として油かすなどの固形肥料を少量与えるようにします。
基本的には、日当たりの良い場所で育てます。30度を超してしまうと、暑さで弱ってしまいますので、真夏は風通しの良い場所に置いてあげると良いでしょう。半耐寒性植物ですが、霜や寒風に当てなければ0℃くらいまでは耐えることができます。
地植えの場合には、冬場に霜や凍結の心配があれば、株元をワラや腐葉土でおおうなど、対策をするようにしましょう。もし不安な場合は、秋に掘りあげて鉢植えにすると良いでしょう。鉢植えの場合は凍結や霜を避けられる場所に移動させましょう。
増やし方や害虫について
増やし方としては、種まきの他にさし木も可能です。さし木は親と同質の株ができます。挿し木の適期は6月頃で、小さな苗は寒さに弱いため、冬場は霜や寒風の当たらない暖かい場所で管理するようにしてください。挿し木の方法としては、芽先を10センチくらいに切って、その後1時間ほど水に挿して吸水させて、湿らした用土に挿します。
その後、根が出るまでは乾かさないように半日陰の場所で育てるようにします。病害虫はあまり心配する必要はありません。それでも環境や気温の変化で虫が付く事もあるので注意することは大切です。予防としては、苗木を購入して育てる場合には、元気な苗を選ぶようにしましょう。害虫としては茎や葉つぼみにアブラムシが付くことがあります。
アブラムシが発生してしまうと、すぐに増殖し、茎や葉にくっついて栄養を吸い取ってしまいます。そのまま放置してしまうと、弱って枯れてしまいますので、早めに薬剤散布する等して対応するようにしましょう。もともとの予防策として、日当たりが良く、風通しの良い場所に置くことが大切です。風通しが良いと蒸れを防ぎ、風によって害虫や菌を飛ばしてくれます。
そのために時々剪定をしてやったり、葉も茂りすぎないよう摘み取ったりすることも大切です。また鉢植えの場合は、直接地面に置かないようにして、レンガや置石の上等に鉢を乗せて風の通り道を作ってやると良いでしょう。一旦、害虫が付いてしまうとすぐ広がって、他の植物にも伝染してしまうので、事前の予防と早期発見が大切です。
ステビアの歴史
ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産のキク科ステビア属の多年草です。学名はSteviarebaudianaで、別名はアマハステビアとも呼ばれています。高さは50センチから1メートル前後、茎は白い細毛に覆われています。夏から秋にかけて、枝先に白い小花を咲かせます。
見た目は何の変哲もない草の一種のようですが、根・茎・葉部分に強い甘みがあり、主にハーブとして用います。原産地の殆どでは、古くから先住民が甘味料などとして利用していました。16世紀になる頃には、南米パラグアイでは甘味料として使用されていました。ペルーの先住民は避妊に使用していましたが、現在では、その効果は否定されています。
また南米の先住民グアラニー族が単に甘味料として用いているのみならず、医療用として、心臓病や高血圧、尿酸値を低くするなどの目的で使用してきたこともわかっています。現在でも、ハーブの一種として、糖尿病や高血圧の治療、二日酔い、精神的疲労に対する強壮剤として利用されています。また日本にて本格的に栽培されるようになったのは比較的最近のことです。
人工甘味料の安全性の問題で次々と禁止になり、人工甘味料に代わる安全な天然甘味料が求められた事が切っ掛けでした。研究を進めて行く中で、フランスで1931年にステビアについて安全性の試験が行なわれていることが判明し、これが人工甘味料に代わる天然甘味料になると判断され、その結果として1971年には、世界で初めてステビア甘味料の工業化することに成功します。
ステビアの特徴
16世紀からパラグアイでマテ茶の甘味料として使用され、20世紀に入ってから全世界各地で広範囲に使用されるようになりました。現在では、パラグアイ、ブラジル、日本、韓国、タイ、中国で商業生産されています。頭花と呼ばれる小さく白い花が群がって咲きます。葉の特徴としては、やや先の尖った楕円形で、対生で向かい合って生えています。
花の後にできる実は熟しても裂開しない、そう果と呼ばれるタイプのもので、種子は1つで全体が種子のように見えます。ステビアの製法は砂糖の製法と殆ど同じ工程となっています。乾燥葉を水につけて甘味を抽出し、その後活性炭などで脱色されて純度の高い甘味成分に精製されます。一般的には「血糖値が低下する」「血圧が降下する」「利尿作用がある」「強壮作用がある」といわれています。
日本では甘味料の添加物としての使用が認められています。消化器系研究に関して、最高権威である米国消化器病学会週間において、C型肝炎ウイルスの抑制効果について発表されています。それによるとエキス濃度が高いほどC型肝炎ウイルスを抑制しており、さらにエキス常用患者において副作用はほとんどみられないということがわかっています。
同発表においては、さらに安全で効果的なウイルス薬になる可能性があるということも示唆されています。他にも、ステビアは様々な研究機関でその効果が研究されており、糖尿病、癌に対しても効果があるといった発表もされており、甘味料だけでなく様々な分野でも注目されています。
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
ゲッケイジュの育て方
英語ではローレル、フランス語ではローリエ、日本語では月桂樹と呼ばれています。クスノキ科の常緑高木植物で地中海沿岸の原産と...
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...
-

-
リビングストンデージーの育て方
リビングストンデージーの特徴として、まずは原産地となるのが南アフリカであり、科・属名はツルナ科・ドロテアンサスに属してい...
-

-
ヘリコニアの育て方
ヘリコニアは単子葉植物のショウガ目に属する植物です。大きく芭蕉のような葉っぱから以前はバショウ科に属させていましたが、現...
-

-
ミニカボチャの育て方
ミニカボチャをはじめとするカボチャの原産地は、インド地方やナイル川の沿岸地域、南米大陸北部のペルー、アンゴラなど様々な学...
-

-
フィロデンドロン・セロウム(Philodendoron bi...
フィロデンドロンとはギリシャ語で「木を好む」という意味を持つ言葉です。セロウムはサトイモ科に属するフィロデンドロン属の仲...
-

-
ティアレ・タヒチの育て方
ティアレ・タヒチのティアレとはタヒチ語で花という意味があります。つまりティアレ・タヒチはそのままタヒチの花という意味の名...
-

-
イワカガミダマシの育て方
イワカガミダマシはソルダネラ・アルピナの和名ですが、漢字では岩鏡騙しといい、ヨーロッパのアルプス山脈やピレネー山脈、アペ...
-

-
アーティチョークの育て方
アーティチョークの原産地や生息地は地中海沿岸部や北アフリカで、古代から栽培されているキク科のハーブです。紀元前から高級な...




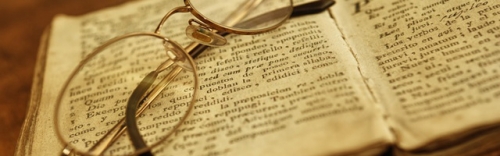





ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産のキク科ステビア属の多年草です。学名はSteviarebaudianaで、別名はアマハステビアとも呼ばれています。高さは50センチから1メートル前後、茎は白い細毛に覆われています。夏から秋にかけて、枝先に白い小花を咲かせます。