チョロギの育て方

育てる環境について
日当たりの良い場所を好む植物です。しかし、半日陰でも育てる事は可能です。暑さや寒さにも非常に強い植物です。プランターで栽培する場合は、深さ30cmくらいの容器を使用し、鉢植えで育てる場合は直径20cmの鉢で1株が育てるのが良いでしょう。特に土壌の質は選ばない植物です。ただし、出来るだけ排水のよい場所で育てた方が良いでしょう。
連作障害も特にはありませんが、しそと連作するのだけは避けるようにしましょう。丈夫な植物なので、それほど水をあげる必要がありませんが出来れば土を乾燥させないようにしましょう。水も少なめ~普通量で問題なく育っていました。地植えの場合は、植え付ける場所も半日向ぐらいでも育てる事が出来ます。
植え付け後、特に手入れをしなくてもよく育つというのが魅力的です。またチョロギは花も楽しむ事が出来る植物です。プランターでも栽培することが出来ます。根が浅い植物なので乾燥と雑草には弱い植物です。その為、夏場には少し注意する必要があります。10月下句から12月頃、茎や葉が枯れてきたら収穫することが出来ます。
育てる環境はそれほど気にしなくても丈夫に育てる事が出来る植物です。その為大変育てやすく、また繁殖しやすい植物なので増やす場合も比較的容易です。ただし、土の乾燥だけ若干気をつけるようにすればしっかり育てる事が出来るでしょう。お庭でも育てる事が出来る植物なので、是非楽しみながら育ててみましょう。
種付けや水やり、肥料について
植える場合は春に行います。塊茎部分を横に寝かせて植え付けをしていきましょう。株間は20cmくらい必要ですが、塊茎が縦横無尽にあちらこちらに伸びて脇芽が出てくるので出来れば広めの方が良いでしょう。庭に植える場合は、深めの板などで仕切りを作っておいた方が良いかもしれません。塊茎の植え付けしたら芽が出るまでに2週間くらいかかります。
チョロギの草丈が10cmくらいになった時点で肥料をあげると良いでしょう。塊茎は地面の下3cmから6cmくらいの場所に出来るので軽く土寄背した方が良いでしょう。茎葉が枯れてきたら、株を堀りあげて収穫します。ランナーが長い植物なので、株から離れたところにでも塊茎が出来ます。
堀り残しが出てしまうと、翌年、発芽してしまい雑草化してしまうので注意しましょう。肥料はそれほど必要としない植物ですがあげる場合は有機質肥料をあげると良いでしょう。野菜球根種はホームセンターなどで春先入手することが出来ます。それを植えつけて成長させていきましょう。土が乾燥したら、水やりを行ないます。
それほど肥料や水やりについて神経質にならなくても良い丈夫な植物なので安心して育てる事が出来るでしょう。また、肥料をあげなくても問題はありませんが、あげれば良く成長してくれます。根が浅い植物なので、年に数回は土寄せを行ってあげると良いでしょう。しっかり育てれば収穫量も多くなり、おいしいチョロギをたくさん頂く事が出来ます。
増やし方や害虫について
増やし方は比較的簡単です。地植えすると、収穫残りの根や塊茎からどんどん発芽します。その為、翌年もしっかり収穫することが出来るでしょう。害虫は特にいません。また病気の心配もない植物なので大変育てやすくなっています。一度植えれば容易に増やす事が出来る植物です。
また収穫したチョロギを植えればまた生えてくるので、是非たくさん収穫しておいしく頂きましょう。お正月くらいしか食卓にあがらないチョロギですが、様々な料理に使用することが出来ますし、クセのない味わいになっているので大変食べやすい植物です。酢漬けが一般的ですが、是非色々な料理に挑戦してみましょう。
可愛らしいくるくるとした形が印象的なチョロギですが、大変育てやすくそれほど手間暇かける必要もない植物です。お勧めは容易に増やす事が出来る地植えですが、プランターなどでも栽培することは可能です。育て方も簡単で、しっかり収穫も出来花も楽しめてしまう植物なので、家庭菜園として人気が高くなっています。
実際植えたいけどどこで売っているのか分からないという人もいるかもしれませんが、春先にホームセンターで販売していたり、またインターネットなどでも購入することが出来ます。是非入手して育ててみましょう。自分が育てたものが成長してしっかり収穫出来ると嬉しいですよね。肥料を与えればより成長が良くなるので、たくさん収穫をしたい人は肥料をあげてしっかり管理していきましょう。
チョロギの歴史
チョロギはシソ科の植物です。中国が原産の植物です、日本には江戸時代に伝わった植物です。その名の由来は、朝鮮語の”ミミズ”を”チョロイン”と呼び、その”チョロイン”が語源という説がありますが、詳しくは分かっていません。巻貝のような特殊な姿をしています。また別名”草石蚕(くさいさご)”と呼ばれる事もあり、
見た目が虫に似ているからこう呼ばれているようです。チョロギは地下にできる長さ3cmくらいの巻貝のように見える塊茎を食用にする事が出来ます。味は淡白な味わいで、加熱するとユリネに似たような味があります。最も有名な調理法としては、お正月などのお節料理の中に入っているのを見る事が多いでしょう。
梅酢で赤色に染めて、食されています。その為、チョロギは赤色と思っている人もいるかもしれませんが、あの赤は着色されている為、実際の塊茎の色は白色になります。チョロギは”長老喜”とも書き、縁起ものと言われている為、お節料理やお祝い事の食事の際に使用されています。
フランスではこのチョロギはクリーム煮にして食べられているそうです。色々な食べ方があるんですね。普段はあまり口にする機会はありありませんが、お祝い事などのシーンで1度は見たことがあるものではないでしょうか。特殊な形をしているので、とても印象に残ります。酢漬け以外でも天ぷらや煮物、炒めものなどとして食することが出来るので、是非家庭で栽培しておいしく頂きましょう。
チョロギの特徴
チョロギは秋の初め頃に薄紅紫の唇形の花を咲かせます。日向を生息地とし、塊茎は両端が細く数珠状にくびれており、長さが2cmから3cmくらいの巻貝の様な形をしているのが特徴です。塊茎は、秋に収穫することが出来、塩漬けにしたり色々な方法で食べる事が出来ます。調理法によって色々な料理に変身することが出来ます。
チョロギは比較的丈夫な植物です。それほど肥料をあげなくても成長することが出来ます。水も少なめでも問題なく育てる事が出来ます。また、一本が枯れてしまっても脇芽が伸びてくるので、水さえあげていれば枯れるという事心配ないでしょう。チョロギの葉はシソ化なのでギザギザした葉になっています。
また葉が細かい毛に覆われており、良く見てみるととげとげしています。チョロギの茎は大変も丈夫です。茎にも細かい毛が生えているので、油断して触ってしまうとすると細かい毛が指に刺さってしまう可能性があるので注意しましょう。草丈は30cmから60cmくらいにまで伸びるので、倒れないように支柱などで対策する必要があります。
また、6月から7月にかけて淡紅色から薄紫色の花を咲かせます。非常に強健な植物なので、害虫もあまり寄り付かず、追肥もいらない初心者でも作りやすい植物です。見た目も面白い形なので、料理のアクセントとしても重宝する植物です。生で食べても味がしませんが、色々な料理に使用し味付けをする事でおいしく頂く事が出来る植物です。
-

-
ミヤマオダマキの育て方
ミヤマオダマキはキンポウゲ科のオダマキ属になります。ミヤマオダマキの特徴としては、葉はハート形になっていても、その丸美帯...
-

-
ラディッシュの栽培方法
ラディッシュとは別名二十日大根と呼ばれております。約30日くらいで収穫が可能です。大根と言っても白色ではなく紅色で丸くて...
-

-
ドウダンツツジの育て方
ドウダンツツジは、かわいらしいふっくらとした見た目の花をつける植物で、灯台躑躅、または満天星躑躅と書くのだか、その漢字の...
-

-
バオバブ(Adansonia)の育て方
バオバブは古くから人類の歴史と深く関わり続けている樹木です。人類が2足歩行をする400万年前以前からフルーツや葉を食料と...
-

-
ミズアオイの育て方
かつてはこのように水辺に育っている植物を水菜ということで盛んに食べていたそうで、万葉集の歌では、春日野に、煙立つ見ゆ、娘...
-

-
茎レタスの育て方
紀元前6世紀頃、ペルシャ王の食卓に出されていたと言われている野菜にレタスが有ります。現在では、結球するタイプの玉レタスが...
-

-
トリカブトの仲間の育て方
トリカブトとはキンポウゲ科トリカブト属の植物の総称で、その多くは多年草の植物です。強い毒性があることで知られており、危険...
-

-
デンファレの育て方
日本で洋ランと言えば、コチョウランと同じくらい有名なデンファレですが、この呼び名は実は略称で、正式名はデンドロビウム・フ...
-

-
アイビーの育て方について
観葉植物にも色々な種類が有りますが、その中でもアイビーは非常に丈夫な上に育てやすいので初心者や、観葉植物の育て方が分から...
-

-
コダチアロエの育て方
アロエの種類は約300種類にものぼり、大変種類が多い植物になります。日本で良く見られるアロエは”コダチアロエ”と呼ばれ、...




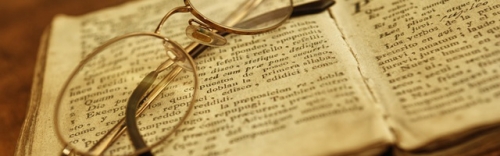





チョロギはシソ科の植物です。中国が原産の植物です、日本には江戸時代に伝わった植物です。その名の由来は、朝鮮語の”ミミズ”を”チョロイン”と呼び、その”チョロイン”が語源という説がありますが、詳しくは分かっていません。巻貝のような特殊な姿をしています。