アカリファ(Acalypha spp.)の育て方

アカリファ(Acalypha spp.)の育て方
アカリファは植え付けや植え替えを4月から10月頃まではいつでもすることができます。土は赤玉土を7、腐葉土を3の割合で混ぜ合わせるなどしたものに水はけを良くしてくれる川砂を1混ぜたものか市販されている草花向けの培養土を使うのが良いでしょう。
植えつける場所は日当たりの良い場所を選びます。日陰では葉の色艶がなくなって枝だけが間伸びしてしまいます。冬は越冬させるには最低でも5度、もし花を咲かせたいということであれば最低でも10度は必要です。春から秋までは屋外で、冬は室内で育てるようにするのがいいです。
ただし寒いだろうからと暖房の風に直接あてるようなことはしてはいけません。枯れてしまう原因になります。また日中は日当たりの良い窓辺に置いてあげてもいいのですが、夜になると冬の窓辺は極端に冷え込んでしまいますから窓辺ではなく、部屋の真ん中のほうに移動させるようにしましょう。
肥料は植えつける時に遅効性のものを混ぜ込んでおき、秋までは追肥として同じ肥料を2か月に一度与えるか液体肥料を10日に1度与えるようにします。水は基本的に土の表面が乾いたらたっぷりと与えるようにします。
しかし冬は生育が鈍りますので水はそれほど必要としませんが、土の表面が乾燥したと感じてから2、3日ほどおいてから与えるようにするとちょうど良い湿り具合になります。冬場は土が乾燥しにくいので、たくさんあげ過ぎてしまうと根腐れや他の害虫などが寄ってくる原因になります。
かかりやすい病気は灰色かび病で、低温期に肥料が多過ぎたり多湿状態になってしまうと発生します。害虫はハダニが発生しやすいので気をつけます。ハダニはその名の通り、葉の裏側にくっついて汁を吸ってしまうので葉が傷んでしまいます。
ハダニは水に弱い性質がありますから、時々葉水を表裏して予防しておくといいでしょう。もし発生した場合は早めに薬剤で退治してしまいます。またアブラムシも発生することが多いので見つけたらすぐに退治します。
アブラムシはすぐにたくさん増えてしまうので、後でいいかと考えてるとやろうと思った時にはすでに枯れてしまっていたということになりかねませんので、薬剤を買いに行く前にも下に落とさないようにしてアブラムシをとってしまっておいてもいいです。
アカリファの栽培時の注意点
アカリファは剪定をしてあげるときれいな形に整えることができます。また寒さには弱いので、寒さのせいで下の葉が落ちてしまうことがあります。そういう時にも剪定をします。行なうのは4月から5月の間で、作業は切り戻しというものです。
伸び過ぎてしまっている枝を全体の高さの3分の1くらいになるくらいまで短く切ってしまいます。そしてその後は株元に化成肥料もしくは観葉植物用の置肥をします。あとはいつものように水やりをし、管理しているとワキ芽が出てきて新しい枝が育っていきます。
また花が終わってしまうと花の色が黒ずんできますので、そういうものは見た目もあまり良くないですからカットしてしまいます。またアカリファを植えてから1年か2年ほどたったら、春に植え替えを行ないます。
鉢から株を出して古い土を落としてから新しい土に植え替えます。その時にもっと大きな株にしたい場合は鉢を一回り大きなものに変えて植えつけるようにします。古い土は全体についているものの3分の1ほどを落とすだけだけで大丈夫です。
種付けして増やせるのか?
アカリファは挿し木で増やすことができます。切り戻した時の枝を利用して、2、3節分ほどの長さにカットし、川砂やパーライトや鹿沼土などに挿しておくことで2か月ほどで発根してきます。発根するまでは強い日差しがあたる場所は避けて管理します。
土は乾かないようにしっかりとチェックしておく必要があります。この方法は成功率も高いですから初心者の方は種まきよりはこの挿し木で増やしていくという方法をするほうがオススメです。種でどうしても育てたいという方は開花後に果実ができますので、
それを採取しておき、封筒などに入れて熟したら中から種を取り出します。開花後に種ができ始める目安は花の色が黒ずんできた時です。温度管理ができる環境であればすぐにまいてもいいのですが、もしそういう環境がないのであれば種は保管しておいて春になってから種まきするようにします。
また株分けで増やすこともできます。根を傷つけないようにして適当な大きさに手で分けてしまいます。あとはきれいな土と鉢に植え替えして管理します。植え替えの時期に行なうようにすると良いです。
アカリファつまりキャッツテールの花言葉はその名の通り、猫のようにという意味があるのでしょう、気ままや愛撫、陽気、上機嫌、とまどいなどがあります。アカリファのふわふわした可愛らしい花穂はプレゼントした時にも喜ばれる植物です。
アカリファ(Acalypha spp.)の歴史
アカリファは別名をキャッツテール、ファイアテール、サマーラブ、シェニールといいます。原産地や生息地はインドで、細かく言いますと西インド諸島のドミニカからハイチの辺りです。常緑性の多年草で、属名のアカリファは古代ギリシャ語のイラクサを意味するアカレフェが由来となっています。
キャッツテールという別名は雄花が密集して穂のようになってフサフサとした猫のしっぽのように見えるから、シェニールは同じく穂が紐にも似ているからそう呼ばれています。種子名のreptansは匍匐性のという意味があります。
日本に渡来したのは明治時代末期のことでした。トウダイクサ科エノキグサ属の植物で、花を楽しむことができるヒスピダ種とカマエディリフォリア種、葉の鑑賞価値が高いウィルクシアナ種の3種類が主に栽培されています。
実は日本国内にも路地などでエノキグサが自生しているのを見ることができますが、通常このエノキグサは観賞用というよりは雑草扱いのため、栽培されるということはありません。同じ属に属しているベニヒモノキとよく似ていることで間違えられることもありますが、アカリファはベニヒモノキよりも花穂が短いです。
アカリファの特徴とは
アカリファは草丈が20cmから2mほどの高さで、6月から8月頃に開花します。約300から400種ほどの仲間が分布しているといわれています。花がきれいなものは鉢花として販売されていますし、葉が美しいものは観葉植物として人気があります。
また沖縄などの亜熱帯地方では庭木として植えられていることもあります。花穂はまるで猫じゃらしのようで、そこからキャットテールという愛称がついたと考えられます。四季咲き性なので適した温度さえあれば1年中花を咲かせてくれます。
コンテナの縁や吊り鉢からたらすようにして育てるのも可愛らしいので見ごたえがあります。花穂は蕾の時点で赤く色づいており、咲き始めると大きさは約5cmから10cmほどになります。雨にあたらないように工夫をすれば開花期間が長い花ですから約1か月間ほどはきれいな花を見ていることができます。
似ているベニヒモノキはアカリファよりもずっと大きく、花穂の長さは50cmほどの大きさになって垂れ下がります。また白くてふさふさとした花穂をつけるアエルバという花もありますが、こちらはヒユ科ですから全く違う植物なのです。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カラテアの育て方
タイトル:アフェランドラ・スクアロサ‘ダニアの育て方
タイトル:キャットテールの育て方
-

-
ノースポールの育て方
ノースポールは別名クリサンセマム・パルドーサムとも呼ばれる花です。北アフリカに自生しているレウカンセマム・パルドーサムを...
-

-
イチイの仲間の育て方
イチイの仲間は日本を含め世界各地に生息地があり、日本も沖縄を除くほぼ全土がイチイの原産地となっています。その発生は「古生...
-

-
リクニス・ビスカリアの育て方
リクニス・ビスカリアの歴史はそれほど解明されていません。実際語源はどこから来ているのかははっきりしていませんが、属名のリ...
-

-
スズランの育て方
春を訪れを知らせる代表的な花です。日本原産のスズランとヨーロッパ原産のドイツスズランがあります。ドイツスズランは、草姿お...
-

-
いちごの育て方
いちごの歴史は古く、すでに石器時代から食べられていました。南米や北米が生息地になり、野生の果実は甘味が少なく大きさも小粒...
-

-
ウラムラサキの育て方
ウラムラサキの歴史に関しては、ミャンマーやタイが原産地となっています。現在でもこれらの地域が生息地となっています。ミャン...
-

-
カロライナジャスミンの育て方
カロライナジャスミンは、北アメリカの南部から、グアテマラが原産の、つるで伸びていく植物です。ジャスミンといえば、ジャスミ...
-

-
ニワゼキショウの育て方
特徴としては、被子植物、単子葉類の植物となります。キジカクシ目、アヤメ科になります。花の季節としては5月から6月とされま...
-

-
ヘレニウム(宿根性)の育て方
この花に関しては、キク科、ヘレニウム属に属する花になります。花の高さとしては50センチから150センチほどになるとされて...
-

-
ホトケノザの育て方
一概にホトケノザと言っても、キク科とシソ科のものがあります。春の七草で良く知られている雑草は、キク科であり、シソ科のもの...




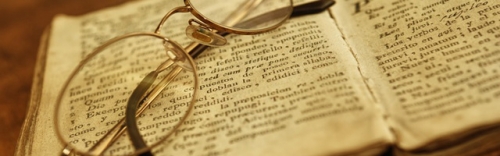





アカリファは別名をキャッツテール、ファイアテール、サマーラブ、シェニールといいます。原産地や生息地はインドで、細かく言いますと西インド諸島のドミニカからハイチの辺りです。