ネリネの育て方

ネリネの育てる環境について
ネリネは水の管理を第一に考えた方がいい花なので、直接地面に植えるよりも、土の状況が把握しやすい、鉢植えに植えることをおすすめします。また、鉢がない場合はプランターなどで育てることも可能ですが、あまり広い場所に植えてしまうと花が咲かない可能性もあるので気を付けましょう。
基本的にひとつの鉢に対してひとつの球根ですが、市販されている寄せ植えなどではひとつの鉢に対して3つほど球根が植えられている場合もあります。花が終わる頃に葉っぱが伸び始めます。もともとアフリカが原産なので、耐寒力があまり強くありません。
冬の間は土が凍らないように注意する必要があります。日当たりのよい窓辺などに置いて凍らないように対策をしてください。冬の間の水やりは土が乾いてからすると根の発達が良くなります。春には屋外に出すようにし、太陽の光を思い切り浴びせるようにしてください。
あたたかくなってきたからといって、長雨の時期など外に出しっぱなしにしてしまうと、今度は根ぐされを起こしてしまうことがあります。5月の半ば頃には球根は大きくなり、この頃には子球もつくようになります。夏場25度を超えるような日が何日か続くようになると、
葉が黄ばみ休眠期に入ります。枯れてしまったかのように見えることもありますが、あわてて処分してしまわないようにしましょう。雨の当たらない涼しい場所に置いて夏を越せるような環境を整えるようにしてください。緑の葉のまま夏を越す種類もあるので同じように涼しい場所に置いてください。
ネリネの種付けや水やり、肥料について
水はけの良い土を使用するようにしましょう。例えば、赤玉土、鹿沼土、軽石を同じ割合で混合したものや一般に言われる山野草用土を使用するのがおすすめです。およそ4年に1度の植え替えの際、多少の元肥を施すことをおすすめします。肥料を与える場合は緩効性肥料を用いるようにしてください。
ただし、鉢の大きさ同様、多肥栽培では栄養成長ばかりしてしまうので、注意しましょう。花が咲かなくなってしまうおそれがあります。基本的にネリネは雨量の少ない地域や土の肥料分が乏しい地域が生息地なので、肥料や水は多く必要ない、ガーデニングの初心者でもわりと育てやすい植物です。
そのため、多湿の日本では水やりによってかえって株を腐らせてしまうこともしばしばありますので、水やりの頻度は多過ぎないように中止ましょう。ネリネは時期によって水やりや管理の方法が大きく異なる植物です。例えば夏場になると、葉っぱが黄ばんできて休眠期に入ります。
冬を越す植物があるように夏を越す植物もあります。これを知っておかないと枯れてしまったのかと思い、水を大量にあげてしまったり、肥料をたくさんあげて元気になるようにと株に負担をかけてしまう人も少なくありません。
また、この時点でもう株は死んでしまったのではないかと勘違いして早急に株を処分してしまったり植えかえしてしまう人もいるので、そのようなことはせずに涼しいところに保管しておいて、水で濡らさないようにする必要があります。
ネリネの増やし方や害虫について
ネリネはあまり病気をしない丈夫で育てやすい花です。植え付けの時に土を加湿にして発根部を腐らせてしまうと株自体がだめになってしまうこともありますが、基本的には大きな病気はあまりありません。土は乾かし気味にすると良いでしょう。
ネリネ自体に虫がつくことはあまりありませんが、近くにアカダニなどの害虫がついた植物がある場合は、ネリネにうつってしまうこともあるので気を付けましょう。霧などを吹いたりして葉を洗うようにすると殺虫剤などを使用せずとも退治ができます。
ネリネに限らず多くの植物にいえることですが、開いたばかりのやわらかい花にはナメクジがつきやすくせっかく開いた花を食べてしまい穴だらけにしてしまうこともあります。そのような害虫は見付け次第その場で駆除をするようにし、花を守る必要があります。
アブラムシやアオムシなども同様に見付け次第駆除、または殺虫剤で退治するようにしましょう。ネリネは球根の植物なので、おすすめの殖やし方はやはり球根が良いと思います。分球は品種によっては割れやすいものや質の良くないものがありますが、球根はクローンなので、完全に同じ個体ができます。
今育てているネリネをたくさん増やしたい場合は、この方法で増やすと良いでしょう。およそ2年から3年で花が咲くようなサイズになります。種からも増やすことができますが、こちらは花が咲くようになるまで長い時間がかかりますので、気長に栽培したい人はこちらの方法で試すと良いと思います。
ネリネの歴史
ネリネという名前の由来はギリシア神話の海の女神であるネレイデスにちなんだものです。花びらに金粉やラメをちりばめたようなきらきらとした光沢から、ダイヤモンドリリーとも呼ばれる可憐な印象を与える花です。南アフリカが原産で、およそ30種ほどの種類がある球根植物です。
大航海時代にプラントハンターと呼ばれる人が南アフリカからイギリスに持ち込んだことで存在が知られるようになりました。17世紀後半にイギリスで品種改良が始まり、ついでオランダにて切り花向きに改良されました。特に歴史上に名高い資産家であるロスチャイルド銀行のオーナー、
ライオネル・ロスチャイルドによってその品種改良が大きく進展していきました。アメリカやニュージーランドなど世界各国で品種改良が進み、日本に入ってきたのは大正時代にあたります。当時はネリネの彼岸花のようなビジュアルが敬遠され、あまり普及することはありませんでした。
日本において彼岸花はあまり縁起の良い花ではなかったのでその影響が大きくあります。日本においてネリネの品種改良が始められたのは、昭和初期頃。広瀬巨海の手によって進められましたが、当時の品種は現在ほとんど失われています。
流通する園芸種の多くはネリネ・サルニエンシスという種類をもとに改良されたものですが、他にもボーデニー種やウンデュラータ種といった種類があり、同じネリネでも耐寒性などの面で育て方が異なるので注意するようにしましょう。
ネリネの特徴
ネリネは一本の茎に対しておよそ10輪ほどの花が咲き、花のサイズはおよそ5から6センチ程度の大きさです。ひとつの球根に対し一本のすらりとした40センチほどの茎が出てきて花を咲かせます。彼岸花に似た花を咲かせますが、彼岸花よりは少し小さな花をつけます。
また、彼岸花の茎が切った時に中が空洞なのに対し、ネリネはそうではありません。似たような花にはリコリスやアマリリスがあります。ネリネの特徴はダイヤモンドリリーという名に恥じないそのきらめいた美しさにあります。ひとつひとつの花のサイズはそこまで大きいわけではありませんが、
豪華な印象を与える花で、存在感のある花です。花の中央から伸びるおしべとめしべがさらに豪華な印象を与えます。植えたままでも美しい花を咲かせますが、大きな特徴はその花持ちの良さにあるのではないでしょうか。1輪目が咲き始めた時に花を切れば、
その後2週間以上楽しむことができます。 もともと乾いた地域が原産なので水がなくてもしおれにくいこともあり、遠距離の運搬も可能な丈夫さを持っています。カラーバリエーションもさまざまで赤、白、ピンクといった定番の色の他、紫やイエローの種類もあります。
カラーバリエーションの豊富さとそのきらきら光る様子からブーケや生け花にはとてもおすすめの花です。見た目からもわかるように彼岸花に似た特徴を持っています。花が咲き始めてから葉っぱが出てきて、冬の間は青々とした葉っぱを楽しむことができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ノコンギクの育て方
-

-
キバナコスモスの育て方
キバナコスモスはメキシコの比較的低い場所に自生する草花で、花が咲いた後は枯れてしまい、種を取ることで毎年開花させることが...
-

-
さつまいもの育て方
さつまいもは原産が中南米、特に南アメリカ大陸やペルーの熱帯地方と言われます。1955年にさつまいもの祖先に該当するイポメ...
-

-
フィロデンドロンの育て方
フィロデンドロンとは、サトイモ科フィロデンドロン属の常緑多年草です。「樹木を愛する」という意味のギリシャ語から名付けられ...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
ハンカチノキの育て方
ハンカチノキはミズキ科ハンカチノキ属の落葉高木です。中国四川省・雲南省付近が原産で、標高1500~2000m位の標高の湿...
-

-
ディフェンバキアの育て方
ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウと...
-

-
ゼブリナの育て方
ゼブリナは、ツユクサ科トラデスカンチア属で学名はTradescantia zebrinaです。別名はシマムラサキツユクサ...
-

-
ワレモコウの育て方
この植物においてはバラ目、バラ科になります。ひと目見たところにはバラにはとても見えそうもありませんが、よく見てみるとたし...
-

-
ヤブヘビイチゴの育て方
分類としては、バラ科キジムシロ属の多年草ということですので、バラの親戚ということになりますが、確かにバラには刺があるとい...
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...




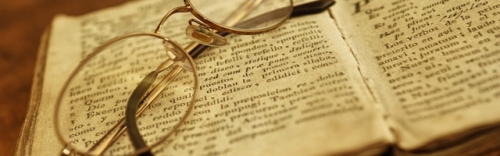





ネリネという名前の由来はギリシア神話の海の女神であるネレイデスにちなんだものです。花びらに金粉やラメをちりばめたようなきらきらとした光沢から、ダイヤモンドリリーとも呼ばれる可憐な印象を与える花です。