ツルニチニチソウの育て方

育てる環境について
育て方・栽培する環境に関して、常緑のツル植物であるツルニチニチソウは寒さに強く非常に頑健です。暑さには若干弱いですが、繁殖力が強く繁茂せずともしぶとく残ります。常緑とされていますが、真冬にあまりに気温が下がると落葉することもあります。
しかし根が生きていれば翌年にはまた芽を出しますので、そのままにしておきましょう。日当りに関しては、非常に強い植物のため、日向はもちろん日陰でも育ちます。日陰でも十分生育する頑健さで、育ちすぎて他の植物を駆逐することもあります。
ツル性で匍匐するために日陰に植えていても、より環境のよい日向の方へと伸びて行きます。花つきをよくするには日当たりが望ましいですが、斑入り品種は半日陰のほうが美しく見えます。またツルニチニチソウは匍匐している茎の節目から根を出しますが生育が旺盛でよく広がるので、
グランドカバーに適します。ただし放置しているとあっという間に広がります。広がりすぎないように引っこ抜くようにしましょう。植える場所をよく考えて、広げたくない場合はツルの切り戻しを定期的に行います。乾燥に強い反面、土壌の過湿を嫌うので、水はけのよい土壌で育てます。
ツルニチニチソウはヒメツルニチニチソウに比べると、やや寒さで葉が傷みやすいので、葉を長く観賞したいときは冬に簡単な防寒をするとよいでしょう。鉢植えの場合、用土は水はけと通気性に富んだ土が適しています。市販の草花用培養土を用いるか、赤玉土小粒5、腐葉土4、砂1などの割合で配合した用土を用いましょう。
種付けや水やり、肥料について
種付けは、基本的に真夏と真冬を除けば植え替え、植え付けはできますが、3月下旬から5月上旬、および9月下旬から10月下旬が適期となっており、30cmほどの間隔で植えつけましょう。株元の節を埋めるように深植えにします。水やりに関しては、鉢植えの場合は土の表面が乾いてからたっぷり与えるようにし、
過湿は避けましょう。土が濡れているのに水を与え続けると、根腐れを起こしてしまいます。夏場は乾燥が早いので毎日水を与えますが、他の季節は土の状態を確認しながら水を与えましょう。深い鉢に植えた場合は、土の表面が乾いていても土に水がしっかり残っていることがあるので、
そういう場合は毎回鉢を持ち上げて重さで水が残っているか判断するように習慣づけをしましょう。庭植えの場合は、一度根がしっかりと張ったあとは、水やりは特に必要ありません。ただし、真夏に日照りが続くようであれば水を与えてあげましょう。
肥料に関しては、植えつけ時に元肥として、緩効性化成肥料を用土に混ぜておきます。また、生育する時期・花が咲く時期である春から初夏に掛けて、液肥や固形肥料をやることでかなり生育がはやくなり、よく茂ります。液肥をやるときは一週間に一回程度を目安にしてください。
ただ頑健で他の植物のテリトリーを邪魔するくらいなので、状況に応じて肥料を調節してください。肥料をやらなかったからといって枯れることはありません。ただし、鉢植えの場合は、肥料切れすることがあるので、花後に緩効性化成肥料や有機質肥料を施します。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては、株分けまたはさし芽で増やすことができます。株分けは、親株を分けて増やす方法と、つるの節から根が出たものを、切り取って増やす方法の2つがあります。つるが土に根を下ろしていたら、そこから切って苗にすることができます。
切ったツルを土に挿しておくと、比較的簡単に根付きます。似た品種のヒメツルニチニチソウは、ほふくする茎の節から根を出して増えるので、その部分を親株から切り離して植えてもよいでしょう。さし芽を行う方法は、たくさん増やしたいときに用いられます。
初夏に生育・伸長が止まって茎(つる)が硬くなったころに、先端を切ってさし芽用土にさしましょう。生育の管理に関して、切り戻しをする必要があります。つるの伸びが速く、広がりすぎるときは、不要な部分の切り戻しや間引きを行いましょう。また、斑入り品種から緑葉の枝が出た場合は、
早めに切り取ります。基本的に、日陰に植えても日向を求めてぐいぐい伸びていき、他の植物を浸食していきますので、成長の仕方を注意して管理するようにしましょう。かかりやすい病気や被害を受けやすい害虫に関してですが、茎葉やツルが密に茂って風通しが悪くなると、
カイガラムシが発生することがあります。害虫の予防のためにも伸びすぎたツルは適宜間引いて整理しましょう。またカイガラムシが発生してしまった場合、すす病も誘発してしまうので早めに薬剤を散布して駆除するようにしましょう。
ツルニチニチソウの歴史
夾竹桃(きょうちくとう)科に属しているツルニチニチソウは、学名を「Vinca major」「Vinca」といい、ツルニチニチソウ属の植物です。ツルギキョウともいい、キキョウ科にツルギキョウという植物があり、キキョウ科のものが標準和名のツルギキョウです。
原産は地中海沿岸とされ、北アメリカ・南アメリカ・オーストラリア・日本に、のちの世に広がりました。紫色のプロペラ状(5弁)の花を、つる状に伸びた茎の先につけます。ちなみに、学名の「major」は「巨大な、より大きい」という意味があり、
「Vinca(ビンカ)」はラテン語で「vincire(結ぶ、巻き付く)」という意味があり、それぞれこれらふたつの言葉を併せたものが由来となっています。Vinca(vincire)は、茎が柔らかく曲がりやすいことから来ています。原産・生息地である地中海を中心としたヨーロッパ内では、
「蔓日日草を身につけていると、悪いものを寄せつけず、繁栄と幸福をもたらしてくれる」という、魔除け・お守りや幸運を呼ぶ役割があるという言い伝えがあります。また、常緑で落葉もあまりせず冬の間も枯れることがないため、不死の力や魔力を持っていると信じられていました。
ツルニチニチソウはその別名として、学名から取って「ビンカ」と呼ばれることもあります。また、よく似た種類に「姫蔓日日草(ひめつるにちにちそう)」があります。開花時期はツルニチニチソウより遅く、春から夏にかけて咲きます。この2つは非常に酷似しており、なかなか見分けがつきません。開花時期は、2月下旬から5月下旬にかけてです。
ツルニチニチソウの特徴
ツルニチニチソウは、ツルニチニチソウ属のつる性の多年草または亜低木に分類されています。ツルニチニチソウ属(学名・ビンカ属)は、日本ではツルニチニチソウとそれより小型のヒメツルニチニチソウの2種がよく知られています。庭園などに植栽されているほか、
まれに野生化もしています。繁殖力が強く、繁茂せずともしぶとく生き残ります。茎が地表を這い、節から根を下ろして広がります。グラウンドカバーやコンテナ、吊り鉢の縁から垂らすなど、長いつるを生かして多種多様に利用されています。
花は春から初夏にかけて、立ち上がる茎の葉腋に青や白色の花を咲かせますが、花よりもむしろ、葉に斑の入る品種がガーデニング素材として親しまれています。花の形はニチニチソウに似ています。柱頭は円盤状をしており、その上に毛のある突起物があります。
このような柱頭の植物は珍しいとされています。茎は最初直立していたものが徐々に横に這い出して伸びます。葉には光沢があり、幅広くきれいな卵型で、大きさは5~8cm程度でちょっと大きめです。緑葉に白や黄色の斑が入る品種があり、斑の入り方にもバラエティがあります。
なお、斑入り品種は花つきがあまりよくないため注意が必要です。耐寒性・耐陰性・耐乾性に優れ、周年観賞することができます。ニチニチソウ同様に繁殖力が非常に強く、観賞用によく栽培されています。ちなみに、ビンカアルカロイドとは異なるアルカロイドを含んでいます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:チシマギキョウの育て方
タイトル:トリカブトの仲間の育て方
タイトル:ディネマ・ポリブルボンの育て方
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
ハシカンボクの育て方
ハシカンボクは日本が原産とされる植物です。漢字で書くと波志干木となりますが、その名前の由来はわかっていません。また別名を...
-

-
長ネギの育て方
昔から和食をメインとしてきた日本にとって、長ネギは馴染みのある食材です。メインディッシュでバクバク食べるというより、添え...
-

-
カリンの育て方
カリンは昔から咳止めの効果があると言われてきており、現在ではのど飴に利用されていたりします。かつてはカリン酒等に利用され...
-

-
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の育て方
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の歴史は古く日本では最も古い文献古事記に桓武天皇が、ユリを摘んでいた若い女性に心を奪...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...
-

-
アスコセントラムの育て方
古来より植物と人間の生活は密接に繋がっている。食料として利用されるだけでなく、住居の材料にもなりますし、現在では観賞用と...
-

-
ミヤコワスレの育て方
ミヤコワスレ日本に広く生息している花ですが、もともとはミヤマヨメナという植物を指しています。日本では広く分布している植物...
-

-
リナムの育て方
この花の特徴としてはアマ科の植物になります。草丈としては50センチから70センチぐらいになることがあります。花の時期とし...
-
雪割草の育て方
さまざまな種類がありますが、その中でも小さくて可愛らしいイメージがあるのが雪割草で、キンポウゲ科ミスミソウ属の多年草の園...




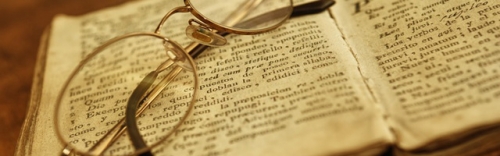





夾竹桃(きょうちくとう)科に属しているツルニチニチソウは、学名を「Vinca major」「Vinca」といい、ツルニチニチソウ属の植物です。ツルギキョウともいい、キキョウ科にツルギキョウという植物があり、キキョウ科のものが標準和名のツルギキョウです。