レンズマメの育て方

育てる環境について
原産地は西アジアから地中海沿岸で、コムギやオオムギ、エンドウなどと同時に栽培化されたと考えらてれいます。現在の生息地はアメリカ、インド、オーストラリア、トルコ、カナダ、中国、ネパール等となっています。古くは『旧約聖書』にも登場しており、レンズ豆の煮物とひき換えに、双子の兄が長子の権利を弟に譲ったという話が残されています。
煮込み料理に適しており、カレーやスープ等の煮物などに用いられることが多い食材です。こうしたことからインド料理、イタリア料理、フランス料理においてはでは定番の食材でもあります。2006年には、アメリカの健康専門月刊誌による調査の結果、世界の5大健康食品の一つとしてインドのレンズ豆が選ばれたほど栄養価は高いです。
またイタリアにおいては、レンズ豆の形が硬貨に似ていることから、お金持ちになれるよう祈願して大晦日の夜に煮物を食べる風習があります。しかし日本の農家においてはほとんど栽培されていません。家庭園芸等で栽培されることが多いようです。地中海沿岸の栽培地からも想像がつくように、空中湿度が少なく、空気がサラっとしているような環境を好みます。
反対に空気が通らないような狭い場所や、熱のこもりやすい場所ではすぐに弱ってしまいます。ガーデンシェルフやフラワーラックなどを使って地上から離して、湿度の溜まらないような場所で育てると良いでしょう。室内で育てている場合、冬でも発芽させることが可能です。耐寒性があります。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては種子からの栽培となります。種は通販等で購入することができます。水につけると1日から2日で発芽します。春まきの場合は3月中旬から6月頃、秋まきの場合は9月中旬から11月が適期となっています。培養土を入れたポットに、深さ約2センチの穴を3箇所か4箇所つくり、各穴に1粒ずつ種を入れていきます。
草丈7から8センチになった頃が定植時期です。レンズ豆は長雨に弱い植物ですので、雨が直接当たる場所では枯れてしまう場合があるため要注意です。雨降りの日は、こまめに雨の当たらない場所に移動するようにしましょう。日頃の水やりでは、土が完全に乾いてから次の水やりをするようにします。水のやりすぎに注意しましょう。
土をいつでも湿らせておくのではなく、乾かすことが大切です。日光は大好きな植物なため、日当たりの良いところで育てたいところですが、高温が苦手であるということも知っておくことが大切です。栽培適温は15から20度となっているので、これ以上温度が高くなる日は、南から西の日差しを遮るか、涼しい場所に避難させるようにしましょう。
5から6月になる頃には青々とした実ができてきます。莢が完全に枯れて乾燥したものから収穫ができます。1つ1つを丁寧にハサミで切り取って収穫するようにしてください。レンズ豆は、ひとつの鞘に2つの豆が入っています。本当に小さいので収穫後の豆を取り出すのが少し大変かもしれません。豆は乾燥させてから利用するのもよいですし、スプラウト栽培に利用するのも良いでしょう。
増やし方や害虫について
レンズ豆はザル等を使って簡単にスプラウト栽培することもできます。レンズ豆は発芽するとフィチン酸が分解され、ミネラルが吸収され易くなるので、食用にすることが目的なのであればこの栽培方法がお勧めです。この場合、土は酸性土壌、粘土質、泥炭でも育てることができます。逆に弱酸性の土、乾燥気味の土は避けるようにします。また肥料の少ない土、水分の多い土では実が付かない場合もあるので注意してください。
育てる際には緑豆もやしの様に芽を長く伸ばさずに、芽が5ミリから1センチ位で収穫します。これ位に成長した時が、発芽によって増える栄養がピークとなります。乾燥豆には無いビタミンCが豊富になって、ビタミンA、E、B群が増加します。他にも澱粉の一部が糖に変わって甘くなり、消化が非常に良くなります。
また発芽させると、短時間の加熱で食べられるので、無水鍋で蒸し煮にすれば、熱に弱い栄養が失われることを最小限に抑えることができます。また成長させ過ぎないことで、豆自体の美味しさもそのまま味わえます。他にも、レンズ豆は陽性な豆なので、発芽させても、それほど陰性に過ぎることはありません。
もし、アルファルファスプラウトの青臭みが好きな方は、生でシャリシャリとした歯ざわりを楽しむことができます。栽培事例が少ないことから、特に注意するべき病害虫については報告されていませんが、風通しを良くしたり、水の適切な管理など、一般的な注意は必要です。
レンズマメの歴史
レンズマメは、マメ科ヒラマメ属の一年草、およびその種子です。和名は、ヒラマメ(扁豆)で、学名はLensculinarisです。このLensは、光学用途で使われる「レンズ」の語源です。レンズの発明は13世紀頃、ロジャー・ベーコン(1234~1292)が文字の上に拡大鏡を置いて、拡大してみたのが最初とされていますが、この時作成された凸レンズがレンズマメの形状に似ていたことから、このように呼ばれるようになりました。
直径4から8ミリ、厚さが2から3ミリと扁平で、光学レンズ(凸レンズ)のような形をしています。この豆の表皮の色は褐色や緑褐色のほか暗緑色、黒褐色等です。皮をむいた状態では黄色、赤橙色等があります。中国での呼び名は「兵豆」、「扁豆」、「浜豆」等で、英名では”lentil”と呼ばれています。
この豆の起源はメソポタミア地域で、徐々に西方に向かって分布域を広げ、エジプト、ギリシャ、ローマへと伝わったと考えられています。レンズマメは新石器時代から栽培されてきたと推測されており、古代から食用として利用されていたと考えられる植物の一つに数えられています。
紀元前には栄養価の高い食品として人々によって活用されてきました。日本では生産は行われていません。一般に流通しているレンズ豆は、主に米国等から輸入されているものとなっています。世界における生産量は300万トン程度で、主な生産国は、印度、トルコ、カナダとなっています。
レンズマメの特徴
地中海地方から西アジアの原産とされていますが、現在では南欧州や北米地域で食用として栽培が行われています。茎は直立しており、高さは25から50センチに成長します。よく分枝し、軟毛に覆われています。小さな豆果の中に、丸くて扁平な形の種子が2個できます。大きさは直径4ミリから9ミリ程度です。
種類は一般的に知られる「グリーンレンズ豆」「ブロンドレンズ豆」「赤レンズ豆」の三種の他、数十種類も存在しています。日本ではあまりなじみがありませんが、世界各地で身近に利用されている食材で、あらかじめ水につけなくても料理できる手軽さに加え、栄養価の高いことから、世界中で人気のある食材でもあります。
レンズ豆の栄養素は非常に豊富で、免疫力を向上させる働きや貧血予防に役立つことでも知られています。主な栄養素としては、免疫力を高める良質タンパク質に富み、ガン細胞の増加を抑える働きがあるレクチン、体内の塩分濃度を適正な状態に調整し、高血圧予防にも役立つカリウム、貧血を予防する鉄分などのミネラル等が含まれています。
他にも疲労回復効果のあるビタミンB群や、整腸作用がある他、便秘を改善したり、不要な物質や有害物質を吸着して体外に排出する働きがある食物繊維も含まれています。また調理上の特徴として、直接煮込めるということがあります。普通大豆などでは丸1日位水に浸さなければなりませんが、レンズマメは水に浸ける時間が短く、下茹も必要ありません。
-

-
カリフォルニア・デージーの育て方
科名はキク科であり、学名はライアであり、別名にライア・エレガンスという名を持つのがカリフォルニア・デージーであり、その名...
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
観葉植物と盆栽の育て方と栽培時の注意点
空前のガーデニングブームにより、観葉植物や盆栽と言った家庭で楽しめる植物が流行しています。簡単な知識と栽培方法を用いて育...
-

-
ニンジンの上手な育て方について
ニンジンは、春まきと夏まきとがあるのですが、夏以降から育てるニンジンは、春に比べると害虫被害が少なく育てやすいので、初心...
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
梅(ハクバイ)の育て方
梅は非常に色が豊富です。濃いピンクがありますがそれ以外には桜のような薄いピンクがあります。白っぽいピンクから真っ白のもの...
-

-
プルンバゴの育て方
プルンバゴは、イソマツ科、ルリマツリ属(プルンバゴ属)となります。また、和名は、ルリマツリなどと呼ばれています。プルンバ...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...
-

-
マサキの育て方
マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicu...
-

-
ディッキアの育て方
まだまだ我々日本人にとって馴染み深いとは言えない植物、ディッキア。数多くの種を保有する植物群のなかでも、かなり特徴的な形...




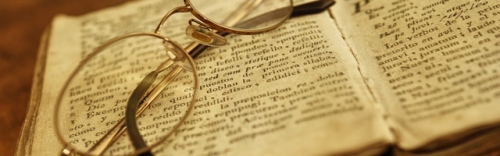





レンズマメは、マメ科ヒラマメ属の一年草、およびその種子です。和名は、ヒラマメ(扁豆)で、学名はLensculinarisです。このLensは、光学用途で使われる「レンズ」の語源です。レンズの発明は13世紀頃、ロジャー・ベーコン(1234~1292)が文字の上に拡大鏡を置いて、拡大してみたのが最初とされていますが、この時作成された凸レンズがレンズマメの形状に似ていたことから、このように呼ばれるようになりました。