ヒデリコの育て方

育てる環境について
ヒデリコは畑の雑草として駆除される植物であり、非常に強靭でもあるので特別な栽培環境は必要ありません。但し、日当たりの良い湿地を好み、田んぼのあぜや湿った草地に生えている雑草ですので、それに準じた環境を与えるのが好ましいと思われます。また、世界中の暖かい地域に生息する植物なので、寒い地方よりは暖かいところの方が育てやすいと言えます。
日本原産であるかどうかは解釈のわかれるところですが、かなり古い時代から日本の気候に馴染んできた植物なので、国内の本州以南であればさほど神経質に育てる必要はありません。園芸種ではないので、栽培方法を詳しく記した資料は見当たりませんが、放置していても良く育つと思われます。
湿地を好む植物であるため水はできるだけ絶やさない方がいいでしょう。日当たりを好むので、できるだけ日の当たる場所に置くことも大切です。水辺で旺盛に生育するヒデリコは、ビオトープには欠かせない植物です。ビオトープで利用する場合は、その特性を考えてできるだけ水に近く日当たりのいい場所に配置するようにしてください。
重金属を多く吸収する特質を有するヒデリコは、水質を浄化するという大切な役割を果たしてくれます。その涼しげな姿で、夏のビオトープを彩ってくれることでしょう。なお、ヒデリコは1年草なので冬越しはできません。花の時期が終わり、秋になると種をつけて枯れていきます。しかし、春になればまた、こぼれた種から新しい芽が出て、再び旺盛に生育していきます。
種付けや水やり、肥料について
本州以南の田んぼのあぜや湿った草地に自然発生的に生える雑草の一種ですので、育て方についてはあまり神経質になる必要はないと思われます。雑草扱いであることから、育て方についての資料は存在しないと考えた方がいいでしょう。自然界においてはこぼれ種から育つ植物ですので、もし種が手元にあるのであれば、3~4月頃に湿った環境に蒔いて薄く土をかけておきます。
鉢で育てる場合は、5~6月頃に元気な株を選んで植え替えを行うといいでしょう。環境次第でかなり大きな株に育つので、大きく育てたいのであれば、株が育つに従って順次大きな鉢に植え替えていってください。肥料は緩効性肥料の置き肥で十分ですが、切らさないようにした方がより大きく育ちますし、花穂もたくさんつきます。
湿った環境を好みますので、水はできるだけ絶やさないようにします。ビオトープに用いる場合も、池の水が枯れてしまったりすることがないよう十分に注意することが大切です。畑の厄介な雑草として、駆除の対象になるほど丈夫で強靭なの植物ですので、水遣り以外は特に気をつけなければいけないようなことはありません。
照りつける夏の日差しの中で、ほっそりとした涼しげな葉を伸ばし、満天の星のように花穂をつけた姿は、ビオトープでにおいても一段と映えることでしょう。また、鉢植えとして育てた場合も、地味な色合いは夏の盛りには却って涼感を引き立て、たくさんの花穂が風にサラサラと揺れる姿は、暑さに疲れた心身を癒してくれることと思われます。
増やし方や害虫について
前述のようにヒデリコは一年草なので、増やすのであれば種を取ります。2.5-3mm程度の小穂にできる果実は、倒卵形で長さ約0.6mmと非常に小さいので、花穂ごと保存しておくといいでしょう。通常は、こぼれ落ちた種から自然に発芽して増えていくので、冬が終わったら花穂から種のみ落として植えつけます。
害虫に関しては、ヒデリコはバッタ類、特にイナゴが好んで食べる植物なので、葉の食害を避けたいのであればイナゴが来ないように気をつけなければいけません。ビオトープの場合はイナゴを呼ぶ植物という解釈ができますが、観賞用に育てる場合はイナゴに食害されると美しい葉が台無しになるので避けたいところです。
但し、イナゴ自体が強い農薬が普及してからそれほど多く発生することはなく、農家でも頭を悩ませるほどではないそうなので、予防に神経質になることはないと思われます。たまに飛来してくるのを見つけ次第処分すれば十分に事足ります。厄介な雑草として位置づけられるほどですから特に病気の発生なども心配する必要はありません。
カラフルな花をつけるわけでもなく、邪魔な雑草として疎まれることの方が多いヒデリコですが、丸い小穂をたくさんちりばめた姿はとても可憐で、見ていて飽きることがありません。野にあって大きな株に育ち密生している姿は
堂々としていながら幻想的で、おとぎ話に出てくるような風情を醸し出しています。雑草だからと排除するのではなく、その美しさに目をとめて向き合ってみると、意外な魅力が見えてくるかもしれません。
ヒデリコの歴史
畑の雑草の一つとして非常にポピュラーな植物であるヒデリコは、アジアの熱帯から温帯にかけて広く分布し、原産地がどこであるかも不明なほどその生息地を広げています。日本での生息地も本州から琉球列島にかけてと幅広く、水田のような日向の湿地に特に多く見られます。
日本に古くから自生している植物ですが、農耕文化が国外からもたらされた時に同時に入ってきた、史前帰化植物であるという説もあり、現在も議論が分かれるところです。水田の厄介な雑草として扱われることが多いヒデリコですが、雑草としての強靭さを活かした様々な用途が検討されています。
家畜肥料や緑肥として用いられるほか、亜鉛を多量に吸収する特性から、バイオフィルターとしての応用を検討されたこともあるようです。民間療法では生薬として用いられることもあり、全草に消炎効果や利尿効果があると言われています。また、漢方としては日照瓢払草の名で用いられています。
地味でありながら可憐な形状に惹かれる人は多く、絵本の題材として用いられることもあります。日本の古書には、江戸時代に編纂された「筑前国産物帳」という資料に「ゑつ」という名称で記載されており、
古くから認識されてきた植物であることがわかります。姿かたちは可愛らしいものの、特に目をひく特徴を持たないためか、子どもの遊びに取り入れられたというような記録はなく、昔からままごと遊びなどに用いられることはあまりなかったようです。
ヒデリコの特徴
ヒデリコは高さが20~60cmの小柄な植物で、秋には種子を落として枯れてしまう1年草です。湿地や田んぼのあぜなどに生育し、休耕田など生育を邪魔する要素が少ない環境においては、密生して大きな株を形成することもあります。細く扁平な葉を、株の基部から二つの方向に向かって出すので、株全体が扁平な扇形になるのが大きな特徴です。
夏になると葉の間から茎がたくさん伸びて直立し、先端で分岐してたくさんの花穂をつけ、花穂の先が放射状に延びて小さな球形の小穂をつけます。丸く可愛らしい小穂がたくさんついた姿は、よく見ると星をちりばめたように美しく、夏の野にあって涼しげに見えます。この花は一度に開花するものではなく、
新しい茎がどんどん伸びて次の花穂をつけていくので、開花期間は非常に長くなり、星をちりばめたような可憐な姿を長く観賞することができます。湿地を好んで育つ植物ですが、非常に強靭で「日照り子」の名の通り日照りの時でも旺盛に生育します。幼苗の頃は、他のカヤツリグサ科の雑草やイネ科の雑草との区別が難しいのですが、
夏になって花穂が出てくると、容易に判別できるようになるほど特徴的な外見を持つため、水田などに生えていたらすぐに見分けられます。瑞々しいグリーンと淡い褐色の花穂の対比は、強い夏の日差しの下ではとても涼しげで、どんなに太陽が照りつけても萎れることなく風に吹かれる姿は、暑さに疲れた人々に涼感をもたらしてくれます。
-

-
つい捨てちゃう、アボカドの育て方
最近では、サラダやグラタン、パスタなどに使われることもなりスーパーでもよく見かけるようになったアボカド。「森のバター」や...
-

-
ノアサガオの育て方
ノアサガオなどの朝顔の原産地や生息地はアメリカ大陸で、ヒマラヤやネパール、東南アジアや中国南部という説もあります。日本に...
-

-
シロダモの育て方
現在に至るまでに木材としても広く利用されています。クスノキ科のシロダモ属に分類されています。原産や分布地は本州や四国や九...
-

-
アボカドのたねは捨てずに育てよう
「森のバター」とも呼ばれている果実をご存知でしょうか。これは、アボカドの事を指しますが、栄養価が高く、幅広い年代に人気の...
-

-
フジバカマの育て方
フジバカマはキク科の植物で、キク科の祖先は3,500万年前に南米に現れたと考えられています。人類が地上に現れるよりもずっ...
-

-
サボテンの育て方
サボテンといってもその名前が指す種類はとても幅広いです。一つ一つ特徴も異なることでしょう。しかし、一般の人々がサボテンと...
-

-
パセリの育て方
その歴史は古く、紀元前にまでさかのぼります。特徴的な香りにより、薬用や香味野菜として使われてきました。日本には、鎖国時代...
-

-
コバイケイソウの育て方
この植物は日本の固有種ということですので、原産地も生息地も日本ということになります。わたぼうしのような、まとまった小さな...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
ベンケイソウの育て方
ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多...




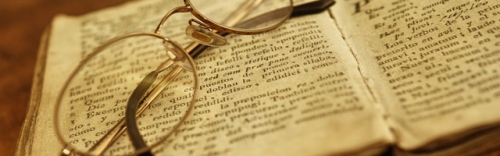





ヒデリコは高さが20~60cmの小柄な植物で、秋には種子を落として枯れてしまう1年草です。湿地や田んぼのあぜなどに生育し、休耕田など生育を邪魔する要素が少ない環境においては、密生して大きな株を形成することもあります。細く扁平な葉を、株の基部から二つの方向に向かって出すので、株全体が扁平な扇形になるのが大きな特徴です。