ニワトコの仲間の育て方

育てる環境について
日当たりのよい山野に生えている普通の樹木です。昔から一般家庭の庭にもよく植えられていますので、知っている人も多い樹木です。下のほうから分岐する株立ち状の形の樹木でで、自然のままだと、3から6mにもなります。樹皮は、黒褐色で、放射線状に伸びる独特な樹形を好む人が、多くいます。新しい枝には、必ず3mm程度の大きさの、クリーム色や淡い紫色の小さな花をたくさんつけます。
果実は、初夏から盛夏にかけて、赤く色づきます。どの部分も、薬としての効果がありますから、さし木にして育てたものを、春に花を、夏には、茎や葉っぱを、秋には根っこを、それぞれ採取して、干して保存すると言う人もいますが、その変わった枝ぶりを楽しむ人もいます。ニワトコそのものが、
ハエなどの虫を寄せ付けないという効果を持っていると言われていますから、植える場所によっては、その効果もあり、重宝する樹木です。日本の寒冷なところ以外、どこでも自生している樹木ですから、花にしても、樹木そのものの形にしても、どこかで見たことがあると言う人のほうが、多いでしょう。自生しているものを見ていると、
栽培するというイメージは、ありませんが、植木鉢に植えて、観賞用にすることも、庭に植えて、剪定をして体裁よくすることも、可能です。じめじめしているとか、日が当たらないなどという問題さえなければ、すくすくと成長する剛健な植物です。育てるだけなら、水や用土をまめに頑張らなくても、失敗することは、殆どありません。
種付けや水やり、肥料について
ニワトコは、日本生まれの日本育ちですが、山野に自生していたため、乾燥にだけは、弱いですから、土の表面が、乾かないようにしなければなりません。けれども、水は、常に必要ですが、水のやりすぎで多湿状態になってしまうと、良くありませんので、気を付けなければなりません。世話のない樹木ですから、肥料は、ほとんど不要です。
葉の落ちる頃に、化成肥料を、足元に適量ばらまくだけで十分育ちます。肥料はさほどたくさん要りません。落葉期の冬に化成肥料を適量株元にばらまいておきます。土の質も選ばない樹木ですから、気を遣うことはありませんが、水はけだけは気を付けましょう。もちろん堆肥や腐葉土の入った良質の用土であるに越したことはありません。
植えつけは、春先か秋口に行いますが、生育は、とても速いので、鉢植えの場合は、隔年に大きな植木鉢に植え替える必要が、ありますので、気を付けましょう。樹木ですから、育て続けると、2から3m位にはなります。盆栽として育てる場合でも、庭木にする場合でも、その点を踏まえておく必要があります。
増やすのも簡単な植物ですから、育て続けないで、採取して、煮出したものを、入浴剤代わりに風呂に入れ、リュウマチや神経痛の薬効を確かめるのも興味が持てますし、果実酒を作って利尿効果を得て、健康に役立てるというのも、良いでしょう。ニワトコは、世話が、非常に簡単なうえに、色々な楽しみ方や利用の仕方があることを知れば、栽培の喜びが、何倍にもなる植物です。
増やし方や害虫について
春から秋にかけて、いつでも、挿し木をすれば、増えます。生き生きとしている若い枝の先端を10cm強切り取って、よく湿らせた用土にさせば、後は、すくすく育ちます。けれども、高温多湿の状態には、弱いですから、日本の夏場の天気には気を付けて、風通しの良いところに置いて、育てるということを忘れてはいけません。
自然に自生する樹木ですから、成長も繁殖も、簡単ですし、病気も害虫も気にするものは、ありません。ただ、栽培する限りは、食用に用いるか、観賞に室内や軒下に置くという目的の人たちも多いですから、支柱をしたり、枝葉を伐採したりしながら、好みの大きさや形に保つためには、花の季節には、花がらつみも必要ですし、葉や茎が伸びて、
茂ってきたら、整理したり、切ったりすることもしなければなりません。観賞用にする場合も、食用とする場合も、季節に応じて、あるいは、生育の変化に応じて、細かなするべきことがあります。満足できれば、どんどん増やして、その喜びをいくつにも分けて、家族や友人たちに配ることもできるでしょう。
ニワトコのように自生の植物を、どのように手を加えて、変化させて、その存在を喜びに満ちるものに変えるかという点に、栽培のやりがいが見えてきます。育て方や増やし方において、何も失敗のない樹木です。育てる目標や目的において、その通りになってこその成功です。何度でもやり直しのできますから、初めての栽培でもチャレンジできます。躊躇ない挑戦をしてみましょう。
ニワトコの仲間の歴史
ニワトコの仲間は、ヨーロッパや中国や朝鮮にもありますが、日本でも、寒い北国を除く、ほとんどを原産地として、分布している、珍しくない樹木です。生息地は、一般の山野にふつうにみられる植物で、湿気がある程度ある、日当たりの良いところに育っています。外国では、魔除けやハエが来ないようにトイレのそばに植えるなど、
その効能は、様々で重宝されていました。日本でも、ニワトコの枝を切り、正月の飾り物に使ったり、鉢植えにしたりして、玄関先に飾り、病気除けや厄除けのように飾られていたところもあります。薬効が、色々とあるため、発汗や解熱、利尿効果のある花を開花直前に採取し、夏には、むくみや打ち身や打撲、
神経痛やリュウマチに効果のある茎や葉っぱを採取し、晩秋から冬の初めにかけて、むくみや利尿効果の根を採取して、乾燥させて、保存をして、家庭内の漢方薬として重宝されていた時代があります。薬用酒として作り置きする家も、珍しくは、ありませんでした。地植えでは、大きな樹木になりますが、家を守る樹木として、植えている家を、今でも、よく見かけます。
しかし、とても愛らしい花盛りや秋口の赤い実のなった樹木をめでる人たちは、いますが、昔のように漢方薬的な利用をする人たちは、今では、ほとんどいません。また、鉢植えにして、軒下や玄関先に置いて、花や子房のかわいらしさや赤い実の愛らしさは、観賞に良く、それを楽しむという人のほうが、多くなっているようです。盆栽として、他の作品と並べても、見ごたえがあるので、十分満足できる観賞用樹木です。
ニワトコの仲間の特徴
ニワトコは、日本にも元々山野に自生していた樹木ですから、何も気にしなくとも、育ちます。ただ、日本生まれの日本育ちでも、高温多湿状態は、どんな樹木や草花にとっても、絶対に良くありませんから、夏場の多湿な時期だけは、風通しに気を付ける必要があります。庭先に植えても、鉢植えにしても、手入れをしなければ、
いくらでも大きくなりますし、実を落とすと、そこから増えるということもあります。自生する樹木や草花は、生命力が、非常に強いですから、どのような目的で、ニワトコを栽培するのかで、世話することは、色々と違ってきます。枝ぶりなどを気にするのであれば、支柱で形を整えたり、散髪をしたりして、低木に保つことも必要でしょう。
かわいい花の盛りを楽しんだり、赤い実のなった美しい姿をめでたりするのなら、大木のままであっても醍醐味がありますし、小さく鉢植えにしていても、室内を美しさで飾ってくれるでしょう。薬用に用いるのであれば、いつ何を採取するかというのを知っておかなければなりません。ただ、どんな目的に用いるにしても、水分の調達と栄養分のある土、日光は、自生の植物と言っても、命の源です。
環境が、良ければ良いほど、多くの花と実を付けますし、立派です。土が肥えていて、水はけのよい質の良いものかを確認して、そうでなければ、快適環境に作り替えて、人に自慢できるニワトコ作りをしましょう。もちろん、少々のことでは、枯れることはありませんから、環境の悪さに樹木がダウンしそうなときは、早めに気が付けば、立ち直ることも可能ですので、気楽に始めてみましょう。
-

-
ポリキセナの育て方
この花の特徴としては、ヒアシンス科になります。種から植えるタイプではなく、球根から育てるタイプになります。多年草のタイプ...
-

-
シクラメンの育て方
シクラメンはもともと地中海沿岸地域の山地を生息地としている、サクラソウ科の原種であるシクラメンを基にして、品種改良を加え...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...
-

-
カブの育て方
カブはアブラナ科アブラナ属の越年草で、アフガニスタン原産のアジア系と、中近東〜地中海沿岸が原産のヨーロッパ系の二種類に分...
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
きゅうりの育て方
インド北部のヒマラヤ山麓がきゅうりの原産地や生息地で、現在から約3000年以上前には栽培されていたのです。その後シルクロ...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
シュガーバインの育て方
シュガーバインは、ブドウのような葉をつけ、葉のつけ根からひげのような根(気根)が伸びて、他の植物に巻きつくことで広い面積...
-

-
大根の育て方
大根の原産地は地中海沿岸といわれていますが、いろいろな説もあります。紀元前2500年ごろにエジプトでピラミッドを通ってい...
-

-
ソラマメの栽培~ソラマメの種まきからソラマメの育て方
ソラマメの種まきは関東を標準にしますと10月下旬から11月上旬になります。地域によって種まきの適期は異なるので種袋で確認...




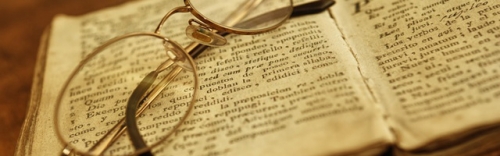





ニワトコの仲間は、ヨーロッパや中国や朝鮮にもありますが、日本でも、寒い北国を除く、ほとんどを原産地として、分布している、珍しくない樹木です。生息地は、一般の山野にふつうにみられる植物で、湿気がある程度ある、日当たりの良いところに育っています。