イチジクの育て方

スタートは種付け(苗の植え付け)
イチジクは亜熱帯果樹ですが、日本の家庭で育てる場合、収穫時期で品種がわかれます。盛夏前に収穫できる夏果専用種は、梅雨時の水分で実が腐りやすくなるので少し育て方が難しいです。盛夏~秋に成熟する秋果専用種・梅雨から秋まで通してでできる兼用種でしたら耐寒性もあり日本の風土に合っていて、より失敗が少ないでしょう。
西日本では庭に直植えで問題なく育ちますし、関東・東北では直径30cm(10号サイズ)ほどの鉢に苗を種付け(植え付け)ます。これなら冬期に風除けしやすく、必要なら室内に移動できます。直植えの際は日当たりがよく適度な日陰も確保できて風にさらされない場所を選び、水はけも水もちも必要ですので、場所や土質は考慮してください。
種付けの時期は休眠期である冬の間がよいですが、寒冷地では春まぢかになるまで待ってから植えましょう。品種を混合したり受粉の心配をしなくていいので1本から植えることができます。苗は根のよく張った小さ目の苗を選びます。売られているのはさし木苗が多いです。
土は培養土(市販)7に赤玉土2、砂1がよいでしょう。この混合土1リットルにつき苦土石灰20グラムと粒状肥料5グラムをよく混ぜこんで種付けます。腐葉土を足してもよいです。50cmの深さ・広さの穴(鉢)にこの混合土を敷き、苗木の根をよくはらったものを置いてさらに混合土で覆います。これらの数値は目安ですので、経験や地域によって臨機応変に。
イチジクの育て方で重要なのは、枝の伸びと実の数は比例するということです。根や枝を伸ばしすぎると日があたらなくなったり、実の数が多いわりに味が落ちたりしますので、枝の剪定はこまめに行います。植え付けのその日からその見立ては始まっていますので、まずは地表から30cmくらいの高さで切り詰めましょう。支柱を立ててやり水をたっぷりやりましょう。
水やり、肥料、収穫までの育て方
イチジクは湿っぽい環境に弱いので、土が乾いたら水をやる程度にしましょう。しかしぐいぐいと伸びる力が強いため、よく様子を見て水分が不足しすぎないようにだけ気をつけてやります。鉢植えではすぐ蒸発するのでこまめにチェックしてやります。特に夏場は油断しないように。
熱い地域の植物の栽培の常として、成長の仕方は大変パワフルです。枝別れを増やしながら実も同時についていきますので、エネルギーつまり肥料はシーズンに合わせたこまめな補給が必要です。寒いうちから成長の支度は始まっていますので、年の終わるころに有機質の肥料を与えます。場所は根本近くよりも樹冠下あたりが効果的です。油かすや粒状肥料を200グラムほどが適量です。
さらに極寒の時期にも同様に50グラムほどを与えると夏場の成長に程よく作用します。収穫が落ちつくころ、秋の終わりごろにも50グラムほど施しましょう。春から夏にかけて与えないのは、盛夏のころまでには枝の成長を終了させておきたいからです。あまり広がりすぎると花や実に栄養がいきません。石灰分は弱アルカリ~中性の数値に調整するとよいです。
いよいよ収穫、夏果は梅雨時に収穫開始、秋果はお盆過ぎ頃からが目安です。イチジクは果肉がやわらかくて傷みに弱いため、市場に出るものは育て方の工夫をし、早熟の状態で収穫するケースが多いです。ご自宅での栽培では自由にできるので、木上で完熟させることも可能ですね。鳥などの被害には対策を取りましょう。
収穫のタイミングは実の先端部分が割れてくるのでわかります。熟すごとに甘味が増し、酸味が減っていきますが、油断すると数日であっという間に柔らかくなっていきます。あまり熟しすぎたものはジャムやコンポートなどにはよいですが、生食したい場合はあまり熟させないように気を付けて見ていた方がよいですね。
剪定、害虫対策などの世話
イチジクに害虫はつきにくいですが、カミキリムシが好む木として確認されています。幹に穴があくと木くずが出て気づきやすいです。専用の薬剤を選んで注入し、駆除するようにしましょう。成虫を発見したら薬に頼らずそのまま取り除くとよいです。
前述しましたが栽培で重要なのは枝ぶりです。コントロールできますので全体の姿に気を配りましょう。収穫前、初夏には葉の茂り始めた枝の頭の部分を少し飛ばしておきます。収穫後はの剪定は品種によってその方法は違います。秋果種はその年に新しく伸びた部分の枝に実がつきますが、夏秋兼用種は前の年の秋に実がもう出ており、その状態で冬を越し、梅雨どきに収穫してさらに新しい枝に秋の実もつきます。
ですので夏果の芽の部分は切らないようにします。切り口には殺菌剤の塗布をするとよいでしょう。各枝は30cmくらいに留めるようにするのが目安です。直植えでしたら三年くらいで樹高1.5mくらいに育つようなイメージを持ってみましょう、各枝はやはり30cmくらいの長さが目安です。鉢植えでしたら剪定次第で小振りに育てることができます。
イチジクの歴史
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000年以上も前から栽培され親しまれていました。この原産地周辺の歴代の覇者国の食卓を飾り、滋養のある甘味・保存食として地中海地方からヨーロッパにまで広まっていき化石で確認もされています。聖書に登場するので急速に世界中に名が知れ渡ることにもなりました。
日本には江戸時代に、ペルシャから中国を通って伝えられました。長崎に上陸したイチジクは薬として珍重されます。長生きの秘訣はイチジクを食すこと、と言われて、干して保存食にし旅先にもよく持っていきました。挿し木で簡単に増やせるので、手軽な甘味として全国で人気が出ました。
江戸時代に日本にきたはじめの品種は、葉が三つの部分に裂けた形をしています。後に明治時代にきた他の品種は、深く五つに裂けていて特徴が違います。葉は大きく、枝の伸びる姿は勇壮とも言える奔放ぶりで、絵画の題材にもされてきました。茎を切ると乳のような汁が出、青臭い特有のにおいがありますがこれを薬とすることもありました。
和名が定まるまでには「南蛮柿(なんばんがき)」「唐柿(とうがき)」「蓬莱柿(ほうらいし)」などと一種珍しいものへの憧れのような呼び名で呼ばれていました。蓬莱というと中国の神聖な山の名前で、古来日本でも蓬莱という桃源郷の存在は夢をかきたてるようなモチーフでしたので、イチジクがいかに異国情緒にあふれた果物だったかが読み取れます。
イチジクの特徴
クワ科・イチジク属に所属し、名前「無花果」の由来は「花がなくても果実が実るように見える」という意味ですが、実際には花は存在します。「映日果」とも表記します。ペルシア語の「アンジール」という名称が転化を重ねて「イチジク」という音になったとも言われます。
花は初夏、無数の小果として付きます。雌雄異花ですが、同じ花嚢の内面に両方つくので一本で実を結びます。品種はいろいろありますがほとんどの種は熟すと濃い紫色に染まります。生でも食べられ、乾燥させてドライフルーツとしても重宝されます。洋菓子の生地に練りこんだり、ジャムやコンポート、ソースの材料として大変人気の高い素材です。
葉を乾燥させたものは漢方の生薬として使われます。整腸作用に優れるため腹痛の薬の代表格でした。また、実や葉から乳液のような汁が出ますが、これは樹脂分を含み、いぼの治療や外傷、痔に効果を発揮しました。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
タイトル:レモンの育て方
キンカンの育て方
-

-
エクメアの育て方
エクメアはパイナップル科のサンゴアナナス属に属します。原産はブラジルやベネズエラ、ペルーなどの熱帯アメリカに182種が分...
-

-
芝桜の育て方
たくさん増えると小さな花がまるで絨毯のように見えることから公園などにも植えられることが多い芝桜は北アメリカ東海岸が原産で...
-

-
ガウラの育て方
ガウラは北アメリカを原産地としている花ですが、北アメリカでは「雑草」と認識されているようです。主な生息地はアメリカ合衆国...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
マツリカの育て方
特徴としてどのような分類になるかですが、シソ目、モクセイ科、ソケイ属と呼ばれる中に入るとされます。常緑半蔓性灌木になりま...
-

-
ゲラニウム(高山性)の育て方
高山性ゲラニウムの学名は、ゲラニウム・ロザンネイです。別名でフクロウソウとも呼ばれている宿根草で、世界にはおよそ400種...
-

-
アボカドの種を観葉植物として育てる方法。
節約好きな主婦の間で、食べ終わったアボカドの種を観葉植物として育てるというチャレンジが密かなブームとなっているのをご存知...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
サクランボの育て方
栽培の歴史はヨーロッパでは紀元前から栽培されており、中国に記述が残っていて3000年前には栽培されていました。日本には江...
-

-
プチトマトの育て方について
今回はプチトマトの栽培の方法と、育て方について説明します。プチトマトは、カロテンとビタミンCという栄養が豊富なので、体に...




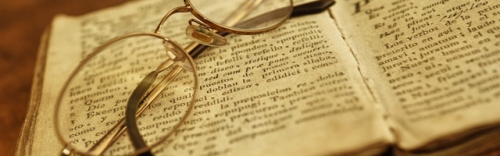





イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000年以上も前から栽培され親しまれていました。この原産地周辺の歴代の覇者国の食卓を飾り、滋養のある甘味・保存食として地中海地方からヨーロッパにまで広まっていき化石で確認もされています。聖書に登場するので急速に世界中に名が知れ渡ることにもなりました。