ベンケイソウの育て方

育てる環境について
ベンケイソウは名前のように大変強健な植物になります。秋に花が咲いたら今年はもう咲かず、後は地上部が霜に当たって枯れるだけになってしまいます。寒さに大変強く、冬の季節に凍っても大丈夫なので一年中外で育てる事が出来ます。基本的には日当たりのよい場所で育てますが、夏の日差しは少し強すぎる場合があるので、
夏は午前中は日光が当たるような半日陰の場所で育てると良いでしょう。寒さには比較的強い植物で、葉が枯れ落ちて完全になくなり宿根して冬を越します。暖地で育てる場合は多少霜に当たっても大丈夫でしょう。鉢植えで育てる場合は軒下に置いておけば心配ありません。栄養分の有る土や水はけの悪い土には植えない方が良いでしょう。
水やりは比較的少ない環境で育てる方が良いでしょう。夏の暑さにも強く、乾燥気味で育て、水をあげる際がたっぷりあげるようにしましょう。日光をたくさん当てて育てると大きく育ちます。用土をあげればさらに育つので、大きく育てたい場合は用土をあげてみましょう。花付きも良い植物なので、見応えもたっぷりです。
多肉植物のベンケイソウ科は大変育てやすい植物です。マイナス5℃くらいになるところでも外で育てる事が出来ます。霜が降りる場合は、部屋の中へ入れなくても軒下でも十分です。ただしあまり水分の多い地域では育てにくくなってしまいます。その為、雨が多く降る地域では注意が必要です。雪がかぶっても芽を出す物もいるくらい強い植物です。
種付けや水やり、肥料について
植え付け時期は3月から4月頃、株分けするか、または地植えするととても良く育ちます。収穫した種からも育てる事が出来ます。水をあげる場合は土の表面が乾いたら与えるようにしましょう。多肉植物は多湿をとても嫌うので、水の与え過ぎには十分気をつけながら育てていきましょう。2年に1回を目安に植え替えをします。時期は春先に行います。多肉植物なので、それほど肥料を必要としません。
もしあげるのであれば、春の4月から6月頃に緩効性の化成肥料か液体肥料を与えるようにしましょう。それほど頻繁に肥料をあげる必要はないでしょう。過湿にとても弱く、乾燥には強い多肉植物なので、庭に植えるのであれば水を極力控えめにして、日が当たる場所と水はけの良い場所で育てれば簡単に育てる事が出来ます。
ただし、日陰の場所で水はけの悪い場所で育ててしまうと、根っこが腐ってしまう可能性があるので注意が必要です。一般的には鉢植えで育てている人が多いようです。梅雨になったら出来るだけ雨の当たらない場所に移しましょう。また、室内で日の当たらない場所で育てる場合は水のやり過ぎは注意しましょう。
乾燥には強い植物ですが、水はけには注意が必要です。あまり肥料をあげすぎてしまうと、徒長してしまい花が小さくなってしまう場合があります。また、冬は水分を体内に吸収します。その為、細胞内の体液が薄まってしまうしもやけになって溶けてしまう場合があるので、冬場の水やりには十分注意しましょう。
増やし方や害虫について
ベンケイソウを増やす場合は挿し木や株分けで増やしていきます。この方法であれば比較的簡単に増やす事ができるでしょう。挿し木をする場合は5月頃が良いです。挿し木が面倒と言う方は、株分けの方が楽に増やす事が出来るでしょう。株分けをする際に一緒に行っても良いです。害虫はそれほど付きませんが、蛾の幼虫が葉を食べてしまう場合があります。
見つけた場合はスミチオンなどを散布して早めに駆除するようにしましょう。他にはアオムシがつきやすいので、定期的にチェックしましょう。見つけたら薬剤などで駆除しましょう。ベンケイソウは肥料もそれほどあげなくて良いので植え付けも簡単ですし育てやすい植物です。花が咲くと観賞用としてもとても映える植物になります。
庭先などに生えていると、見応えがあって庭全体が明るく感じるでしょう。また雑菌に弱い植物になるので、一度使用した用土は使わないようにした方が良いでしょう。出来るだけ乾かしぎみに育てる方が良いので、水やりもそれほど慎重にならなくても大丈夫です。乾かしぎみに育て、また水分をあげる際はたっぷりあげましょう。
ポットで購入した場合は植え付けを行う際、ついている土はなるべく落とさないようにして植え付けしていきましょう。増やし方も初心者でも簡単に行うことが出来るので、たくさん増やしてお庭を賑やかにしてみましょう。その際、害虫には気をつけて、時々葉の裏などもチェックするようにしましょう。
ベンケイソウの歴史
ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多少異なってきます。日当たりのよい場所などに生えており、葉に厚みのある多肉質な多年草になります。日本では昔から各地で観賞用とし栽培されてきました。現在では一部の山岳地域を除いて、ほとんどが栽培されなくなってしまいました。
日本には古くから渡来しており、日本へは遣唐使などによって中国からもたらされたと言われています。薬草としても栽培されていました。その野草として栽培していたものが徐々に野生化したのではないかとも言われています。このベンケイソウという和名は、多肉の葉が水分が無くなって乾燥してしぼんでしまっても、
暑い日差しのなかで発根することから、その強さを弁慶にたとえて「ベンケイソウ(弁慶草)」と付けられたと言われています。大変生命力の強い植物なんですね。水分を葉にしっかり貯蓄する事が出来る植物で、1400種もあると言われています。現在ではオオベンケイソウが鉢植えなどの主流として出回っています。
大変力強い植物ですから、それほど手入れをしなくても良いので比較的育て方も簡単です。自宅で観賞用として栽培しても、きれいな花を咲かせてくれるでしょう。種類も豊富にあるので、色々植えて楽しむのも良いですよね。観賞用としてお部屋にあるだけでも見応えたっぷりで見ていて飽きない植物になります。
ベンケイソウの特徴
ベンケイソウはその種類によっても異なりますが、中でも一番流通しているオオベンケイソウは薄い紅色の小さな花が群がってつくのが特徴です。花弁は5枚になっており、横に平らに開きます。萼片は5枚あり、雄しべは10本で、楕円形の葉が向かい合って生える対生になっています。日本では北海道から本州の中部まで幅広い地域を生息地としています。
海外でも、朝鮮半島、中国東北部、シベリア、モンゴルなど様々な地域で見る事が出来る植物です。草丈は30cmから80cmセンチ程あり、ベンケイソウ科の植物の中には、種を使用せずに葉から直接芽がでて増えるものがあります。夏から秋にかけて、茎頂に集散花序を出し多数の花を密生させるのが特徴です。
その名の通り、大変環境に順応能力があり、力ずく生育する植物になります。まさに弁慶のように、たくましく成長していく姿が見物の植物です。鉢植えやプランターなどで栽培しても、大変きれいな花を咲かせてくれるのでガーデニング初心者でも育てやすい植物です。肉厚な葉から芽が出てくる姿は大変可愛らしく、なんとも不思議な植物です。
他にもベンケイソウ科の植物にはセイロンベンケイなど色々な種類があります。花壇に植えても存在感たっぷりなので、是非自宅の庭に植えてみましょう。日当たりを大変好む植物になるので、しっかり太陽の光を浴びさせましょう。そうすることにより、ぐんぐん成長してくれます。また、水やりを少々忘れても枯れないので育てやすい植物です。
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...
-

-
みつばの育て方
みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になってい...
-

-
ドラゴンフルーツの育て方
サンカクサボテンの実の事を総称してピタヤと呼びます。ピタヤはベトナムから輸出する時の商品名であり、日本に輸入される時には...
-

-
ギヌラの育て方
ギヌラは、アフリカからマレー半島にかけてが主な生息地とするキク科ギヌラ属に属する多年草の植物です。ギヌラ属と言うのは、ユ...
-

-
ヒメオドリコソウの育て方
春先の3月から5月頃にかけて花を咲かせるヨーロッパ原産のシソ科の草花である”ヒメオドリコソウ”。学名をLamiumpur...
-

-
アオキの育て方
庭木として重宝されているアオキは、日本の野山に自生している常緑低木です。寒さに強く日陰でも丈夫に育つうえ、光沢のある葉や...
-

-
イヌタデの育て方
イヌタデの特徴としては、タデ科の植物であり色のついた花がゆらゆらと揺れているのが特徴の一つとして挙げられるでしょう。上記...
-

-
サルビア(一年性)の育て方
サルビアの正式名称はサルビア・スプレンデンスであり、ブラジルが原産です。生息地として、日本国内でもよく見られる花です。多...
-

-
チューリップの栽培の仕方
チューリップはユリ科の植物で品種には早生系、早生八重、晩生系など色々な種類があり、その種類によって草丈や開花期が異なりま...
-

-
アカリファ(Acalypha spp.)の育て方
アカリファは別名をキャッツテール、ファイアテール、サマーラブ、シェニールといいます。原産地や生息地はインドで、細かく言い...




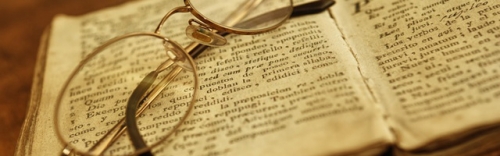





ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多少異なってきます。日当たりのよい場所などに生えており、葉に厚みのある多肉質な多年草になります。日本では昔から各地で観賞用とし栽培されてきました。