セッコクの育て方

セッコクの育てる環境について
セッコクは自然の降雨のみの水分補給で1年を過ごすことができるため乾燥には比較的強い性質を持っています。育て方としては、日当りのよい岩場などに自生している植物ですので、ラン科植物の中では日照を好む種類ですので日のあたる明るい場所を選んでください。
セッコクの根は空気中に出ていますので空気を好む性質です。冬前には葉が落ちてしまいバルブの状態で冬を越していくのですがこのバルブ部分には翌年再び花を咲かせます。春頃から秋頃は日当りのよいところで管理して夏場は半日陰に移動してあげるとよいでしょう。
夏の直射日光に晒され続けていると、葉が黄色っぽく変色してしまうことがありますので注意するようにしてください。開花し終わってから新芽が固まるまで日にあてておくこといよって締まった株に育てていくことができます。夏場は気温がとても高くなって乾燥しやすくなりますので、
30パーセントから50パーセントほど遮光してあげて葉焼けを防いであげるようにしてください。秋頃になると花芽が樹実してくるシーズンに入ります。秋も半ば頃を過ぎてきたら再び遮光を弱て花芽の付きがよくなるようにしてあげましょう。
冬場はあまり寒風にあてないようにするために、置き下などに移動したりフレームなどを利用して保護してあげることがおすすめです。その他の対策として、ワラなどをまいてあげることで寒さから保護することができます。風通しのよい樹木の下や軒下につり下げて栽培することができるのであれば理想的です。
セッコクの種付けや水やり、肥料について
セッコクは乾燥に強い性質を持っている植物ですので多湿には弱く、年間を通して水やりは控えめにしてあげることがおすすめされています。セッコクの貯水組織は茎にありますので、根は反対に乾燥を好みます。水やりは水ゴケなどの植え込み材料が乾いてからあげるとよいでしょう。
水ゴケは乾きすぎると水を吸収しなくなるので注意してください。冬場は生育が止まってしまいますので水やりの回数を減らすようにしていきましょう。水を与え過ぎてしまうと、根腐りしてしまうケースがありますので注意してください。肥料は施さなくても生育することができますが、
4月頃になると茎の根際の新芽が伸びる生育期に入りますので薄めの液体状の肥料を2週間に1回程度与えてあげることによって充実した株に育てることができます。新芽は5月頃から6月頃にかけて成長して秋頃から冬にかけて寒さにあたることで落葉して休眠に入っていきます。
バルブ部分に栄養が残っている状態になっていると花芽がつきにくくなってしまいますので、夏以降になったら肥料を施すことは避けてください。鉢植えで育てていく場合は、成長期に週2、3回ほど液体状の肥料をスプレーで葉面散布するのも効果的です。
セッコクは庭の木などに着生させることもできますので、コケが生えているような岩やマツなどの針葉樹、モミジ、ウメなどに紐を使って縛って固定してあげてください。根付いていくまではたっぷりと水やりをしてあげましょう。
セッコクの増やし方や害虫について
セッコクの増やし方は、株分けや高芽とりなどでおこなわれています。株分けをする場合には、植え替えの際に一緒におこなっていくようにしましょう。新芽をつけた状態でバルブを5本以上にして分けることがおすすめされています。
切り分ける際は、バルブとバルブの間をナイフやハサミで切断すると傷みがありません。高芽とりは、古いバルブに高芽と呼ばれるわき芽ができますので、発根して独立した株になったら外して植え込んでいきます。折れたバルブを横に寝かせて高芽を出させることもできます。
古くて傷んでいるようなバルブがあった場合は取り除いていくようにしてください。植え付けや植え替えをおこなうのに適している時期は春の芽出し前です。一般的には、素焼き鉢で水苔植えが普及しています。水ゴケで植えている場合は、水ゴケが傷んできますので
2、3年に1回は新しい水ゴケを使って植え替えをおこなっていくことがおすすめされています。砂上をする場合は、3年から5年くらいに1度は植え替えをしていきましょう。鉢は通気性のよい素焼き鉢を使います。大きさは株と比較してやや小さめのものを選ぶと過湿にならずによいでしょう
ヘゴ板や樹木に貼り付けて育てているものは特に植え替える必要はありません。古典植物として栽培されている着生ランのフウランとは異なり、株分けや古い茎を切り離してミズゴケの中で腋芽の発芽を促す矢伏せによって株の増殖は比較的容易だとされています。
セッコクの歴史
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木の上や岩盤などに根を張って生活する着生植物で水分は空気中からとります。セッコクというのは漢字で表記すると石斛で、中国原産の近似種にあてられた名称です。
セッコクは健胃、強壮作用などがあることから漢方薬として用いられていました。薬用として利用されていたことから、記紀神話の医療神の少彦名命にちなんで少彦薬根という古名を持っています。江戸時代頃から日本で育種、改良され、独自の発展を遂げた園芸植物、
また明治時代以降でもその美的基準において栽培、育種されている植物です。セッコクは中国と日本で古来から珍重されたものに基づいた鑑賞基準の元で、栽培鑑賞されている数種のラン科植物東洋ランとしての名称は長生蘭です。一般的に葉変わりを楽しむことが多かったのですが、
昭和の終わり頃から花変わりも楽しまれるようになってきたことから花物の品種も登録されています。日本の他にも朝鮮半島、中国などに分布しているセッコクは、洋ランの中でデンドロビウムと呼ばれているものの一種です。
デンドロビウムは、熱帯アジアを中心としてオーストラリアまでおよそ1000種類以上が生息しています。セッコクは、古くから日本で栽培されてきた植物で江戸時代は長生草、大正時代以降は長生蘭というとても縁起のよい名前で親しまれてきました。
セッコクの特徴
セッコクの茎は細長くて内部に水分を蓄えられるようになっています。緑色を帯びているのですが少しずつ黒紫色へと変わっていきます。葉は長いものではおよそ40センチメートルほどになります。温暖な地域のものほど長くなる傾向があるとされています。
多数の節があり節ごとに出る葉の基部の鞘に包まれています。細長い長楕円形をした葉っぱは、厚みがあって少し堅いのが特徴です。ツヤのある葉は左右交互につき、葉は年の終わりには葉鞘との間で脱落します。新しい芽は古い茎の基部から横に出てきます。
葉がなくなってしまった茎も翌年には花を開花させます。主な開花シーズンは夏の初め頃で、茎の先端あたりの節から花茎を出して1から3輪ほどの花を咲かせます。花は赤紫がかった白の花弁で、大きさはおよそ3センチメートルから4センチメートルほどでよい香りがあります。
唇弁以外の五弁は、同じくらいの大きさの卵状楕円形をしており先端部分は少し尖っています。唇弁の外見は他の花弁と似たような形で、側弁の基部が下側の外で蕊柱との間の奥の方にくぼみが入り込んで作る短い距につながっています。
デンドロビウムは、ギリシャ語の樹木を意味するdendronと、生活するを意味する bionが語源となっています。最近では栽培が容易になってきたことや花変わりが多数発見されたことから全国的に普及しています。耐寒性に優れている性質を持っていますので、冬場に戸外で凍り付いても枯れてしまうことはありません。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セロジネの育て方
-

-
ハスの育て方
ハスはインド亜大陸を原産とするハス科の水生植物です。その歴史は植物の中でも特に古く、1億4000万年前には既に地球上に存...
-

-
アイスランドポピーの育て方
ポピーというケシ科はなんと26属250種も分布しており、ケシ科ケシ属でも60種の仲間が存在します。ケシ科は麻薬成分モルヒ...
-

-
レンギョウの育て方
花の特徴としては、キク類、真正キク類、シソ目、モクセイ科になります。属名としてフォーサイシアと呼ばれることもあります。園...
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
初心者からはじめるミニ盆栽の育て方
少し前に流行ったミニ盆栽。若者にもひそかに人気があります。盆栽はなんといっても風格があります。3000円くらいから1万円...
-

-
キクイモの育て方
キクイモは一年中育てることができる多年草の為、一度植えますと基本的に毎年開花する植物です。また、この名前は日本での名称で...
-

-
ハクチョウゲの育て方
ハクチョウゲの特徴は、何と言っても小さくて可愛らしい花を咲かせる事ではないでしょうか。生長が早い植物ですが、刈り込みもき...
-

-
ヒポエステスの育て方
ヒポエステスは南アフリカのマダガスカル島が原産と言われており、他の生息地としてはユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱...
-

-
アボカドの育て方
アボカドは7000年以上前から栽培されているという言い伝えがあります。アボカドは南アメリカ北部からメキシコ高地が原産で、...
-

-
初心者でもできる、へちまの育て方
へちま水や、へちまたわし等、小学校の時にだいたいの方はへちまの栽培をしたことがあると思います。最近は夏の日除け、室温対策...




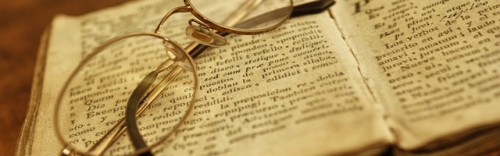





セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木の上や岩盤などに根を張って生活する着生植物で水分は空気中からとります。