レウカデンドロンの育て方

育てる環境について
熱帯植物の中では比較的耐寒性に優れた性質を持ちます。なかでも長年日本の環境下で栽培されたものなら0℃まで耐えることができたり、冬の積雪に埋もれてしまっても耐えられる場合があります。しかし、もともとは暖かい気候を好む植物ですので可能であればどんなに低くても5℃までを目安にすることで株を長持ちさせることができます。
環境のストレスは花つきや葉のつや、発色に影響が出ますのでより美しい姿を保つには本来の生息地の環境に近づけることが何より大切だといえます。上記の点から、地域にもよりますが日本では地植えよりも移動可能な鉢植えが主流となっており、とくに冬場は屋内にて管理するのが一般的です。
屋内といっても暖房をかけた暖かい部屋で管理をする必要はなく、外気に当たらない玄関先での管理で十分です。やむを得ず一年中屋外で栽培をする場合は、根本と土表面をワラで覆ったり盛り土をして防寒対策をしっかりと施す必要があります。関東地方よりも南部の太平洋側に面している暖かい地域であれば、地植えが可能な場合もあります。
そのほか、あまり多湿にならないように注意します。夏場の高温多湿な環境では枝が乱れやすく、枯れの原因となります。なるべく日当たりの良い場所で管理し、水はけのよい土で育てたり風通しの良い場所に適宜移動することで元気に育てることが可能です。また、日光を好む植物ですが葉焼けの原因となる夏場の直射日光だけは避けるようにします。
それ以外は日光を良く浴びせることで葉つきや色づきが良くなります。半日陰でも育成は可能ですが、葉つきが少なくなったりする場合があります。育て方は難しくはないので、環境さえ整えて管理ができれば大きな樹へと育てることも可能です。
種付けや水やり、肥料について
種が出回っていることはほとんどないため主に挿し木から根付かせたもの、もしくは出回っている鉢植えからの植えつけを、3月から5月頃に行います。冬場の植え替えや、比較的気温の低い初春は根を痛めやすく立ち枯れの原因となりますので避けるようにします。土は、排水のよい酸性の土を好み肥料分の少ないものを敷くようにします。
肥料となる栄養素を生成している細菌類を、もともと根に飼っているため、肥料分が多い土に植え替えてしまうと枯れの原因となります。そのため鹿沼土や赤玉土、ブルーベリー用の土を使い必要があればピートモスを混ぜ酸性に傾けるようにします。本来、熱帯の乾燥地に自生する植物なのでやせ地で育てることがかえってストレスなく育ちやすい環境となります。
根詰まりしている鉢植えを植え替える際は、根についた土を落とさず土ごと植え替えるようにします。土を落としてしまうと根を痛め、傷から細菌類が不必要に繁殖し立ち枯れの原因となります。水やりは、土の表面が乾いたら十分に行います。根が浅く水切れを起こしやすいため、土が完全に乾ききることがないように注意が必要です。また多湿にも弱い傾向があるため、水やりには一番の配慮が必要です。
とくに夏場は乾きが早い分多くの水をあげがちですが、気温の高くなる正午前に水やりを行ってしまうと蒸れにより株が弱ってしまいます。そのようなことを避けるためにも、夏場の水やりは早朝と日が沈んだ夕方が最適です。肥料はほとんど必要としませんが、与える場合には生育の盛んな春と秋に緩効性の置き肥を施します。「レウカデンドロン」の性質上、リン酸分の少ないものを与えるようにします。
増やし方や害虫について
挿し木でふやすことが可能です。春に出回る切り花を利用するか、すでに成長している株の枝を剪定し、用意してもよいです。成長している株から枝を切る場合は、株の大きさにもよりますが短くても10cm程にカットします。またその年に生えた枝以外の枝からは根が出ないので注意します。切り口はよく切れる刃物で斜めに切ることで水揚げの効率を挙げることができます。
切り落とした挿し穂は3時間ほど水につけ、しっかりと水揚げします。水があがった挿し穂は小粒の赤玉土もしくは鹿沼土に挿し、それ以降は根が出るまで直射日光の当たらない明るい窓際などで管理するとよいです。土が乾いたら水やりをし、環境にもよりますが、乾き気味に管理する方がよいとされています。
発根するまでには1ヶ月から2ヶ月ほどかかるので、挿し木をする鉢や容器は透明で根の様子を確認出来るものが好ましいです。また、発根前の挿し穂は絶対に抜かないようにします。無事発根に成功した場合は、前の植えつけの方法に従い植えつけを行います。比較的成長が遅い種ではありますがゆっくりと時間をかけて育てることで、将来的には挿し木から立派な株に育てあげることが可能です。
かかりやすい病気や害虫はとくにありませんが、夏場の気候や屋内管理による蒸れで立ち枯れを起こすことが多くあります。その場合、枯れてしまった葉は早めに取り除き風通しのよいところで乾燥気味に管理してください。株自体が枯れていない限り、引き続き様子をみて水やりを行います。また、まれにカイガラムシが付くことがありますので発見した場合はハブラシなどでこすり落とします。
レウカデンドロンの歴史
「レウカデンドロン」は、南アフリカ原産の常緑低木で熱帯地域を中心に広く自生しています。科目はヤマモガシ科レウカデンドロン属に分類され、「リューカデンドロン」と呼ばれることもあります。この名前はギリシャ語に由来しており、葉の角度や光の当たり方により銀色や白色に見えることからリューカ(Leuca=白い)、デンドロン(dendron=木)と名付けられたといわれています。
また、和名を「ギンヨウジュ(銀葉樹)」ともいいその姿や形は国や時代に関係なく受け継がれています。上述にもあるように原産は南アフリカですが、現在ではハワイやオーストラリアでも頻繁に栽培されています。近年では栽培されているもの以外に自生している樹木も増えています。南アフリカで栽培されたもののほとんどはせん定で枝を切り花とし、主にヨーロッパに輸出されています。
また、日本に輸入されているもののほとんどはオーストラリアで栽培されたものであることが多いです。熱帯気候の国々では主に地植えされ一本一本の樹木を大きく育てる傾向にありますが、日本では栽培環境や気候の関係により、切り花もしくは鉢植えとして市場に出回っています。
熱帯植物特有の鮮やかな発色と色の変化の様子は、日本に生息する植物にはほとんど見られないため近年ではフラワーアレンジメントに多く用いられています。そういった事柄から一般に流通するもののほとんどの割合を切り花が占め、鉢植えとして売られている場合はすぐに売り切れてしまうほどです。
レウカデンドロンの特徴
「レウカカデンドロン」の特徴は、夏の終わりから秋の終わりにかけて葉の先端がだんだんと赤く色づき、やがて美しいグラデーションを見せる姿です。色づいているのは花を守るためのガク部分にあたりホウといいます。これは花ではなく、花は実際にはホウに包まれるようにして中心部に存在します。開花時期は主に9月から10月ですが、品種によっては春に開花するものもあります。
外側からは花を目視しづらいため、必然的に花よりも季節によって色づくホウが魅力とされています。開花前から花の終わりまで長い期間この色づきを楽しむことができるので、花以外の魅せどころがあるのもこの植物の大きな特徴といえます。また「レウカデンドロン」は品種が多いことでも有名です。
品種によって樹高や色、色づき方が様々で一般的な赤色のほかピンクや黄色、白などの色に変化するものがあります。また、品種によって色づく時期が異なり秋に色づくものや春に色づくものもあります。そういったことからアレンジや植え方次第では様々な魅せ方ができるのも「レウカデンドロン」の魅力です。
樹高は、一般的に多くみられるもので1mから2mほどになります。生育環境によっては10mを超えるものもあり、環境を整えることでどんどん大きく生育させることができます。大きくなるにつれて茎の下部はどんどん木質化していき、草花のような見た目から徐々に樹木となっていきます。葉は、うっすら白みがかった白銀っぽい色合いをしています。
-

-
リアトリスの育て方
北アメリカが原産の”リアトリス”。日本には、大正時代に観賞用として渡来した花になります。苗で出回る事が少なく、切り花とし...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
リビングストーンデージーの育て方
リビングストーンデージーは秋に植えれば春頃に花が咲きます。しかし霜には弱いのでなるべく暖かい場所に移動させるか、春に植え...
-

-
ヌスビトハギの育て方
ヌスビトハギの仲間はいろいろ実在していて、種類ごとに持っている特質などに違いが見られ、また亜種も実在しています。例に出し...
-

-
トサミズキの育て方
トサミズキの生息地は、四国の高知県です。高知県(土佐)に自生することからトサミズキ(土佐水木)と呼ばれるようになりました...
-

-
カキドオシの育て方
カキドオシは草地に生息する年中草です。特徴としては茎はまっすぐと伸びるのですが成長するにつれて地面に倒れます。開花すると...
-

-
スイカズラの育て方
スイカズラの学名はロニセラ・ジャポニカということで、ジャポニカと付いているので日本原産の植物ということがわかります。日本...
-

-
春菊の育て方
春菊の原産地はトルコやギリシャの地中海沿岸を生息地としていたと言われています。その後地中海沿岸から東アジアの地域へ伝わっ...
-

-
ユズ類の育て方
ゆず類に関しての特徴としては、まずはそのまま食べるのは少し難しいことです。レモンにおいても食べると非常に酸味が強いです。...
-

-
サラセニアの育て方
サラセニアは北アメリカ大陸原産の食虫植物です。葉が筒のような形に伸びており、その中へ虫を落として食べることで有名です。生...




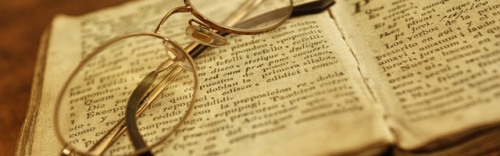





「レウカデンドロン」は、南アフリカ原産の常緑低木で熱帯地域を中心に広く自生しています。科目はヤマモガシ科レウカデンドロン属に分類され、「リューカデンドロン」と呼ばれることもあります。この名前はギリシャ語に由来しており、葉の角度や光の当たり方により銀色や白色に見えることからリューカ(Leuca=白い)、デンドロン(dendron=木)と名付けられたといわれています。