ルエリアの育て方

育てる環境について
ルエリアの育て方についてはいくつかのポイントがあります。まず4月~6月、あるいは9月~10月などの春秋の季節に関しては戸外の直射日光が当たる場所に置いて育てます。ただし、種類によっては直射日光を嫌う品種もありますので、よく調べた上で行ってください。また、いきなり直射日光に当てないように少しずつ日光に慣らしていくと良いでしょう。
この時期の水やりについては、あまり頻繁に与えない方がよく育ちます。目安としては用土が乾燥して白っぽくなってきたら行うくらいで大丈夫です。4月前後は気温の変化が激しいため水は少な目がベターです。次に夏場の時期、月で言うと7月~8月頃は日差しが強いため、半日陰の戸外に置いて育てるのが良いでしょう。
また、この時期は暑いので人間も植物も水分が必要です。毎日水を与えるくらいがちょうど良いです。そして最も用心しなければならない冬の時期です。暦に直すと11月~3月頃はできれば部屋の中に入れてレースのカーテン越しに日光が当たるような場所に置いて育てて下さい。冬の寒い時期は水やりは控えめで構いません。用土が完全に乾燥しきってから水を与えるようにします。
なお、5月~9月頃になって株が大きくなると鉢の底から根が出始めることがあります。放っておくと根づまりを起こす可能性があるので植え替える必要があります。目安は2年に一度くらいで考えておくと良いです。鉢から根っこごと抜き出した後、根を痛めないよう気をつけながら土を2/3くらい残して、サイズが一回り大きい鉢に植え替えて完了です。
種付けや水やり、肥料について
春から秋にかけて、ルエリアは成長期を迎えます。したがってこの時期に肥料を与えると良く育ちます。代表的な肥料としては主成分にチッ素、リン酸、カリウムを同じ比率で配合した化学肥料か、油かすもしくは緩効性の化成肥料が適しています。置き肥として使用します。また、液肥であれば3月~4月の新芽の成長時期に合わせて2週間に一度くらいの頻度で与えると良いです。
希釈タイプであれば、約1000倍程度に薄めて使用します。目安は観葉植物に与える程度です。植え付けの用土に関しては小粒の赤玉土:腐葉土を6:4または7:3くらいの割合で混ぜた土が適しています。なお、赤玉土とは関東ローム層の赤土をふるいに掛けて、均一に粒子を整えた土です。「大粒」「小粒」とあります。赤玉土は時間の経過と共に粒が崩れてきて、粘土状になります。
ちなみに、安物の赤玉土は粒が脆いので、植え付けの際には注意が必要です。価格的に割安な川砂を一割程度、混合しても問題ありません。もしくは市販の物なら観葉植物や草花用の培養土でも大丈夫です。種のまき方、付け方は特にコツはいりません。もともと野生で咲いている品種は数多くあり、
はじけて飛んだ種がやがて芽を出して、育つというパターンが大半のようです。繁殖力旺盛なので、こぼれだねだけでなく地下茎から広がって殖えるという場合もあります。鉢植えではなく庭に植えている場合などは雑草化する可能性もあります。その場合は春先に芽が出た時に間引く必要があります。
増やし方や害虫について
増やし方は挿し木が一般的です。時期は春から秋にかけて、4月~9月頃に枝を5~7センチくらいの長さに切って、バーミキュライトや小粒の赤玉土などの用土にさします。ちなみにバーミキュライトというのは土質改良土の一つです。主成分は黒雲母という鉱物で加熱し、膨張させて小粒状に砕いた土です。加熱した時にヒルのような動き方をすることから「ヒル石」とも呼ばれています。
このバーミキュライトはとても軽く、多孔質なので水分、養分の保持がとても優秀です。さらに粒と粒の間に隙間があるので、植物の根の呼吸も促進されるという利点もあります。人工的に焼成された清潔な無菌用土なので、挿し木にはとても適しています。害虫に関してですが暖かい時期(春~秋)には、ナメクジやヨトウムシの被害が報告されています。葉を食べてしまいます。また、8月~10月にはアブラムシが発生することもあります。
アブラムシは植物の樹液などを吸汁します。この吸汁で植物が萎れたり枯れたりすることはありません。しかしアブラムシは様々なウイルスを媒介する厄介な存在です。なお、ウイルスによる病害は一度かかると治すことはできません。アブラムシは幼虫も成虫も、植物の葉だけでなく、茎や花や実からも吸汁します。
窒素成分の多い肥料を与えると葉に大量のアミノ酸が生成されます。アブラムシはこのアミノ酸を好むので発生してしまうのは仕方が無いことです。まれにカイガラムシが発生する事例もあります。これらの害虫の駆除にはカルホスなどの薬剤が効果的です。
ルエリアの歴史
ルエリアはルエリア属キツネノマゴ科の多年草で生息地はアメリカ、アジア、南アフリカの熱帯地域などです。その名前は、フランスの植物学者ジャン・リュエルにちなんで名づけられたと伝えられています。花言葉は「正直」、「愛らしさ」、「勇気と力」などがあります。比較的小さな花をつけるその様子は「愛らしさ」そのもので、品種的に丈夫に育つためか、
力強く生育するところから「勇気と力」の花言葉が贈られたのが容易に推察できます。また、8月14日の誕生花でもあります。なお、この名の由来になったジャン・リュエルはなんと15世紀の植物学者で彼の著書「植物の本性について」は、図こそ入っていないものの、当時までに伝えられてきた植物書の学問的集約を行うことを意図して作成されたもので、
ヨーロッパにおける一般読者のために編纂された植物学の最初の著作に位置づけられています。「植物の本性について」には薬草の詳細はもちろん、産地やにおいや味までもが記述され、多くの植物に対応する仏語の呼称はこの本によってつけられました。これまでの先人の著作の翻訳・編集という要素はあるものの学問的な意義は極めて大きかったと言えます。
非常にたくさんの種類があり、それぞれ特徴があります。その数は150種類に上るとも言われ、色も開花時期もまちまちです。ただし共通して言えるのは原産地がペルー、エクアドル、コロンビア、ブラジルなどの南アメリカであること、比較的暖かい場所で良く育つことが挙げられます。
ルエリアの特徴
あまりにも種類が膨大であるため、一例としてルエリア・スクアロサを挙げますと花の径はだいたい3~4センチくらいで、花の色は青、または紫色です。花冠は筒状になっていて、先端は5つに裂けるようになっています。また、柳葉るいら草という別名を持っています。前述したとおり他にも様々な種類があるのですが、ほぼ全ての品種は寒さに弱く、摂氏10度以下の環境では生育が鈍ってしまいます。
そのため、冬場は可能であれば室内で育てた方が望ましいです。やはり、もともとが赤道に近い場所を原産にしているため、仕方が無いところでしょう。逆に言えば弱点はそのくらいで、後述しますが水遣りも一般的な観葉植物に与える量で充分ですし、特別な肥料も必要ありません。日なたでよく育ちますが半日陰のような場所でも大丈夫です。
何より花をつける期間が長いので必要最低限の世話をするだけで、ほぼ一年中、花を観賞することができます。特に育てやすく、花や葉が綺麗な種は観賞用によく栽培されています。一例を挙げるとルエリア・グラエキザンスは細長いラッパのような形の赤い花をつけます。温かい環境であれば、花が枯れることは無く、真っ赤な花が観賞用にとてもよく合います。
草丈はやや長めで50~60㎝ほどまで伸びます。丈夫でとても育てやすいので人気があります。赤だけでなく、紫の花をつける品種もあります。代表的な品種にルエリア・ツベローサがあります。また、ピンク色の花を付ける品種にルエリア・ロセア、青い花をつける品巣にルエリア・キリオサなどの品種があります。
-

-
ライラックの育て方
ライラックの特徴としてあるのはモクセイ科ハシドイ属の花となります。北海道で見られる事が多いことでもわかるように耐寒性があ...
-

-
熱帯スイレンの育て方
スイレンは18世紀以前から多くの人に愛されてきました。古代エジプトにおいては、太陽の象徴とされ大事にされていましたし、仏...
-

-
タカナ類の育て方
アブラナ科アブラナ属のタカナはからし菜の変種で原産、生息地は東南アジアと言われています。シルクロードを渡ってきたという説...
-

-
カミソニアの育て方
カミソニアとは北アメリカの西部を原産とする植物であり、62種類もの品種があります。アカバナ科ですが、開花後に枯れてしまう...
-

-
ウラシマソウの育て方
ウラシマソウ(浦島草)は、サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、日本原産の植物です。苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸...
-

-
イワレンゲの仲間の育て方
イワレンゲの仲間は、ツメレンゲやコモチレンゲなど、葉っぱが多肉状態で、サボテンと育て方と同じ配慮で育てれば、毎年美しい花...
-

-
アオキの育て方
庭木として重宝されているアオキは、日本の野山に自生している常緑低木です。寒さに強く日陰でも丈夫に育つうえ、光沢のある葉や...
-

-
トサミズキの育て方
トサミズキの生息地は、四国の高知県です。高知県(土佐)に自生することからトサミズキ(土佐水木)と呼ばれるようになりました...
-

-
キュウリの育て方
どうせガーデニングをするのであれば、収穫の楽しみを味わうことができる植物も植えたいと希望する人が少なくありません。キレイ...
-

-
エキナセアの育て方
宿根草ブームが巻き起こってから、すっかり宿根草の代表選手となった印象のあるエキナセアですが、古くは400年ほど前にアメリ...




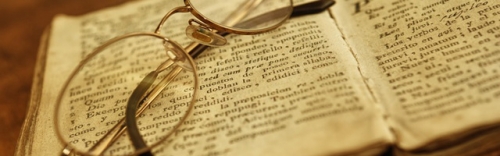





ルエリアはルエリア属キツネノマゴ科の多年草で生息地はアメリカ、アジア、南アフリカの熱帯地域などです。その名前は、フランスの植物学者ジャン・リュエルにちなんで名づけられたと伝えられています。花言葉は「正直」、「愛らしさ」、「勇気と力」などがあります。比較的小さな花をつけるその様子は「愛らしさ」そのもので、品種的に丈夫に育つためか、力強く生育するところから「勇気と力」の花言葉が贈られたのが容易に推察できます。また、8月14日の誕生花でもあります。