ディッキアの育て方

育てる環境について
最近の日本では、数年前から多肉植物が大きな話題となっていました。可愛らしいぷっくりとした緑色の健康そうな葉が、丸く楕円の形を帯びて実るのですから、短い花期をひっそりと終える花々よりも長く愛される傾向にあります。小さな植木鉢で簡単に手入れが出来るのもポイントが高いです。
ディッキアもまた、広く愛好家がいる多肉植物やオーストラリア産の植物同様、乾燥地帯に自生する種ですので、その育て方はいかに原産地特有の土質を再現してあげられるかが全てとなってきます。これらの種が長い間日本の園芸界に浸透してこなかった一番の理由が環境の違いです。
梅雨を含んだ高温多湿の季節をもつ日本では、予備知識無しではこれらの植物を十分に生育できません。山岳地帯に自生する種ですので、通常の多肉植物以上に通気性、水はけの良い土を割合に占めた植木鉢を用意してあげる必要性があります。通常の園芸では、直射日光を当てすぎるとすぐに花や茎が枯れてしまいますが、同種は日光に当てれば当てるほど強くガッシリとした成長を見せてくれます。
また、スコールが頻繁に起こる山岳地域での進化ということで、水を体内に蓄える力もあります。サボテンのような、水の与え過ぎによる根腐れを起こしてしまうといった失敗談が少ないのも魅力です。これらの観点からみて、ディッキアという種は、従来の外国産多肉植物のなかでも、比較的育てやすい部類に入ると考えられます。ただし、日照不足と湿気には十分気をつけてあげることです。
種付けや水やり、肥料について
ディッキアの生育において、よく話題になるのが活着の方法とその知識についてです。農業に適さない土壌、過酷な気候のなかでも太陽光と水さえあればガンガンと成長する頼もしい植物ですので、日本に輸入されてきた従来の多肉植物と比べ、本格的な活着も可能になります。時期は、冬場は避け、気温が20度を常に超えた暖かい季節が適切です。
株元をしっかりと洗い流し、古い組織を取り除いてあげます。コップに入れ、水を株部分にまでは浸からないよう気をつけて注ぎ入れます。水質が腐るのを防ぐため定期的に新しい水に入れ替えつつ、2週間から1ヶ月ほど様子を見てあげましょう。下から新しい根が降りてきたらその周りに水苔などをまいてあげ、適切な割合で作った用土が入った植木鉢に移し替えてあげましょう。
用土の割合は、ピートモス2~3、軽石2~3、腐葉土1などでも結構です。これは、オーストラリア産の低木植物の植木鉢での栽培時に使われる用土割合ですが、アロエ並みの生命力を持つディッキアですから、これよりももう少し栄養素が低く乾燥質な土壌をあてがってやっても構わないくらいです。
水は通常1ヶ月に一回ほどで十分ですし、少々水を与えすぎた所で根腐れを起こすこともありません。低気温の環境下でも節水状態さえ守ってあげれば問題なく育ちます。植木鉢の大きさに合わせた成長を見せてくれるので、ご自宅の庭やベランダの規格などに合わせた鉢選びから始めてみても面白いでしょう。
増やし方や害虫について
サボテンやアロエなどで有名な多肉栽培において、常に我々が意識しなければならない問題の一つに、軟腐病があります。水はけが上手くいかず、茎の芯の部分に古い水が残り続けた結果、それが腐り黒い点や白いシミなどが葉に目立つようになる状態です。こうなった場合、胴切りと呼ばれる色が変わった部分を刃物で削って、その傷口に殺菌剤を塗布しておく方法をとります。
成長点が異常をきたす場合が多いこの症状をどれだけ早期に改善できるかが、ディッキアの増やし方における一つのポイントといえます。害虫には比較的強い個体であるのですが、それでも虫が歯を噛んだその傷跡から細菌が入ることもあるため、殺虫剤の使用も前向きに検討するべきです。
生命力が強い種ですので、ある程度栽培を続けていると、親株のすぐ横から新しい株が生えてきます。これを独立させて活着、また新しい植木鉢に移してといった方法で少しずつ数を増やしていきましょう。太陽光と通気性を損なうと一気に水腐れや害虫を呼ぶ原因となりますので、特に梅雨時期などには植木鉢の下にスノコなどを引いて、
風の通り道を確保してあげることが重要です。定期的な水やりや防虫・防水対策を行い日光を確保してあげれば、夏場には綺麗な黄色やオレンジの色の花を咲かせてくれることもあるディッキア。上品な大人のオシャレさを醸し出す素敵な植物であるだけに、枯らすことなく長い年月に渡っての栽培を心がけていきたいところです。
ディッキアの歴史
まだまだ我々日本人にとって馴染み深いとは言えない植物、ディッキア。数多くの種を保有する植物群のなかでも、かなり特徴的な形状を持つこの多肉植物は、原産地を南アフリカ地域としており、高い気温での栽培が求められる植物です。日本語ではシマケンザン(縞剣山)とも呼称されるシャープな形状が昔から欧米諸国では大変な人気を誇っており、
最近では日本でも徐々にですがその魅力を広めつつあります。しかし、生息地がブラジル、アルゼンチンなどの山岳地帯であることから、まだまだ日本への輸入が本格化はされておりません。しかし、だからこそ今この時期にディッキアを先んじて入手しておくことで、これから日本国内にも訪れるブームを一足先に楽しむことができます。
このパイナップル科アナナス類常緑多年草は、普及率こそ低いものの日本でも熱狂的なファンを一定数獲得している非常に面白い植物であり、東京や大阪などでは展示会が開かれることも。多肉植物やオーストラリア産植物のブームに乗じて、サボテンやそれらサボテン科の草花に近しい珍しさをもつ植物を扱う店舗も増えてきました。
どれも手軽な大きさとお値段の植木鉢一つで栽培可能な植物であるため、生育も夢ではありません。酸素濃度も薄く、雨にも乏しい緯度の高い国の山岳地帯で独自進化を遂げてきた植物、英語でもブレード、刃の異名を一部含んでいる古くから人々に愛されてきたディッキア。これを期にどっぷりとその魅力にハマってみるのも悪くないかもしれません。
ディッキアの特徴
パイナップルといえばあの爽やかな甘みと噛み解していく繊維がもたらす歯ごたえが面白い果物ですが、しかしその外観は堅牢そのもの。果実部分も非常に硬質であり肉食獣の爪や犬歯も届きませんが、何よりも葉の部分が特徴的です。固く鋭いギザギザ部分があり、外敵から不用意に食べられることを回避するための独自進化を遂げています。
そんなパイナップル科に属するこのディッキアという植物は、正に外敵から身を守るためだけに存在するような自生する剣といえましょう。細長く成長する薄い多肉植物特有の葉の周囲を、いくつもの小さく鋭い刺が覆っています。色合いもシックなものが多数あり、ベランダに置くだけでさながら海外映画のワンシーンのような雰囲気を醸し出してくれます。
ディッキアのような低い位置に自生し強烈な刺をもつ植物の一番の被害者はチーターなどの肉食動物です。彼らは馬などの草食動物に比べ低い姿勢でかなりのスピードのダッシュを行うため、つい刺に目を刺され失明するといった自然界のハプニングも少なくはないといいます。
長年学者たちの間で議論されてきた自然動物の目のトラブルは、こういった自己防衛手段をもつ一部の植物が原因とされていたといいます。ディッキアは南アフリカ地域の山岳地帯に群生する植物ですが、やはり外敵から身を守るための武器を全身に備えた進化を遂げています。シンプルな見た目とその攻撃的な外観こそが同種の最大の魅力にして多くのファンを世界中に増やし続ける一番の理由です。
-

-
ヒョウタンの育て方
ひょうたんの歴史について、ご紹介したいと思います。ヒョウタンは本来中国原産の植物で、日本に入ってきたのは、奈良時代前期だ...
-

-
サンタンカの育て方
サンタンカは、アカネ科の植物で、別名ではイクソラとも呼ばれています。原産地は熱帯の各地です。サンタンカは、中国南部からマ...
-

-
カレックスの育て方
カレックスはカヤツリグサ科の植物の一つ属です。ですから一つの種を指すのではなく、実際には多くの種が含まれます。変異しやす...
-

-
スイートピーの育て方
スイートピーは西暦一六九五年に、カトリックの修道僧で植物学者でもあったフランシス・クパーニによってイタリアのシシリー島に...
-

-
ロニセラの育て方
ロニセラは北半球に広く分布するつる植物で、北アメリカの東部や南部が原産地です。初夏から秋まで長期間開花し、半常緑から常緑...
-

-
マネッティアの育て方
マネッティアの特長としては、花は濃いオレンジ色になっており強いオレンジ色というよりも、優しさにあふれる色になっているので...
-

-
コスモスの育て方
夏の終わりから秋になると可憐な花を咲かせるコスモスですが、もともとはメキシコ原産でキク科の植物です。メキシコ周辺には20...
-

-
ブルーファンフラワーの育て方
ブルーファンフラワーはクサトベラ科スカエボラ属で、別名はファンフラワーやスカエボラ、和名は末広草といいます。末広草と名付...
-

-
キンシウリの育て方
キンシウリは19世紀末期に中国、朝鮮半島から日本に伝わった覚糸ウリ(かくしうり)が訛って、呼び名がついたと言われています...
-

-
マツムシソウの育て方
マツムシソウは科名をマツムシソウ科と呼ばれており、原産地はヨーロッパを中心にアジア、アフリカもカバーしています。草丈は幅...




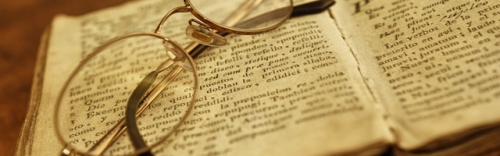





まだまだ我々日本人にとって馴染み深いとは言えない植物、ディッキア。数多くの種を保有する植物群のなかでも、かなり特徴的な形状を持つこの多肉植物は、原産地を南アフリカ地域としており、高い気温での栽培が求められる植物です。