オカワカメの育て方

オカワカメの育てる環境について
様々な健康効果を持つ野菜として重宝する事、夏場の太陽を遮り、部屋の中の温度を下げてくれる効果も有る事からも栽培をしてみたいと言う人も多いのですが、育て方のポイントとして栽培を行う環境にはオカワカメの生育を考える必要が有ります。
それは、オカワカメと言う植物はつる性の植物であり、背丈は3メートルにも及ぶと言う事です。建物に数本の支柱を立てて、そこにネットを張る事でツルはネットを伝わり上へと延びて行きまが、ネットを使わなくても支柱を立ててあげることでツルは支柱を伝って上へと延びて行きます。
尚、育てる環境については直射日光を遮るなどの目的で植える人もいることからも、日当たりが良い環境であり、風通しの良い場所を選ぶ事、そして注意したいのが水はけの良い場所を選ぶ事です。収穫時期と言うのは夏場が主体となりますが、6月の終わり頃から10月の半ば頃が収穫時期で、
収穫時期に葉腋についているムカゴを保管しておくことで翌年の栽培にも利用することが出来ます。これは翌年の大切な種としても利用することが出来ると言う事です。寒さについては一般的な植物と同じで強くはなく、冬場は地上部分は全て枯れてしまいます。
ですが、地下根茎については寒い時期でも生きているので、掘り起こして室内に取り込んであげたり、温暖な気候の地域では盛り土をおこなってあげたり、マルチングをしてあげることで越冬させることも出来ると言ったメリットも有るのです。
オカワカメの種付けや水やり、肥料について
マルチングは畑の表面を紙、プラスチックフィルムなどを利用して覆って上げることであり、冬場などに地下に埋まっている根茎を保存する場合などに利用すれば、翌年もそのまま栽培をする事も可能です。初めてオカワカメを栽培する時は苗を使うと便利です。
苗はホームセンターなどに置いてありますし、ホームセンターに無ければインターネットの通販サイトで入手が可能です。定植に適している時期と言うのは春から初夏にかけの5月の上旬から中旬にかけてとなり、苗を植え付けますが、苗は直接地植えをしても良いですし、
大型のプランターを用意してそこに植え付けても構いません。尚、植え付けを行う2週間ほど前に、1平米あたり100gの苦土石灰を土に混ぜておきます。そして、植え付けを行う時に完熟牛ふん堆肥を1平米あたり2kgと粒状肥料を100gを混ぜて土壌を作り上げます。
プランターを利用する場合は、市販されている野菜用の配合土を利用しますが、これに粒状肥料を1ℓ当たり4gの割合で混ぜてから植え付けを行います。苗を植える時の株間は20㎝程度開けることが大切で、大型のプランターであれば2~3株程を植える形になります。
また、大型のプランターを2つ並べる場合は、それぞれの端に植えた苗の間隔を20㎝以上離しておくことを忘れないようにします。尚、水やりについては表土が乾燥した時点でたっぷりと水やりをしてあげます。
また、プランターで栽培する場合は、粒上肥料を1ℓあたり5gの量を、月に1度の割合で、土の表面にばらまいてあげたり、液体肥料を1000倍に薄めて、週1度の水やり代わりにまいてあげます。
オカワカメの増やし方や害虫について
オカワカメは地植えとプランター栽培では肥料を上げるタイミングなどが異なりますが、地植えの場合は植え付け前に施す元肥や追肥として、粒状肥料を1㎡あたり30gを月に1度の割合で地面にばらまいて施してから土寄せを行う事が大切です。
プランターの場合は、粒状肥料用土をプランター1リットルあたり5gの量を、月に1度の割合で表面にばらいまいてあげるか、液体肥料を1000倍に薄めた液を作り、週1度の水やりの代わりとして与える事で成長を促すことが出来ます。
因みに、オカワカメは食材としても重宝するわけですが、収穫は7月から10月頃が旬であり、比較的若い葉を摘み取り料理に使う事で柔らかいオカワカメを料理に使うことが出来ます。尚、オカワカメは背丈が3メートルを超えるほどの成長を行う植物でもあり、
真っ直ぐ伸びる性質が在る事や枝分かれがしないので、若い苗の時に数回摘心を行っておいて、上方の節部分にあるわき芽が伸びるように促し、収穫する時は葉だけを摘んでしまうのではなく、草姿のバランスを考えてツルをある程度切り戻すよう心掛けることで緑のカーテンとしての役割を持たせることが出来ます。
また、増やし方のポイントとしては、さし芽、ムカゴを取って植えたり、地下の球根を分けてあげることで増やす事が可能になります。尚、害虫については殆ど影響を及ぼすものは有りませんが、アブラムシが発生するケースも有りますので、アブラムシが発生した時などは殺虫殺菌剤を散布して退治ます。
オカワカメの歴史
オカワカメと言うのは料理のレシピなどでもお馴染みの食材です。ワカメ名の付くことからも見た目がワカメに似ていたり、栽培する事で長い期間収穫が出来る事からも多くの人が栽培をして料理などのレシピに利用しています。
うどんの中にワカメを入れるようにオカワカメを利用したり、小松菜やホウレンソウのような胡麻和えにするなど、色々なレシピが在ります。尚、オカワカメの生息地と言うのはどになるのかなのですが、日本国内においては全国的な生息地を持ちます。
また、原産は何処になるのかなのですが、まず日本に伝来したのは中国であり、原産自体は熱帯アジアや熱帯アメリカなど熱帯地方に分布している事からも、生息地は熱帯の気候に属するエリアと言う事になります。
尚、オカワカメはアカザカズラ、ツルムラサキ科のつる性の多年草であり海草ではなく土の上に生息する植物です。オカワカメと聞いて海草とイメージする人もいるのですが、地下に球根を作って、葉腋にはムカゴと言う丸い形の球上のコブを作ります。
また、このムカゴは薬用に利用すると言われており、中国ではこれを薬用として利用しているのだと言います。熱帯アフリカ、熱帯アジアから中国に広まり、中国から長寿の薬草として日本に伝えられたと言う歴史が在ります。
長寿の薬草と言うプロフィールを持つと同時に、様々な健康効果が在る事や栄養価が高いなどの理由からも健康維持の目的で自宅の庭などで栽培をする人が増えているのです。
オカワカメの特徴
オカワカメは、長寿の薬草とも呼ばれている健康野菜です。漢字で書くと、「雲南百薬」となることからも、長寿の薬草、百薬と言った健康効果を持つ野菜です。尚、どのような健康効果が在るのかと言うと、オカワカメにはマグネシウム、カリウム、亜鉛、銅、葉酸、ビタミンAと言った成分が含まれています。
マグネシウムは糖尿病、狭心症、心筋梗塞、動脈硬化と言った予防効果を持ちます。カリウムは、骨粗鬆症、狭心症、高血圧、亜鉛は細胞の廊下を防いでくれたり、ガン化するのを防止する効果、そして味覚異常の予防などにも効果を持ちます。
葉酸は貧血、動悸や息切れ、皮膚に生じるシミなどの予防効果、銅は鉄分の吸収を高める効果やコレステロールや糖の代謝を促進する効果を持ち、抵抗力が低下してしまうなどの予防にも役立ちます。ビタミンAはメラニンの発生を抑制する効果を持ち、
シミやそばかすなどの予防効果、悪玉コレステロールの酸化を防止し、動脈硬化、ガン予防にも役立てることが出来ると言った様々な健康効果を期待出来ます。尚、オカワカメの葉と言うのは薄いのが特徴で、葉を切ると粘り気が在り、このヌルヌル感も健康に良いと言います。
最近は、オカワカメを緑のカーテンとして栽培する人も増えていると言いますが、緑のカーテンと言うのは窓の外側に緑を植えて直射日光を遮る効果を持つもので、一般的にはニガウリなどが有名ですが、オカワカメをこれの代用にする人も多くなっており、食材として利用出来ることからも2つのメリットを持つ植物として親しまれています。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オカヒジキの育て方
タイトル:オカノリの育て方
-

-
植物の育て方を押さえてオリジナルな庭づくりを楽しみましょう
最近では、様々な所でガーデニングなどの園芸講座が開かれています。自分オリジナルな庭を作ることが出来るため、一つの趣味とし...
-

-
オリヅルランの育て方
オリヅルランはユリ科オリヅルラン属の常緑多年草で、初心者にも手軽に育てられるため観葉植物として高い人気を誇っています。生...
-

-
ネギとミツバの栽培方法
ネギは中央アジア原産のユリ科の多年草で、白ネギ(長ネギ)と青ネギ(葉ネギ)・ワケギに大きく分かれており、古くから薬味とし...
-

-
ルナリアの育て方
別名にゴウダソウやギンセンソウの名を持つルナリアは、学名Lunariaannuaで他にマネープラントという名を持つ二年草...
-

-
ルピナスの育て方
特徴の1つは寒さに強く、暑さに弱い事があります。具体的には寒さであればマイナス5℃程度まで耐えられます。外に置いておいて...
-

-
ハッカクレンの育て方
ハッカクレンは、メギ科の多年草となっています。原産地は中国となっており、古くから薬用植物として珍重されてきたという歴史が...
-

-
トマトの育て方
トマトは和・洋・中のあらゆる料理に使用され、生でも加熱しても使用される万能野菜です。またその栄養価も非常に高い野菜でもあ...
-

-
イクソーラ・コキネアの育て方
この花の特徴は何といっても花です。アジサイのように小さな花が密集してひとつの花のように見えるところです。細かいことを言う...
-

-
アッケシソウ(シーアスパラガス)の育て方
アッケシソウはシーアスパラガスと呼ばれているプラントであり、国内総生産第一位の国が属している地帯などの寒帯の地域を生息地...
-

-
たまねぎと夏野菜の育て方
たまねぎは秋に植えて、春に収穫します。一方、夏野菜は春に植えて夏に収穫します。畑を作るときには、この春野菜と夏野菜を両方...




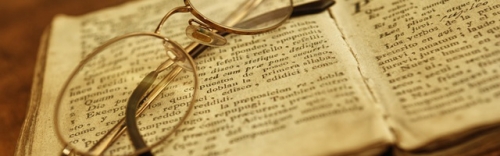





オカワカメと言うのは料理のレシピなどでもお馴染みの食材です。ワカメ名の付くことからも見た目がワカメに似ていたり、栽培する事で長い期間収穫が出来る事からも多くの人が栽培をして料理などのレシピに利用しています。