アメリカハナミズキの育て方

育てる環境について
アメリカハナミズキの育て方としては、次のような点に注意することです。すなわち、日頃の手入れと安置環境の2つです。若い木の場合は、枝もよく伸びますが、長く伸びすぎた枝はきちんと切り落とすことが重要です。それというのも、いくら日当たりの良いところに植えていても、長く伸びすぎると、日陰になっているところにまで伸びます。
そうなると、枝に十分な栄養が行き渡らず、細長くなってしまいます。そのため、日頃から枝の長さには注意しておく必要があります。また、秋から冬にかけては、落葉してしまった枝はきちんと切り落としましょう。枝を切る際の注意としては、枝分かれしている付け根のあたりを切ることです。枝先に花芽ができるので、この点はきちんと確認した上で切り落としてください。
このような管理は3年くらいまでは続ける必要があります。3年も経てば小枝は勝手に落ちるようになります。また、置き場所としては、日当たりの良いところを好みます。そのため、日当たりが良くて風通しのよいところに植えてあげてください。しかしながら、年中、直射日光が照りつける場所は避けてください。それというのも、あまり直射日光には強くないからです。
特に、真夏になると、ずっと直射日光があたるようだと、株元が乾燥しすぎてきて弱ってしまうことがあるからです。したがって、半日陰になるようなところがもっとも適しています。もし、すでに植えてしまったのであれば、真夏になったら株元にワラを敷いてあげてください。これで乾燥を防ぎます。冬になったら、耐寒性が非常に強いので、放置しておいても大丈夫です。
種付けや水やり、肥料について
栽培方法としては、どのようなものがあるかというと、次のようなものがあります。つまり、種付け、水やり、肥料の観点から書いていきます。水やりについては、土の表面において乾燥してきたら、たっぷりと水を与えます。水切れが続くと、弱くなってしまいます。特に真夏の時期においては、乾燥状態が続くと、葉が落ちます。
真夏は継続的に水を与えましょう。冬は乾燥気味で問題ありません。むしろ、休眠活動に入っているので、水やりは控えたほうが良いでしょう。肥料については、与える時期が重要になってきます。2月頃と真夏の8月頃に与えると良いです。それでは、どのような肥料が良いのかというと、油かすと骨粉を混ぜたものを与えてあげてください。
比率は半々くらいでかまいません。株元の土を掘ってたっぷりと埋めてあげてください。そうすると、非常に大きく生長します。ちなみに、用土については、水かけの良い用土を利用してください。水はけの良い用土が手に入らなかったら、川砂を少し混ぜておくと良いです。水はけがよくなります。
ホームセンターにも用土はいくらでも売っていますので、こうした心配はあまり要りませんが、品数が少なかったら、どこにでも販売している腐葉土を使用しても問題ありません。種付けについては、自然に任せておくのがベストです。時期になったら種ができますので、それを採取しましょう。変わったことをすると、樹木に悪影響を与えてしまいます。
増やし方や害虫について
アメリカハナミズキの増やし方についてですが、これは3つあります。すなわち、種まき、接ぎ木、さし木の3つです。種まきについては、秋になると果実をつけますので、その果実の果肉の部分を丁寧に取り除きます。このとき、荒っぽくすると種に傷つけてしまうので、注意が必要です。そうして、種子を取ったら、水で洗って冷蔵庫に保管します。
なぜ冷蔵庫で保管するのかというと、秋頃に植えてもあまりすくすくと成長しないからです。2月頃に撒くのがもっとも適しているので、その季節になるまで、保管しておく必要があるということです。そうして、2月になったら、水はけのよい用土に撒いてあげてください。次に、接ぎ木についてです。これも種撒きと同様に、時期が重要です。
接ぎ木の時期としては3月頃がベストです。ここでも注意が必要です。接ぎ木を行った株は乾燥に弱いので、しっかりと腐葉土や用土を用いて覆ってあげてください。これで乾燥は防止できます。これらがアメリカハナミズキの一般的な増やし方です。最後に、さし木についてですが、これは比較的新しく出てきた枝を7センチから8センチ程度に切り落として用土に挿します。
これで終わりです。また、害虫対策としては、アメリカハナミズキに被害を与える害虫はテッポウムシが挙げられます。これはゴマダラカミキリの幼虫のことですが、幹の内部で内部を食べてしまいます。発見の仕方としては、穴がないかを確認します。その穴が侵入口なので、その穴に向かって殺虫剤を吹きかけます。もしくは穴にふたをします。これで駆除できます。
アメリカハナミズキの歴史
アメリカハナミズキの歴史について言及していきます。まず、このアメリカハナミズキは原産地が、その名前からわかるとおり、アメリカです。アメリカに広く分布している植物で、メキシコの一部にも生息しています。つまり、日本ではないということです。それでは、いつ日本にきたのかというと、明治時代に日本に渡来したと言われています。
明治45年の1912年頃に日本の東京がアメリカのワシントンに桜を贈ったのですが、その返礼としてはアメリカからアメリカハナミズキが贈られてきました。もちろん、それ以前から日本でもあったみたいですが、正式の記録としては1912年に日本に渡来したことになっています。今では、日本に渡来したアメリカの代表的な植物として有名で、日本でもなじみの深い植物になっています。
ちなみに、この名前の由来ですが、アメリカ原産ということから、アメリカという名称が付いていますが、ハナミズキについてはあまり知られていません。このハナミズキという名称は、花のきれいなミズキという意味で付けられました。別名としてアメリカヤマボウシという名前ももっています。
こちらのヤマボウシは、日本にも分布している植物ですが、花の姿が非常に似ているということからこの別名が付けられました。英名はドッグウッドと言います。この名前の由来は、昔は犬の皮膚病の治療薬として用いられたからです。そのため、ドッグという名称が付いているわけです。
アメリカハナミズキの特徴
アメリカハナミズキの特徴はどのようなものなのか書いていきます。アメリカを代表する花木で原産地はアメリカです。春になったら、枝にたくさんの花を咲かせます。この花びらは厳密には葉っぱなのですが、非常にかわいらしい花で非常に人気があります。花の色は基本的には白ですが、他にいろいろな色があります。ピンクなどもあります。
開花後の秋になると、小さな実をつけます。色は赤色です。晩秋になると、紅葉になって落葉します。そのあと、冬になると、休眠活動に入ります。そうして、春になったら新芽を出して夏までが生育期になります。これが繰り返されるわけです。樹の高さは4メートルにまでなりますが、高いにものになると、10メートルにまで達します。
これは非常に高いです。日本の家庭でも人気のある花木でよく目にします。日本での生息地としては、北海道から始まって本州にかけて広く分布しています。しかしながら、沖縄や九州などでは生息はあまりしていません。これは、比較的年中暖かいところだとなかなか生育がうまくいかないからです。
それというのも、この植物は冬の時期はしっかりと休眠しないと、生育しない性質を持っているからです。そのため、年中比較的暖かい九州、沖縄ときには四国では休眠活動が妨げられて生育不十分になってしまいます。反対に、北海道の北部では、寒さが非常に厳しいため、生育期になかなか生長できないため、その地域でも栽培は難しいです。
-

-
エゾミソハギの育て方
エゾミソハギの特徴について言及していきます。原産地はヨーロッパを中心に日本各地です。生息地としては、北海道と九州上部です...
-

-
ダンギクの育て方
中国や朝鮮半島、台湾、日本が原産地となるダンギクは、30センチから80センチほどになる山野草です。日本では九州や対馬地方...
-

-
ミラクルフルーツの育て方
小さな赤い果実のミラクルフルーツは、あまり甘くなく、食した後、しばらくは、酸味のあるものを食べると、甘く感じ、とてもおい...
-

-
カレックスの育て方
カレックスはカヤツリグサ科の植物の一つ属です。ですから一つの種を指すのではなく、実際には多くの種が含まれます。変異しやす...
-

-
カガブタの育て方
この植物は、ミツガシワ科アサザ属の多年草ということで、湖沼やため池などにみられる水草ですが、原産地及び生息地はアジア、ア...
-

-
ラッセリアの育て方
この花については、オオバコ科、ハナチョウジ属とされています。科としてはゴマノハグサ科に分類されることもあるようです。原産...
-

-
初心者からはじめるミニ盆栽の育て方
少し前に流行ったミニ盆栽。若者にもひそかに人気があります。盆栽はなんといっても風格があります。3000円くらいから1万円...
-

-
ヒトツバタゴの育て方
20万年前の近畿地方の地層から、泥炭化されたヒトツバタゴがみつかっています。しかし、現在の日本でヒトツバタゴが自生するの...
-

-
クランベリーの育て方
クランベリーという洒落たネーミングは、可愛らしい花びらの形状を見て、鶴の頭部と同じようなイメージであることから付けられた...
-

-
チューベローズの育て方
チューベローズはリュウゼツラン科であり学名をポリアンテスツベロサと言い、球根に由来するラテン語となる塊茎状のツベロサの意...




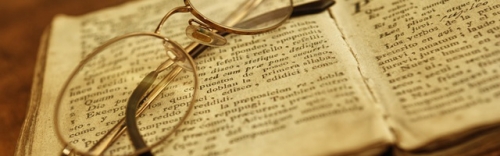




アメリカハナミズキの歴史について言及していきます。まず、このアメリカハナミズキは原産地が、その名前からわかるとおり、アメリカです。アメリカに広く分布している植物で、メキシコの一部にも生息しています。つまり、日本ではないということです。それでは、いつ日本にきたのかというと、明治時代に日本に渡来したと言われています。