ヒメヒオウギの育て方

ヒメヒオウギの育てる環境について
育てる環境として確認しておくべきとなるのはまず種をまく時期ですが、これは10月ごろから2月までがベストな時期であると言えます。冬場に雪が積もるような地域だと庭撒きは難しくなりますが、そうではない地域であれば庭撒きをしても問題なく次の春までに発芽することができます。
この際にはなるべく日当たりが良く、冬場でも凍結しないような場所を選ぶようにしましょう。もし凍結しそうな地域であるのであれば庭には植えないようにするか、藁などで霜よけをすることが必要です。そうではない地域、例えば東北以北などの地域では基本的に鉢植えになりますが、
その場合は2月から3月の間に準備し、春になるまでは室内で生育させるようにすると良いでしょう。日当たりが少ない場所や、やや寒冷になる場所であっても花を咲かせることは出来ますが、そうした環境で育てた場合には咲く花の量がかなり少なくなってしまいます。
そのため庭ではそうした環境が用意できないという場合には、鉢に植えて状況に合わせて動かせるようにしておく方が無難です。ヒメヒオウギは花の量が少なくとも美しい花ではありますが、しっかり育てればそれだけ多くの花を付けて目を楽しませてくれるだけに、
庭の中などであっても生育に適した地域を選ぶようにした方が良いでしょう。土としては水はけが良ければどのようなものでも構いませんが、ホームセンターなどで販売されている培養土や赤玉土と腐葉土の混合土を利用するとよく育ちます。
種付けや水やり、肥料について
育て方として、まず種付けの時期は寒冷地域では2月から3月などの雪が溶けたあと、そうではない地域では10月から2月の間に行うのが基本です。寒冷地域で冬場に準備して庭で咲かせたいという場合には、最初の段階は鉢で育てて、雪が溶けて温かくなってから庭に植えかえをするというような形でも対応することが可能です。
幸いヒメヒオウギは頑丈な性質を有していますから、そうした方法であってもしっかり行えば問題なく開花してくれることでしょう。水やりは3月から5月にかけて、土の表面が乾いたらたっぷりとあげるようにするのが基本です。ただ開花後はそこまで水が必要になることはありませんから、
よほど雨が降らずに感想が続いているというような場合を除けば水やりは行わなくてもよいでしょう。花が咲き終わった休眠期に水をやる必要はありませんが、雨が降ったとしても特に気にする必要はありません。この時期に行うべき手入れは特にないのです。
肥料に関しても特に必要はなく、何度もこまめにあげるというようなことは行わなくてもかまいません。むしろ開花を迎えるまでに肥料をあげすぎるとそれが原因となって弱ることがありますから、注意が必要です。ただ3~4月ごろの成長期に関しては薄めた肥料を少しあげると、
より花が多く、美しく咲くようになりますから、バランスを判断できるのであればこのタイミングで肥料をあげると良いでしょう。また、もし株分けをして増やすことを考えているのであれば花が落ちた後で液体肥料を与えて株を肥培するようにしましょう。
増やし方や害虫について
ヒメヒオウギは繁殖力に優れているため分球で容易に増やすことができます。特に自然分球の形でも増えていきますから、よほど繁殖力が強い植物が近くにない限り、増やさないようにする方が難しいでしょう。また分球のほか、種からの発芽も可能となりますから、
花から種を回収して増やしたい場所に撒くことで、容易に増やすことができます。このことからヒメヒオウギを増やすことは簡単であると言えるのですが、しっかりと庭を管理したい場合だと、こぼれ種が原因となって意図しない繁殖が発生することがありますから、
開花期を終えたあとの花がらは早めに摘み取っておくことが必要です。次に害虫・病気に対してですが、これも高い耐久性があるためにさほど心配する必要はありません。病気に関してはほとんど見られることもありませんから、特に心配はいらないでしょう。
しかし害虫に関してはアブラムシがつくことがあり、放置しているとアブラムシによる被害が出ることもあります。アブラムシ以外の虫害はほとんど見られませんが、アブラムシが繁殖すると外見を損なううえに他の植物への被害拡大も考えられますから、見つけ次第防除することが必要です。
アブラムシの防除にはいくつかの方法がありますが、最も手軽なのは殺虫剤を利用する方法でしょう。ホームセンターなどに行くとアブラムシを対象とした殺虫剤が多く販売されていますから、長く効果が続く浸透移行性剤を選んで使用することで大半の被害を防ぐことができます。
ヒメヒオウギの歴史
現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書きますが、その名前にふさわしい赤色の花を咲かせることで有名です。品種によっては必ずしも赤色ではないこともありますが、多くの場合は花びらの根元に赤い色が入っています。
現在では庭先などはもちろんのこと、地域によっては山野や道路沿いなどでも広く見ることができますが、歴史的に見るとそこまで古くから日本にあるというわけではありません。このヒメヒオウギが初めて日本国内に入ってきたのは大正期とされており、主に観賞用として輸入されてきました。
ただ性質として耐寒性にやや優れていること、繁殖力に優れていることがあり、観賞用として持ち込まれたものが種子などによって自然界に移動し、そこで繁殖したのです。こうした輸入されてきた観葉植物が自然の中で繁殖するということは珍しくなく、日本国内では珍しくない野草になりました。
ただ佐賀県ではヒメヒオウギが自然界で繁殖し、生態系を破壊することを危惧して栽培が禁止されていますので、佐賀県やそもそも越冬することができない寒冷地帯などではあまり見ることがありません。ヒメヒオウギは現在、フリージアの仲間であるとされていますが、
かつてはラペイロウジア、もしくはアノマテカの仲間とされていたこともありますから、古い植物の本などだと現在とは分類が異なっていることもあります。ですが現在ではフリージアの仲間として世界的に扱われるようになっていますから、間違えないようにしましょう。
ヒメヒオウギの特徴
花としての特徴は目立つ赤色の花の色です。品種や個体によって色合いには違いがありますが、ヒメヒオウギの開花期である5月などの春になると、自然の中で力強く咲く赤い花を見ることができます。また地域によってはヒメヒオウギを庭に植えていることも多く、春という季節の彩りとして愛好されています。
植物としての特徴にはいくつかありますが、観賞用としてはかなり頑丈な性質を有していることが大きな特徴であると言えるでしょう。特にある程度の耐寒性があるため、冬になっても雪が積もらないような地域であれば、こぼれた種から発芽して花を咲かせることもあります。
南アフリカ原産の植物であるクロコスミア・オーレアとクロコスミア・ポッシーという二つの植物を両親に持って交配されて生まれた植物ではありますが日本国内の関東以西の地域であれば人が手を加えなくとも越冬して春に花を咲かせることができますから、
このことは植物としても非常に頑強であると言えるでしょう。さらに驚くべきと言えるのが、繁殖する土地を選ばないことです。荒れ地で花を咲かせたかと思えば湿地帯でも問題なく開花し、また日当たりの良い地域、日当たりの悪い地域を問わずに生育することができます。
そのため全世界を生息地として野生化しており、世界的に見ることができる花となっています。ただこの点は山野に種子を捨てるとそれだけで繁殖してしまうリスクを持っているということでもありますから、栽培後、種などを処分する際には責任を持って処分するようにしてください。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クロコスミアの育て方
タイトル:フヨウの育て方
タイトル:ヒメリュウキンカの育て方
-

-
ムクゲの育て方
ムクゲはインドや中国原産とされる落葉樹です。生息地は広く、中近東になどにも分布しています。韓国の国花として知られています...
-

-
オオアラセイトウの育て方
オオアラセイトウは別名ショカツサイとも言われる中国原産のアブラナ科の植物です。紫色が美しい小花はその昔三国志で有名な軍師...
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...
-

-
芝桜の育て方
たくさん増えると小さな花がまるで絨毯のように見えることから公園などにも植えられることが多い芝桜は北アメリカ東海岸が原産で...
-

-
エンドウとツルレイシの栽培と種まき時期
エンドウの原産地は、エチオピアから中央アジアや中近東でさやを食べるサヤエンドウと、若い子実を食べるグリーンピースがありま...
-

-
落花生の育て方
落花生は、豆科植物で生息地は、南アメリカ・アンデス山脈の東側が原産といわれています。ここから南米各地に広まりコロンブスの...
-

-
ニューサイランの育て方
ニューサイランはニュージーランドを原産地としている植物であり、多年草に分類されています。ニューサイランはキジカクシ科、フ...
-

-
人参の育て方
原産地はアフガニスタンで、ヒンズークシーという山のふもとで栽培されたのが始まりだといわれています。古代ギリシャでは薬用と...
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...
-

-
ニオイスミレ(スイートバイオレット)の育て方
ニオイスミレは、別名でスイートバイオレットとも呼ばれています。スミレ科のスミレ属に属しています。耐寒性多年草で、原産地は...




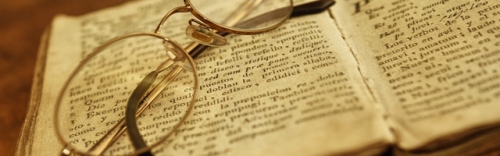





現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書きますが、その名前にふさわしい赤色の花を咲かせることで有名です。