ワケギの育て方

ワケギの基本的な育て方と土づくり
ワケギは、栄養価が高く薬味として人気のある野菜ですが手間がかからずプランターなどで手軽に育てることができる野菜です。野菜作りに、種付けせずに球根から育てますので、慣れていない人でも簡単に育てて、収穫が楽しめます。植え付けて1か月ほどもすれば摘み取って料理に使うことができますので、ちょっとした自給自足気分を味わえます。
育て方のポイントとしては、普通に育てるのであれば全国各地、殆どの土地で栽培することができます。ワケギの育成に適した温度は16~18℃ですので秋から春に育成して、夏は休眠することになります。ワケギは花が咲きませんので種はありません。ですので種付けをして育てるのではなく球根を植え付けての栽培となります。
また、種を作らない分種付けする必要はなく、球根を休眠状態で保存することで翌年また植え替えることができ、球根を分けていくことでどんどん増やすことができます。
このようなポイントを念頭に置いた育て方をします。種がないため種付けはできませんので球根を手に入れます。
栽培をされている方がいれば分けてもらうか、休眠が終わる8月頃にはホームセンターや園芸店で販売されてますので充実したよい球根を選んで購入します。球根は外皮がついたままですと根が出てくるのが遅れてしまいますので外側の皮を取り除きます。そのうえで2~3球程に分けておきます。そして植え付ける前には水を吸って発芽しやすくなるように球根の頭の部分を1/4ほど切り取っておきます。
畑は、日当たりのよい水はけのよい場所を選びます。植え付ける2週間ほど前に苦土石灰を施してよく耕しておきます。更に1週間前には、堆肥や化成肥料を元肥として施し耕します。その後1週間ほど土を落ち着かせるため間を置きます。植え付ける場所に浅いまき溝を作り、その溝に球根を植え付けます。球根の間隔は10~20㎝程取り、球根の先が少し見えるくらいの状態で土をかけます。
この時、深く植えないように気を付けましょう。プランターでの栽培は、赤玉土、腐葉土をそれぞれ7:3の割合で混ぜてこれを用度とします。土には堆肥や化成肥料の元肥を混ぜ込んでおきます。プランターの場合は面積が狭いので球根の間隔は5㎝程度で構いません。この場合も球根の上部が見えるくらいに浅く植え付けます。
植え付け後の育て方
植え付け後は水が不足すると生育が悪くなってしまいますので水やりには注意が必要です。8月に植え付けですから生育期がまだまだ高温であるため土壌が乾燥しやすいため定期的に水を与えてやるようにして乾燥しないようにします。葉丈が10㎝ほどになったら1回目の追肥を行います。この時、雑草があれば除草し土寄せを行っておきます。
その後は様子を見ながら2週間ほどの間隔を目安に追肥、土寄せを行います。ワケギによく見られる病気は「白色疫病」や「べと病」が発生しますので、畑の水はけが悪くならないように管理し冠水や乾燥あるいは追肥の過多や不足などの育成の妨げになるような原因を作らな異様にします。株を丈夫に育てることが病気の一番の予防となります。
また、発生しやすい害虫にはネダニ類やネギアザミウマといったものがいます。対策としてはマルチやシルバーテープなどを利用し、発生しやすい土壌である場合は植え付けの前に薬剤などを散布しておくといった対策法があります。
収穫と掘り下げ
草丈が30㎝程になったものから収穫します。収穫時期が早すぎると葉が密になっておらず、収穫量が減りますし、遅すぎると株元が肥大しすぎて質が悪くなってしまします。収穫方法は株元から4~5㎝の場所を刈り取って収穫します。この時、地面に近い場所で刈り取ってしまうと次に生えてくる葉の伸びが悪くなってしまいますので注意します。
収穫しても追肥を行います。そして、葉が伸びてきたら再び収穫することができます。このように繰り返し刈り取って収穫することができます。また、球根ごと抜いて収穫してもかまいません。収穫後翌年も植え替えて栽培をしたい場合は球根を保存しておいて翌年植え付けをして同じように栽培することができます。
育てた球根を保存することでまた買いなおす必要がありませんし、保存して植え付けることも試してみて損はないでしょう。タネ球として残す株は、収穫はほどほどにして放置しておくと5月頃には球根が肥大して、葉も倒れてしまいます。葉が倒れて黄色くなって枯れてきた状態が休眠状態に入ったサインですのでこの時期を見逃さないように掘り上げます。
この、掘り上げが早いと腐ったり乾燥に耐えられず干からびたりしてしまいますのでタイミングを逃さないようにします。引き抜いた球根は土をよく払って、風通しのよい日の当たらない場所で乾かして保存しておきます。
この時乾燥が不十分ですとカビが発生してしまいますので十分に乾燥しておきます。このようにして、栽培を続けているとどんどん増えてしまい食べきれなくなってしまうこともあります。個人で食べる分だけでよい場合はかえってプランターで栽培したほうが便利でしょう。
ワケギの歴史
原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地であるとする説など様々な説が混在しており、はっきりしていません。日本へは5世紀ごろに伝わったとされています。ワケギは玉ねぎとネギの雑種でありネギ属に属しています。
日本では、広島県尾道市の特産で出荷量も日本全国で1位となっています。県の南に位置する三原市や尾道市は、古くからのワケギの産地として有名です。気候も温暖で冬でもそれほど冷え込むことがなく、栽培に適しており,柔らかく上質な品質のワケギを生産しています。
大正の終わりごろには、すでに産地として成り立っていましたがその後の戦争によって野菜の統制が行われ、戦時統制のため主食になりえる麦やサツマイモなどへの転換を余儀なくされました。このためワケギの生産は一時影をひそめることになります。しかし、昭和24年に野菜の統制が撤廃されると、すぐに栽培が再開することになり、昭和30年には早出し栽培,という技術が確立され年に2回の生産に成功しました。
ワケギの特徴
ワケギは種からではなく球根で増やしていくタイプの野菜です。ですので一般的なネギより根の部分が少し膨らんでいます。葉ネギと同じように、主に緑色の葉の部分を収穫する野菜です。名前の由来は漢字で書くと「分葱」と書き植え付けた球根からいくつかに分けつすることからその名前が付けられたと言われています。
味は、他のネギと比べると癖がなく、香りもそれほど強くなくまた、辛味も少なく多少甘味もあります。この味の特徴を生かした料理に「ぬた」と呼ばれるものがあります。
栽培は簡単で収穫も数回行うことが出来るため、野菜作りに慣れない人でも簡単に育てて収穫を楽しむことが出来ます。
旬は、3月から4月の春が一番おいしく栄養価が高いと言われています。ワケギに含まれる栄養素はベータカロチンとビタミンC が特に豊富に含まれており、その他にはカリウム、鉄そして食物繊維も含まれています。このベータカロチンは活性酸素を抑える働きがあり活性酸素によってもたらされる癌などの病気を予防してくれます。
同じく活性酸素によって促進される細胞の老化を遅らせ皮膚や目の健康を保つ働きもあります。ビタミンC においては、免疫力を高め風邪を予防したり、美肌効果もありベータカロチンと合わせてアンチエイジングの効果も期待できます。また、カリウムは取りすぎた塩分を体外に排出する働きがあり高血圧に伴う政治病の予防に一役買ってくれます。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
にらの育て方
長ねぎの育て方
-

-
ギンリョウソウの育て方
ショウゾウソウ科の多年草ですが、新エングラー体系ではイチヤクソウ科、APG分類体系ではツツジ科に分類されています。属名の...
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
アボカドの種を植えて観葉植物にしよう
アボカドというと、「森のバター」や「バターフルーツ」と呼ばれ、高脂肪で栄養価が高いことで有名です。脂肪分の80%以上が不...
-

-
マンゴーの育て方
マンゴーは、ウルシ科のマンゴー属になります。マンゴーの利用ということでは、熟した果実を切って生のまま食べるということで、...
-

-
プリムラ・ポリアンサの育て方
プリムラ・ポリアンサは、ヨーロッパを原産でクリンザクラとも呼ばれています。17世紀には、プリムラの野生種から幾つかの品種...
-

-
オルレアの育て方
オルレア(オルラヤ)は、ヨーロッパ原産のセリ科の一年草です。日本でのオルレアの栽培の歴史はまだ浅いですが、最近、急激に庭...
-

-
アカンサスの育て方
アカンサスはキツネノマゴ科アカンサス属またはハアザミ属の植物で、別名をギザギザの葉がアザミの葉に似ていることから和名を葉...
-

-
ウコンの育て方
ウコンという名前は知っているものの、現在では加工されて販売されていることがほとんどのため、実際にはどのような植物であるか...
-

-
デイジーの育て方
デイジーの原産地は地中海沿岸部と北アフリカです。原産地やヨーロッパなどでは多年草と扱われていますが、日本では夏越えが厳し...
-

-
様々な植物の育て方の違いを知る
生き物を育てる事は、人間にとって大切な時間をもつ事でもあり、自然と癒しの時間になっている場合もあります。




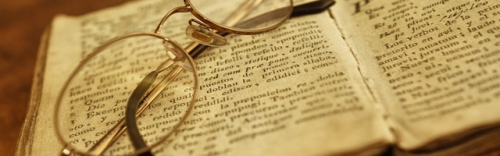





原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地であるとする説など様々な説が混在しており、はっきりしていません。日本へは5世紀ごろに伝わったとされています。ワケギは玉ねぎとネギの雑種でありネギ属に属しています。