ナンブイヌナズナの育て方

育てる環境について
ナンブイヌナズナの育て方はやや難しいです。元々平地で生息していた植物ではなくて、特定の地域のみ分布する植物ですから、簡単ではありません。まず、日当たりの良い場所を選ぶ必要があります。それとともに、風通しの良い場所を選びましょう。
雨が長く続くと弱る可能性があります。梅雨の時期には直接雨が当たらないように、屋根のあるところで栽培するのが良いです。夏になると暑さが厳しくなることもあります。あまりにも日差しが強いときに直射日光が当たると弱ってしまう可能性があります。
高温多湿になった場合には、風通しを良くするのは良い方法ですし、30%くらいの遮光をすると良いです。冬の寒さにはある程度は強いですが、風が強いところでは芽が乾くために痛む可能性があります。暖かい場所におく必要はありませんが、風の当たらないハウスに取り込んだ方が賢明です。
土壌が多湿になるのを嫌いますから、鉢は通気性の良いもので水はけの良いものを選んだ方が良いです。鉢穴が大きめの焼き締め鉢を用いるのが良いです。軽石の鉢に植えるのも良いです。水はけとともに保水性もある程度は必要となりますから、堅めのものと柔らかめのものの両方を配合すると良いです。
根が多湿になることによって色々な病気になることがありますから、水はけには特に注意する必要があります。風通しを確保するためには色々な工夫が必要ですが、園芸棚においておくと簡単に風通しを確保できます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けるのは春の花が咲いた後の4月中旬から5月初旬くらい、もしくは9月中旬から10月初旬が適しています。根の先を少しカットして根を広げるます。こうすることによって用土を入れやすくなります。少し上M気味に行うのが良いでしょう。そのタイミングですが、
植え替えは毎年、もしくは2年に1回くらい行います。水やりについては、1日に1回で良いでしょう。春や夏は朝にやると良いですが、昼は夕方か寄るが良いです。夏の暑い時期には値が高温多湿になることが多く、これが影響して育ちが悪くなることがあります。
昼間の暑い時間単に多湿にならないようにするためには、日が暮れて少し涼しくなってから水やりをするほうが良いです。また、夏は活動を休止していることが多いですから、暑くなりすぎたときには水を控えた方が良いでしょう。冬は控えめにした方が良いですが、
乾きすぎないようにしなければなりません。表面の土が乾いたらみずやりをするというくらいで、乾ききらないようにするくらいがちょうど良いです。冬は水をやりすぎるとダメです。肥料をやる時期は2回あって、一つ目が4月下旬から6月下旬までで、
二つ目が秋の9月下旬から11月上旬です。一つ目は花が終わってからの成長のためで、二つ目は休眠前のエネルギーの貯蓄のためです。肥料をおくのは春と秋に1回ずつくらいで良く、液体肥料は2週間に1回くらいおくと良いです。夏の暑い時期には活動を停止して休眠します。
増やし方や害虫について
ナンブイヌナズナは株分けと種まきとで増やします。株分けは、植え替えの祭に行えば良いでしょう。株が大きくなって手で分けられるくらいがちょうど良いです。あまりにも細かくすると成長できなかったり、あるいは成長に時間がかかったりしますから、
少し大きめに分けることを心がけるべきでしょう。芽の数は一つではなく、3つくらいはあった方が良いです。また、根もたくさんついているような状態になるのがベストです。タネで増やすためには、まずタネを採取しなければなりません。花が咲いた後に、
そのままにしておくと果実が茶色くなってきます。茶色くなった状態になると採取できます。そのまま蒔いても良いですが、タネができた直後には発芽しませんから、しばらく保管しておくのも良いです。保管しておいたタネは3月頃にまいておきます。
種を蒔くと2週間から1ヶ月くらいで発芽します。その年の内に開花するものもあれば、翌年にならないと開花しないものもあります。開花してそのままにしておくとタネができますが、このタネをすぐに蒔いても発芽します。ナンブイヌナズナは、どちらかというと病気や害虫には弱い傾向があります。
特に、根が傷むことが多いです。高温や多湿になると根が傷むことが多いですから、根が高温多湿にならないように注意が必要です。病気ではありませんが、根の生長が早いですから根詰まりにも注意が必要です。虫としてはとにかくアブラムシがつきやすいですから、早めに防除します。
ナンブイヌナズナの歴史
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、日本で変異を遂げて現在の形になり、そして日本のみで生息地を広げていったと考えられます。日本は島国ですから、陸を伝って他の植物が入ってくることはなく、
そのために固有種が育ちやすいという傾向はあります。ナンブイヌナズナもその一つで、日本にしか自生していない植物です。日本に古くから入ってきたアブラナの一種が、日本で独自に変異したものと考えられます。日本の全国に分布しているのではなくて、
夕張山地や日高山脈、北上山地などにしか分布していません。北海道産のものと本州産のものとで若干の違いがあり、特に夕張産のものはユウバリナズナとして区別されることもあります。名前の由来は、岩手県で発見されたことが影響しています。岩手県の早池峰山で発見されたために、
この地方の名前をとって「南部」という言葉が胚っています。原産は日本と言って良いでしょう。高山植物で環境の悪いところでも育つと言うことから貴重な植物とされています。近縁のイヌナズナは雑草として扱われることを考えれば、その違いは非常に大きいでしょう。
花はイヌナズナよりもやや大きいです。かつては多く生息していたそうですが、現在では環境相から絶滅危惧種として指定されていますし、北海道からも指定されています。特殊な場所でしか生息できないこともあって、環境の変化には弱いです。
ナンブイヌナズナの特徴
ナンブイヌナズナは、花の咲く茎と咲かない茎とがあります。花の咲く茎は10センチくらいにまでなることがあります。花の咲かない茎はもう少し伸びます。花が咲くのは6月から8月で、茎の先端に総状花序を出します。状況によって異なりますが、
だいたい数個から十数個くらいの花をつけます。花の一つ一つは小さく、5ミリくらいです。黄色い4つの花びらからなります。葉はロゼット型で、根元に密生しています。自生している地域ではだいたい6月から8月に花が咲くのが一般的なのですがが、
栽培している場合には4月から5月くらいに花を咲かせます。温度の違いが大きく影響していると言えるでしょう。温度が下がって冬が近づいてくると、ロゼット型の葉は目を包むように巻きます。寒い地域で進化してきたために、このようにして寒さから身を守る仕組みができあがっているのです。
寒い時期になると休眠に入って越冬します。イヌナズナはんほんの色々なところにありますが、多くのものは白い花を咲かせるという特徴があります。ナンブイヌナズナは、このイヌナズナの中で黄色い花を咲かせるという特徴があります。
発見された当時は変異したものだと考えられていたようですが、その後、ロシアの植物学者のマキシモビッチにいおって新種として同定されました。見た目はアブラナに似ています。花の雰囲気はアブラナにそっくりなのですが、大きさが異なりますし、葉っぱの形も異なり、特徴的です。
-

-
リーフレタスの育て方
紀元前6世紀にはペルシャ王の食卓に供されたというレタスですが野菜としての歴史は非常に古く、4500年前のエジプトの壁画に...
-

-
洋種サワギキョウの育て方
キキョウは日本で古くから好まれている花の一つです。生息地としては日本だけではなくて中国大陸や朝鮮半島などで、この地域が原...
-

-
ヘリクリサムの育て方
このヘリクリサム、ホワイトフェアリーの一番の特徴は何といってもその触り心地です。ドライフラワーかと思うような花がたくさん...
-

-
タツタソウの育て方
タツタソウ(竜田草)は別名イトマキグサや、イトマキソウ(糸巻草)と呼ばれているメギ科タツタソウ属の植物です。花色は藤紫色...
-

-
ハナトラノオ(カクトラノオ)の育て方
種類としては、シソ目、シソ科に属します。多年草の草花で、草丈としては40センチから高くても1メートルぐらいとされています...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
スリナムチェリーの育て方
スリナムチェリーはフトモモ科の常緑の低木でこの樹木の歴史は非常に古くブラジルの先住民族が赤い実を意味するスリナムチェリー...
-

-
ゴーヤの栽培こでまりの育て方あさがおのの種まき
種物屋さんに行くといろいろ知識の豊富な方がいらっしゃいますのでわからない時はまずはそういう専門家に相談してみます。そうし...
-

-
ヤシ類の育て方
ヤシ類の特徴としては、まずはヤシ目ヤシ科の植物であることです。広く知られているものとしてはココヤシ、アレカヤシ、テーブル...
-

-
いろんなものを栽培する喜び。
趣味としてのガーデニングについては本当に多くの人が注目している分野です。長年仕事をしてきて、退職の時期を迎えると、多くの...




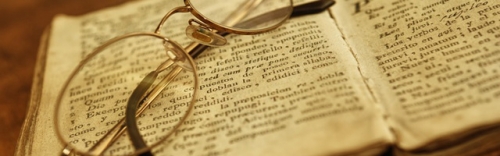





ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、日本で変異を遂げて現在の形になり、そして日本のみで生息地を広げていったと考えられます。