にらの育て方

にらの栽培の基礎と苗作り
にらは耐寒性があり、露地栽培でも容易に越冬させることが出来る多年草の野菜です。育て方は、株分けしたり苗を作って畑に植え付けていく方法と、種を直播してそのまま収穫するという育て方の二通りあります。
育て方を容易にすることと早く収穫するためには苗を作って植える方がよいでしょう。ただし、株分けした苗を使う場合、あまりに古いかぶは収穫量や品質に劣化が見られます。
種付けの時期は、春と秋のどちらでも行うことが出来ますが、どちらかというと春栽培のほうが育成が順調になる傾向が見られます。まず、種付け前に苗床の準備をしますが、苗床全面に石灰をまいてよく耕し中和しておきます。
肥料は苗床1㎡あたり堆肥を500~750gと石灰は1㎡あたり80g程度を目安とします。苗床の準備が出来たら、用意した種を水に一昼夜浸けておきます。その後、陰干しにして水気を取っておきます。
元肥を入れた苗床に畝を作り、15㎝間隔のまき溝を作っておきます。このまき溝に1㎝程度の間隔で種付けをして薄く土をかけておきます。この時十分な量の水を与えます。発芽までは乾燥しないように新聞紙や切り藁などで種付けした土の表面を覆っておきます。
おおよそ10~20日ほどで発芽となりますが、発芽を確認したら成長を妨げないようにすぐに新聞紙を取り除きます。この後5㎝程になったところで、株間が2㎝間隔になるように間引いて調整します。
この間、梅雨明けした後は乾燥防止のため敷き藁をして水やりをします。葉の状態を見て色が薄いようでしたら液肥で対応します。草丈が約20㎝程になった頃に根を切らないように掘り出して苗の完成です。
にらの畑の準備と苗の植え付け
植え付ける1か月ほど前に、苦土石灰を1㎡あたり100~150gほど混ぜ込みます。幾度も収穫したり株分けしたりして長期栽培をしますので、根の張りをよくするためなるべく深く耕しておきましょう。
植え付ける1週間前に幅約60~120㎝程度の畑の広さに合わせて畝を作ります。畝の表面を平らにならし、幅60㎝程度の畝幅であれば15~20㎝間隔の列に同じく15~20㎝の株間で苗を4~5本束にして少し深めに植え付けていきます。
間隔はあまりに狭いとよくありませんが、にらはよく育ちますのでそれほど神経質にならず畝の大きさに合わせて均等に植え付けてよいでしょう。植え付けた後はたっぷりと水やりをします。プランターに植え付ける場合は、畑での育て方と同様にある程度の間隔を空けます。長い間収穫を楽しみたい場合は本数を減らして間隔を空けた方がよいでしょう。
植え付けた後、25~30日のころに1~2回ほどの中耕と土寄せをしておきます。このとき根が浅く地表に伸びていますので傷めないように注意しましょう。水やりの方法として、畑で栽培している場合は、土が完全に乾いていなければあまり頻繁にする必要はありません。
しかし、完全に乾いてしまうと育ちが悪くなりますので常に土の状態を見て乾いたらたっぷりと水やりをします。このような強い野菜一般にいえることですが育成の際にあまり水やりなどを頻繁にするとかえって悪い結果を招くことが多く、育成が悪くなったり枯れたりしてしまいます。
甘やかすとよくありませんが、放置するのもよくありません。生き物を育てるのには、何か共通したものがあることを感じさせる一面です。追肥は1か月に1度を目安に育成の状態を見ながら行います。畑が乾くようでしたら敷き藁などで乾燥を防ぎます。
にらの収穫
にらの収穫は植え付けた年の翌年4~10月まで収穫可能です。草丈が20~15㎝程になったら収穫時期の目安とします。地上から4~5㎝程の部分から刈り取り収穫します。収穫したにらは、その刈り取り跡から新しい葉を出しますので、葉数3~4枚で、草丈が20~25㎝になった頃に再び収穫することが出来ます。
夏場は収穫が遅れると葉が硬くなってしまいますので遅れないようにしましょう。収穫は、株を弱らせないために年に1~2回とし、その後は株を休ませます。直播した1年目のものはそのまま収穫しないで1年後まで収穫するのを待ちます。
2年目からは前述と同じようにして収穫します。夏の盛りには葉が硬くなりがちですが炒め物などにすると食べられます。とう立ちしたものを刈り取ったり株が弱ってきたら追肥を行い芽の勢いを回復させればまた更に収穫することが出来ます。
何年間も収穫を繰り返したりしているうちににらの株は肥大化して、葉が密生してか細くなってしまいます。そうした場合は株の更新を行います。このように肥大した株は掘り出して分割し、新しい場所に植え替えます。
そのあとは一年目と同じような育て方で栽培することでまた、健康な葉を出すようになってきます。株の更新の際、古い株を掘り出すときは根がかなり深く張っているため傷つけないように鍬などを使って慎重に掘り出しましょう。
分割した株は、元肥をした水はけのよい畝を作り植え付けますがこの時、深く植えすぎたり、切り口を土で覆ってしまわないように気を付ける必要があります。
にらの歴史
にらの原産地は定かにはなっていませんが、中国西部から東アジアにかけての地域生息地ではなかったかと考えられています。モンゴルやインド、ベトナム、そして日本などでたいへん古い時代から栽培されていたと言われています。
このように東アジアでは盛んに栽培されていたのですが、ヨーロッパではほとんど栽培されませんでした。理由は定かではありませんが春菊などと同様にの癖があり薬効成分の強い野菜は民族的にあまり受け入れられないということも考えられます。
日本へ伝わったのは中国からといわれており、「古事記」には「賀美良(かみら)」という呼び名で記されています。平安時代の薬物辞典である「本草和名」には、「韮の和名は古美良(こみら)」という記載が認められそのほかの「万葉集」や「延喜式」といった有名な書物にも記載されていることからこの時期にはすでに親しまれていたことが伺えます。
そうしたことからも、日本での栽培の歴史もかなり古く、9~10世紀ごろには始まっていたと言われています。にらは、体を温める効果のある野菜として東北地方以北では、昔から親しまれてきました。
このことは中国の古い医学書にも記されていて野菜の中でも体を温める効果が高く、体に良いものであるため常食すると健康に良い、とされています。このことからも分かるように、当初は薬草としての認知のされ方をしていたものと考えられます。
にらの特徴
にらはユリ科の多年草です。丈夫で育てやすく、刈り取って収穫した後、再び新しい葉を出しますのでこれを年に数回収穫することが出来ます。家庭菜園やプランターなどで初めてでも簡単に栽培できる野菜です。
戦前では強い臭いが嫌われてあまり普及しませんでしたが、中華料理など食の多様化が進む現在ではあまり嫌われることもなく店頭にも普通に並ぶようになりました。冬から春にとれるものは?が肉厚で柔らかいものが出回り、夏には細葉の種類が出回ります。
その差はありますがほぼ一年中手に入れることが出来ます。にらの独特の臭み成分はアリインといわれる硫化アリルのひとつでこれはにんにくや玉ねぎにも含まれており強い刺激臭ともいえる臭いがします。
しかしこの物質がにらの薬効の元であり、スタミナ野菜といわれる所以でもあります。アリインにはビタミンB1と連携してスタミナを維持する効果があります。スタミナの基となるのはビタミンB1ですがアリインはこのビタミンB1働きを長く継続させる効果を持っていますので結果的ににらが持久力をアップすることになるわけです。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
ワケギの育て方
長ねぎの育て方
-

-
グロリオーサの育て方
グロリオーサの育て方は簡単ではありませんが、難し過ぎるというほどでもありません。マメに手入れをする方であれば問題なく育て...
-

-
シロタエギクの育て方
シロタエギクの原産地は、地中海に面した南ヨーロッパの海岸地帯です。現在ではイギリス(連合王国)南部を含むヨーロッパの広い...
-

-
エマルギナダ(ヒムネまたはベニゴウカン)の育て方
この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありませ...
-

-
イソトマの育て方
イソトマは、オーストラリアやニュージーランドなどの大西洋諸国にて自生している植物です。本来は多年草として知られていました...
-

-
ヒマワリの育て方
野生のヒマワリの元々の生息地は、紀元前3000年頃の北アメリカとされています。古代インカ帝国でヒワマリは、太陽の花と尊ば...
-

-
ミニトマトのプランターの栽培方法
ミニトマトの栽培は初心者でも簡単に育てられ庭がなくても、プランターで栽培出来きるので、プランターでミニトマトの育て方はと...
-

-
宿根アスターの育て方
アスターは、キク科の中でも約500種類の品種を有する大きな属です。宿根アスター属は、中国北部の冷涼な乾燥地帯を生息地とす...
-

-
オミナエシの育て方
オミナエシは多年草で無病息災を願って食べる秋の七草の一つです。原産や生息地は日本を始めとした東アジア一帯です。草丈は20...
-

-
コデマリの育て方
コデマリは中国中部原産の落葉低木で、「コデマリ(小手毬)」の名はその漢字が示す通り、小さな手毬のように見える花の姿に由来...
-

-
植物の栽培育て方のコツを教えます。
最近はインテリアグリーンとして植物を栽培するかたが増えてきました。部屋のインテリアの一部として飾るのはもちろん、植物の成...




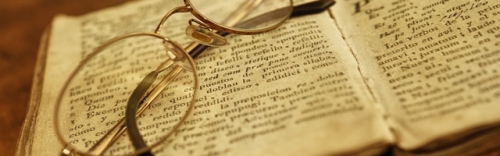





にらの原産地は定かにはなっていませんが、中国西部から東アジアにかけての地域生息地ではなかったかと考えられています。モンゴルやインド、ベトナム、そして日本などでたいへん古い時代から栽培されていたと言われています。