モモ(桃)の育て方

育てる環境について
花は3月から4月の上旬に見られますが、桃の花は春の季語にもなっているということで、その影響の大きさがわかりますが、色は白から濃い紅色まで色々あります。中でも淡い色の花が多く、この花が咲くと春の訪れを感じるという植物でもあります。また観賞用もあり、華道でも切り花として使われているということです。
また葉は、漢方でも利用されているようで、乾燥したものを風呂などに入れて、あせもなどの治療に使ったりしていたということなので、皮膚病に効くのかもしれません。また花が咲いたあとに、葉が出てくるということで、そのことも面白いですが、大きな実をふんわりと、淡い緑で包み込むような奥ゆかしさもあるので、そのことも好まれる理由だろうということですが、実と葉のバランスも良い植物でもあります。
特に日本人には、この淡い色の花や葉は好まれるということでしょう。また美味しさということでも、フルーツの中では特に美味しくて、硬いままでも、熟して柔らかくなっても美味しいですし、これをデザートなどで利用しても、どのようなデザートでも美味しく食べられるのが特徴です。また癖がない甘さも、人気がある理由でしょうが、
この甘さも淡い甘さなので、美味しくいただけるということになります。この果物は嫌いな人はあまりいないでしょう。このように日本人だけではなく、世界中で栽培されていますし、観賞用としても人気があり、広く知られているフルーツということになります。やはりガーデニングでも、楽しみたい植物のひとつでもあります。うまく育てられた時に最初の実は格別な美味しさでしょう。
種付けや水やり、肥料について
育て方ということでは、植え付けは、やはり春の植物なので、3月から4月と、秋の10月から11月の2回ということになります。また剪定は1月から2月で、同じ時期に肥料も与えます。また成熟する実ですが、品種により異なり、植える時にも品種を選んで、いちばん作業がしやすいように、また収穫しやすいようにすると良いということになります。
品種の違いでは、例えば白桃は8月頃収穫できますし、白鳳は7月などです。その他の品種もだいたい収穫は7月から8月のようで、ちょうど夏の盛りの暑い時に収穫ができますので、冷やして食べると美味しくいただけますし、この時期には冷たいデザートもたくさん食べますので、それらの食材として利用しても、喜ばれるのではないかということですが、
特に自家製ということでしたら、興味を持たれて、喜ばれるということは間違いないでしょう。また寒さに強い植物なので、温度がマイナスでも枯れることはなく、マイナス15度からマイナス20度ぐらいでも休眠状態ならば生き延びるほどです。しかし育つ温度は、年平均9度以上ということです。なかなか育てやすそうな植物ですが、
寒さが厳しいところは年間を通じて、あまり日本でもないでしょうから、ガーデニングでも栽培しやすいのではないでしょうか。また夏の成熟期では、日照量が多い場所で、雨が少ないところで、また昼と夜の温度差がある地域が良いということでした。植え付けですが寒冷地では春に、温暖な地域では秋に行うのが良いということです。
増やし方や害虫について
また受粉では、花粉が少ない品種もありますので、その点よく調べて受粉できるように工夫すると良いということになります。例えばどうしても選びたい品種が花粉が少ない時には、花粉が多い品種を一緒に植えるとかです。この植物は自分の花粉でも大丈夫なので、その点は花粉さえあれば受粉できるということになります。
人工授粉も考えておくということです。また剪定でも注意が必要で、古い枝から葉新芽ができにくい植物ということですから、新しい枝を切らずに残しておくということがポイントです。それらの枝から新芽が出るからです。その点も注意が必要になります。また肥料は溝を掘って配合肥料を与えれば良いので簡単に出来ます。
また美味しい果実を得るためには、成る実を少なくしておくということも必要になります。間引きですが、この場合には摘果と言いますが、基準としては葉が15枚から20枚でひとつの実という感じですが、枝では30センチぐらいでひとつ、60センチぐらいの枝で2つか3つという感じが良いようです。また病害虫の被害に合っていないものを残します。
また枝の先端に新しい葉が伸びているようなものも残します。病気としては、縮葉病や灰星病などがありますが、それぞれ対処法がありますので、インターネットなどで調べたり、専門家に相談して適切に処置をします。また害虫ではアブラムシ、モモハモグリガ、シンクイムシなどがいますが農薬などで駆除できますので、その点も注意して対処します。そうすると美味しい実もいただけるということになります。
モモ(桃)の歴史
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染み深い植物でもありますし、毎年必ず食べる果物にもなっています。この植物は意外なことに、バラ科の植物で、もも属ということで、多くの品種があるということもわかりますが、あのトゲのある食べられないバラからは想像ができない植物でもあります。
そんな意外性もある植物ですが、原産地は中国で、中国でも西北部の黄河の上流ということです。また歴史も古くシルクロードを通って、紀元前4世紀頃には、もうヨーロッパに伝わっていたということですから、古代ローマでも桃が食べられていたということになり、シルクロードや古代ローマ帝国などの、
古代ロマンもかきたててくれる植物ということでもありますが、その頃の有名人たちも食べていたということでは、今食べる時にも、その歴史を感じるということになり、非常にロマンチックな食べ物ということになります。ことわざでも色々なものがあり、いかに昔から食べられていたかもわかります。
語源としては花や木より、実が重要ということから、みみということで、そこから転化したしたのではないかということですが、桃太郎の昔話でも、大きな実を切ると、その中から生まれたとあるので、やはり実実からの転化が正解かもしれません。そのような色々な歴史も面白いものがありますが、それほど身近な果物でもあります。
モモ(桃)の特徴
またこの漢字ですが、木の実がふたつに別れるということから、この漢字が生まれたとありました。なかなか面白いものですが、またピーチという言葉も面白くて、ペルシャ語が語源ですが、なんとペルシャのリンゴという意味だそうです。このピーチも食品などでよく使われているのでわかりやすいですが、ペルシャのリンゴというのは面白い表現です。
肝心の日本では、縄文時代から日本の古代種があったようで、小ぶりの品種だったそうです。遺跡から種の欠片が見つかっているようで、長崎県で発見されているということでした。その後大陸から大きな実の品種が伝わり、今に至っているということですから、その意味でも非常に古くから食べられている果物ということになりますが、
プラムも日本語だと似たような和名ですが、やはりこれもバラ科で同じ系統になります。しかしこちらは桜に近いということで、これも驚かされる事実です。このようにバラ科の系統は面白い植物でもあり、またガーデニングでも家庭菜園の植物でも楽しめるということで、とても興味深い植物ということが言えます。
また食べられるということでも、ガーデニングで、庭に1本ぐらいは植えておきたいようにも感じます。買わなくてもすみますし、満足感も得られるということです。また生息地ということでも産地が福島県、山梨県、長野県なので、日本でも十分育てることができるということになります。また花もきれいなのでその楽しみもあります。
-

-
カンナの育て方
原産地は熱帯アメリカで日本には江戸時代前期にカンナ・インディアカという種類のものが入ってきて、現在では川原などで自生して...
-

-
トウミョウの育て方
エンドウ豆の歴史は古く、紀元前7000年の頃には南西アジアで作物としての栽培が始まっていました。その痕跡はツタンカーメン...
-

-
レンブの育て方
特徴としては、被子植物、双子葉植物綱にあたります。フトモモ目、フトモモ科、フトモモ属になります。ここまで来るとフトモモの...
-

-
コルディリネ(Cordyline)の育て方
屋内で育てる場合には鉢植えになりますが、葉の色彩を落とさないためにも、日に充分当ててあげることが必要です。5度を超え、霜...
-

-
オクラの育て方
アオイ科に属する野菜で、原産地は、マントヒヒの生息地で知られるアフリカ北東部です。エジプトでは紀元前から栽培されていまし...
-

-
風知草の育て方
風知草はイネ科ウラハグサ属の植物です。別名をウラハグサ、またカゼグサとも言います。ウラハグサ属の植物は風知草ただ一種です...
-

-
ヤマホタルブクロの育て方
キキョウ目キキョウ科キキョウ亜科ホタルブクロ属の植物で、花の色は紫色や白い色のようです。学名はカンパニュラ・プンクタータ...
-

-
カネノナルキの育て方
多年草であるカネノナルキは、大変日光を好む植物です。しかし、日陰で育てても特に枯れるわけではありません。非常に生命力溢れ...
-

-
スプレケリアの育て方
スプレケリアは別名「ツバメズイセン」と呼ばれる球根植物で、メキシコやグアテマラなどに1種のみが分布します。スプレケリアは...
-

-
プルモナリアの育て方
プルモナリアはムラサキ科プルモナリア属に属し、多年草です。園芸ではプルモナリアと呼ばれていますが、ハーブティーなどにも使...




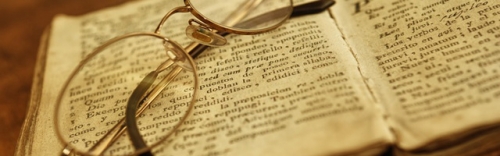




桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染み深い植物でもありますし、毎年必ず食べる果物にもなっています。この植物は意外なことに、バラ科の植物で、もも属ということで、多くの品種があるということもわかりますが、あのトゲのある食べられないバラからは想像ができない植物でもあります。