シーマニアの育て方

育てる環境について
シーマニアは、日本では10月から12月頃に、鉢植えの状態でよく売られています。しかし、南米の熱帯から亜熱帯地方の森林に自生する植物なので、寒さに対しては弱く、日本で育てる場合には、育て方に注意が必要です。年間を通して鉢植えに栽培し、
最低気温15℃を下回らない環境においてあげる必要があります。冬場は、室内に置いて室温が15℃を下回らないように気を付ける必要があります。日光に当てる必要がありますので、日中は室内の日当たりのよい場所に置いてあげるようにします。
但し、日当たりのよい場所は窓辺などになるため、夜になると温度が下がる恐れがあります。そのため、日没前には暖かい場所に移してあげる必要がありますが、エアコンの暖かくて乾燥した風が当るような場所は嫌います。多年草なので何年か育てることができ、
慣れてくると15℃を下回っても10℃程度までは耐えることができる場合もあります。しかし、冷風に当るとすぐに枯れてしまうので注意が必要です。春と秋は、15℃を下回らない環境ならば、屋外に置いても問題ありません。この季節には、日光によく当てると、よく育ちます。
シーマニアは、熱帯産の植物ですが、森林の中で自生していた腫なので、暑さにはあまり強くありません。また、湿度が高い環境にも適応できません。そのため、夏場は屋外に置いても構いませんが、直射日光に当らないように、建物の北側などの日陰で、風通しの良い場所を選んで育ててあげる必要があります。
種付けや水やり、肥料について
日本では一般的に鉢植えで売られており、そのままの鉢や、少し大きめの鉢に移し替えて育ててあげればよく育ちます。花は咲き、自生している場所では種で殖えるのですが、種から育てるのは難しいため、一般的には10月から12月頃に鉢植えで購入します。
4月から9月頃の間が成長期なので、この時期にたっぷりと肥料を与えると、丈夫な株に成長します。1000倍に薄めた液肥や、化成肥料を月に1回程度与えます。シーマニアは、多湿の環境を嫌う半面、水が少なくなるとすぐに葉が萎れてしまう性質を持っています。
そのため、表面の土が渇いたら、たっぷりと水を与える必要があります。冬場は花期であり、株自体の成長は緩慢になるため、水やりは控えめにします。春から秋にかけては成長期に当るため、この時期には十分な水を与える必要があります。しかし夏場に水を与える際には、
葉に水がかかると萎れてしまうため、注ぎ口の細い如雨露を用いて、土の表面だけに水がかかるように注意して水やりする必要があります。湿気を嫌うため、水はけのよい土に植えてあげる必要があります。また、水受け皿に水が溜まった場合にはすぐに捨てるように気を付けておかないと、カビが生えてしまいます。
水受け皿にカビが生えると、植木鉢の中にまで繁殖して、シーマニアの成長にも影響する恐れがあります。水やりに関しては、熱帯産の植物のため、冷たい水を与えると萎れたり、最悪の場合枯れることもあります。特に冬場は、15℃程度の水を与えるように注意が必要です。
増やし方や害虫について
本来の生息地に自生している場合、シーマニアも種で繁殖します。しかし、日本で鉢植えで育てる場合には、種から育てるのは一般の方には難しいため、殖やしたい場合には株分けや挿し木で殖やします。時期としては5月から6月頃が適しています。
但し、この時期は日本では梅雨の時期に当るため、高温多湿の状態にならないように注意が必要です。株分けや挿し木をしたばかりの苗は、周囲環境の影響に弱いためです。シーマニアにつく害虫としては、アブラムシやホコリダニがいます。
特にホコリダニは非常に小さい虫なので、人間の肉眼で確認することは困難です。また、アブラムシは一度つくと完全に駆除するのが難しい害虫なので、両者とも予防に重点を置く必要があります。アブラムシに対しては、園芸用の殺虫剤が効果的です。
但し、これは人間にも良くありませんので、散布する時には屋外で行う必要があります。ホコリダニに対しては、殺ダニ剤を用います。これも屋外で散布します。また、ホコリダニがついてしまった場合には、虫自体は見えませんが、ホコリダニが好んで食べる新芽が変形したり、
ひどい場合には枯れてしまいます。このような場合には、被害に遭った枝を切り取ってしまい、その後殺ダニ剤を散布して、残ったホコリダニの退治と、残った枝につくことを予防します。害虫以外にも、灰色カビ病や葉先枯病にかかることがありますので、湿気の多い環境を避けて、風通しの良い場所で育てることと、水やりの際に受け皿に溜まった水を放置しないことが大切です。
シーマニアの歴史
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です。古来現地の人たちがどのような名前で呼んでいたのかは明らかになっていません。しかし、この植物に付けられた学名については記録が残っています。
現在シーマニアと呼ばれている園芸品種の植物は、1855年に、ドイツの植物学者・園芸学者であったEduard August von Regelによって学名が与えられました。その学名は、Seemannia temifoliaと言います。但しこの学名は現在ではなくなっていて、現在のSeemannia sylvaticaのことだと考えらています。
いずれにしても、この植物はイワタバコ科の植物の中でも、Seemannia属の一種と考えられていたのです。しかし、1976年に、イワタバコ科植物の専門家であるHans Wiehlerによって、同じイワタバコ科の植物であっても、別の属であるGloxinia属の植物であるとされました。
現在では遺伝子解析が進んだため、系統学的に所属する属名や学名が明確にされており、Seemannia属とGloxinia属の植物の学名は整理されました。形態学的研究も発展しており、その成果として、当初Seemannia temifoliaと名付けられた植物は、Gloxinia nematanthodesとGloxinia sylvaticaという二つのイワタバコ科Gloxinia属の植物であることが分かっています。
シーマニアの特徴
シーマニアは、赤色或いはオレンジ色の花を咲かせる開花植物の多年草です。草丈は20cmから30cm程度ですが、大きく育てると60cm程度まで成長します。一つの枝から多数枝が分かれ、その枝に肉厚で細長い形状の葉が多数つきます。葉の表面は深い緑色、裏側は薄い緑色をしています。
葉は対性なので、向かい合った2枚が一緒に茎から生えてきますが、3枚から5枚程度が輪になって一緒に生えてくるものもあります。葉の先端は尖っていますが、葉の縁は滑らかです。表面には裏表共に白い毛が生えています。常緑性のため、季節によって葉がすっかりなくなることはありません。
枝の先端部分近くの葉の脇から花枝が伸びて花がつきます。開花時期は8月後半から2月までの期間に及ぶため、枝を伸ばして成長しながら次々に花を咲かせていきます。花の形は、釣鐘状であり、花弁は筒状に繋がっていますが、その先端だけが小さく五つに割けていて、割けた部分が外側に向かって反っています。
花弁の内側には、白または黄色になっていて、斑点があります。花の全長はおよそ2.5㎝です。花が終わると、さく果ができます。これは、熟すと裂ける性質をもった果実で、裂けることによって種子を散布します。
根にはうろこ状の地下茎があります。また、地表や地表近くの地中に匍匐茎と呼ばれる茎を伸ばし、伸びた先で株を立ち上げて増えることもできます。日本では、園芸店などで、鉢植えの小さな株の状態で手に入れることができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シネラリアの育て方
タイトル:ジニアの育て方
-

-
フィゲリウスの育て方
フィゲリウスはゴマノハグサ科に属している植物です。また別名をケープフクシアといいますが、花の形は他の植物と少し変わってお...
-

-
ロシアンセージの育て方
ロシアンセージはハーブの一種です。名前からするとロシア原産のセージと勘違いされる人も多いですが、それは間違いです。原産地...
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
イキシオリリオンの育て方
花については被子植物、単子葉類になります。クサスギカズラ目とされることがあります。ヒガンバナ科に属するとされることもあり...
-

-
ゴマナの育て方
ゴマナは胡麻の菜と書きますが、胡麻の葉っぱに似ていることから、この名前がついたと言われていて、キク科ですので、花も菊に似...
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...
-

-
スイセンとシクラメンの育て方について
ここでは、植物の育て方についてお伝えします。秋に植えつけをする花といえば、スイセンやシクラメンがありますね。スイセンとい...
-

-
ネメシアの育て方
ネメシアは日本においてはウンランモドキとも呼ばれており、園芸用の植物として愛されてきている品種です。最近では2000年に...
-

-
コブシの育て方
早春に白い花を咲かせるコブシは日本原産です。野山に広く自生していたことから、古くから日本人の生活になじみ深い植物でもあり...
-

-
エゴポディウムの育て方
セリ科・エゴポディウム属の耐寒性多年草です。和名はイワミツバと呼ばれ、春先の葉の柔らかい部分は食用にもなります。エゴポデ...




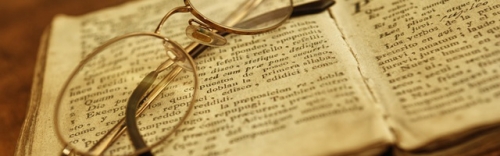





シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です。古来現地の人たちがどのような名前で呼んでいたのかは明らかになっていません。