シライトソウの育て方

育てる環境について
シライトソウは育て方が簡単な植物で、庭植えでも鉢植えでも育てることが出来ます。秋から春までは明るい日陰で育ててあげるようにしましょう。乾燥が苦手とする植物ですので、強い日差しと風当たりには注意が必要です。鉢植えの場合は、春や秋など涼しい季節には
午前中にだけ陽に当たるようにしてあげるとよいでしょう。出来るだけ温度変化の少ない場所に置くことがポイントです。夏場は日差しが強すぎて葉を傷めてしまいますので、日除けなどを使って70%ほどの遮光をしてあげるようにします。近くに人工芝などを敷いて打ち水で湿度を保つようにしましょう。
庭植えの場合は、夏場に日陰になる場所を選びます。周囲に背の高い花などを植えたり、花壇で囲ってあげるなどの工夫が必要です。シダなど、似た環境で育つ植物を周りに植えてあげ、本来の生息地である森林の状態に近づけてあげるようにしましょう。
毎年、もしくは一年おきには植え替えをしてあげます。適期は9月から10月頃、または初春頃です。用土は赤玉土4、軽石砂4、腐葉土2の割り合いで混ぜたものを使用します。湿度は好みますが、多湿にし過ぎると根腐れの原因になりますので、水はけの良い土にします。
乾燥気味であれば軽石の割合を減らしたり、ヤマゴケなどを使って保湿性を高めておきます。鉢植えの際は、出来るだけ深めの鉢を使用するようにしましょう。庭植えにする際は、鉢植えの用土を客土として使用するとよいでしょう。その時に増えすぎた分は株分けに使用します。
種付けや水やり、肥料について
シライトソウは種まきによって増やすことが出来ます。秋ごろに種をつけますので、それを採取して植えてあげるとよいでしょう。保存しておきたい場合は湿らせた川砂かピートモスに混ぜて、冷所で保存するようにします。その際も出来るだけ早めに蒔いてあげるようにしましょう。
一年を通して、表土が乾いてきたらたっぷりと水を与えてあげるようにします。とにかく乾燥を嫌いますので、乾かないようにすることが最も大切なポイントです。鉢植えの場合はより乾きやすくなりますので、鉢を砂床に埋めたり、二重鉢にしておくと効果的です。
また、植え付ける際に鉢底の穴から太めの縄が出るようにし、底面吸水が出来るようにしておくのもよいでしょう。底面吸水用の植木鉢もホームセンターや園芸店などで販売されていますので、それを使用すると手軽でお勧めです。庭植えの場合も日に一度水やりをするようにします。
夏の間は特に乾燥しやすいので株の周りに打ち水をして、湿度を保ってあげましょう。真昼は日差しで水分が沸騰してしまうことがありますので、早朝、もしくは夕方などの涼しい時間帯に行うようにします。春と秋には油かすなどの固形肥料を月に一度の割合で
置き肥してあげるようにします。肥料と株が直接当たらないように注意して埋めておきましょう。春先はチッ素分の多い液体肥料を週に一度くらい与えるのもよいでしょう。秋ごろに与える際には今度はリン酸分の多い液体肥料を週一で与えます。
増やし方や害虫について
シライトソウは種まきと株分けによって増やすことが出来ます。採り蒔きした種は翌春には発芽しますので、秋ごろに種が収穫できたら是非蒔いておきましょう。植え替えをする際に大きくなりすぎている株があれば、それを利用して株分けをしてあげます。
鉢から丁寧に株を取り外し、新しい用土に植えつけてあげれば大丈夫です。庭で植えている場合は3年に1度位の割合で掘り起こし、株を分けてあげるようにしましょう。あまり大きくなりすぎた株は花がつかなくなります。シライトソウは病気に強い植物です。
しかし、たまにアブラムシやナメクジが発生することがあります。アブラムシは、数が少なければセロハンテープなどで貼り付けて駆除することも出来ます。養分を吸い取ってしまいますので、見つけ次第早めに対処することが重要です。数が多ければ専用の薬剤を使用して駆除しましょう。
牛乳を霧吹きでスプレーするとアブラムシは窒息してしまいますので、この方法もお勧めです。牛乳の代わりにトウガラシを煮詰めて冷ましたエキスを吹きかけても効果的です。ナメクジも同じく養分を吸い取って株を弱めてしまいますので、見つけ次第早めに捕殺します。
ただ、ナメクジは土の中に卵を生んでいることも多いため、専用の殺虫剤をまいておく方がよいでしょう。また飲みかけのビールなどを深めの容器に入れて株の近くに置いておくと、ナメクジはそちらに誘引され、その中で溺死してしまいますので、その方法もお勧めです。
シライトソウの歴史
シライトソウとは、日本や朝鮮半島を原産としているユリ科シライトソウ属の多年草です。その名の通り、真っ白な糸を束ねたような花を咲かせます。シライトソウの花はとても特徴的で、ふわふわとして可憐な印象があります。可愛らしい花が群生している様はとても見事です。
人為的撹乱の多いところにはあまり生息しませんが、最近では野草愛好家の方々によって栽培されていることもあります。江戸時代に日本に滞在していたスウェーデンのカール・ツンベルクによる『日本植物誌』によって世界に知られるようになった花です。
『日本植物誌』にはシライトソウという名と共に「雪の筆」という呼び名も記載されています。日本では秋田以西から九州まで広く分布しており、主に低山や湿った崖の傾斜地などを生息地としています。このように日本各地に生息しているため、
ヤクシマシライトソウ、アズマシライトソウ、ミノシライトソウ、クロカミシライトソウなどの変種もあります。しかし、多くはレッドリストに登録されており絶滅の危機に瀕している状態です。また、近似種としてチャボシライトソウもあります。
シライトソウよりも小さめで、花の部分に大きな違いがあります。花弁は少し長めで、紫色のものを咲かせることもあります。凛としていて、爽やかなシライトソウの花は昔から茶花としてもよく使用されてきました。派手すぎず、素朴な美しさがありますので、茶会の席に飾られて親しまれてきました。
シライトソウの特徴
本州から九州の幅広い地域に分布していますが、人の多いところにはほとんど生息していません。山や林、谷などの明るい木陰、岩陰などで時折見ることが出来ます。ショウジョウバカマに似たロゼット状に広がる葉は3〜14センチほどの細長いタマゴ型です。
縁はノコギリ状に波打っており、深い緑色で艶はあまりありません。その為、白い花とのコントラストをより引き立たせています。葉の中心からスラリと花茎が一本伸びています。生育地によって異なりますが、その高さはマチマチで、15センチほどの低いものから50センチほどの高いものまであります。
4月〜7月頃に花茎の先端に花を咲かせます。その名の通り、真っ白で美しい花で、下の方から順番に咲いていきます。6枚の花被片があり、上部の4本だけは線状で長めですが下部2本は小さくて目立ちません。また6本の雄しべ、1つの雌しべも含みますが、それらはほとんど見分けがつきません。
一つ一つの花弁は1センチ位ですが、それらが集まってフワフワした可愛らしい花穂を形作っています。一見したら10センチ〜20センチほどの白いブラシのような花が密集しているように見えます。この頃の花茎は花が咲いている部分が白くなります。
またシライトソウの花はとてもいい香りがします。果実は3〜4ミリ程度の楕円形です。果実が熟す頃には花茎は緑色になります。種子は2〜3ミリほどの楕円形をしています。花が終わって、暑さが和らいだ頃、種をまいて増やすことが出来ます。
-

-
サンギナリア・カナデンシスの育て方
サンギナリア・カナデンシスとはケシ科サンギナリア属の多年草の植物です。カナデンシスという名の由来はカナダで発見されたこと...
-

-
観葉植物として人気のシュガーバインの育て方
シュガーバインは可愛らしい5つの葉からなるつる性の植物です。常緑蔓生多年草で育て方も簡単なので初心者の人にもおすすめです...
-

-
クリアンサスの育て方
クリアンサスの特徴としては鮮やかな赤い色の花でしょう。またその他に白やピンクなどもあります。草丈はそれほど高くなく80セ...
-

-
テイカカズラの育て方
テイカカズラという名前の由来は鎌倉時代初期にいた歌人である藤原定家です。定家は後白河法皇の娘である式子内親王に恋するので...
-

-
キュウリの育て方
どうせガーデニングをするのであれば、収穫の楽しみを味わうことができる植物も植えたいと希望する人が少なくありません。キレイ...
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
アッケシソウ(シーアスパラガス)の育て方
アッケシソウはシーアスパラガスと呼ばれているプラントであり、国内総生産第一位の国が属している地帯などの寒帯の地域を生息地...
-

-
タマネギの育て方
タマネギはユリ科に属する野菜で、100グラムあたりリンが30mg、カリウムは160mg、ビタミンB1が0.04mg、食物...
-

-
イワコマギクの育て方
イワコマギクは和名としてだけではなく、原産地となる地中海海岸地方においてはアナキクルスとしての洋名を持つ外来植物であり、...
-

-
セアノサスの育て方
セアノサスはカナダ南部や北アメリカにあるメキシコ北部が原産となっています。花の付き方が似ているという理由から、別名をカリ...




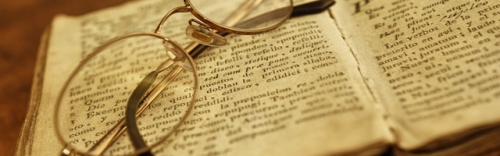





シライトソウとは、日本や朝鮮半島を原産としているユリ科シライトソウ属の多年草です。その名の通り、真っ白な糸を束ねたような花を咲かせます。シライトソウの花はとても特徴的で、ふわふわとして可憐な印象があります。