サンビタリアの育て方

育てる環境について
育てる環境としては日当たりが良い場所が適していて、生育期間が一年なのですが、日当たりが良くて風通しの良い場所に植えておくと美しい花をたくさん見ることができます。問題となるのは日本の梅雨の時期で、この時期は雨が多く湿度も高いことからサンビタリアが根腐れや立ち枯れ病などを起こすことが多くなってしまいます。
日本で栽培をする場合にはこれらの病気になるのは珍しくないので根腐れの場合には腐って根を取り除いて、立ち枯れ病の場合は間引きをして風通しを良くするだけで症状が改善していきます。暑さには非常に強いのですが、寒さに関してはあまり強くはないので、
日本の冬には注意が必要でとくに湿気を含んでいる地面に霜が降りてしまうと根元の部分がひどく傷んでしまうので、霜の降りない環境に植えることを心がけなければなりません。日常的に気をつけるべきことはある程度の乾燥状態に置いておくことと、
日光を積極的に当てること、肥料をあまり与えないことで、栄養分が多すぎると吸収することができないので、植物が逆に弱ってしまうことになります。また水分に関しても必要以上にサンビタリアに与えてしまうと根が十分に吸収できないので弱ってしまって、
腐る場合があります。日本は季節によっては非常に湿気が高いので水分は与えなくても十分に生育が可能となっています。また種まきをして育てる場合には北風の直撃する場所や霜の降りる場所を避けるようにしなければなりません。
種付けや水やり、肥料について
サンビタリアは種から増やすことのできる植物ですが、土に関しては水はけの良い土を好む性質があるので、赤玉土の小粒のものや中粒のものを使用して、これに腐葉土や川砂などを混ぜた土を使うことで、日本の気候にも負けないように生育させることができます。
花が咲いたらサンビタリアは枯れてしまうので、植替えの必要性はないのですが、苗を購入した場合には花の咲く時期がくる前の5月から6月の間に植え付けを行います。この植物は横に広がって行く習性があるので、複数のサンビタリアを植え付ける場合には、
30センチ以上の間隔で植え付けを行わないと立ち枯れ病などを起こす可能性が高くなります。肥料に関してはほとんど与えなくても十分に生育させることができますが、花の数を多くしたい場合にはリン酸が多く含まれている液体肥料を10日に1度程度の頻度で与えるだけで十分に美しい花を咲かせることができます。
また窒素分の多い肥料を使ってしまうと葉の部分がよく育つのですが、花つきが悪くなる傾向があるので、なるべくリン酸を多く含むものを使う必要があります。水やりに関しては極端に乾燥をしている場合以外では与える必要はありませんが、
最近の日本では温暖化が進んでいるので、湿度も高いことから高温多湿の状態が続くことがあります。土が湿っていると根腐れを起こしやすい植物なので、植える場所に注意をしてあまりに湿気が多い場合には水やりをしないように注意をすることが大切です。
増やし方や害虫について
増やし方は基本的には種から増やすことになりますが、生育が非常に早い植物なので春に種をまくと夏にはきれいな花を楽しむことができます。場合によっては秋に種をまくこともできるのですが、耐寒性があまりないので、冬の間に枯れてしまうこともあるので、
春に種をまくことが望ましいとされています。基本的には鉢や小さな箱に種を巻いて苗が育ってきたら花壇などに植え替えを行います。苗が大きくなってから花壇などに植え替えをしても根が定着しないので小さいうちに植えつけることが重要です。
また花壇やコンテナなどに種をまいてそのまま栽培することもできます。かかりやすい病気は根腐れ病や立ち枯れ病などですが、これらは土の中に繁殖している細菌が原因となっているので殺菌することができないので、治療が難しいとされています。
症状を少しでも改善させるためには病気になった部分を切除して茎を間引くなどして風通しを良くすることで、これによって湿度を下げることができるので細菌の繁殖を抑えることができます。害虫としてはアブラムシが考えられるのですが、この害虫は小さな虫なのでピンセット等で取り除くことは不可能です。
アブラムシは数匹の場合にはとくに被害はないのですが、繁殖を繰り返して大量に発生すると葉を変色させるなどの被害が出てくるので、植物の光合成が正常に行えなくなったり、栄養分の吸収ができなくなるので、花の数が減ってしまったり葉の色が悪くなることがあります。
サンビタリアの歴史
サンビタリアは北アメリカの南から中南米を中心にした地域に自生していて、現在発見されているものは7種類であるとされています。サンビタリアの中でも園芸用の品種としての歴史があるものとしてはグアテマラからメキシコ周辺に分布しているもので、これらは明治時代の初頭に日本に入ってきたものです。
夏から秋に花を見ることができるのおですが、その後はすぐに枯れてしまうので、春に種をまいて夏から秋に花をつけてその後は種子をまくということを繰り返す一年草で、茎の部分は立ち上がらないで地面を這うようにして広がるのが特徴となっていて、
花は黄色やオレンジであることが多いのですが、内部は黒褐色となっています。日本ではジャノメギクとも呼ばれていて、小さなひまわりのようなその花は世界中で人気となっています。代表的なサンビタリアの品種としてはスプライトやアイリッシュ・アイなどがあり、
これらは園芸用の品種として作られたもので、花の中心部分が褐色ではなく緑色になったり、花つきが良いなどの特徴を持っています。アメリカ北部でも自生している品種なのですが、栽培などが盛んに行われているのがグアテマラやメキシコの品種なので、
原産国としてはこれらの国々となっていて、品種改良などが行われて盛んに栽培をしているのがこれらの国々です。日本においては園芸用の植物としての知名度はそれほど高くないので、ガーデニングの専門店などでもなかなか見つけられないのですが、育てやすい植物なので初心者でも栽培することができます。
サンビタリアの特徴
サンビタリアの生息地は基本的にはアメリカから中南米にかけての気温が暑い地域なのですが、日本でも明治時代から栽培されているので暑さだけでなく寒さに対する強さも兼ね備えている植物なので、育て方などが他の植物と比べても難しいことはないので、
非常に育てやすい植物として人気となっています。草の高さは20センチから30センチ程度なのですが、庭植えにした場合には周囲の地面を這うようにして広がって行く特徴があるので、ある程度の広い土地を必要としてます。開花時期が比較的長くなっていて、
5月の中旬から11月の下旬までなのですが、梅雨の時期の湿気に弱いので立ち枯れ病などにかからないように風通しを良くする必要があります。また立ち枯れ病になった場合にはその部分を切り取るなどして風通しを良くすると症状が改善する可能性があります。
種まきの時期は春から初夏にかけてで、開花期の直前にしっかりと肥料を与えることで花の季節を長くすることができます。乾燥に強いという特徴があるのですが、日本の真夏の気候は非常に熱くて湿気も多いので乾燥しすぎた場合には水やりをこまめにする必要があります。
中南米の熱帯で育ってきた品種なので乾燥に強い特性があるのですが、水分を与えすぎてしまうと立ち枯れ病や根腐れを起こしてしまうので、水分の管理をしっかりとする必要があります。また日本の冬の霜などにも弱いので庭植えの場合は霜がおりない場所に植える必要があります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:スネールフラワーの育て方
タイトル:シレネの育て方
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
自宅で植物を育てよう
部屋に植物があると生きたインテリアにもなり、その緑や花の華やかな色は日頃の疲れやストレスへの癒やしにもなります。ただ、生...
-

-
ハナカイドウの育て方
ハナカイドウは、原産は中国です。「カイドウ」と呼ばれることもあります。中国では華やかな花を咲かせると言うことから、古くか...
-

-
ブラッシアの育て方
ブラッシアはメキシコからペルー、ブラジルなどの地域を生息地とするラン科の植物で、別名をスパイダー・オーキッドと言います。...
-

-
雲間草の育て方
日本の園芸店で市販されている雲間草は、一般的に「西洋雲間草」、「洋種雲間草」と呼ばれているヨーロッパ原産のものです。元々...
-

-
大根の育て方
大根の原産地は地中海沿岸といわれていますが、いろいろな説もあります。紀元前2500年ごろにエジプトでピラミッドを通ってい...
-

-
アリストロキアの育て方
アリストロキアの特徴と致しましては、花の独特な形状があります。数百種類にもなるそれぞれの形状は個々で異なりますが、そのど...
-

-
ミニバラの育て方
バラと人間との関わりは古く、およそ7000年前のエジプトの古墳にバラが埋葬されたとも言われています。またメソポタミア文系...
-

-
フユサンゴの育て方
リュウノタマ、フユサンゴとも呼ばれているタマサンゴは、ナス科ナス属の非耐寒性常緑低木です。ナス科は、双子葉植物綱キク亜綱...
-

-
ネフロレピスの育て方
ネフロレピスはシダの仲間に属する植物で、亜熱帯地方や熱帯地域を主な生息地として世界中に分布しています。中米を原産とし、現...




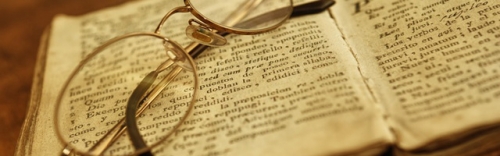





サンビタリアは北アメリカの南から中南米を中心にした地域に自生していて、現在発見されているものは7種類であるとされています。サンビタリアの中でも園芸用の品種としての歴史があるものとしてはグアテマラからメキシコ周辺に分布しているもので、これらは明治時代の初頭に日本に入ってきたものです。