ブンタン類の育て方

ブンタン類の育てる環境について
ブンタンは暖かい気候の土地を生息地としており、寒さに弱くマイナス2度くらいの寒さにしか耐えられないため日本では西日本のほうが栽培に向いていますが関東でも暖かい地域であれば露地栽培が可能です。冬に冷たい風が当たらない場所に植え、根本を藁などで養生します。
果実は晩生種のほうが甘くおいしいものができますが、早生品種のほうが寒さに強く木も小さいので育てやすいため観賞用に向いています。寒い地域での育て方は鉢植えにして冬の間は室内や軒下などで育てることもができますが、2、3年ごとに植え替えが必要になり、
木に対してあまり大きすぎる鉢を使用すると根腐れを起こすことがあります。大きな木に成長するため鉢に植えるときは1本のみにします。日当たり、水はけのよい肥沃な土地を好みます。春に新芽を出すために寒い時期には落葉しますが、
寒すぎると落葉が多くなり光合成の量が減ってしまい枯れる恐れがあるため温度には注意が必要です。1本の木でも自分の花粉で受粉をして実をつけることができますが、違う柑橘類を近くに置くとより実が大きく、たくさんなりやすくなります。
自家結実すると種のない小さな実になるため受粉樹には開花時期が同時期のハッサクや日向夏を利用します。植えるときは枝が広がるため葉が重なると日当たりが悪くなるので、風通しのためにも木と木の間は4メートルは開けて植えます。摘果すると実が大きく育つため、露地栽培の場合は7月頃に直径3センチほどのものを摘果します。
ブンタン類の種付けや水やり、肥料について
種は比較的簡単に発芽させることができます。果肉からとった種をぬめりがなくなるまできれいに洗った後、乾燥させずに土にまき水を与えます。撒くのに適しているのは3月から4月ですが、その前に種を入手した場合は冷蔵庫で撒くときまで保管することが可能です。
ポット植えの苗木を植える場合は根を崩さないようにすればいつでも植えることが可能ですが、暖かい春になってからのほうが育ちやすくなり、真夏は乾燥するので可能であれば避けるようにします。土は乾燥しないように注意し、表面が乾燥してきたら鉢の底からでてくる位たっぷりと水を与えます。
土は水はけのよいものが良いため市販の柑橘用の土や培養土を使用し、肥料は花がつく5月頃まではあまり与えないようにして花が咲きはじめたら増やしていきます。7月、10月に即効性のある肥料を与えることで収穫量が増え、12月に有機肥料を与えると翌年の実がたくさんなるようになります。
窒素肥料を多くすると皮が厚くなります。全体の日当たりを良くし、樹の形をつくるために3月中旬までには少しだけ剪定を行い長く伸びた枝を切りますが花芽のでる1、2月には行わないようにします。葉を落としすぎると栄養が足りなくなり実の味が薄くなるので、
切りすぎないようにします。日照りが続くようであれば庭植えの場合でも水やりをします。水分が足りないと葉が黄色く枯れてしまい、果実も大きく成長せず、果汁が少なく味の悪い実になります。
ブンタン類の増やし方や害虫について
ブンタンは3月下旬から4月に台木となるカラタチ等の木に接ぎ木して増やすことができます。できるだけその年に伸びた丈夫な枝を切り口の組織を壊さないようにきれいな状態で切り取り、切り口をしっかりと合わせて接ぎ木した枝の水分が蒸発しないようにすることが大切です。
台木の部分は土の中に埋めずに土の上にだすようにすると病気に強くなります。8月から9月には芽の周辺部のみを穂木として、台木の枝や幹の途中に切り込みを入れて芽を差し込み固定して接ぐ方法もあります。ブンタン類は皮が厚いため病気にかかりにくく害虫にも強いと言えますが新芽のころにはアブラムシがつくことがあります。
アゲハチョウの幼虫や毛虫がつくと葉を食べられてしまうため、見つけた場合はすぐに取り除くようにします。カイガラムシがつくと葉や実に黒いススのような糞がつき、スス病になるためマシン油や石灰硫黄合剤などの薬剤を12月から3月に散布して駆除したり、
葉に水をかけて流すことで予防することができます。また主枝などからでてくる小さな芽を取り除くことでハモグリガによる被害やかいよう病を防ぐことができます。エカキムシは新芽に寄生するため新芽の時期に防除する必要がありますが、
柑橘類は5月から10月と長期間にわたって新芽が出ます。そのため数回にわたって防除が必要になりますが、4月から5月の新芽の時期にエカキムシの防除をするとアブラムシやアゲハチョウにも効果があります。
ブンタン類の歴史
ブンタンはミカン科ミカン属の大型の柑橘類の一種でザボン、ボンタンなどと呼ばれ、ブンタン類には柑橘類最大の晩白柚や日本原産の安政柑、河内晩柑などの種類があります。原産地は東南アジア、インドネシア、マレー半島とされており、日本には安土桃山時代から江戸時代初期に鹿児島に種子が持ち込まれました。
単胚種のため品種改良ではなく自然交雑をすることによって独自の品種が多数生まれました。グレープフルーツやハッサク、ナツミカンなどもブンタンの自然交配によってできた柑橘とされています。東南アジア、台湾、中国、日本で栽培されており約40種が確認されていますが、
実際に栽培されているのは15種程度です。ブンタン類は九州南部や高知県で多く栽培され、生産量の9割を占める高知県では土佐文旦という独自の品種ほか、皮の内側が薄い紫色で果肉が紅色をしているウチムラサキという品種がありこれがブンタンの原種とされています。
名前の由来は中国語で洋ナシ、長卵の形を意味するというものや、清国の謝文旦という人物が日本に漂着して文旦を御礼として置いていった、中国の文という俳優の家に立派な柑橘の木があったからといういくつかの説があります。
標準和名のザボンという名前はポルトガル語由来で、輸入されたブンタンはポメロという名前で売られています。現在栽培されている苗木は明治時代以降に中国や台湾から導入したものを育成、交雑したものがほとんどです。
ブンタン類の特徴
果実が直径15センチから25センチ、重さ500グラムから2キロ以上と大きいのが特徴です。外皮が厚く弾力果実の半分を占めており、風通しのよい冷暗所に置いておくと1か月程日持ちすることができます。実は独特の甘みと苦味を持ち、果汁は品種によって多いものと少ないものがあります。
九州で栽培されている種類のほうが実が大きく皮も厚く、果汁が少なくぽろぽろとした歯切れのよい食感で、高知の土佐文旦は400グラムから600グラムとブンタン類としては比較的小さめの実がなり、外皮が薄く種と果汁が多いジューシーな味わいです。
収穫直後はクエン酸が多く酸味がきついため、ハウスの中や地面を掘った中に貯蔵して追熟させることで甘くなります。厚い皮には苦味がありますが、ナリンギンというビタミンPの一種が多く含まれており高血圧を抑える効果があるため表面をとった白い皮をザボン漬けやマーマレードなどにして利用します。
香りが強く部屋に置いておくと芳香を楽しむことができ、大きな晩白柚は飾って見た目を楽しむこともあります。木は高さ3メートル程度に成長して10センチ程度の楕円形の大きな葉が3メートル四方に広がり、甘い香りのする5枚弁の白い大きな花をつけます。
ブンタン類は単胚性のため種から育てると雑種となり元のものとは違う木の性質を持ち、実をつけるまでに10年以上かかることもあり、味も違う実ができます。そのため橘などの台木に接ぎ木をする必要があります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クロウエアの育て方
-

-
ワスレナグサの育て方
そのような伝説が生まれることからもわかりますが、原産はヨーロッパで、具体的には北半球の温帯から亜寒帯のユーラシア大陸やア...
-

-
フジの育て方
藤が歴史の中で最初に登場するのは有名な書物である古事記の中です。時は712年ごろ、男神が女神にきれいなフジの花を贈り、彼...
-

-
ドイツアザミの育て方
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑...
-

-
ソテツの育て方
この植物に関してはソテツ目の植物になります。裸子植物の種類に当たり、常緑低木になります。日本においてはこの種類に関しては...
-

-
モッコウバラの育て方
花の中でも王様と呼ばれるほどバラに魅了される人は多いです。そのためガーデニングをはじめる際にバラを育ててみたいと思う人は...
-

-
植物の栽培に必要な土と水と光
植物の栽培に必要なのは、土と水と光です。一部の水の中や乾燥している場所で育つ植物以外は、基本的にこれらによって育っていき...
-

-
カリフラワーの育て方
カリフラワーはブロッコリーが突然変異で白くなったもので、原産地は地中海沿岸です。ブロッコリーと同様野生のカンランから派生...
-

-
カモミールの育て方について
カモミールはハーブの一種です。ハーブというのは、食用や薬用に用いられる植物の総称です。人の手が必要になる野菜とは異なり、...
-

-
センブリの育て方
センブリはリンドウ科センブリ属の二年草です。漢字で「千振」と書き、その学名は、Swertiajaponicaとなっていま...
-

-
サルナシの育て方
見た目が小さなキウイフルーツの様にも見える”サルナシ”。原産国は中国になり、日本でも山間部などを生息地とし自生している植...




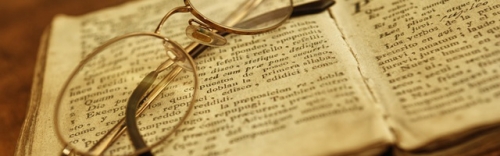





ブンタンはミカン科ミカン属の大型の柑橘類の一種でザボン、ボンタンなどと呼ばれ、ブンタン類には柑橘類最大の晩白柚や日本原産の安政柑、河内晩柑などの種類があります。原産地は東南アジア、インドネシア、マレー半島とされており、日本には安土桃山時代から江戸時代初期に鹿児島に種子が持ち込まれました。