シネンシス・エピソードの育て方

育てる環境について
またオオヒエンソウ属はデルフィニウム属と同じで、オオヒエンソウは和名だそうで、一般にはデルフィニウムと言われているそうです。ですのでデルフィニウム・シネンシスと呼ばれている花の交配種がシネンシス・エピソードと言われている花ではないかということになります。育て方ということや様々な特徴も、
デルフィニウム・シネンシスを基本に考えると育てられるのではないかと予想ができます。キンポウゲ科デルフィニウム属は、ヒエンソウとオオヒエンソウがあるので、きんぽうげ科ヒエンソウ属であるシネンシス・エピソードも非常に近い種ということは言えるでしょう。またオオヒエンソウのデルフィニウムには3つの系統があり、
エラータム系とシネンセ系とベラドンナ系で、シネンシスエピソードはシネンセ系の植物ということでしょう。この系統は茎がきゃしゃで、そこに可憐な花を咲かせているということなので、やはりこの植物もこの系統の花ではないかということがわかります。いずれにしろ日本では馴染みの薄い植物ということになります。育て方も、デルフィニウムシネンシスに準ずるということでしょうが、
そうするとわかりやすいということになります。要するにオオヒエンソウはデルフィニウムと同じ植物ということなので、その点でもデルフィニウムの育て方でだいたいのところは合っているのではないかということが分かります。そのように工夫しながら、新しい植物の場合は、育てていくということが良いのではないかということになります。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、開花は5月から6月で、植え付けは春と秋ですから3月ぐらいと10月から12月ぐらいです。原産地は山岳地帯でヨーロッパ、シベリア、モンゴルなどの中国で、シネンセ系統は中国のモンゴルあたりですから、山岳の環境が好きな植物ということがわかりますので、育て方でもそのような地方での環境に近いようにしてあげるとよく育つのではないかということになります。
基本は多年草ですが、日本での栽培では温暖な地方のガーデニングということになりますので、1年草の扱いで栽培しているようです。肥料は地植えでも鉢植えでも3月の初めと10月の中旬頃のようです。育てるのには初心者では難しいという感じの植物だろうということですが、このように育て方を調べてもあまりわからない植物なので、
一般のデルフィニウムを育てたほうが初心者向きということがわかります。また寒さに強く、暑さに弱いということもわかりますので、鉢植えなどで室内などに移動できるようにすると冬はともかく夏は良いのではないかという感じもします。また今年種を蒔いても花は次の年ということになります。
発芽温度は15度から20度くらいですので、開花が5月6月頃ですから、温度管理も発芽時期は重要になります。寒さに強いですが寒冷地では霜よけをしたほうが良いとのことでした。生育温度は10度から20度で、0度近くまでならば枯れることはないようです。また土壌は水はけを良くするということで、これは他の多くの植物と変わりません。
増やし方や害虫について
またその他の土壌でのポイントは中性に近い弱アルカリ性を好むようですので、そのような土壌にしておきます。また連作障害が出やすいので、多年草ではあるのですが、1年毎に育てることになりますから、次の年は別の場所や鉢で育てるということになります。同じ土壌では育てないようにするということも注意ポイントになります。
また種から育てる場合には、種まき用の土に種を蒔き、その上に1ミリから2ミリほど薄く土をかぶせます。発芽適温が15℃ということに注意します。種自体は光を嫌うようなので土をかぶせますが、そのことも注意します。そして発芽したら、葉が2,3枚の頃ポットに植え替えて、葉が5,6枚になるまで育てます。
その後庭に植え替えますが、日当たりがよく水はけが良い場所に植えます。また地植えではなく鉢植えの場合には7号鉢ぐらいの大きさの鉢にひと株ずつ分けて植えます。庭に植える場合の土は堆肥と腐葉土、油かすなどを混ぜた土に植えます。そして追肥は有機固形肥料を与えます。追肥は春と秋頃ですが状況に応じで5月頃与える場合もあります。
病害虫は一般的な害虫ですが、アブラムシ類、ヨトウムシ類で定番の害虫ですが、それぞれ対策を立てて駆除するということになります。できるだけ早めに気が付くと駆除しやすくなりますので、特にヨトウムシ類はよる行動するので、
夜も気をつけておくということが必要です。また病気では灰色かび病という病気があり、低温多湿時に発生するということで、カビが生えてしまうので、湿度も気をつけるということが必要になります。そのように育てるときれいな花が見られることになります。
シネンシス・エピソードの歴史
ガーデニングでは、色々な花が栽培されていますが、非常に珍しい花もあり、その花が美しい場合には、どのような花か調べてみたいということや、できれば育ててみたいという人も多いようで、インターネットなどでも画像などをアップして花の名前を尋ねている人たちもいます。
しかしそのような花は、珍しいのでインターネットでの検索でもわからずに尋ねているので、答えも知っている人が少ないということとで、明確な答えがない場合が多いようです。そんな中でもシネンシス・エピソードという淡い紫色の花があり、とても美しいので、調べてみましたが、
ほとんど資料がなく、非常に珍しい花ということだけしかわからないという結果になりました。それで育て方以前に購入するところもないということで困りましたが、原産地はヒマラヤと欧州ということで、何故に二箇所かというとそれぞれの種の交配によって生まれたということのようです。
きんぽうげ科ヒエンソウ属ということと花が5月から7月にかけて咲くということ。また高さが70センチぐらいまで育つということ。花は小型の一重咲きで、赤紫の花を穂状の茎に沿ってつけることやオオレイジン草系も交配されているということなどが特徴で、
高温多湿に弱く夏の暑さに弱いということもありました。また切り花用に栽培されているということもあるようです。また発芽の適温は20度ぐらいで、種で繁殖するようです。このような花に魅了されると、不完全燃焼になったようで非常に困るということになります。
シネンシス・エピソードの特徴
そもそもシネンシスという言葉が中国産ということで、シナからきている言葉なのでシネンシスという言葉だけではあまりにもたくさんの植物があるということになります。またシネンシスという名前がついた場合でも、中国とは全く関係ない勘違いで付くこともあり、後でそのことがわかっても、そのままの名前で学名が変わらないという習慣があるそうで、それも混乱させているようです。
シネンシス・エピソードには、オオレイジンソウも交配されているということですが、レイジンソウというのはキンポウゲ科トリカブト属の多年草で花が舞楽の奏者である伶人がかぶる帽子に似ているということからついた名前だそうです。日本でも自生している花でもあります。
猛毒のトリカブトもこの仲間ですが、花が珍しいので交配に使ったのかもしれません。この花の生息地は本州でも北の方の寒い地方に自生しているということですので、シネンシス・エピソードの高温多湿の夏に弱い性質にも似ていますし、ヒマラヤ種も入っているということですので、育て方ということでも似てくるのではないかという予想ができます。
またデルフィニウムという花があり、この花もシネンシス系ですが、青い花なのでシネンシス・エピソードに似ているようにも感じます。こちらはよくある花のようで、育て方も詳しくわかる花です。シネンシス・エピソードがきんぽうげ科ヒエンソウ属ということですから、この植物にも近いのではないかということも予想ができます。
-

-
ドルステニアの育て方
ドルステ二アはクワ科の植物で、アフリカ東部のケニアやタンザニアのあたりから、海を挟みアラビア半島の紅海沿岸が原産となり生...
-

-
クラウンベッチの育て方
クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴...
-

-
ハスの育て方
ハスはインド亜大陸を原産とするハス科の水生植物です。その歴史は植物の中でも特に古く、1億4000万年前には既に地球上に存...
-

-
リンドウの育て方
リンドウは、リンドウ科、リンドウ属になります。和名は、リンドウ(竜胆)、その他の名前は、ササリンドウ、疫病草(えやみぐさ...
-

-
オレガノの育て方
オレガノは、もともとはヨーロッパの地中海沿岸を生息地とする植物です。ギリシャの時代からあり、ヨーロッパの文化の一員になっ...
-

-
夏野菜の育て方と種まき
今では、ベランダや小さい空きスペースを使って、自給自足生活を楽しむ人が増えています。種をまき、または小さな苗から育ててい...
-

-
ワケギの育て方
原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地で...
-

-
ノアサガオの育て方
ノアサガオなどの朝顔の原産地や生息地はアメリカ大陸で、ヒマラヤやネパール、東南アジアや中国南部という説もあります。日本に...
-

-
オオイヌノフグリの育て方
気温が下がりつつある秋に芽を出して、冬に生長し春の早いシーズンに小さな花を咲かせるプラントです。また寒い冬でも過ごせるよ...
-

-
チョロギの育て方
チョロギはシソ科の植物です。中国が原産の植物です、日本には江戸時代に伝わった植物です。その名の由来は、朝鮮語の”ミミズ”...




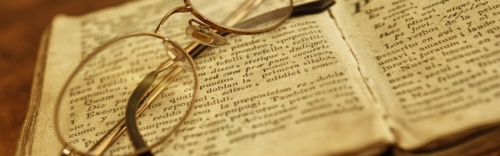





シネンシス・エピソードがきんぽうげ科ヒエンソウ属ということです。シネンシス・エピソードという淡い紫色の花があり、とても美しいので、調べてみましたが、ほとんど資料がなく、非常に珍しい花ということだけしかわからないという結果になりました。