ツルグミの育て方

育てる環境について
育てる環境は特別寒さの厳しい場所でなければ問題なく育てる事が出来ます。砂地でも育てる事が出来る程扱いやすい植物です。理想的な育て方としては赤い実が沢山つくように育てたいはずです。挿し木で増やしていく方法がありますが、初めての場合は苗木を購入してみるのがおすすめです。
徐々にツルが出てきますので、支柱などを使って育ててみるといいです。初めは鉢植えからスタートし、少し成長しましたら庭に直接植えてみるのもひとつの方法です。庭に植える際にはツルが伸びていく事を想定してベストな場所に植えるといいです。基本的にはそれ程水やりに気を配る必要はありませんが、苗木の頃は土の表面が乾かない程度に水やりをするといいです。
庭に植え付けを行う時期は成長が緩慢になる10月位か、寒い時期が終わりつつある3月位がベストになります。大きな穴を掘り、土と腐葉土を混ぜたもので植えて行きます。十分に栄養分を与える事でしっかりと育ち、実を付けます。苗木から実がなる位になるまでには3年から5年くらいかかるようです。気長に成長を待つ事が大切です。
栽培中は剪定をしながら大きくしていきます。剪定を上手に行う事でたくさんの実を付ける事が出来ます。注意しなければならないのは花芽を剪定してしまわない事です。伸びすぎた枝を切ったり、傷んだ枝を切って風通しをよくします。こうする事でより日当たりがよくなります。昆虫のいない場所では人工受粉が必要な場合もあります。
種付けや水やり、肥料について
水やりはしっかり根が生えている庭木においてはそれ程気にしないで大丈夫です。肥料も特別必要はありませんが、鉢植えの場合は、土が乾かない程度に水やりをします。時には固形の肥料や水溶性の肥料をあげると成長がよくなります。鉢植えの状態で花を咲かせて実を付けるように育てる事も可能です。鑑賞用に楽しむ場合は鉢植えがおすすめです。
実をしっかり収穫したい場合は庭に直接植えた方が大きくなります。剪定を上手に行う事で沢山の実を付けます。しっかり熟したタイミングが食べ頃です。収穫しますと日持ちがしない為、ジャムにしたり、ピューレにして保存するといいです。甘酸っぱい味わいを色々な形で楽しむ事が出来ます。苗木はホームセンターや園芸店で購入する事が出来ます。
最近はインターネット通販でも購入する事が出来ます。苗木の大きさは30センチ位の物が多いです。花は咲くけれども実が付かないという悩みもよくあります。そのような場合は、花の満開期とその後2回程度、ジベレリン1万倍液を花の表面に霧吹きを使用して吹きかけます。グミの魅力は実ができる事です。上手に育てて沢山実がなるようにします。
扱いやすい植物ですので初心者でも十分挑戦する事が出来ます。ベランダでのガーデニングでも挑戦する事が出来ます。その場合は鉢植えで楽しみます。新緑の美しい時期に可愛らしい赤い実がなります。風通しのよい日の当たる場所に配置しておきます。葉が沢山重なっていると日が当たりづらくなってしまいます。
増やし方や害虫について
増やし方は基本は挿し木で増やします。茎を斜めに切って水揚げをよくします。茎の下部分は葉を取り除き、場合によっては葉を半分に切る事で水分を葉に奪われないですみます。園芸店に行きますと挿し木用の用土が販売されていますので使用するといいです。根が付くまでは表面の土が乾かないように水やりをします。
根が付いたがどうかの確認は新しい芽や葉が伸びてきたかどうかで判断します。しっかり根が付くまでは半日陰位の場所が適しています。風通しの良い場所がおすすめです。根が付けば生命力は強くなります。挿し木に適した時期は気温が上がる6月位が適しています。
ツルグミは害虫はあまり付かないのが特徴です。赤い実がなりますと鳥が食べに来ますので注意が必要です。鉢植えで楽しむ場合、時にはアブラムシやうどんこ病になる事もありますので、時々チェックしてあげるといいです。実を食べる事を前提にしますとあまり薬を使用したくない事が多いですので、冬の石灰硫黄合剤をまいて対処する方法があります。
土質は選びませんが、水はけのよい土を好みます。若い内には枝がよく伸びますが自然にまとまってきます。栽培が非常に簡単で増やしやすい植物です。初心者でも十分育てる事が出来ますので挑戦してみるといいです。害虫対策も簡単でよいのでお手入れが楽です。挿し木で増やした苗木を盆栽に挑戦してみるのも楽しいです。色々な形で楽しむ事ができるツルグミは家族で満喫できる植物です。
ツルグミの歴史
ツルグミは原産国は日本、中国、台湾となっています。寒さには若干弱くなっています。日本では本州、四国、九州、沖縄などにあります。グミ科に分類されていて、常緑つる性低木となります。比較的温暖な山地に生える事が多く、崖などでも見られます。奄美大島瀬戸内町で販売されています。観光資源PRとしています。
正式名称はツルグミですが、奄美大島ではクビ木と呼ばれています。奄美では古くから風邪の時のせき止めとして使用したり、ケガをした際の化膿止めとしても活用されています。今でも健康管理の為に煮出したお茶を飲んでいる人はいます。古くから伝わった習慣で、血圧降下や冷え性にも効果があるとされています。
また殺菌効果がある為か飲み口はすっきりとしています。インターネットなどを利用してクビ木を購入する事が出来ます。古くから奄美の山のお医者様とされているクビ木のお茶を飲んでみるのもよいかもしれません。地域によって伝わる効能や利用法は異なります。中には化粧品として活用している地域もあります。
グミ科には色々あって、落葉樹ではナツグミとトウグミがあります。常用樹にはナワシログミとツルグミがあります。全て、花や果実はよく似ていて見分ける事が困難になっています。文化的背景は万葉集などには現れていませんが、江戸時代の本草綱目啓蒙などにその名が登場しています。ツル性になっている植物の為、他の植物にからまりながら成長していく事もあります。
ツルグミの特徴
ツルグミの特徴はその名の通り、枝がツル状に伸びていきます。常緑になりますので、生垣にするお家にあります。フェンスに巻きついて伸びていく事で目隠しとなります。最大の特徴は赤い実がなる事です。楕円状の実はさくらんぼに似ています。毎年秋に花が咲いて、翌年の春に実がなります。5月位から赤みを帯びてきて、6月位には熟して食べ頃になります。
日本生息地としては温暖なエリアを中心に生息しています。山がメインですが、海沿いの崖などにも生えています。寒さに弱い傾向がありますが、温暖なエリアでは強い生命力を示してくれます。日が当たる所を好んでいます。葉は5センチ位の楕円の形となっています。葉の裏側は特徴的で、銀色の毛が放射線状に広がっています。
赤褐色の鱗片が密生している事もあり、赤っぽく見える事があります。幹が太くなり他の植物にからまって大きくなりますと花を咲かせるようになります。若い木はあまり花が咲きません。昔から薬効が期待されていましたが、近年は化粧品としてもその効果が期待されています。スキンケアとして顔や全身に使用する事が出来ます。
保湿性が高く、お肌をよい状態に整えてくれます。商品化したものがインターネットで購入する事が出来ます。自然の力を一度試してみるといいです。また鉢植えのツルグミも販売されています。鑑賞用として購入する人がいます。赤い実はかわいらしさがあります。盆栽用としても販売されていますが苗木よりも割高になっています。
-

-
グミの仲間の育て方について
グミと言うとお菓子を連想する人は多いものですが、お菓子のグミと言うのは、グミの仲間となるものを原料として、果汁を搾りだし...
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
きつねのぼたんの育て方
きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は...
-

-
アカザカズラの育て方
夏になると、近年は省エネが叫ばれ、電力の節約のためにさまざまな工夫がなされます。つる性の草のカーテンもそのひとつだと言え...
-

-
ガザニア・リゲンスの育て方
ガザニア・リゲンスの特徴について言及していきます。まずは花言葉から書きます。花言葉は「あなたを誇りに思う」です。植物の分...
-

-
リクニス・コロナリアの育て方
花の特徴として葉、ナデシコ科、センノウ属となっています。いくつかの花の名前が知られていて、スイセンノウの他にはフランネル...
-

-
植物の栽培、育て方のコツ。
植物を育てるのは生き物を飼うのよりはだいぶ気楽にできます。動かないので当然といえますが、それでもナマモノである以上手を抜...
-

-
アスチルベの育て方
アスチルベの歴史は比較的浅く、ドイツで品種改良された園芸種ですが日本にも自生しているので古くから親しまれてきました。日本...
-

-
パンジーゼラニウムの育て方
パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ...
-

-
すなごけの育て方
特徴は、何と言っても土壌を必要とせず、乾燥しても仮死状態になりそこに水を与えると再生するという不思議な植物です。自重の2...




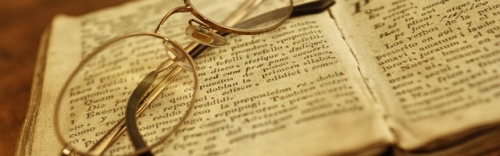





ツルグミの特徴はその名の通り、枝がツル状に伸びていきます。常緑になりますので、生垣にするお家にあります。フェンスに巻きついて伸びていく事で目隠しとなります。最大の特徴は赤い実がなる事です。楕円状の実はさくらんぼに似ています。毎年秋に花が咲いて、翌年の春に実がなります。