カレンジュラの育て方

カレンジュラの育て方
カレンジュラは9月頃から11月頃にかけて植え付けをします。日当たりが良い場所に植えるのが基本です。日当たりがあまり良くないと花付きがあまり良くないためです。土は水はけが良く、さらに水もちが良いものが適しています。小粒の赤玉土を7、腐葉土を3の割合で混ぜ合わせたものを利用するのがオススメです。
市販されている花と野菜の培養土であればそのまま使えばOKです。酸性の土の場合は苦土石灰を混ぜて土作りをしても良いです。ポットに入っている苗を植えつける場合は65cmほどのプランターで4株程度と考えておくとちょうどよいです。もう少したくさん植えたいという場合は6株までにしておきましょう。
どの植物でもいえることですが、あまりにぎゅうぎゅうに植えてしまうと風通しが悪くなり、病気などにかかりやすくなります。寒冷地の場合は苗の植え付けは春頃にしておいたほうが良いです。地植えにする場合はあらかじめ土にゆっくり効いてくるタイプの化成肥料を混ぜ込んでおくようにします。ただしあまりチッ素成分が多すぎないものにします。
これは茎だけが伸びて花の付きが悪くなってしまうことが考えられるからです。またカレンジュラを栽培していく上で病気にかかりやすくなってしまうので避けたほうがいいです。生長が悪い時や葉の色がいまいちだと感じた時には10日に1度程度でいいので液体肥料をカレンジュラに与えてあげるのも育て方のコツです。
かかりやすい病気にはウドンコ病があります。原因は風通しの悪さなので適度に株を間引いておくなどしておくといいです。ウドンコ病はその名の通り、小麦粉のような白い粉のようなカビが発生してしまう病気です。害虫ではヨトウムシに注意が必要です。ガの幼虫なのですが、見た目はイモムシに似ています。
体は茶色っぽいのですが、若い幼虫ですと緑色をしています。夜行性で暗くなった時に隠れていた場所から姿を現して葉や茎を食い荒らしてしまいます。ですから育て方のコツの一つとしては時々でいいので、夜に懐中電灯などを使って株の周りをチェックしてみることです。もしヨトウムシがいたら即退治してしまいましょう。殺虫剤も効果があるのですが、大きくなってしまったヨトウムシには効かないことがあります。
カレンジュラを増やしたい時は?
カレンジュラを増やしたい時にはどうしたらよいのかといいますと、栽培していると花が枯れた後に種付けされているのを発見することができます。その種を保存しておいて秋にまくのです。そうすると発芽率がとても高いです。
しかもカレンジュラの種付けされた種は寿命が長いといわれていて、種付けされたものを採取してから5年ほどたっているものでも発芽するそうです。しかし確実に発芽させたいのであれば、その年の種付けでとれた種をまいてしまうほうが発芽率もその分高くなるので良いです。
種を直接まくのであればプランターや花壇にそのまままいてしまっても良いですし、ポットに入れて苗を作ってから植え替えるようにしても良いでしょう。もし種付けをする必要がない株があれば、その花は切り取ってしまえばこぼれ種などで増えていく心配がありませんので、その作業は忘れないようにしたほうがいいです。
カレンジュラのたくさんある花言葉
カレンジュラには花言葉がたくさんあります。慈愛、別れの悲しみ、乙女の美しい姿、失望、悲しみ、用心深い、悲嘆、静かな思いなどです。これらの悲しみに関係した花言葉はギリシャ神話が由来となっています。
暗い悲しみという花言葉もあり、こちらは当時キリスト教が広まっていたヨーロッパでローマ皇帝のシンボルカラーである黄色を嫌ったことからつけられたといわれています。ローマ皇帝はキリスト教徒を迫害していたといわれていますので、そのことから黄色を否定的に見ていたためです。
ただ昔はその開花時期が長いことから変わらぬ愛の象徴になっていたこともあり、陽気な恋や初恋、変わらぬ愛などの花言葉もあります。献身という意味もありますので、花束として贈ってみるのも素敵です。結婚式の花飾りや礼愛のお守りなどにも使用されていました。
カレンジュラは皮膚のガードマンと呼ばれるほど皮膚や粘膜、血管などに効果的だといわれています。ハーブティーとして飲まれることも多いですが、生理痛や潰瘍による痛みなども和らげますし、月経不順や更年期障害の緩和にも良いとされています。
また発汗や解熱作用もありますから風邪の引き始めなどに飲むことで改善が期待できます。ただしカレンジュラにアレルギーを持っている方も時々いますから、自分がアレルギーを持っていないかということをわかっている場合のみ飲んでみるのがいいです。殺菌力や消炎力もありますから日焼けややけどの時にも使えます。
カレンジュラの歴史を知っておこう
カレンジュラはキンセンカのことで、ポット・マリーゴールドという別名があります。原産地や生息地は南ヨーロッパで、育てるのはそれほど難しいといわれていません。南ヨーロッパにはカレンジュラの原種がおよそ15種類ほどあります。日本へは江戸時代末期に渡来したといわれています。
カレンデュラという名前はラテン語の一年中という意味があるカレンダから由来しています。これは毎月の最初の日に利子が支払われていた古代ギリシャで、いつの月初めにも花を咲かせるほど開花期が長いからだといわれています。和名のキンセンカは花色が黄色をしており、形が盞に似ているため、金盞花と名付けられたといわれています。
カレンジュラにはいろんな別名があり、数か月にわたって花が咲いていることから長春花、常春花、長生花、常夏花、時知らずなどがあります。ポットマリーゴールドは英名で、コモンマリーゴールドという英名もあります。カレンジュラは花壇やプランターなどで植えられてる他、ワイルドフラワーとしても利用されています。
トウキンセンカと呼ばれることが多いオフィシナリス種が最も多く栽培されているのですが、これ以外ではホンキンセンカが古くから栽培されています。昔は忍耐やずっと変わらぬ永遠の愛を象徴する花として愛されていました。
カレンジュラの特徴とは
カレンジュラは半耐寒性の一年草です。葉は毛に覆われており、長倒卵円形をしています。花は切花だけではなく仏花としてもよく利用されていました。品種改良もよくされていることから園芸品種も少なくありません。一重咲きと八重咲き、アネモネ咲きタイプの3種類があります。
カラーもいくつもあって、あんず色、柿色、黄色、紅橙色などがあります。開花して間もない花はハーブとしても利用されており、サラダの色どりやポプリ、入浴剤、殺菌作用があることから乾燥させて虫刺されなど薬用としても利用されることがあります。花を煎じてできた液体は外傷ややけど、しもやけのシップ剤などに利用されることもあります。
開花は12月頃から翌年の6月頃までで、草丈は20cmから大きなものですと80cmほどにまで成長します。苗は11月頃から翌年の3月頃までよく園芸店などで見かけることができます。冬から春頃にかけての風物詩としてカレンジュラを植える人は多いです。花の中心部分が黒っぽいものもよくあり、強く育てやすいのも特徴です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カレンデュラの育て方
タイトル:イベリス・センパーヴィレンスの育て方
-

-
セッコクの育て方
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木...
-

-
マンサクの育て方
マンサクの名前がついた由来といわれるものは3つあります。1つは豊年満作というところからきたという説です。マンサクは樹木い...
-

-
シンビジウムの育て方
ランはヒマラヤから中国、日本、オーストラリア、南米など広範囲に分布していますが、その中でもシンビジウムは約50種ほどある...
-

-
ボリジの育て方
この花については、シソ目、ムラサキ科、ルリジサ科に属するとされています。一年草なので1年で枯れてしまいます。高さとしては...
-

-
アボカドの種を観葉植物として育てる方法。
節約好きな主婦の間で、食べ終わったアボカドの種を観葉植物として育てるというチャレンジが密かなブームとなっているのをご存知...
-

-
ミニトマトのプランターの栽培方法
ミニトマトの栽培は初心者でも簡単に育てられ庭がなくても、プランターで栽培出来きるので、プランターでミニトマトの育て方はと...
-

-
スカビオーサの育て方
別名を西洋マツムシソウといいます。英名ではピンクッションフラワーやエジプシャンローズ、スイートスカビオスなどあります。ス...
-

-
熱帯スイレンの育て方
スイレンは18世紀以前から多くの人に愛されてきました。古代エジプトにおいては、太陽の象徴とされ大事にされていましたし、仏...
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
リューノヒゲの実の育て方
別名ジャノヒゲとも呼ばれるのがリューノヒゲの実であり、国内での生息地は北から南にかけてで、山地の林などに生息し、原産地は...




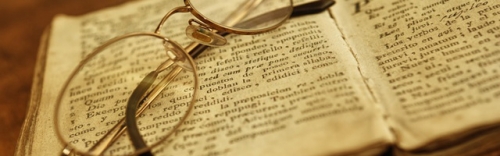





日本ではキンセンカという名でよく知られているカレンジュラのことをよく知って育て方を工夫しながら栽培していきましょう。カレンジュラはキンセンカのことで、ポット・マリーゴールドという別名があります。原産地や生息地は南ヨーロッパで、育てるのはそれほど難しいといわれていません。南ヨーロッパにはカレンジュラの原種がおよそ15種類ほどあります。日本へは江戸時代末期に渡来したといわれています。