バンレイシの育て方

育てる環境について
バンレイシは生産地が国内最西端の島が実在する都道府県とごく限定されていますが、我が国でも栽培するのは可能です。しかし、育て方としては鉢植えで育てるのが適しているとされています。また温度管理に気を付けるというのも大切です。というのもバンレイシは寒いところに対しては少し弱いという特質を持っていて、氷点下2度ぐらいが耐えられる寒さの限界だとされています。
また摂氏10度以下になると生長が止まるとも言われています。なので、寒い地域で育てたり、冬のシーズンに栽培したりする際には暖房設備のあるところで育てるのがベストです。鉢植えでなくとも庭で植えるというのも不可能ではないですが、住んでいる地域によっては外で栽培するのが不可能な場合があり、国内で最も北に位置している都道府県の場合は外での栽培は適していないです。
外で育てる場合で適している地域は首都圏が属している地方を基準にして、そこから南の地域であると言われています。そういう地域に当てはまらないところは室内で育てるのが無難です。だんだん気温が低くなってくる10月以降は保温管理をしておくのが大事になってきます。
広い場所で育てた場合は5メートルの高さに生長しますが、鉢植えで育てた場合は生長の進み具合が遅くなります。生長するスパンが早いとされていて、適している環境の下で、苗木から栽培した場合は2年ほどで実が結び収穫が可能となり、種子から栽培した場合でも3年ほどで実がなって収穫するのが可能となります。
種付けや水やり、肥料について
水やりに関しては、どういうシーズンであるかどうか、関係なく与えるのが無難ですし、気温が高いシーズンは乾燥するきらいがあるので、多目に与えるのがベターだとされています。また乾燥していないかどうか、こまめにチェックしておくというのも一つの手です。肥料を与えるのが2月、12月を除く偶数月が適しているシーズンだとされています。
ただ、シーズンは多少栽培している地域によって違いはあるので、温暖な地域であれば与えるシーズンを少し早め、反対に寒冷な地域であれば、少し遅らせて行なうのがベターです。なおこういうシーズンの調整は肥料を与える行為だけに限らず、枝の剪定、果実の収穫などにも言える事柄です。
与える肥料は化成肥料ですが、一部では有機配合肥料を与えて栽培している者も実在しています。土ですが排水の機能が高い土で育てるのが正しい育て方だとされています。またバンレイシは1本だけでも実を結ぶプラントです。なお、収穫するシーズンは生育させている場所によって多少の違いがありますが、9月か10月ぐらいだとされていますが、
収穫が可能なタイミングとしては、花が咲いてから数カ月ほど経過したシーズンが適していると言われています。枝の剪定ですが、基本的にはしなくても大丈夫だと言われていて、剪定を行なうのであれば、1月ぐらいに枝を整うために行なう程度で構わないです。置き場所ですが、半分日陰になっているような場所でも生長します。
増やし方や害虫について
バンレイシは、前に述べている通り、1本の苗でも実を結ぶのが可能であるプラントであり、また挿し木あるいは接ぎ木でも繁殖が可能だとされています。したがって受粉するために複数の苗を用意しなくとも果実を作り出すのが可能です。ただ授粉をさせなければ実がなりにくいと言われているので、果実を作りたいのであれば授粉をさせるのが大切です。
害虫に関してですが、基本的に害虫による被害は少ないと言われています。しかし、キクイムシの仲間が実在する場合があるので、そういう事態になった場合は薬剤を散布して被害を小さくするようにします。疾患にも強いプラントだとされています。なお、キクイムシはバンレイシ以外のプラントにも見られる昆虫であり、我が国では数百種も実在しているとされています。
また家の柱に使われている木材も食い荒らすというケースも珍しくないです。基本的に幼虫だけではなく成虫も木材、樹木を食い荒らすとされています。キクイムシを駆除する薬剤も販売されていて、ネットでも言うまでもなく販売されています。前述のように害虫、疾患が発生するという事態にはなりにくいとされていますが、
栽培を行なう際に気を付けておきたいのは前の段落で記述している通り、温度の管理です。温度が低すぎると生長が止まってしまう事態になりかねないので、常に一定の温度を保てるように調整しなければならないです。冬のシーズンの間は一定の温度を保った室内で栽培するのが適しています。
バンレイシの歴史
バンレイシは果実の皮の突起の形が仏教を創設した者の頭に似ているのでシャカトウとも呼ばれているプラントです。ちなみに英語ではシュガーアップルと呼ばれています。熱帯に属されているところで栽培されていて、我が国でも国内で最も西側に位置している島が実在している都道府県で生産された果実が少しながらも出回っています。
しかし原産地は国内総生産第一位の国から近く、かの新大陸を発見した者が上陸したとされる島、かつて帝国があった高山が位置している国をはじめとする地域だとされていて、そこを生息地としていたのが、今ではあまたの国で栽培されているという事態になっています。また名前の由来は南蛮で育てられたレイシだとされています。
牛肉麺で名が知られている国では1600年代にチューリップの国の者が持ち込んだとされていて、一部の地域では名産品になっていますし、そういう果実を使ったアイスクリームも実在しています。また国内総生産第二位の国でも栽培されていますが、そういう国の場合は1800年代に華僑が国内総生産第二位の国でバンレイシを育てたのがきっかけだとされています。
食材だけではなく薬として使われているとされています。葉っぱの部分は下痢を止める薬、または下剤、かゆみを抑える薬などに使われ、種の部分はココナッツオイルに漬けて使用すれば、シラミが集らないようにするための薬としての役割を果たせます。国内総生産第一位の国でも薬として使われています。
バンレイシの特徴
前にも述べていますがシャカトウと呼ばれているのは、果実の形が仏教を創設した者の頭に似ているからだと言われています。またシュガーアップルという呼び名も果実の糖度が高いという特質を持っていて、事実食べてみるとかなり甘い味がするとされています。食感は、石細胞と呼ばれている、梨などに実在している細胞があるためにジャリジャリとしています。
熟していない果実を熟させるのであれば、20度から25度ぐらいのところで数日置いておくと熟するとされています。熟してから食べて、残した果実を保存するのであれば冷蔵庫のような温度の低い場所で保存するのが適しています。なお、熟していない果実を温度の低いところで保存すると風味などが劣る現象が発生すると言われています。
また熟すると皮が黒色に変わり、柔らかくなります。そして皮が勝手に割れてきます。出回っている果実は熟していない果実が大半を占めていますが、我が国への流通はほぼないとされていて、訳としては持ち運びに不適当な果実であるから、保存がきかない果実であるからだとされています。
種子には毒が実在しているので、食べる際にはきちんと取り除いてから食べるのがベストです。食べ方としてはリンゴなどのようにカットして、スプーンですくって食べるというのが一般的ですが、熟した果実は脆くなっていて、手でも割れるくらいになっています。シャーベット、ケーキなどの食材として使われるケースも実在しています。
-

-
サンショウ(実)の育て方
学術的な系統では、ミカン科サンショウ属ということで、柑橘類に所属しているということも面白いですが、香料関係の植物は、この...
-

-
ローズゼラニウムの育て方
ローズゼラニウムの特徴は、やはりバラのような甘い香りです。クセのある甘ったるさではなく、ミントが混ざったようないわゆるグ...
-

-
エイザンスミレの育て方
エイザンスミレは多年草のスミレの仲間ですがこのスミレ属は広く世界中で愛されている花です。エイザンとは比叡山を指し、この比...
-

-
ヒサカキ(実)の育て方
ヒサカキは、日本でもよく見られる低木ですが、よく神社などにあります。それは榊の代わりに玉串などで用いるからで、仏壇などに...
-

-
エリゲロンの育て方
花の特徴として、種類はキク科になります。和名でキクの名前が入っていることからキクに似ていることはわかりますが種類に関して...
-

-
ホウレンソウの育て方
ホウレンソウの特徴としては、冷涼な地域などや季節に栽培されると育ちやすいということで、冷え込んだりすると柔らかくなり美味...
-

-
オンシジウム育て方
オンシジウムの一種で特にランは熱帯地域で種類も多くさまざまな形のものが見られることが知られています。それらを洋蘭と呼び、...
-

-
ヘデラの育て方
ヘデラは北アフリカ、ヨーロッパ、アジアと広い地域を生息地とする非常に人気がある常緑性のつる植物です。非常に様々な品種があ...
-

-
小松菜の栽培に挑戦してみよう。
今回は、小松菜の育て方について説明していきます。プラナ科である小松菜は、土壌を選ばず寒さや暑さにも強いので、とても作りや...
-

-
アボカドのたねは捨てずに育てよう
「森のバター」とも呼ばれている果実をご存知でしょうか。これは、アボカドの事を指しますが、栄養価が高く、幅広い年代に人気の...




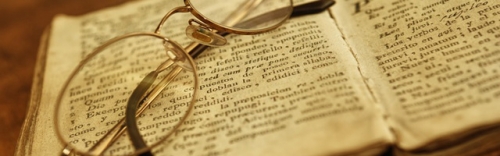





バンレイシは果実の皮の突起の形が仏教を創設した者の頭に似ているのでシャカトウとも呼ばれているプラントです。ちなみに英語ではシュガーアップルと呼ばれています。熱帯に属されているところで栽培されていて、我が国でも国内で最も西側に位置している島が実在している都道府県で生産された果実が少しながらも出回っています。