クロウエアの育て方

育てる環境について
クロウエアは日当たりと風通しのよい場所を好みます。高温多湿と植える際の土に注意すれば、育て方はそれほど難しくありません。鉢植えの場合の置き場所は、春から秋は日光のよく当たる場所か明るい日陰になる場所が適しています。高温多湿に弱いため、梅雨の時期は雨を避けられる場所に置き、
真夏は直射日光が当たらず風通しのよい場所に置いて、温度や湿度が上がりすぎないように気をつけましょう。梅雨明けから秋のお彼岸までは半日陰程度がちょうどよいです。冬はベランダや室内の日当たりのよい場所に置きます。凍らない場所であれば大丈夫です。
ある程度の耐寒性はありますが、霜や冷たい風に当てると株が傷んでしまいます。株が傷むと春からの成長に大きく影響しますので、注意しましょう。霜が降りない地域では、特に防寒対策をしなくとも戸外で冬を越させることができます。地植えにする場合は、水はけのよい場所を選んで植えつけます。
水はけが悪い場合は、まわりに排水用の溝を掘るか、盛り土をしてから植えつけるようにします。酸性の土を好むため、植えつける場所に石灰を混ぜることは禁物です。土は、水はけと水もちのよい酸性土を好みます。鹿沼土小粒と酸度未調整ピートモスを同じくらいの分量で配合した土などに植えつけるとよいでしょう。
ピートモスは酸度を調整してあるものもあるため、入手する際は表示に気をつけて選びましょう。植えつけは、芽を出して成長する前の3月頃が適当です。鉢植えのものを植え替える際も同じ時期がよく、2年に1回程度、ひと回り大きな鉢に植え替えていきます。
種付けや水やり、肥料について
春から秋は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。クロウエアは過湿の環境に弱く、いつもじめじめと土が湿っている状態だと弱ってしまいます。乾燥には比較的強いですが、すぐに水切れする環境も苦手です。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらすぐにたっぷりと水を与えてください。
特に夏は、水切れさせないように気をつけてあげましょう。冬は寒さで成長が遅くなるため、水やりを控えてやや乾かし気味に管理するとよいでしょう。地植えの場合は、特に水を与える必要はありません。ただし、周囲より一段高くなっている花壇などに植えている場合は、
雨が何週間も降らないような時には水を与えてください。肥料は、4月~7月と9月~10月に、ゆっくり効くタイプの化成肥料を与えます。配合は、窒素・リン酸・カリウムが同じくらいのものがよいでしょう。または、上記の時期に草花に与えるのと同じ程度の濃度の液体肥料を与えてもよいです。
真夏は暑さで生育が弱るため、肥料は控えます。成長して丈が伸び、樹形のバランスが悪くなってきたら、枝を半分くらいの位置で切り戻すとよいでしょう。春から初夏の花のピークがいったん終わった後に切り戻すと、
夏の花を見ることはできませんが秋に一斉に咲く様子を楽しむことができます。春から秋まで花を途切れさせたくない場合は、秋の終わりに切り戻します。暖かい場所で育てている四季咲き性のものは、3月頃に切り戻しを行ってもよいでしょう。
増やし方や害虫について
クロウエアは、さし木で簡単にふやすことができます。5月~6月、または9月頃に、その年に伸びた新しい芽で元気のよいものを選び、先から2~3節のあたりで切り取って、30分ほど水に挿して吸水させます。その後、湿らせた赤玉土か、
鹿沼土小粒と酸度未調整ピートモスを同量ずつ配合した土に挿します。市販のさし芽・種まき用の土でも大丈夫です。1か月ほど経つと根が出てきます。真夏は水切れさせやすいので、根が出るまでは乾燥に気をつけましょう。クロウエアは過湿に特に弱く、
日本の気候では過湿で急に枯れてしまうことがあるため、数年に一度はさし木して、予備の苗を作っておくと安心です。病気には強いですが、まれにカイガラムシとアブラムシが発生することがあります。予防のためには、日当たりと風通しのよい環境で育てるのが第一です。
カイガラムシの成虫は殻をかぶっていたり、ロウ状の物質で覆われているため、駆除が難しい害虫です。発生してしまった場合の駆除の方法としては、手や歯ブラシなどでこすり落とす方法と、薬剤を使う方法があります。
切り戻しを兼ねて、カイガラムシの発生している枝を切り除いてもよいでしょう。薬剤は幼虫にはすぐに効果がありますが、成虫に対しては産卵抑制や孵化しない卵を産ませるなどのなど間接的な効果となるため、駆除までには時間がかかります。
アブラムシは薬剤で駆除するのが効果的です。薬剤はすぐに効きますが、アブラムシは繁殖力が旺盛で、成虫は条件がよければ1日で数匹~数十匹の子を生んで増えていくため、長期間効果が続くタイプの薬剤を使うのが便利です。
クロウエアの歴史
クロウエアはオーストラリア島南部原産の、ミカン科クロウエア属の常緑小低木です。クロウエアの名は、イギリスの植物学者・園芸家のジェームス・クロウを記念してつけられたものです。5弁の花びらを持つ小さな花が緑の葉の中に浮かんでいるように見える様子が星を連想させ、
さらに生息地がオーストラリアであることから、日本に持ち込まれた際は「サザンクロス(南十字星)」の名で紹介されました。南十字星は南十字座ともいい、南天の星座のひとつです。88ある星座の中で最も小さいですが、南の空のシンボルとして、オーストラリアやニュージーランドなどの国旗にもあしらわれています。
小さな星でできた小さな南十字星と、クロウエアの花のイメージはよほどぴったりきていたのか、現在でも日本では「サザンクロス」の名で流通しているのを多く見かけます。しかし、英語だとサザンクロスと呼ばれる植物は、セリ科の別の植物となります。
よく知られている種としてはサリグナ種とエクサラタ種とがあり、その2種をかけ合せて作られたポーリンダ・エクスタシーなどの園芸品種もあり、よく栽培されているものには10種ほどがあります。サリグナ種とエクサラタ種には見かけ上それほど違いはありませんが、
花の咲く時期が異なり、またサリグナ種の方がやや葉が大きいです。日本で主にサザンクロスの名で流通しているのはエクサラタ種の方です。エクサラタ種は、英語では「スモール クロウエア(Small crowea)」と呼ばれています。
クロウエアの特徴
クロウエアの花はかわいらしい星の形をしており、直径は1~3cm程度で、肉厚で蝋細工のような光沢があります。色は濃淡さまざまなピンクのバリーしょんのほか、白もあります。花は上部の葉のわきにひとつずつつき、色を保ったまま1週間以上も咲き続けます。
つぼみもたくさんつき次々と花を咲かせるため、長く花を楽しめる植物として人気があります。一定以上の気温があれば、ほぼ1年を通して花が咲きますが、主な開花期はサリグナ種が秋から冬、エクサラタ種は春と秋です。樹高は20cm~2mほどと幅がありますが、
枝は次々と枝分かれしてよく茂ります。葉はやや細かく、先端のとがった細めの楕円形をしています。クロウエアはミカン科ですが、茎と葉からは柑橘類特有の香りがします。エクサラタ種はもともとオーストラリアのビクトリア州とニューサウスウェールズ州の森林地帯に分布する種です。
繊細で細長い葉を持ち、ピンク色の小さめの花は基部中央がドーム状に盛り上がっています。基本的には春と秋に花を咲かせ、暑すぎる夏や寒すぎる冬には休眠しますが、四季咲きの性質を持ち気候がよければ年間を通じて咲くこともあります。
サリグナ種はオーストラリア東部、ニューサウスウェールズ州の中部に分布し、海岸沿いのまばらな林に自生しています。葉がエクサラタ種よりも大きく幅が広いです。花は薄ピンクから濃いピンクまであり、花びらの幅もエクサラタ種よりやや広い印象を受けます。
エクサラタ種とサリグナ種を交配させて誕生したのが、ポーリング・エクスタシーという園芸種です。一般的には鉢花として栽培されていますが、比較的耐寒性があり、暖かい土地や平地では地植えすることも可能です。
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...
-

-
オシロイバナの育て方
日本に入ってきたのは江戸時代に鑑賞用として輸入されたと言われており、当時この花の黒く堅い実を潰すと、白い粉が出てきます。...
-

-
ファレノプシス(コチョウラン)の育て方
学名はファレノプシスですが、和名をコチョウランとも言い、日本でランと言えば、胡蝶蘭を思い浮かべるくらい有名で、人気がある...
-

-
スリナムチェリーの育て方
スリナムチェリーはフトモモ科の常緑の低木でこの樹木の歴史は非常に古くブラジルの先住民族が赤い実を意味するスリナムチェリー...
-

-
クガイソウの育て方
クガイソウは、日本でも古くから知られていた植物で、昔の植物の書物にも載せてあるくらいですから、相当有名な薬草だったという...
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...
-

-
とうもろこしの育て方
昔の生息地や原産地、起源は正確には分かっておらず、現在のとうもろこしの先祖にあたる野生のものが見つかっていないのです。大...
-

-
ギリアの育て方
種類としてはハナシノブ科になります。別名があり、タマザキヒメハナシノブ、アメリカハナシノブなどの名前が付けられています。...
-

-
ネコノヒゲの育て方
このネコノヒゲの特徴は、何と言ってもピンと上を向いた猫の髭の様な雄しべと雌しべではないでしょうか。髭の様な雄しべと雌しべ...
-

-
ピメレアの育て方
ピメレアは育てるのに、簡単で丈夫な植物になりますが、どうしても夏場は気をつけてあげないといけないです。夏場は高温になって...




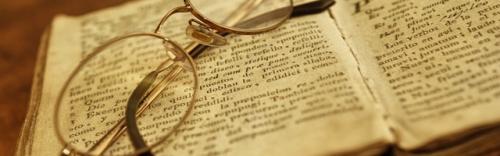





クロウエアはオーストラリア島南部原産の、ミカン科クロウエア属の常緑小低木です。クロウエアの名は、イギリスの植物学者・園芸家のジェームス・クロウを記念してつけられたものです。