イワシャジンの育て方

育てる環境について
イワシャジンを育てる環境については基本的には山地の気候などを参考にすると栽培方法が理解しやすいのですが、高い樹木の根元の部分や岩などの表面に自生している植物であることから、乾燥することを何よりも嫌っていて、とくに夏の暑い時期に乾燥をするとそのまま枯れてしまうことがあります。
また岩場などで見られる植物であるということからコンクリートなどに自生すると考える初心者もいるのですが、コンクリートは夏の強い日差しをそのまま反射してしまうので植物を高温にして乾燥させてしまいます。アスファルトやコンクリートの上で自生できる植物は限られていて、
特に山地を生息地としている植物はなるべく直射日光が当たらない場所で、さらに風通しが良い方角での栽培が良いとされています。湿った気候で生息している植物なので、梅雨の時期のように湿度の高い季節は気温が高くても十分に適応するのですが、
梅雨明けしてしまうと太陽の光が強くなるので、日陰となる場所を選んで育てないと乾燥と高温によって、枯れてしまうことがあります。また冬の間は休眠状態になるのですが、寒さのために地面が凍ってしまうと株が弱ってしまうので翌年になっても花を付けなくなります。
冬の時期は根の状態で越冬するので、雨が当たらない環境で十分に体力の回復をさせることが必要なので、棚の下などで育てると霜などが降りないのでコンディションが良いまま翌年に小さな花をたくさんつけるようになります。
種付けや水やり、肥料について
乾燥が苦手な植物なので水やりのタイミングは非常に重要で、水が不足してしまうと全体的に体力を失ってしまって、枯れてしまうことがあります。基本的な水やり方法としては土の表面が乾いたらたっぷりと水分を与えるというもので、真夏の時期には乾燥しやすいので
最低でも1日に1回は水やりをしなければなりません。しかし夏に風通しの良い場所に置いたとしても高温になると乾燥してしまうので、1日1回にこだわらずに乾燥がひどい場合にはもう一度水やりをしてもかまいません。湿度が高い環境を好む植物なのですが、
水が土の中に溜まりすぎている状態は苦手なので、鉢植えをする場合にはなるべく水はけの良い用土と選ぶようにしなければなりません。桐生砂と軽石の小粒を同じくらい配合したものと鹿沼土を混ぜて、さらに市販の山野草の培養土を使うと水はけが良くて、
イワシャジンにとって最適の土を作ることができます。また水持ちが悪くなった場合にはミズゴケなどを使うと理想的な栽培環境を作り出すことができます。肥料に関しては春から秋にかけて液体肥料を10日に1度くらい与えておくことで、十分に生育することができるのですが、
真夏の暑い時期には生育がストップするので、肥料を与えないようにする必要があります。生育が止まっている植物に肥料などを過剰に与えてしまうと吸収できない肥料が細菌などの餌になって根元の部分を腐らせる原因になることがあるので、注意が必要です。
増やし方や害虫について
イワシャジンの増やし方は種まきと株分けがあるのですが、種まきをする場合は冬の初めから早春にかけての時期で、発芽をした後は毎年植え替えを行って苗を作る必要があります。発芽を確認してから花を咲かせるまでの期間は2年から3年とされています。
株分けをする場合には植え替えをするときに行うのが一般的で根が簡単に別れる場合にはそのまま手を使って分けてしまっても良いのですが、手で分けられない場合にはナイフなどを使って芽の位置を確認しながら作業をしなければなりません。害虫としては春に芽の部分や茎にアブラムシが発生することがあります。
アブラムシは直接被害として芽や葉の裏に寄生をすることで植物の汁を吸い取ってしまうことがあるのですが、少数のアブラムシなら何も問題は起きません。しかし大量に発生してしまうと生育状況が悪くなってしまって、葉が枯れてしまうだけでなく全体的に体力を失って、最終的に枯れてしまうことがあります。
また葉の表面にコブができたりするので美観を損なってしまいます。また間接的な被害としてはウイルス病の媒介で、この場合は植物の栄養素を吸い取ったアブラムシが他の植物に移動することで、感染させてしまう病気なので、大量に発生する前に薬剤などを使って
駆除をすることが重要です。薬剤が効果的なのですが、アブラムシの繁殖能力は非常に高いので、長期間効果が続く浸透移行性剤を使うと便利です。様々な薬剤の利用ができるので、環境に合ったものを選んで使用すると健康的な生育状況を守ることができます。
イワシャジンの歴史
イワシャジンは関東地方の南西部や中部地方の南東部の山地の岩場などで見つけられることができる紫色と小さな花をつける大きめの多年草で、秋につける釣鐘状の花が個性的で、岩場などから垂れ下がるようにして花が咲きます。とても風情のある植物なので日本国内で非常に人気の高い山野草です。
この種類には原産地や生息地などの気候などによって変異することが多い品種で、様々な種類があるので愛好家などは様々な場所のイワシャジンを栽培して楽しんでいます。昔から人気のある花ですが、地下にごぼうの根を束ねたような根茎をもっていて、
株元の部分に独特の形をした葉を広げてその中心から細い茎と糸状の葉が立ち上がって花の芽を生育させていきます。この花芽は夏の気温が高い時期に成長して、秋になると小さな花を次々に咲かせ続けます。そしてその時期が終わると茎が枯れて休眠状態になります。
乾燥に弱い品種なので生育期に乾燥することが内容に注意が必要で、基本的には山の中で自生している植物なので育て方に関してはなるべく地面の湿度を保って、直射日光が当たらないようにする必要があります。これはこの植物の生育環境に関係していて、
山の中は基本的には太陽の光が直接入ってこない場所なので乾燥することもなく、強い光などもイワシャジンには届きません。実際に栽培をする場合には山の中と同じような環境を作ることで多年草を楽しむことができます。冬は地上に出ている部分が枯れますが、地中ではしっかりと根を張っています。
イワシャジンの特徴
イワシャジンの特徴としては紫色の小さな花の付き方が特殊であるということで、釣鐘状の花がぶら下がるように岩などから垂れ下がっている姿がとても個性的なので、日本各地の山地などでも人気となっていて、また場所によって少しずつ品種が異なっているのも特徴で、
自生している環境によって様々な変異を繰り返して適応しながら生育していく植物なので、少しずつ違った特徴をもつ種類がいろいろな場所で栽培されていたり、自生しています。また湿気を好む植物なのでコンクリートなどの上で栽培するなどするとすぐに枯れてしまうので、
なるべく直射日光が当たらない場所に置く必要があります。また日陰の岩などに自生していることが多いので、庭などで栽培する場合には木陰の岩などで栽培をさせると長持ちさせることができます。また関東よりも西の地域でイワシャジンを栽培する場合には
夏の時期の気温や乾燥には気をつける必要があり、風通しを良くしたり日陰に置くなどしてある程度の湿度を確保しないと急激に体力を消耗させてしまって、枯れてしまうことがあります。愛好家に人気の栽培方法としては軽石で作った鉢や高さがある程度ある鉢などに植えることで
垂れ下がる花を美しく演出することができるので、垂れ下がる株姿を鑑賞するためにはこのような工夫を必要としています。また様々な色の花を集めるのも愛好家の楽しみの一つとなっています。冬になると緑の部分が枯れて無くなってしまうので休眠している位置を確認しておく必要があります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ウェデリア(アメリカハマグルマ)の育て方
タイトル:イワチドリの育て方
-

-
ベニバナの育て方
ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...
-

-
ベニサラサドウダンの育て方
ベニサラサドウダの大きさは、2メートルから大きいもので5メートル程度にまで生長します。若い枝は無毛で、その葉の長さは、お...
-

-
コマツナギの育て方
この植物は背丈が高く40センチから80センチまであり、マメ科コマツナギ属の落葉小低木に分類されています。同じマメ科に属す...
-

-
金のなる木の育て方
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなど...
-

-
ハナカンザシの育て方
原産地はオーストラリア西南部で、砂地でよく育ち乾燥を好み自生しています。日本ではドライフラワーなどに良くつかわれています...
-

-
ニオイスミレ(スイートバイオレット)の育て方
ニオイスミレは、別名でスイートバイオレットとも呼ばれています。スミレ科のスミレ属に属しています。耐寒性多年草で、原産地は...
-

-
シシリンキウム・ロスラツムの育て方
北アメリカを原産地として日本には明治時代の1890年ごろに渡来してきました。鑑賞用として入ってきたのですが、繁殖力が強い...
-

-
ヒメシャラの育て方
ヒメシャラはナツツバキ属のうちのひとつです。日本ではナツツバキをシャラノキ(沙羅樹)と呼んでおり、似ていますがそれより小...
-

-
ハクサンイチゲの育て方
花の高さは約15センチから30センチで、上記でも述べたように大群落をつくります。その姿は絨毯を敷き詰めたようで圧巻です。...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...




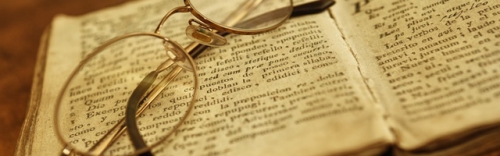





イワシャジンは関東地方の南西部や中部地方の南東部の山地の岩場などで見つけられることができる紫色と小さな花をつける大きめの多年草で、秋につける釣鐘状の花が個性的で、岩場などから垂れ下がるようにして花が咲きます。とても風情のある植物なので日本国内で非常に人気の高い山野草です。