サポナリアの育て方

育てる環境について
サポナリアを育てる上で大事なことが日当たりです。まず、日当たりの良い場所を好みます。日当たりが少し悪くても枯れることはありませんが、日当たりが良い方が花付きが良くなります。ですから、たくさんの花を楽しみたいというのなら、日当たりの良い場所におくと良いです。
冬になると枯れて根っこの部分だけが残ります。根っこの部分で冬を越します。根は寒さに強く、そこそこの寒さでも枯れることはありません。温度としてはマイナス15度くらいまで耐えられると言うことですから、日本の多くの地域ではそのままにしていても越冬できるでしょう。
あまりにも寒い地域では防寒対策が必要となります。生命力や繁殖力は非常に強いですから、増えすぎて困ることもあります。大きくなれば株分けをして繁殖を抑えるのは良い方法だと言えるでしょう。また、地下茎で増えることが繁殖を広く行わせている理由の一つであることにも注意が必要です。
地下茎が広がりすぎないように囲いを設けるなどの方法は効果的な方法の一つだと言えるでしょう。サポナリアについてもう一つ注意しておかなければならないのは魚毒性です。魚介類に対して毒性を持つ物質がありますから、注意が必要です。
池が近くにある場合には植えない方が良いです。鉢植えにして絶対に近づけないようにするのなら良いですが、地植えで近くに植えるというのは勧められません。池のある庭には植えないというのが基本だと考えておいた方が良いです。
種付けや水やり、肥料について
春から秋に植え付けます。日当たりの良い場所を選びます。土壌としては石灰分を好む傾向があります。ですから、苦土石灰などを混ぜておくと良いでしょう。日当たりが悪いと花があまりできなくなりますから、日当たりの良い場所を選ぶことが必要です。
地下茎で一気に広がる傾向がありますから、繁殖しすぎないように注意しなければなりません。地下茎が広がらないようにするためには、地中に仕切り板を埋めておくというのは良い方法です。地下茎が広がってからそれを止めるのは難しいですから、先に板を埋めておくと管理するのが楽です。
庭植えにした場合には、水やりはほとんど行わなくて良いです。逆に、水はけが悪いと根腐れしやすくなりますから、水やりをしない方が良いです。鉢植えの場合には、用土が乾いてから水を与えます。つぼみができてから花が咲くまでの間は多くの水分を必要としますから、
この時期には水を乾かさないようにしましょう。痩せた土地でも良く育ちますから、庭植えの場合には肥料をやる必要はありません。鉢植えの場合にもそれほど肥料は多くは必要としませんし、肥料なしでも育ちますが、
花を多くつけたい場合には肥料を与える方が良いです。春と秋に緩効性化成肥料をおいておくと良いでしょう。肥料をやり過ぎると弱ることがありますから注意が必要です。夏の暑い時期にはあまり成長しませんから、肥料をやる必要はありません。むしろ、肥料をやらないほうが良いです。
増やし方や害虫について
株分けで増やすのが安全な方法だと考えられます。株分けをすれば遺伝形質がそのまま引き継がれますから、同じ環境で育てれば同じ花を咲かせます。また、さし芽も同じで、さし芽で増やした場合にも同じ花を咲かせるでしょう。成長が旺盛ですから、株分けは容易です。
生命力も強いですから、さし芽をすることによってすぐに増やすことができます。タネで増やすこともできます。タネで増やす場合、花が咲いた後に、その花をそのままにしておいておきます。そうするとタネをとることができます。4月から5月頃にタネを蒔いておくと発芽します。
種まきをすると遺伝形質は変わりますから注意が必要です。野生種の場合にはタネで増やしても変化のない場合が多いです。たとえば日本で流通しているツルコザクラは野生種の一つですから、タネで増やしても変わったものができる可能性は低いです。
しかし、八重咲きの品種はタネで増やすと八重咲きでなくなってしまうこともありますから注意が必要です。確実に八重咲きのものを増やしたいのであれば、株分けにするか、あるいはさし芽で増やすのが良いと考えられます。
病気としては根腐れや白絹病があります。水はけが悪い場合に起こる病気ですから、水分を調整することは必要です。害虫としてはアブラムシがあります。アブラムシは見つけたときにすぐに防除すれば被害を防ぐことができます。八重咲きの品種ではマメコガネがつきやすいですから注意しましょう。
サポナリアの歴史
サポナリアはシャボンソウ、ソープワートと言われることもあります。種名ではなくて属名です。実際には約20種があります。野生種の生息地は南ヨーロッパから西南アジアです。サポナリアが日本に入ってきたのは明治時代です。明治時代に日本にもたらされた植物の中には
薬草として持ち込まれたものが多くありますが、サポナリアもやはり薬用植物として日本にやってきました。根を乾燥させたものがサポナリア根と呼ばれて、薬として使われていたそうです。そのために栽培が始まったのですが、現在では庭植えの草花として栽培が進んでいます。
原産はヨーロッパで、サポナリアという言葉はラテン語です。「サポ」は、「sapo」と記述することから、これが石けんという意味だと言うことはよく分かると思います。サポナリアと読むがソープワートと呼ぶかは言語の違いだとも言えるでしょう。
シャボンソウというのは、それを日本語に直訳したことから始まってます。現在ではサポンソウという呼び方が定着しています。こう呼ばれるようになったのはサポナリンという成分があるからです。サポナリンがあることによって石けんのような泡が出ます。
これが名前の由来だと考えれば分かりやすいと思います。ヨーロッパの地中海沿岸を中心に分布していて、いくつかの品種があります。それぞれの品種で日本に入ってくる時代は異なっていて、同じ属の植物でも入ってくる時代によって呼び方が異なっています。
サポナリアの特徴
サポナリアは地中海沿岸に生息する多年生の植物です。草丈は50センチくらいのものが多いですが、90センチくらいにまで育つこともあります。地下茎によって広がっていく傾向があり、主な開花時期としては初夏から秋の時期になります。茎の頂上分にある鼻の付け根に花芽が形成され、
ここから短い枝を出して花をたくさんつけます。花の色はピンク色です。野生種から品種改良されたものには、濃いピンクのものもありますし、赤色のものもあります。また、八重咲きのものなども作られています。育て方は難しいことはありません。
どちらかというと育てやすい部類に入るでしょう。品種によって特徴は若干違います。有名な品種としてオキモイデスがあります。オキモイデスは枝分かれをして横に広がっていき、茂ってまとまった形になります。20センチくらいの草丈で、
上に伸びると言うよりは横に広がるというイメージが適しています。日本には大正時代にもたらされ、「ツルコザクラ」と呼ばれることもあります。広がっていきってピンクの花を咲かせるために、このような名前がつけられています。
岩の多い庭に用いるとマッチします。もう一つ有名なものとして、ルテアがあります。ヨーロッパのアルプスに生息する原種で、草丈は10センチくらいの小さなものです。高山植物というイメージの強いもので、黄色い小さい花を咲かせます。日本名では「キバナシャボンソウ」と呼ばれることもあります。
-

-
ヤグルマギクの育て方
この花の特徴としてはまずは菊の種類であることです。キク目キク科の花になります。野生の状態で青色の状態になっています。です...
-

-
マスタード(カラシナ)の育て方
特徴として、フウチョウソウ目、アブラナ科、アブラナ属となっています。確かに葉っぱを見るとアブラナ、菜の花と同じような形を...
-

-
コロカシアの育て方
コロカシアの原産と生息地は東南アジアや太平洋諸島です。それらの地域ではタロという名前で呼ばれていて、主食としてよく食べら...
-

-
イワカガミダマシの育て方
イワカガミダマシはソルダネラ・アルピナの和名ですが、漢字では岩鏡騙しといい、ヨーロッパのアルプス山脈やピレネー山脈、アペ...
-

-
エキザカムの育て方
エキザカムはリンドウ科の植物で、別名でベニヒメリンドウ、エクサクムと呼ばれることもあります。 属名の Exacum は、...
-

-
ダイズの育て方
ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つま...
-

-
アザミの仲間の育て方
アザミの仲間の種類は多く、科属はキク科アザミ属です。生息地で言うと、日本に多く見られるのは、日本が原産国であるためです。...
-

-
ギョリュウバイの育て方
ギョリュウバイはニュージーランドとオーストラリアの南東部が原産のフトモモ科のギョリュウバイ属に分類されている常緑樹で、日...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
アシダンセラの育て方
花の特徴としてはアヤメ科になります。草の大きさとしては60センチぐらいから90センチぐらいになります。花が開花するのは秋...




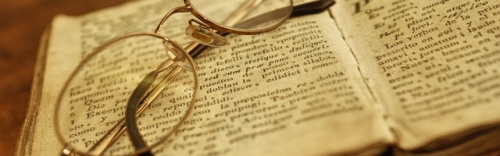





サポナリアの科名は、ナデシコ科で属名は、シャボンソウ属(サポナリア属)となります。また、和名は、シャボンソウでその他の名前は、サボンソウ、ソープワートなどと呼ばれてます。サポナリアはシャボンソウ、ソープワートと言われることもあります。種名ではなくて属名です。実際には約20種があります。野生種の生息地は南ヨーロッパから西南アジアです。