シラサギカヤツリの育て方

育てる環境について
水辺で育てるイメージの強いシラサギカヤツリですが、庭に地植えしたり、鉢植えで育てても大丈夫です。ただ湿地で育つ植物ですので水切れや乾燥には弱く、その点については注意が必要です。株もとを水中に植えてやる場合は問題ありませんが、
鉢植えや地植えで育てる場合は水持ちの良い用土を使用するようにし、土の表面が乾いてしまう前に水やりをおこなうように心がけ、常に土が湿気を帯びている状態にしておくことが重要です。鉢植えで育てるのであれば、腰水栽培という育て方を用いるのも一つの方法です。
植える場所については、なるべく日当たりのいい場所に植えてやります。耐暑性はなかなか強い植物ですが、寒さには弱いので、できることなら日当たりのいい場所に植えたほうがいいでしょう。基本的に丈夫な植物ですので、半日程度でも日が当たるのであれば花を咲かせることはできます。
また上記にも上げたとおり、寒さには弱い植物です。特に冬は地下茎が凍結してしまえば株全体が枯れてしまうので、気温の管理には注意が必要です。したがって北関東以北や冬に水が凍ってしまうような地域では、地植えは避けたほうが無難です。
このような地域で育てる場合は冬に何らかの保護対策を施すか、鉢植えにして冬になると凍結しない場所に移動して育てるといった方法を用いるといいでしょう。その他の地域で育てる場合は、水切れと日当たりにさえ気をつけてやれば、放任しておいてもそれほど問題なく育ちます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けは基本的に、湿度さえあればいつでもおこなうことが可能です。ですから真冬のシーズン以外、なかでも湿度の高い5月から10月にかけてが植え付けに適している時期になります。植え付けに用いる用土は水持ちがいいものを選択する必要があり、あまり軽い土はこの植物には適しません。
一般的な赤玉土を用いても差し支えありませんが、田んぼの土で育てると非常によく生育します。また乾燥を防ぐためにも、株もとがあまり深く沈みこまないように植えるのもポイントです。シラサギカヤツリは植えた後も水やりには特に注意が必要です。
地植えや鉢植えの場合は土の表面が乾かないようにし、いつも湿っている状態にしておかなければいけません。壮健な植物ですが、水切れには非常に弱い植物ですので、こまめに水やりをおこなうようにしましょう。もちろんビオトープやウォーターガーデンに用いる場合など、
水中に株もとを沈めて育てる場合には水やりは必要ありません。肥料は花が生育する4月から10月にかけて、緩行性の肥料を与えます。化成肥料や発行済みの油粕などを津地の中に埋め込んでやるといいでしょう。与える頻度は3週間から6週間に1回程度ですが、
与え過ぎには注意が必要です。生育環境が整っている場所で育てるのであれば、春先に緩行性の肥料を与えただけでも十分育ちます。このようにシラサギカヤツリはとても丈夫な植物です。小さい苗でもひと夏で結構な大きさに株が育ちますので、鉢植えの場合は大きめの鉢を使うといいでしょう。
増やし方や害虫について
シラサギカヤツリを増やす場合は株分けによりおこないます。生育力が旺盛な植物ですので、放っておくと株が込み入ってしまいます。ですから春先に植え替えを兼ねて株分けをおこなうと、数を増やすこともでき、順調な生育も期待することができるのです。
もちろん株分けそのものは、4月から10月にかけての生育期間内ならいつでもおこなうことができるので、育てている人に都合のいいタイミングでおこなってもかまいません。株分けはハサミを用いておこないます。泥を落として根をほぐし、ハサミで株を切り分けます。
切り離した株の根をよく洗い、古い根や病害虫の被害を受けているような根があれば取り除きます。ただし新しい根や細かい根を取り除いてしまうと、生育に影響がでてくる可能性がありますので、根を取り扱う時には慎重におこなわなければいけません。
株分け時に古い根しか見当たらないようであれば、そのままにしておいても問題ありません。根の整理が終わった後は、清潔な用土に植え替えれば株分けは終了です。株分け後には水をたっぷりと与えておきます。病害虫に関しては特に問題ありません。
このシラサギカヤツリ特有の病気や害虫といったものは報告されておらず、基本的には病害虫に関して心配することのない植物です。他の草花との寄せ植えにしても相性の良いシラサギカヤツリですが、病害虫の被害の少なさも、このような場面で栽培するのに非常に適している植物だといえます。
シラサギカヤツリの歴史
シラサギカヤツリはカヤツリグサ科の多年草です。シラサギの名前からもわかるように、花を咲かせた姿が白鷺が舞っているようにも見え、園芸品種として人気のある植物です。立ち姿や名前からして和風なイメージがあるシラサギカヤツリですが、じつは原産地は北米アメリカです。
日本に渡来した時期は詳しく判明しないのですが、現在では庭を彩る花として日本でも広く用いられています。シラサギカヤツリには別名も多く、シューティングスターやスターグラスといった名称も知られています。いずれも花の姿から連想されたものといえますが、
日本人には白鷺に見え、海外の人には星に見えたようです。どちらにせよ花を咲かせた姿が印象的で、人々の心をとらえたのは間違いないでしょう。現在、このシラサギカヤツリはさまざまな鑑賞方法で楽しまれています。庭植えはもちろん、水辺や湿地を生息地としても問題の無い植物ですので、
ウォーターガーデンやビオトープを彩る花として重宝できます。最近は睡蓮鉢などの水鉢で簡単なビオトープを作成するのも人気で、広い庭や池が無くてもベランダなどの狭い場所で水辺の空間を楽しむ人も増えており、そのような趣味を持つ園芸愛好者の人には適している品種でしょう。
また水さえ切らさなければ丈夫に育つうえ、清楚なたたずまいが和の雰囲気にも洋風の雰囲気にも相性がいいので、園芸に興味を持ち始めたばかりの初心者でもあつかいやすい品種だといえます。
シラサギカヤツリの特徴
シラサギカヤツリは水辺でも丈夫に育つのが特徴で、池やビオトープなどを彩る花として栽培しやすい品種です。群植すればたくさんの白鷺が舞っているような優雅な風情を楽しむことができますが、単体の鉢植えで楽しむことも多い植物です。
白鷺が舞っているかのように咲く花ですが、じつはそのように見えているのは花ではありません。白く色づいた花のように見える部分は総苞と呼ばれるもので、「がく」のようなものです。実際の花の部分は中央付近に小さく咲いており、非常に地味な存在です。
シューティングスターの別名のように星のようにも見える姿ですが、開いているのは花びらとは違うのです。またシラサギカヤツリはすらっとした立ち姿が涼しげに見えるのも特徴です。地中で横に伸びる地下茎から出た葉が、まっすぐに空へ向かって出ています。
この葉は冬になると枯れてしまいますが、地中の地下茎は休眠状態になり、冬を越すことができます。凍結してしまえば別ですが、それ以外であれば良く年も花を楽しむことができます。さらに開花時期が長いのもこの植物の魅力の一つです。4月下旬から10月下旬まで長期間にわたって花を楽しむことができます。
気温が低くなる冬が来るとと枯れてしまいますが、温室など気温を一定にできる場所で育てた場合は、枯れることもなく1年中花を楽しむことができます。シラサギカヤツリは美しいだけでなく、育てやすくて長持ちという非常に優れた園芸品種のひとつなのです。
-

-
玉レタスの種まき時期と育て方
レタスは一番馴染みのあるのが玉レタスで、夏に涼しい気候の高原でよく育つ高原野菜といわれています。レタスの栽培方法は、種を...
-

-
パンジーの育て方について
冬の花壇を美しく彩ってくれる植物の代表格は、なんといってもパンジーです。真冬の街にキレイな彩りを与えてくれる植物としては...
-

-
アエオニウムの育て方
アエオニウムはアフリカ大陸の北西の北アフリカに位置するカナリー諸島原産の植物です。生息地は亜熱帯を中心に多くく見られる植...
-

-
タンポポの育て方
道端などで春先に良くみかける”タンポポ”。キク科タンポポ属の総称になります。地中海沿岸・中央アジア原産になり、日本には外...
-

-
オリヅルランの育て方
オリヅルランはユリ科オリヅルラン属の常緑多年草で、初心者にも手軽に育てられるため観葉植物として高い人気を誇っています。生...
-

-
オクナ(ミッキーマウスツリー)の育て方
南アフリカ一帯に分布する樹木で、正式名称をオクナセルラタと呼び、ミッキーマウスツリーとして現在では親しまれている植物の特...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...
-

-
ドクゼリの育て方
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作...
-

-
サルビア・スプレンデンスの育て方
サルビア・スプレンデンスは、ドイツ生まれの植物学者セロウによってブラジルで発見されました。彼はブラジルを中心に植物探検を...
-

-
スズランの育て方
春を訪れを知らせる代表的な花です。日本原産のスズランとヨーロッパ原産のドイツスズランがあります。ドイツスズランは、草姿お...




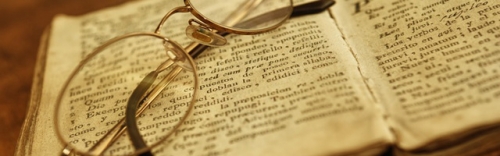





シラサギカヤツリはカヤツリグサ科の多年草です。シラサギの名前からもわかるように、花を咲かせた姿が白鷺が舞っているようにも見え、園芸品種として人気のある植物です。