エレムルスの育て方

育てる環境について
栽培をする上での環境としては、秋に植えて初夏に変えて咲くことになります。寒さには強いとされます。乾燥にも強いので、冬に関してはそれなりに育てやすくなりそうです。冬は咲く準備を懸命にしていますから休眠はしません。この花が休眠をするのは夏になります。花が終わった後に葉っぱなどが枯れて休眠に入ります。
夏の暑さに対して特に問題が発生しないのは、休眠をするからになるでしょう。日本の夏の環境である高温多湿状態はあまり好みませんから、休眠をしてくれるからこそ何年も育てることが可能になります。真夏の暑さに対しては耐性としてはそれほど強くありませんが休眠をするので心配はありません。
その他の季節において日当たりをどのように管理していく必要があるかです。秋、冬、春と全般的に日当たりの良い所を中心に育てるようにします。寒さに対しては耐性があります。土が凍るようなところの場合は対策をするようにします。マルチングと言われる方法があり、土の表面などをシートで覆うようにします。
完全に覆ってしまうと日当たりが悪くなるので気をつけたいですが、冬においても日当たりが必要になるのでシートを上げて日当たりにあてたり、寒さを防いだりの管理をしていくようにします。夏においては休眠をしますがそのままにしておけば秋に生えてくるかといえばそうとも限りません。雨などで湿ってしまうことで枯死してしまうことがあるので、掘り起こして管理するようにします。
種付けや水やり、肥料について
育て方において、植え付けは秋に行います。耐寒温度としては0度位なので一般的なところなら冬越しもそれ程難しくありません。土が凍るような地域でも育てたい場合があります。その時には土が凍らないようにしておけば問題はありません。用土に関しては水はけの良い物を選ぶようにします。市販されている花と野菜の土、培養土を使うことができます。
これに通気性、水はけを更に良くするために川砂を混ぜることがあります。水の通りも良くなるでしょう。水やりに関しては、鉢植えの時はやや乾燥気味の管理をしておきます。過湿状態にならないように、表面が濡れているときに水を与えるようにします。土の中身についてもチェックをして、中が濡れているようであれば水を控えるようにすることも必要になります。
庭植えの場合においてはどのような管理をしていく必要があるかですが、植え付け時に水を与える以外においては特に水を与える必要はありません。夏に関しては休眠をするので水が一切不要です。一旦掘り起こして、乾燥したところに保管をするようにします。そして秋に植え付けを行うようにします。
夏以外に日照りや乾燥などが続くようなことはあまり無いでしょうから、ほぼ水を与える機会としてはないといえるかもしれません。肥料に関しては定期的に与えるようにします。植え付けが終わってから春ぐらいまでは液体のタイプを与えます。与え方としては2週間に1回程度の頻度で与えていきます。
増やし方や害虫について
増やす方法としてはまずは種をまく方法があります。種については花の後につくことがあるので、それをしっかりととっておく必要があります。花自体が非常に小さく、種も取りにくくなることがあるので、花が終わりかけの時には種取りの準備をしておくといいかもしれません。取り巻きと呼ばれる方法で、とったらその後すぐにまくようにします。
元々は球根の花ですから球根ができないことには花を咲かせるのは無理です。球根が出来るまでに5年から6年かかるとされています。今期が入りますが、種が沢山とれていればたくさん増やすことができます。1つずつじっくり増やそうとするなら分球になります。植え替えをするときに球根に小さい球根がついていればそれ外して植え替えします。
分球の注意としてはあまり小さいタイプなどだとそのまま栄養が得られなくて弱ることがあります。大きいタイプのものを外すようにします。分球は一度にたくさん行えるわけではないので種まきよりも増えるスピードは遅くなります。しかし一つずつ確実に増やすことができます。
将来的に一度に複数の分球が出来るようになれば増やしやすくなることもあるでしょう。害虫や病気に関してはあまり木にすることがありません。水分が多くなり過ぎないように注意しながら育てるようにします。自然の花についてはかなり丈夫な茎があるので問題ありませんが、栽培の時には支柱を立てるようにするときれいな姿で栽培ができるようになります。
エレムルスの歴史
花においては、一つの茎に一つの花だけつけるものがあります。また茎は一本でその茎から沢山花をつけるものの、花同士が特に密集しているのではなく独立しているタイプがあります。どちらにおいても1つずつの花をそれぞれ楽しむことが多くなりそうです。一方で花の付き方として非常に小さい花が密集して大きな一つの花のように見せるタイプがあります。
夏の時期によく見かけるとすればあじさいがあるかもしれません。一見きれいな紫色の花が咲いているように見えますが、これは一つではなくたくさんの小さな花が集まって美しい姿を表しています。花の性質によってもそれぞれ異なるのでしょう。エレムルスと呼ばれる花があります。こちらは見た目には花に見えないぐらい少し特殊な形をしているのでインパクトはあります。
実際には小さい花が集まって一つの花に見せているタイプの花になります。原産地、生息地としては中央アジア西部とされています。アジアの中でも乾燥している地域となりそうです。この花の名前からはどのような花かがあまり想像できませんが、別名を聞くと想像しやすくなります。
この名前が花屋さんにあるとスイーツ店に入ったのではないかと感じる人もいるでしょう。それはデザートキャンドルと呼ばれることがあるからです。確かに見た目はキャンドルに似たような形です。草原などに生えているとキャンドルがゆらゆら揺れているようにも見えます。花言葉は大きな希望などがあります。
エレムルスの特徴
花の特徴では、ユリ科に該当します。花が咲く時期としては4月から7月になります。咲き方としては1年を通して咲く多年草になります。高さは比較的高くなり、1メートル50センチを超えるようなタイプもあります。草原などに頭を一つ出しているように咲いていることがあります。花の色として知られているのは白があります。
この白が別名のデザートキャンドルにもつながっているのでしょう。白以外の色もあり、黄色であったり、オレンジ色、ピンクなども知られています。花が特徴的と言えます。パッと見たら長細いワタのような植物ですが、よく見ると小さい花がたくさんついている事がわかります。花穂一本あたりでは300から500近くの花が咲いているとされています。
太い茎が一本真ん中にあり、そこから細かい茎がでていてその先に小さい花がついている形になります。花が直接ついている茎は非常に細いので咲ききってしまうと重さで下をむくことがあります。一方でつぼみの状態の時は茎自体もしっかりしているのか概ね上を向いた状態です。花については下の方からどんどん咲くタイプです。
バラバラに咲くことはないので、上のほうが咲いていたり、下のほうが咲いていたりなどバラバラに咲くようなことはありません。葉っぱに関しては下の方についているのであまりわかりにくい状態になっていることがあります。切り花の場合には主に花の部分だけになるでしょう。葉も入れると大きな花になります。
-

-
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の育て方
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の歴史は古く日本では最も古い文献古事記に桓武天皇が、ユリを摘んでいた若い女性に心を奪...
-

-
トキワマンサクの育て方
トキワマンサクは日本をはじめ中国やインド、台湾などにも生息地があります。もともと日本に自生していた植物ではなく、原産地の...
-

-
クロッサンドラの育て方
クロッサンドラは、促音を抜いたクロサンドラとしても呼ばれ、その名前の由来はギリシャ語で房飾りを意味する「Krossos」...
-

-
ヘゴの育て方
ヘゴ科ヘゴ属のシダ植物です。野生種は最大7〜8m近くにまで伸びる熱帯性の植物です。日本では一般的には沖縄や鹿児島などの南...
-

-
大ギクの育て方
花色や花の形、品種が大変豊富な秋の代表花である大ギク。菊の中では大変大きな花を咲かせとてもきれいな花になります。大きく分...
-

-
ベニサラサドウダンの育て方
ベニサラサドウダの大きさは、2メートルから大きいもので5メートル程度にまで生長します。若い枝は無毛で、その葉の長さは、お...
-

-
シシリンチウムの育て方
シシリンチウムは原産地が北アメリカの常緑多年草となっています。この名前ではピンとこない人でも、庭石菖(ニワゼキショウ)と...
-

-
アルストロメリアの育て方
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。
-

-
春の風物詩 チューリップの育て方について
桜の花に次いで春の風物詩となる植物がチューリップです。独特のふっくらとした形が特に女性に人気があります。卒業式や入学式な...
-

-
イワレンゲの仲間の育て方
イワレンゲの仲間は、ツメレンゲやコモチレンゲなど、葉っぱが多肉状態で、サボテンと育て方と同じ配慮で育てれば、毎年美しい花...




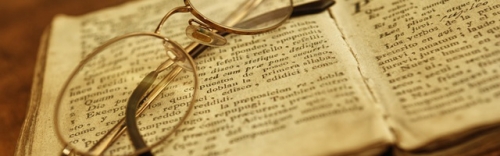





花の特徴では、ユリ科に該当します。花が咲く時期としては4月から7月になります。咲き方としては1年を通して咲く多年草になります。高さは比較的高くなり、1メートル50センチを超えるようなタイプもあります。草原などに頭を一つ出しているように咲いていることがあります。