フランネルフラワーの育て方

育てる環境について
鉢植えは、1年を通じて日当たりがよく、雨を避けられる場所に置くようにします。フランネルフラワーの生息地は日差しの強い乾燥した地ですので、庭植えや花壇では、日当たりのよい場所を選んで植えてください。一見、日差しに弱そうな葉をしていますが、
日に当てないと間のびして花が付かず、株が弱ることもあります。乾燥気味の環境を好みますので、砂などを混ぜた水はけのよい土壌が向いています。植えつけ、植え替えの適期は、4月から5月、9月から10月です。根が弱い植物なので根を傷つけないように根鉢をやさしく扱います。
ここで知ってほしいのが、フランネルフラワーは酸性の土を好むということです。園芸店やホームセンターに売っている市販の「花と野菜の土」といったものを利用しないでください。こういった土は酸性を中和したものになっているので植えると枯れてしまうことがあります。
また、花壇などでも同様で石灰などを使わないようにしてください。鉢植えの用土は、ピートモスと鹿沼土を5対5くらいの割合で植えます。とはいえ、水道の水などは中性なのでいずれは酸性でなくなってしまいます。2年目くらいから元気がなくなってくるのはそういった原因もあります。
地植えでも2年ほどたったら、場所を変えて植え替える必要があります。そのときも、もちろん酸性の土壌であり、日当たりがよいのが条件です。また、鉢植えなどは毎年植え替えてあげるのがベストです。おすすめなのが、ピートモスといった酸性のものを混ぜてあげることです。
暑さや寒さには比較的強いですが、冬には凍らせないように鉢などは軒下などで管理します。庭植えなどでは、寒さで葉が傷むのでビニールなどをかぶせて防寒し、凍るのを防ぎます。霜にあてなければ、冬越しすることも考えられますが、葉が黄色くなったりと見苦しくなるので、鉢などは室内に入れて管理したほうがよいです。
種付けや水やり、肥料について
フランネルフラワーを育てるコツというは、水やりにあります。暑さや寒さに強く、害虫などもあまりいないとされますが、夏の蒸れなどは大変苦手としています。夏場に水をやりすぎると腐って枯れてしまうこともあります。夏でも乾燥気味に育てるのがよく、極端に乾燥させない程度に水やりをします。
鉢の場合は、表面が乾いたらたっぷりと水をあげます。庭植えといったところでは、降ってくる雨の水だけで十分です。夏場で日照りが続くといった場合には、枯れないように水をあげてください。乾燥気味に育てるほうが育成に成功しやすいといえ、根腐れといったことには注意します。
水をやる際も、葉や茎などにはかけず、土だけに水分を与えるようにしてください。フランネルフラワーの羽毛に覆われた葉というのは、水から身を守るためといわれ、それくらい葉に水がつくのを嫌がります。乾燥させすぎても枯れてしまうし、また水をやりすぎてもいけないなど、
まさに水やりこそがこのフランネルフラワーの難しいところで、育成の要といえます。鉢の土が乾いて2、3日経ってから水をたっぷり与えるというタイミングをはかってみてください。大きく育てるためには多めの肥料を必要としますが、根が繊細なので、
高濃度の肥料を施すと肥料焼けを起こしてしまいます。鉢栽培では、液肥を通常の2倍の薄さにして与えるようにし、一週間に一回のペースで与えるなど、回数を多めにしてあげます。庭植えならば肥料はとくに必要ありません。
増やし方や害虫について
フランネルフラワーの増やし方は、種まきです。種まきの適期は5月とされ、種として利用するのは自家採取といったものになります。花が咲いたままにしておけば、花びらの部分が枯れて中心だけになり種が実ります。その種を利用すれば、苗を作ることができます。
種の発芽率については、あまり良くありません。発芽には1か月から2か月といった時間かかり、発芽にかかる期間もまちまちです。なかなか芽が出ずに諦めて放置していたら、知らないうちに芽がでていたという話もよくあります。種まきには、
植え付け同様にピートモスと鹿沼土を半々といった割合の土がよいです。病気については、風通しが悪いと「灰色かび病」が発生することがあります。ひどくなると株が枯れ込んでしまうことがあり、枯れた花がらから病気が発生することがあるので、
花がらや枯葉などはきれいに取り除き清潔にするようにしてください。花が枯れたらすぐに切り取って捨てるようにします。害虫については、ハダニが葉裏につくことがあります。この害虫は、風通しが悪いといった置き場所が原因となることが多いので、風通しのよい場所に移動させてください。
また、切り戻しといった作業で葉を少なくすれば風通しがよくなり、多湿による病気や害虫の発生を防ぐことができるのでおすすめです。新芽の発生も促されるなどの利点があります。切り戻す際は、各枝に必ず葉が残るようにし、葉がなくなるほど刈り込まないように注意します。あまり強く刈り込んでしまうと枯れることがあるからです。
フランネルフラワーの歴史
フランネルフラワーは、セリ科の常緑多年草で原産地はオーストラリアとなっています。生息地は、オーストラリアのような乾燥して暖かい土地とされ、強い日差しでよく育つとされています。同じように、フランネルに似た手ざわりの葉をもつフランネルソウ(スイセンノウ)は、ナデシコ科のまったく別の植物です。
日本での歴史は比較的新しく、輸入切り花しか見かけなかったという感じでしたが、ギフト用の鉢花というのもよく見かけるようになりました。近年では、岐阜県農業技術センターで品種改良された矮性品種の「フェアリーホワイト」の普及もあってかポプュラーになりました。
改良された点というのが、鉢用に向いたコンパクトさと四季咲き性です。ちなみに、原産地であるオーストラリアでは自然に自生しており、改良されたものよりも少し大きくて一季咲きとされています。また、2006年から2007年の鉢物部門でベストフラワー賞ニューバリュー賞、
ジャパンフラワーセレクションにも選ばれるなど日本でも現在、人気がでている花の一つです。アクチノータス属は、オーストラリアを中心に15種ほどありますが、現在、日本で流通しているのはヘリアンティ種のみです。名前の「フランネル」とは、
花や葉に細かな毛で覆われ、感触が布生地のフランネルに似ていることからついたそうです。属性を別名として、「アクチノータス」と呼ぶこともあります。葉が白っぽいのはオーストラリア原産の花には多いもので、強い日差しによる葉やけを防ぐためといわれています。
フランネルフラワーの特徴
フランネルフラワーの特徴といえば、葉についている細かい産毛とされ、肌触りはまるで本物のフランネルのようです。葉だけでなく、花もまた厚みを持っています。その質感の珍しさはもちろんですが、白いマーガレットのような花もまた可愛くて素敵です。
マーガレットに似てはいますが、キク科ではなくセリ科の植物です。エメラルドグリーンの葉が茂り出すと、白いフェルトのような質感の花を咲かせるなど見た目にも魅力があります。鑑賞する以外にも、ドライフラワーや押し花などにも利用できる楽しみがあります。
日本で改良された「フェアリーホワイト」は、白い花びらの先の部分が緑色になっている品種とされ、そのほかの品種にも花びらの先が緑になっている特徴があります。この「フェアリーホワイト」は、岐阜県でしか生産されていないため、流通量というのが少ない花です。
ギフト用の鉢植えとしても人気が高く、また花持ちのよさにも定評があります。一輪の花が咲いている期間がとても長く、そして次々に花を咲かせる特性をもっています。飽きずに長く花姿を楽しむ事ができるのも、フランネルフラワーの利点です。乾燥気味を好むので、水を弾くために全体が産毛で覆われており、強い日差しが大好きな植物です。
反対に夏の湿度といのは苦手らしく、腐らせて枯らしてしまうことがよくあります。ですが、一日の寒暖差が激しい環境で生育しているため、暑さや寒さに強く日本の気候にも向いています。一般的に初心者には育て方が難しいとされていますが、コツさえおさえれば鉢などで簡単に生育できます。
-

-
リアトリスの育て方
北アメリカが原産の”リアトリス”。日本には、大正時代に観賞用として渡来した花になります。苗で出回る事が少なく、切り花とし...
-

-
バラ(つるバラ)の育て方
バラの種類は、かなりたくさんありますが一般的には世界で約120種類あると言われています。記録によれば、古代ギリシアの時代...
-

-
小松菜の栽培に挑戦してみよう。
今回は、小松菜の育て方について説明していきます。プラナ科である小松菜は、土壌を選ばず寒さや暑さにも強いので、とても作りや...
-

-
ピラカンサの育て方
ピラカンサは英名でファイアーソーンといいます。バラ科トキワサンザシ科です。ラテン語のままでピラカンサとされている場合もあ...
-

-
果物から出てきた種を育てる方法
果物には、中に種が入っているものが多いです。果物によっては、食べながら種を取り出して、それを土に植えることで、栽培するこ...
-

-
ヘーベの育て方
ヘーベの特徴は次のようになっています。オオバコ科のヘーベ属に分類されており、原産地はニュージーランドになります。分類は常...
-

-
コツラの育て方
この花の特徴はキク科となります。小さい花なので近くに行かないとどのような花かわかりにくいですが、近くで見ればこれがキク科...
-

-
エリシマムの育て方
エリシマムはユーラシア大陸からアジア全般に向けた広大な地域に生息している植物であり、比較的温暖な地域に生息する多年草とな...
-

-
チューリップの育て方
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから...
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...




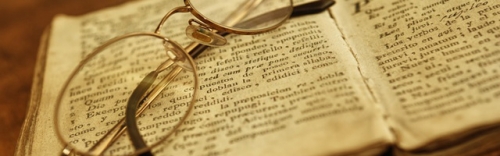





フランネルフラワーは、セリ科の常緑多年草で原産地はオーストラリアとなっています。生息地は、オーストラリアのような乾燥して暖かい土地とされ、強い日差しでよく育つとされています。