ミヤマクロユリの育て方

育てる環境について
ミヤマクロユリはユリの名が付いていますが、ユリ属ではなくバイモ属になります。原野に生えるクロユリに比べると栽培は大変難しい花になり、高冷地以外で栽培しようとしてもなかなか成功することはないでしょう。高温多湿の場所を嫌い、なかなか一般の人が育てようとしても十分に環境に配慮しなければいけなくなるので難しくなってしまいます。
冷涼な環境を必要とするので、育てる場合は風通しが良く涼しい場所で育てるようにしましょう。高山帯で育つ花になるので、なかなか一般の場所で育てている人は少なくなります。条件が良ければ大量に生育する場合もありますが、花の管理が難しく環境に左右されやすい花になります。本州中部の高山に生えている為、なかなか麓では見る事が出来ません。
また、香りも独特の香りがしてきつめの香りになっているので、この香りを嫌がる人もいる為、なかなか栽培する人も少ない花になります。しかし実際見てみると、その魅力的な花から、大変興味を持つ人も増えています。環境に配慮しながら育てる事できれいな花を咲かせる事が出来ます。
涼しい中で育てなければいけないので、気温が高い地域での栽培は難しくなってしまいます。その為、育てる地域も限定されてしまうでしょう。環境さえ整えばきれいな花を覗かせてくれるので、楽しみな花になります。独特の色合いがまたなんとも言えず、登山をしている時に見つけるとつい足を止めてしまいたくなる花になります。
種付けや水やり、肥料について
ミヤマクロユリは一般的に受粉させる場合ハエに花粉を運ばせて受粉させているようです。独特の香りにハエがおびき寄せられているようです。用土は鹿沼土、桐生砂、硬質鹿沼土などの混合用土を使うと良いでしょう。地植えをする場合は、朝日があたり、西日が直接当たらない場所で育て、土のはねない場所を選んで土の表面から約2cm下に植えるとよいでしょう。
展葉期には、出来るだけ朝日がよく当たる場所で育てていきましょう。涼しい場所に自生する花になるので暑さには大変弱い植物になります。梅雨以降はできるだけ涼しいところで管理していくのが良いでしょう。過湿と乾燥を嫌うので、水はけのよい場所に植え、適度な湿度を保ちます。あまり水をやり過ぎては枯れてしまうので気をつけましょう。
また、出芽から葉が枯れるまでは液肥を1~2週間に1回程施し肥培していきます。なかなか素人には環境の配慮や水やり、肥料など難しくて出来ないという人も多い為、ミヤマクロユリは上級者向けの花になります。あまり一般家庭の庭先などではみない花ですが、やはり冷涼ではない土地で育てようとしても枯れてしまったりだめになってしまう事が多いようです。
何度か育てた事がある人であれば環境の配慮などしっかりすることが出来るでしょう。しかしやはり素人が初めて育てようとすると難しくなってしまいます。ホームセンターなどでもあまり販売されていない花になりますので、種や苗を取り寄せて育てることになります。
増やし方や害虫について
クロユリは花が咲いた後に種子は出来るのですが、種子はなかなか発芽しないので、増やすのであれば球根からの栄養繁殖する方法をお勧めします。増や際は、球根を掘り起こして、鱗茎をはがして別途植えると増えていきます。増やす方法は比較的難しくありません。ナメクジ、カタツムリが葉を食害する場合があるので注意が必要です。
夜に水やりをするとこれらが活発に活動し始めるので、夜の水やりは避けるようにしましょう。植え替えをする場合は2年に一度くらい行うと良いでしょう。芽が出てくるまでは土を乾燥させないように注意しましょう。地道にお世話をしていけば増やす事も可能です。害虫に食されてしまうとせっかくの花も咲かなくなってしまうので、
定期的に害虫が付着していないかチェックするようにしましょう。ミヤマクロユリは見た目にもインパクトがある花です。なかなか黒っぽい色をしている花を見る事が少ない為、珍しい花になります。好き嫌いがある花になりますが、大変魅力的で引き込まれてしまう花です。球根にはしっかり養分を与え、
日光や水やりをしっかり管理する事できれいな花を咲かせる事が出来るでしょう。何もしなくても地植えの場合勝手に増えていく場合もあります。鉢植えで育てる場合は、成長と共に植え替えをしていきましょう。あまり高温にならない場所で育てますが、管理が難しく育て方も配慮が必要な花になるので細心の注意を払いながら育てていくときれいな花を咲かせてくれるでしょう。
ミヤマクロユリの歴史
通常のユリとは違い、黒い色をした花を咲かせる”ミヤマクロユリ”。原産国は日本や中国や韓国になります。高山帯の草地に生える花になります。日本で最も有名な生息地は白山になり、室堂周辺などでは大量に群生しているのを見る事が出来ます。石川県の郷土の花で栽培が非常に難しい花になります。
このミヤマクロユリは北の政所と淀君の伝説が有名です。戦国武将の佐々成政が秀吉の正室である、北の政所に「とても珍しい花である」という触れ込みでクロユリを贈呈しました。北の政所はこの花を飾って茶会を開き皆に自慢をしました。側室の淀君は事前にクロユリの情報を入手しており、その花が”白山のクロユリ”だと言うことを言い当てました。
さらにそれ以上に多くののクロユリを取り寄せてはすぐにでも手に入れられる花だと言わんばかりに飾ってみせたと言われています。そんなクロユリは主に北海道の低地に自生している「北海道型」と、本州中部の高山に自生している「本州型」にわけられます。北海道型の方は染色体を3組持っている3倍体になり、草の高さは約50cmくらいになります。
また花数が大変多く、花色は黒に見えるほど濃い暗紫色で、4月~5月にかけて開花します。この北海道型を一般的な”クロユリ”と呼んでいます。本州型は一般的な2倍体になります。草の高さは15cm~30cmくらいと北海道型より低くなります。花は2~3輪ほどしか咲かず、開花時期は7月頃になります。本州型のクロユリを北海道型と分ける為に、こちらを”ミヤマクロユリ”と呼んでいます。
ミヤマクロユリの特徴
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下向きに咲かせるのが特徴です。花びらの内側には黄色い斑紋があり、なんとも言えない魅力的な印象を放つ花になります。季節になるとこのミヤマクロユリを見る為に、登山客が大勢山に登ると言われています。
香りは多少きつめの香りがします。花被片は暗褐色で6枚あり、雄しべが6個だけの雄花と、3裂した花柱を併せ持つ両性花があります。7~8月にかけて見頃を迎えるので、それに合わせて多くの人達が集まってきます。クロユリはその見た目の印象から好き嫌いが分かれてしまう花になりますが、登山客はこの花を見る為に足を運ぶ人もたくさんいます。
群生している姿はまさしく見物です。クロユリの花言は”恋”、”呪い”になります。なんだかイメージ通りの花言葉という印象も受けます。実際見てみるととても魅惑的な花に見えてしまいます。花と言うと色鮮やかな赤や黄色といったイメージを持ちますが、このミヤマクロユリは色が黒っぽく見える為、ちょっと普通の花とは違う様な印象さえ与えてしまいます。
恋の花とも言われており、見ただけでその色からミヤマクロユリだという事はすぐにわかるでしょう。美しいとはお世辞にも言える花ではありませんが、その魅惑的な見た目から多くのファンが存在します。この花をなかなか観賞用として求める人は少ないでしょう。しかし庭先で育てているミヤマクロユリのファンもいます。
-

-
八重咲きコンロンカ(ハンカチの花)の育て方
またハンカチの花という名称もあり、遠くから見るとハンカチがたくさん舞っているように見えるのでハンカチの花と命名されたとい...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
野菜の栽培野菜の育て方野菜の種まき様々な方法があります
野菜の栽培といえば、日本で一番多く栽培されているのは、主食のコメでしょうか。野菜の育て方で調べてみると、多くの情報には、...
-

-
ナスタチウムの育て方
ナスタチウムはノウゼンハレン科ノウゼンハレン属の一年草です。ブラジルやペルー、コロンビアなどが生息地となり、葉と花と種に...
-

-
ツタ(ナツヅタ)の育て方
ツタはナタヅタともいい、ブドウ科ツタ属のツタ植物です。古くから存在していて、日本でもよく使われている植物の一つです。昔か...
-

-
シソの栽培と育て方プラス収穫後の楽しみ
日本人の好むシソは香草であり、料理の添え物や天ぷら、薬味、漬物などに使用されています。大きく分けると青シソと赤シソの2種...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
ニセアカシアの育て方
ニセアカシアは北米原産のマメ科ハリエンジュ属の落葉高木です。北アメリカを生息地としていますが、ヨーロッパや日本など世界各...
-

-
トリトマの育て方
トリトマは、クニフォフィアと言う別名を持つ草花であり、以前はトリトマと呼ばれていましたが、最近ではクニフォフィア属(シャ...
-

-
ゲウムの育て方
ゲウムは、バラ科 のダイコンソウ属(ゲウム属)であり、日本のに山に咲く「ダイコンソウ」と同じ仲間です。そのためゲウムを「...




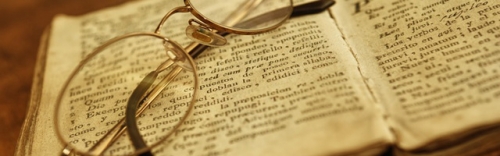





このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下向きに咲かせるのが特徴です。花びらの内側には黄色い斑紋があり、なんとも言えない魅力的な印象を放つ花になります。季節になるとこのミヤマクロユリを見る為に、登山客が大勢山に登ると言われています。