グラマトフィラムの育て方

グラマトフィラムの育てる環境について
元々熱帯の植物と言うこともあって、暖かい場所を好みます。13度から15度の温度が必要となります。ですから、寒い時期には屋外で育てるのは難しいです。冬から春の間は室内で育てるのが良いです。室内の中でも日当たりの良いところにおくと良いです。
5月頃の暖かい時期になってくると屋外で育てることもできますが、あまりにも強い日差しが当たると歯が痛んでしまうことがありますから、直射日光の当たらないところにおくのが良いです。熱帯の植物ですから暑さには強そうに思うかも知れませんが、これは意外にそうではありません。
熱帯では大きな木が育ち、その中で色々な植物が育ちますから、どちらかというと直射日光の当たらないところで育つ植物の方が多いのです。直射日光の当たるところしかない場合には遮光を行います。たとえば、庭で育てたい場合には、直射日光の当たらないようにしなければ葉やけを起こしてしまい、
見た目には枯れているようになりますから注意が必要です。春秋は30%の遮光を施し、夏の暑い時期には50%の遮光を施すと元気に育ちます。冬の寒い時期には室内に入れておくことが必要ですが、室内の温度、できれば15度以上に保っておいた方が良いです。
18度くらいあると元気に育ちます。春くらいから少しずつ日当たりに慣れさせていくと葉やけを起こしにくくなります。多湿を好みますから、風通しがあまり良くない場所でも育てることができるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
グラマトフィラムは水を好む植物ですが、ずっと水を与えていると根が腐ってしまい、枯れる原因になることがあります。植物を枯らしてしまう原因で最も多いのがこの水やりですから、注意が必要です。水やりの基本は、土が湿っているときにはやらないのが基本です。
グラマトフィラムの水やりは、1日に何回すれば良いのかというと、これは環境によって異なります。日当たりの良いところと悪いところでは変わりますし、土の配合などによっても異なります。ですから、土が乾いたら水をやるという習慣をつけると良いです。
土が乾いていない状態で水やりをするのは厳禁です。解説書には1日に1回や2回と書かれていることがありますが、これはあくまでも目安ですから参考程度にするべきでしょう。水やりをするときにはたっぷりと水を与えます。夏の暑い時期には特に水を好みますから、
乾いたらすぐに水をやると言うことを繰り返してやると良いです。冬にも水やりを行います。肥料については、生育が始まる4月中旬くらいから与えます。緩効性肥料か油かす系の肥料が適しています。緩効性の肥料は4月中旬に一度与えておけば良いですが、油かす系の肥料の場合、
4月から7月まで月に1回くらいの頻度で与えていくと良いです。液体肥料を併用する場合、4月から9月くらいの間は週1回くらいのペースでたっぷりと与えます。グラマトフィラムは肥料を好む植物で、肥料が切れると弱ってしまうことがありますから注意が必要です。肥料は多めに与えても良いです。
増やし方や害虫について
増やし方は、基本的には株分けが適しています。種で増やすこともできるそうですが、これはなかなか難しく、あまり一般的な方法ではありません。花が咲けばそこに種ができますから、この種で増やしていくこともできるでしょう。ただ、種で増やすと遺伝的に軽質が異なることもあり、
少し違った下部になることが多いです。挑戦してみる価値はありますが、今の株をそのまま増やしたいと言うときには株分けが最も適しています。グラマトフィラムは育てていると根鉢が大きくなってきますから植え替えも必要です。植え替えをするときに、株が大きくなりすぎていれば分けるのが良いです。
分けるときにはあまり小さくしないほうが良いでしょう。できれば3つ位をセットにして一株とすると良いです。だいたい3年から4年くらい経ったものなら株分けができるようになります。グラマトフィラムは季節を問わず虫がつくことがあります。
花弁の裏側に虫がつくことが多いです。このようになった場合、カイガラムシが発生していると考えられます。カイガラムシは市販の薬で撃退することができますから、見つけたのなら散布して退治します。ハダニがつくこともあります。
葉の裏側が白っぽく変色している場合や、粘性のある液体がついているばあいにははだにが発生している可能性があります。この場合にも市販の薬剤で退治することができます。害虫については早期発見がもっとも大事ですから、速く見つけて速く退治できるようにするのが良いです。
グラマトフィラムの歴史
グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロッパに渡って栽培されるようになりました。ヨーロッパででは、ランの栽培は18世紀に始まったと考えられています。
ヨーロッパの中でイギリスがその中心だったと考えられています。イギリスが世界に進出している時代でしたから、世界の色々なところから新しい植物がイギリスに持ち込まれました。当時は熱帯の植物の育て方の技術がなかったために、ランを手にすることができる人はごく限られていました。
しかし、その後は技術が進歩してくるとともに、新しい品種が作られるようになります。現在では色々な地域で栽培されていますが、技術が確立したのはアメリカだと言われています。19世紀のアメリカに持ち込まれ、ハワイでは洋蘭の栽培が産業として定着するようになりました。
日本でも普及したのは最近のことで、もともとは栽培をして花を楽しむことが目的として好まれていたようですが、最近では開花した株が流通するようになってきました。たとえばハート型に育てられたグラマトフィラムなどがネット上でも販売されていて、
簡単に購入できるようになってきました。購入することもできますが、日本の気候で育てていくことも可能です。熱帯の植物と言うこともあって注意しなければならない点もありますが、日本でも育てる人や増やしている人は増えてきています。
グラマトフィラムの特徴
グラマトフィラムは着生植物で、樹木などに根を張ります。ランの中では大きい方で、いくつかの種類がありますが、世界最大のものもあります。品種によって系以上はいくつかの種類がありますが、葉は長い卵形に広がります。棒状の茎が長く伸びて、左右交互に葉が伸びるものもあります。
根元の部分から複数の葉をつけるものとがあります。開花時期は春から秋頃で、株元から茎が伸びてたくさんの花をつけます。数十から数百くらいの花を咲かせることもあります。茎の長さもそれぞれで異なっていますが、永いいものでは2メートルに達することもあります。
花の色はあまり派手ではなく、どちらかというと落ち着いた雰囲気がありますから、日本の文化にもフィットすると考えられます。花は肉厚で黄色や黄緑色の斑点が入る品種が多くあります。花に文字を刻んでいるように見えることから、
グラマトフィラムという名前がつけられたという説がありいます。品種改良が盛んに行われていて、花に斑点のないものなどもありますし、赤い斑点の入ったものもあります。グラマトフィラムはいくつかの種類に分けられ、代表的なものがいくつかあります。
その一つがスペキオスムです。背丈は3メートル以上にもなる大きなもので、赤い斑点の入った花を咲かせます。もう一つ有名なものとしてスタペリフロルムがあります。花は下にたれて長く伸びます。紫色の斑点が細かく入るために、全体として紫色のきれいな花に見えます。
洋ランの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カトレア・コクシネアの育て方
タイトル:シュンランの育て方
タイトル:セントポーリアの育て方
-

-
花の栽培を通して喜びを感じる
手作りの物を口にしたり、目の保養をする事ができたら、こんなに素晴らしい事はないと考えている人は多く、実際に実行に移す人の...
-

-
レシュノルティアの育て方
レシュノルティアは世界中で見ることが出来ますが、生息地であるオーストラリアが原産国です。この植物は世界中に26種類あると...
-

-
シソの栽培と育て方プラス収穫後の楽しみ
日本人の好むシソは香草であり、料理の添え物や天ぷら、薬味、漬物などに使用されています。大きく分けると青シソと赤シソの2種...
-

-
金のなる木の育て方
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなど...
-

-
コメツガ(米栂)の育て方
コメツガは、昔から庭の木としても利用されてきましたが、マツ科のツガ属ということで、マツの系統の植物ということになります。...
-

-
ロムレアの育て方
南アフリカはアヤメ科の球根が、たくさん栽培されていて、ロムレアもその仲間のひとつです。手に入りにくい球根と言われていまし...
-

-
タイリンエイザンスミレの育て方
多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすい...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
ユリオプスデージーの育て方
特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当...
-

-
サントリナの育て方
種類はキク科になります。除虫菊と同じ仲間なので、そのことからも虫をあまり寄せ付けないのかもしれません。草丈は大きいものだ...




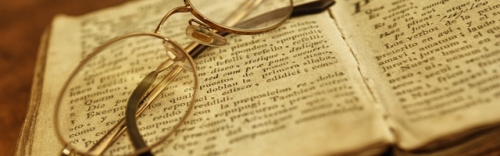





グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロッパに渡って栽培されるようになりました。ヨーロッパででは、ランの栽培は18世紀に始まったと考えられています。