リンドウの育て方

育てる環境について
日本は国土としてはそれほど広くはありませんが、非常に多くの環境があります。海岸沿いから平地もありますし野山のようなところから高山と呼ばれるところまであります。そういったところには独特の花がさくことがあります。リンドウにおいてはどのような環境が適しているかですが、今のところはあまり寒いところでは育ちにくい傾向にあるようです。
花の特性としては比較的寒さには強く、暑さに弱いとされています。しかし南の地域でもそれなりに見られています。北海道など北の方に行くと少なくなる傾向にあるので、そう考えるとあまり北の方では育てられないのかもしれません。一般的に栽培に向いている場所としては、花が咲かない時期においては日当たりに置くと良いとされます。
一方で花が咲く秋ごろにおいては日向から少し離して半日陰のようなところを好むようになるとされます。自然に咲いているものにおいても目立つところに咲くよりかは野山のちょっと陰になっているところが多いように感じられます。陰が全く無いようなところで育てるよりも、家の陰が出来るようなところが適してくるのでしょう。
土の状態としても乾燥しているところよりも湿ったところの方を好むようです。あまりジメジメしたところは良くないようですが、それなりに水分を得ることが出来るところがいいようです。自分で栽培するようなときにも、そういった環境を再現しながら育てるようにすることを心がけるのがいいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
リンドウにおいては、日本では秋咲きのものが主流ですが、世界的においては秋咲きと春咲きのものがあるとされます。育て方で種付けについても春か、秋かによって変わってくることがあるようです。日本では秋のことが多いので、それを想定して種まきをするようにします。時期としては3月から4月ぐらいに行うと良いとされます。
ちょうど春の花がどんどん咲き始める頃に行う花になります。水やりについてはこまめに行うのが良いとされています。乾燥はあまり良くない花になります。乾燥させてしまうと葉が傷みやすくなり、せっかくの緑の葉が枯れたようになってしまう場合があります。水を好む花なので、とにかく水を切らさないようにするのが必要です。
もちろんどの植物にも言えることですが水の与え過ぎはよくありませんからほどほどに行うようにします。春、秋、冬など比較的気温が上がらない時には朝にしっかりと与えることで十分1日水分を得られるようになります。夏に関しては1回だけだと少し足りないこともありますからその時に応じて朝と夕方に与えるようにするといいかもしれません。
特に夕方は徐々に乾燥してくる時間になりますから、この時にしっかりあげるようにすればいいでしょう。用土については、水持ちと水はけの良い物を選ぶようにします。あまり水が残りすぎるのはよくありません。肥料については、山野草用の培養土、赤玉土、鹿沼土などの土に混ぜるようにして与えるようにします。
増やし方や害虫について
この花は多年草になります。毎年枯れて種をとって育てるタイプとは少し異なります。増やし方としては株分けを行うことがあります。行うときとしては植え替えの時に行うと良いとされます。芽が付いていると通常は根があるはずですが必ずしもそれに対応した根があるとは限りません。
無理に株分けをしてしまうとせっかくの株を傷めてしまいますから注意が必要です。それなりの大きさが必要になってきます。無理に引っ張るのではなく、手で引いた時に自然に分かれるような場合において分けることが出来るかもしれません。さし芽をすることもできます。時期としては開花の前の5月から6月辺りに行うと良いとされます。
この時期がポイントであって、時期がずれてしまうと問題もあります。うまく咲いたとそのままにしているとその次の年は枯れてしまっていることがあります。あまり早く行いすぎるのも良くないですし、遅くなるのもよくありません。咲いたからといって安心するのではなく、しっかり様子を見てあげるようにします。
種で増やす方法もあります。花が咲いた後にさやの中に粉のような小さな種ができてきます。自然においておいてもそれが地面に広がることもありますが、とっておけば春にまくことができます。そうすれば秋にはきれいな花を咲かせてくれます。病気に関しては葉や茎の萎縮などによって見分けます。そのような状態になっているものがあるときは他のものの場所を変えるなどが必要になります。
リンドウの歴史
日本においてはいくつかの古い書物が残されています。それらの書物に何らかの記載があるときにはその時代からそれ自身があることを示すと考えてもよいでしょう。近年になって外国から入ってきたものであればそういった記録があるでしょうが、そのような記録がないときは実際に書物などに書かれているかどうかによって知るしかありません。
リンドウに関しては枕草子において記載がされているとして知られています。竜胆は色鮮やかに咲くのが良いと記載されていることから、昔からそれなりにきれいに咲いていた花であることがわかっています。現代においては薬といえば西洋薬が主ですが、昔にはそういったものはありません。自然にあるものの中から薬効を求めることがあります。
この花に関しても何らかの薬効を求められたとされます。その時に根の部分が非常に苦かったようです。漢字においては竜胆と書かれます。万葉仮名では里牟多宇としているようです。熊の胆嚢を干して作る薬があるようですがそれは非常に苦いことで知られています。その薬よりも苦いことからこの名前、漢字が使われているとされています。
良薬口に苦しと言われることがありますが、薬効に関してもそれなりにあると考えられていたのかもしれません。竜自体は伝説上の生き物としてされていますが、恐らくこれくらいの苦さがあるとのことからこの名前が付けられる様になったのでしょう。日本においては生活に必要な花だったことがわかります。
リンドウの特徴
この花の特徴としてはきれいな紫色をしていることです。鮮やかな紫よりも深い紫色と表現される事があるかもしれません。花といいますと春夏秋冬にそれぞれいろいろな花が咲きます。日本においては春に咲く花が圧倒的に多いかもしれませんこの花の特徴としては秋に花をつけることです。
鐘形の花なので道端に咲いていたりすると目を留めてしまう事があるでしょう。太陽の光などに反応をして花が開いたり綴じたりするといわれます。ハスの花などもそうですが、夜の間は一旦閉じます。そして朝日が上がって太陽が出てくると開いてきます。夕方になって太陽の光が弱くなってくると閉じてきます。
曇っているときは太陽の日差しが無いことから閉じたままになっていることが多くなります。秋は晴れていることが多いですから、きれいな花を見ることが出来る機会が多いかもしれません。原産としてはどの辺りになるかですが、広く世界中に分布しているとされています。アフリカではあまり見られていないようですが、それ以外の地域においては何らかの形で咲いているのが確認されています。
日本においてもどこからか持ち込まれたのではなく、元々生えていたとされます。今のところ北海道においてはあまり見ることができませんが、九州や四国、本州において広く見ることが出来るとされています。生息地としてはあまり寒すぎるところは良くないようですが、気候が安定しているようなところで見ることができそうです。
-

-
ローダンセマムの育て方
ローダンセマムの開花時期は春から初夏の間です。一般的な色は、薄く淡いピンク色やホワイトなどがあります。ひまわりのように丸...
-

-
コウバイの育て方
楽しみ方としても、小さなうちは盆栽などで楽しみ、大きくなってきたら、ガーデニングということで、庭に植えるということもでき...
-

-
ウグイスカグラの育て方
ウグイスカグラは、落葉性の低木です。スイカズラ科スイカズラ属の植物ですが、カズラではありません。名前の語感がカズラと似て...
-

-
アマドコロの育て方
アマドコロは、クサスギカズラ科アマドコロ属の多年草のことを言います。クサスギカズラ科は、クサスギカズラ目に属する単子葉植...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
セリの育て方
特徴としては種類がどのようになっているかです。キキョウ類、セリ目となっています。別名としてシロネグサとの名前がついていま...
-

-
ハルジャギクの育て方
ハルジャギクは、キク科ハルジャギク属の一年草になります。学名は、CoreopsisTinctoriaと言います。そして、...
-

-
ホリホックの育て方
この花については、アオイ木、アオイ科、ビロードアオイ属になります。見た目からも一般的な葵の花と非常に似ているのがわかりま...
-

-
ミカニアの育て方
こちらについては比較的身近な花と同じ種類になっています。キク科でミカニア属と呼ばれる属名になります。育てられるときの園芸...
-

-
植物の育て方について述べる
世の中に動物を家で飼っている人は多くいます。犬や猫、爬虫類などを飼って家族と同然の扱いをして、愛情深く飼育している場合が...




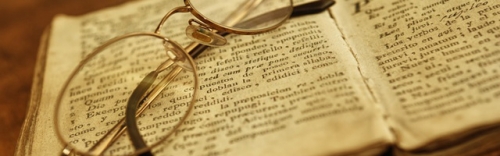





リンドウは、リンドウ科、リンドウ属になります。和名は、リンドウ(竜胆)、その他の名前は、ササリンドウ、疫病草(えやみぐさ)などと呼ばれています。