マツカゼソウの育て方

育てる環境について
日本における主な生息地は、四国から九州で、属している品種も東アジアなどの比較的暖かい土地で育ちますが、北限と言われる宮城県南下の本州でも見られる他、一部北海道でも確認されています。山地の日当たりの悪い林床に自生してることが確認され、こうしたことからも、ミカン科の中では得意な存在でもあります。
品種としてのマツカゼソウ属は、日本以外にはアジア諸国でよく見かけられ、中国や台湾など日本の他の品種の草花が育つ地域に加え、更に大陸を南下し、ユーラシア大陸の海岸沿いのベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー、少し飛ばして西のインドとパキスタン、そこから少し内陸のネパール、ラオス、ブータンにも見られます。
カシミールにも見られると言われているが、インドとパキスタンがカシミール地方の帰属に関して紛争を起こしているため、国としてのカシミールは使わず、インドまたはパキスタンに生息するとするのが一般的です。また、大陸ではない南シナ海のフィリピン、その下のインドネシアでも確認されているため、確認されているとは言われていない、
近隣諸国にも存在している可能性があります。ここまで広範囲に渡り生息が確認されていることが最大の特徴ですが、日本のマツカゼソウは変種ともされているため、諸説落ち着くまでは、東アジアに多く見られるマツカゼソウ属の一種が日本にあると理解しておくと違いがあることも認識ができます。いずれにしても育てる環境としては、東アジア広域に育つことからも、あまり特別な環境を整える必要はなさそうです。
種付けや水やり、肥料について
鉢植えでも植え付けでも栽培が可能です。育て方は、さほど難しい品種ではありません。肥沃な土地で育ててあげるために、腐葉土やバーク堆肥などを使用します。乾燥と直射日光を避けるために、水やりに関しては乾燥を防ぐ程度を心がけ、多少多めの湿気を好むとも言われているため、多めに水やりをしても問題ありません。
鉢植えの場合には、水はけの良い土を選ぶのがコツです。元々日当たりの悪い林床に自生する多年草であるため、直射日光を避け、日陰が望ましいとされます。真夏の直射日光は厳禁です。葉焼けを起こしてしまいます。一般的には、苗木の状態のものを購入し、栽培をしていきますが、多年草であることから、届く時の状態により、株の状態が変わっていることがあります。
これは、他の多年草にも言えることですが、多年草の場合、複数年に渡り同じ株で育つため、咲き終わりの株、休眠中の株はもちろんのこと、株分け後の株など、あまり見たことがない状態で届くことがありますが、いずれも栽培には影響はありません。また、ポイントとして、マツカゼソウは、山草のたぐいに分類され、山草は、そもそも山の木々の下で育ち、直射日光を嫌い、
日陰で涼しい気候を好むと覚えておくと、可能な限り自生している状態を確認して、同じような環境を作ってあげることが大切です。現地で確認するのが難しい場合には、インターネットの画像検索などで探すと、一般の方の写真も含め多く見つかり、参考になります。鉢植えの場合は、3号が適しています。山野草用の肥料など一般的な肥料で問題ありません。
増やし方や害虫について
増やし方については、挿し木と株分けで行います。土壌は、挿し木用専用の土や山野草用の土などを用いれば、比較的容易に増やすことができます。育て方も、比較的難しくないことから、一般の園芸店、ホームセンター、インターネットなどで販売している、それぞれの育成過程にある土や肥料などを用いるだけで、よく育ちます。
これといって大きな病害虫に関する報告はありませんが、一部の地域では、キアゲハが、マツカゼソウ属やセリ科の植物に含まれる、エストラゴール(メチルカビコール)やアネトールなどの精油類によって誘引されるため、食草としてとされます。マツカゼソウ属の属するミカン科は、アゲハチョウの食草として知られています。
しかし、アゲハチョウの種類により、どのミカン科を好んで食べるのかは異なり、属性もさることながら、野生種なのか栽培種なのかにもより変わってくるので、面白い性質を持つ蝶です。自分の種族が元来食草として食べる種類以外のミカン科の草を与えても食べないため、マツカゼソウ属に関して言えば、キアゲハのみとなるので、アゲハチョウの中で羽が黄色いものには注意しましょう。
キアゲハの他にナミアゲハも羽が黄色いのですが、もし区別がつかない場合は、インターネットなどで、成虫、幼虫の画像を調べておくなどしておけば、より安心だと言えます。そもそも独特の匂いがありますので、一定の種族以外近寄りがたい存在でありますが、それが逆に一定の種族に好まれる理由でもあるのでしょう。
マツカゼソウの歴史
松風草と書くこの植物は、古くからある古文書や和歌集などで見かけることがなく、名前の由来には諸説あります。大きく2つあり、一つは姿形がいかにも涼しげで、涼しい風の象徴である松風に吹かれている姿が、そのまま松風草と呼ばれるようになったものと、もう一つは、草姿が松に似ており、松枝草と呼ばれていたものが転じて、松風草になったという説です。
どちらにしても、その奥ゆかしさが、名前をつける上で、自然と調和した日本の文化が反映されています。松風という言葉は、古くから和歌などに読まれており、古典文芸においても用いられていました。かの有名な源氏物語にも松風という言葉が登場し、その他の古典和歌集にも数多く、松風は使われています。
その古き時代から使われている言葉がついた松風草は、道に咲く名もないその小さな白い花に名をつけた方の想い入れとはどんなものだったのでしょう。花の姿もさることながら、名付けの理由などを考えると、非常に情緒豊かで奥ゆかしさがあります。一説によると、松風草は、秋ごろに採取し、全草を乾燥させ、臭節草という生薬として使われていたようですが、
若干の有毒性が確認されており、現在では一般的ではないようです。また、生薬として、臭節草とありますが、松風草の中国名も、臭節草で、中国でも薬草として重んじられていたことが挙げられます。倭名類聚鈔という日本初の辞書の中に、芸香という言葉があり、松風草の使い方に似ていることから、一部で芸香は、松風草のことではないかとも言われていますが、定かではありません。
マツカゼソウの特徴
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種とする説と日本にあるマツカゼソウは、その中の変種であるという説があり、未だに確定した見解が示されているわけではありません。ミカン科では、唯一の草本であると言われ、日本国内では、北端は宮城県まで、
主には四国、九州地方で多く見られます。分布としては、広範囲になりますが、四国と九州に集中していることから、原産地は、四国から九州である可能性があります。また、東アジア全域に生息するマツカゼソウの基本種の原産地は、諸説あります。特徴として、中国名が、臭節草とされているように、においに対して香りと使われていません。
臭いという漢字から見て取れるように、柑橘類の爽やかな香りとは程遠い、悪臭がします。この悪臭のもとは、油点であり、油点は細胞間隙に揮発性の油が溜まって透明に見える腺点のことで、ミカン科の特徴でもあります。葉は互生、3回3出羽状複葉で薄く、日に透かすとこの油点が散りばめられているのをみることができます。
夏から秋にかけ(主には秋)開花をし、円錐状に5mm程度の白色の小花を咲かせます。花弁は4枚、雄しべの数は、7から8本で、雌しべの数は1本です。開花後には、さく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)ができ、4つに分かれています。草丈は、50cmから80cmで、茎自体は細く、直立に伸びていきます。
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
ウスユキソウの育て方
ウスユキソウは漢字で書くと「薄雪草」と書きますが、この植物はキク科ウスユキソウ属に属している高山植物です。因みに、ウスユ...
-

-
初心者でもできる、へちまの育て方
へちま水や、へちまたわし等、小学校の時にだいたいの方はへちまの栽培をしたことがあると思います。最近は夏の日除け、室温対策...
-

-
ハボタンの育て方
ハボタンは日本で改良されて誕生したもので、海外から伝わってきたものではありません。江戸時代の前期に食用のケールがつたえら...
-

-
カタナンケの育て方
カタナンケの草丈は約40㎝ほどになります。寒さに弱い性質を持っている為、冬の時期は霜よけをしてあげる必要があります。また...
-

-
キツリフネの育て方
特徴として、被子植物、双子葉植物綱、フウロソウ目、ツリフネソウ科、ツリフネソウ属になっています。属性までツリフネソウと同...
-

-
マイヅルソウの育て方
こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ていま...
-

-
セルリア・フロリダの育て方
”セルリア・フロリダ”は南アフリカケープ地方が原産の植物になります。日本にはオーストラリアから切り花として入ってきた植物...
-

-
シマトネリコの育て方
シマトネリコは、近年シンボルツリーとして非常に人気を集めている樹木です。トネリコと混同している人も多いですが、日本が原産...
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...




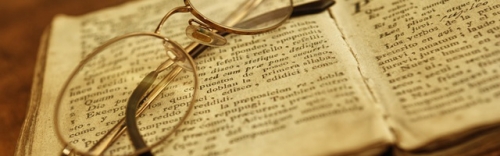





松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種とする説と日本にあるマツカゼソウは、その中の変種であるという説があり、未だに確定した見解が示されているわけではありません。