シンビジウムの育て方

シンビジウムの育て方・植え付け
このランは基本的に鉢植えを購入して入手します。若い株よりも数年たった丈夫な株はその分育てやすく、大きな花を付けます。新しい鉢に植え付けをする育て方では、洋蘭専用のバークや水ゴケを使って植え込み材とします。その際に注意することが鉢の種類です。
プラスティック鉢は通気性が悪く水持ちがよいので植え込み材は洋蘭用バークが適しており、素焼き鉢の場合には水持ちがよく湿り気が長持ちする水ゴケを使うのが良いでしょう。花を育てているうちに茎が一気に伸びてくる時期があります。
そのままにしておくと樹形が乱れてしまうので、花芽が伸びてきたら、支柱を立てて茎が折れずに真っ直ぐに伸びるように誘引しましょう。ただし力尽くで真っ直ぐに誘引すると折れてしまうことがありますので注意が必要です。数回に分けて少しずつ真っ直ぐに誘引しましょう。
シンビジウムの育て方・芽かき
ランは大変花持ちのよい植物で、一度咲くと2ヶ月近く咲き続けます。中には半年近くも咲き続けるランもあり、長く美しい花を楽しむことができます。ただしこのように長期間花を咲かせ続けると株が弱ってしまうので、満開になってひと月ほど花を楽しんだら花を切り取って株を保護してあげることで、次回も美しい花を咲かせてくれます。
シンビジウムの育て方で欠かせないのが芽かきです。大きな花を育てるためにはこの芽かきが欠かせません。花芽と葉の芽育成期間に新芽がたくさん出ますが、この新芽を全て育てて大きくしまっては栄養が分散されてしまい、十分に花まで行き渡りません。場合によっては花が小さくなったり咲かないというケースもあるのです。
そのためシンビジウムの栽培ではひとつのバルブに一つの芽のみを残して、あとは全てかきとります。芽かきとはこの作業をいいます。冬から春に咲くシンビジウムは9月頃にも花芽や新芽が出てきますが、この新芽も全てかきとってしまいましょう。花芽を間違って折ってしまっては花がつかないので間違って花芽をとってしまわないように気をつけましょう。
種付けと増やし方
ランは種付けで増やすことはしません。自宅で増やすときは種付けではなくバックバルブ吹き株分けとバックバルブ吹きで増やします。この方法に適しているのは植え替えをする、3月から4月の春先で、5月には育成期に入って成長が旺盛になってしまうので、4月中に済ませてしまいましょう。
新芽を付けた状態のバルブが3個程度になるようにナイフで切り分けて新しい用土に植え替えをします。バックバルブとは葉のなくなった古いバルブを植え付ける方法で、バルブの付け根から新しい新芽が生えてきます。種付けは行わず、このような方法でシンビジウムを増やすことができます。
シンビジウムの管理栽培方法
ランは冬場、室内で管理しますが5月頃霜がなくなったら室外に出して日光を当てましょう。ただしこれも6月辺りまでです。直射日光が強すぎるとランは葉焼けをおこして枯れてしまうことがありますので日陰で栽培するのが良いでしょう。風通しの良い屋外の日陰がランに最適な環境です。
9月になったら再び日向で管理して秋が来たら室内に入れて栽培します。室内にあっても窓際など日光がよく当たる場所がランの栽培に適しています。ランは7度以下になったら花芽が落ちてしまったり、葉が黄色くなってしまうことがありますので注意が必要です。また急激に暖房等に当たって温まっても葉が落ちてしまうことがありますので寒暖の差がないように注意します。
土が乾いてきたら水ゴケにたっぷり水をやります。特に夏場は水ゴケが乾燥しやすく水切れを起こしやすいので注意が必要です。夏はシンビジウムもよく成長する時期なので、水切れを起こしてしまうと枯れてしまうことにもなりかねません。夏場は朝夕二回の水やりをしてあげましょう。
秋から冬場に関しては少し乾燥気味に育てたほうが花の色が良くなります。成長しているときは水を欲しがりますのでたっぷりと与えましょう。シンビジウムは肥料を欲しがる品種です。春に新芽が出たら固形肥料を与えてバルブがしっかり太くなるまでは10日に1回の割合で液肥をあげましょう。液肥は真夏はストップすることで株の弱るのを防ぐことができます。
2年に一度は鉢を大きなものに植え替えを
2年に一度は鉢を大きなものに植え替えを
栽培しているうちに根が回って鉢が窮屈になってしまうので二年に一回は植え替えをします。傷んだ根を取り除き、一回り大きな鉢に植え替えることでより大きく丈夫な株になります。最適な時期は新芽が伸び始める前の3月から4月にかけてです。
鉢から抜いたら根が回りきっているので、一回り大きな鉢に植え前をしましょう。用土は軽石やパーライトを混ぜた水はけが良いものを使うのも良いでしょう。根が傷んでいる部分はハサミで切り取って取り除いてきれいな根だけを残して植え替えしましょう。こうすることでより大きく丈夫な株に育ちます。
シンビジウムの歴史
ランはヒマラヤから中国、日本、オーストラリア、南米など広範囲に分布していますが、その中でもシンビジウムは約50種ほどあるとされています。インドネシアやタイなどの熱帯アジア地域原産地では特に数多くの品種が分布しておりその多様性を見ることができます。特に中国ではラン栽培の歴史が古く千年も前からランの栽培に関しての文献があることがわかっています。
日本でも豪華な鉢へ植え付けて室内でランを楽しむ習慣があり、東洋はこのランの発展に大きく寄与してきました。花自体は小さいながら、花の形や香りを楽しむなど、欧米とはまた違う東洋ならではのランの楽しみ方があります。ヨーロッパでは豪華絢爛な花の形に重きを置くのでこの花も華やかな花様に品種改良されました。
アジアに植民地を展開したヨーロッパでは一気にシンビジウムの人気が高まり、品種改良が進むにつれ、ウイルス感染で多くの個体を失ってしまった歴史から、メリクロン技術が開発され、現在では健康な個体をメリクロン技術でどんどん増やしていけるようになりました。名前の由来はギリシャ語で舟の形のという意味で花の形が凹んでまるで船のような形に見えるところから来ています。
シンビジウムの特徴
ランは世界中の植物の中でも最も古くからあり、最も品種が多いと言われている多様性が特徴です。同じランでも日本で人気のものにはデンドロビウム、オンシジウムがあります。デンドロビウムは丸い葉や茎が特徴で、オンシジウムは黄色く小さな花が魅力ですが、シンビジウムの特徴はなんといっても美しく真っ直ぐに伸びきった葉と華やかな花弁にあります。
このランが多く分布している生息地の熱帯アジアは貿易風や偏西風の影響で高温多湿の状態で、年中霧が発生し、年間降水量もおおい地域があると思えば、ほとんど雨が降らない乾燥地域もあります。シンビジウムはこのようなさまざまな環境に耐える多くの品種があるのが特徴です。また多くのランは実は樹木など他の植物にくっついて着生生活をしていますが、シンビジウムは地面に直接自分の根を張って生えている地生種です。
このランを多く健康に栽培するために日本ではいち早くバイオ技術が取り入れられ発展してきました。その技術は現在では農業にも活かされており、メリクロン技術というシンビジウムのために開発されたバイオ技術が、農業全体の技術の発展にも繋がっているという特徴もあります。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
タイトル:ビオラの育て方
タイトル:クロッカスの育て方
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
オレンジ類の育て方
インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海...
-

-
マツバボタンの育て方
原産地はブラジルで日本には江戸時代に入ってきたといわれるマツバボタンは、コロンブスがアメリカに進出したことでヨーロッパに...
-

-
グアバの育て方
皆さんはグアバという果実をご存知ですか。あまり聞きなれない人も中にはいるかもしれませんが、最近では健康食品や女性の美容健...
-

-
カリフォルニア・デージーの育て方
科名はキク科であり、学名はライアであり、別名にライア・エレガンスという名を持つのがカリフォルニア・デージーであり、その名...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
ルナリアの育て方
別名にゴウダソウやギンセンソウの名を持つルナリアは、学名Lunariaannuaで他にマネープラントという名を持つ二年草...
-

-
コマツナの育て方
コマツナの歴史は国内では江戸時代まで遡ります。東京の江戸川区の小松川で栽培されていたことが、小松菜という名前になった由来...
-

-
モナデニウムの育て方
モナデニウムは日当たりのいいところで栽培をします。そして育て方は土が乾いたらたっぷりの水を与えてあげます。塊根タイプの植...
-

-
ヘビウリの育て方
インド原産のウリ科の多年草で、別名を「セイロン瓜」といいます。日本には明治末期、中国大陸を経由して渡来しました。国内では...






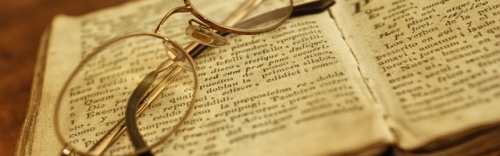





ランはヒマラヤから中国、日本、オーストラリア、南米など広範囲に分布していますが、その中でもシンビジウムは約50種ほどあるとされています。インドネシアやタイなどの熱帯アジア地域原産地では特に数多くの品種が分布しておりその多様性を見ることができます。特に中国ではラン栽培の歴史が古く千年も前からランの栽培に関しての文献があることがわかっています。