ユズ(実)の育て方

育てる環境について
ユズの実を育てる環境としてとして、育て方でも気をつけたいのは、太陽の光によく当ててあげるということです。栽培環境としては、お日様の光を、とても好む植物です。家の庭に植え付けるときには、太陽の光がよく当たる場所を選ぶとよいでしょう。最近では、小さな鉢植えの木を育てるのも人気があります。購入当時は小さくても、数年すれば、すくすくと成長はしていきます。
そんな鉢植えの場合も、お日様の光は、とても重要なポイントです。プランターの場合でも、日当たり良好なゾーンを見極めて、お日様の光をよく当ててあげることです。明るく元気な太陽の光を、たっぷりと浴びた実は、ビタミンCもたっぷりと含んでいます。特に黄色が眩しい皮の部分にはビタミンCが多くて、果汁と比較した時、なんと4倍近くもたっぷりと含まれています。
ゆずが栽培されている畑を見ると、キレイですし参考にもなります。栽培は山の斜面で、石段でできた段々畑で育てられています。これはゆずにとって適切な栽培として、昔から考えられて伝えられている方法です。よく有名なお茶畑でも、似たような栽培を目にすることがあります。
とにかく欠かせないのは、日あたりが良いことです。短期間で栽培する野菜類とは異なり、長い時間を必要とします。長い時間を経過して、やっと開花して、実をつけることになります。そのため、育てるのにあたっても、必要条件の陽の光は外すことなく、環境条件としても揃えておくことが大事です。
種付けや水やり、肥料について
ユズの栽培ですが、植え付けや植え替えの適切な時期としては、3月下旬から4月上旬にかけての時期です。鉢植えやプランターよりの植え替えをするというのは、通気性を良いものとし、根詰まりを起こさないようにする対策でもあります。柑橘類というのは、基本的に細根が多いもので、生育の具合ですとか、鉢のサイズにもよりますが、植え替えは2年に1回くらいのペースで行うことです。
増やすときには、つぎ木をおこないます。これを行う時期は、3月の中旬頃から5月の上旬位の時期で、休眠枝つぎになります。温度も上がった8月中旬から下旬にする芽つぎで、どんどんふやしていくことになります。台木に用いるのは、カラタチが一般的です。水やりですが、バランスが大切になってきます。
植物を育てるのには、太陽の光と栄養のある良い土、そして水です。ユズのためにも、成長には妃乃ひかりと土と水が重要になります。水はけが良いことを意識しながら、ほどよく湿りのある土を土台にしておくことも必要です。水はけのわるさは、水が溜まって根腐れしやすくなります。土壌は、水はけの良さを作ることが大事です。
土の状態を見ながら、適度に水やりをしてあげます。土の表面が乾いてきた頃に、たっぷりと水分を与えてあげるとよいでしょう。肥料は庭に植えている場合は、3月と10月に与えます。プランターでの栽培であれば、3月と6月、あとは10月に速効性化成肥料か、有機質肥料を施すことです。
増やし方や害虫について
可愛らしい黄色い実をつけるゆずですが、害虫には注意しなければなりません。3月から4月の頃は、新芽が出てくる良い時期ですが、カイガラムシやハダニ、アブラムシが発生しやすくなる時です。それに備えて、早い時期に消毒を行っておきます。こういった手入れは手間ではありますが、遅くなってしまうと、すす病になったり、
葉が落ちることもありますから、早めの対処が必要になります。黒点病やすす病というのは、お日様の光が当たりにくいゾーンでの発生率が高めです。日当たりがよく安心していたら、枝葉が多すぎて、内側までせっかくの太陽の光が差し込んでいなかった、というケースもあります。内側まで太陽の光が通らなければ、発生しやすくなりますから、
気をつけたいところです。ハダニやカイガラムシ類といった、害虫の排泄物が要因となり、すす秒などは起こりますから、害虫を予防することが重要になってきます。12月から1月には、マシン油乳剤を散布することで、カイガラムシを予防します。水道の蛇口をひねり、ホースの圧力をパワーアップさせて、葉の裏にかけることで、ハダニ対策になります。
何かと手間隙かかるゆずですが、増やしていくのは楽しいです。柑橘果樹のゆずを、家の庭に植えるというのは、代々家が栄えるとも言われているため、縁起も良いです。加湿気味の場所は好みではないため、増やし方の注意点として、根鉢が地面よりも出ている状態で、浅い感じで植え付けすると良いです。土はちゃんと盛り、水はけよくすることも大事です。
ユズ(実)の歴史
冬至の日にはゆず湯に浸かって、香りも楽しむという、日本古来の風習もあるほど、ユズは日本人にとって馴染みが深い食材です。冬至の日がきたら、ゆず湯に入るというには理由があります。その日にゆずの湯に入ることで、無病息災で過ごすことができるという、古くからの言い伝えがあります。
可愛らしい見た目のゆずですが、成分には優れており、ビタミンCもたっぷりと含んでいます。風邪の予防にもなりますし、披露を回復する効果も期待ができます。歴史あるゆずは、昔の人の知恵で、ゆず湯もあるのでしょう。女性にはうれしいことに、肌の美肌効果も作用は期待できると言えるでしょう。肌荒れを回復させるためにも、良い成分です。
そんなゆずの実は、原産地は中国揚子江上流域だと言われています。そのあたりを生息地として、ほかの地域にも広がっていきました。ゆず湯で国内では有名ですが、日本へ伝わったのは、奈良時代だといいます。しかし、その他にも、日本へ伝わってきたのは飛鳥時代ではないか、という説もあります。
古い書物の記録によれば、渡来した当時は果実といったカテゴリーではなく、薬用という理解のもと、栽培が行われていました。現代とは、だいぶ意識が異なっていたことがわかります。現代においては、
国内でも主に栽培を行っている地域は、いくつかに限られてきます。国内では、徳島県と高知県の栽培が、日本国内全体の、約70%を栽培しています。家庭においても、庭の木にゆずの木があったり、ミニサイズの苗木を購入してきて育てるということもあります。
ユズ(実)の特徴
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くらいかかります。あんなに可愛らしいイエローカラーの実をつけているキュートな実ですが、実は木に近づいてみると、鋭いトゲを持っている木でもあることに気がつきます。
これは、ほかの柑橘類にも言えることですが、美味しい果実をつけているわけですから、周囲から守るための対策とも言えます。柑橘類は自分で栽培して収穫をして、やっと口に入れるという流れを、普通に家庭で行うことはあまりないため、初めてトゲトゲした状態を目にすると驚くかもしれません。
自宅でユズの栽培にトライして、時期が来て収穫をする時になったら、このトゲにも十分に注意をして収穫をすることです。ユズの特徴として、寒さに強いことも挙げられます。基本的に、明るく暖かい太陽の光が大好きな植物です。ですが、寒さにも強いというスグレモノとも言えるでしょう。みかんたちの仲間でありながら、その中にあっても体感性は抜群です。
そのため、寒い東北の土地でも栽培することができます。収穫されて世の中に出回るシーズンとしては、青い状態で7月から10月ころ、市場に流通します。市場に出回るのは完熟の黄色い状態ではなく、まだ完熟前の青い状態です。花を咲かせるのは、5月から6月頃です。収穫の時期は、初冬の頃です。一般的にスーパーなどで見る、馴染みのあるイエローカラーの実は、完熟した状態ということです。
-

-
モミジアオイの育て方
モミジアオイは、ハイビスカスの仲間で、花は、非常に鮮やかな赤色で、花弁も大きく、よく似ています。いかにも夏の花という感じ...
-

-
植物を栽培する時のコツ
栽培や植物を育てるにはさまざまなコツがあります。また、栽培や植物の種類によっても育て方が異なってきます。例えばニンニクで...
-

-
イワシャジンの育て方
イワシャジンは関東地方の南西部や中部地方の南東部の山地の岩場などで見つけられることができる紫色と小さな花をつける大きめの...
-

-
イオクロマの育て方
多くの国でさまざまな花の種類を見かけることができますが、その国の特色にあった植物が生息しています。そのなかでイオクロマと...
-

-
トマトの育て方について
自宅の庭に花が咲く植物を植えてキレイなフラワーガーデンを作るというのも一つの方法ですが、日常的に使う野菜を栽培することが...
-

-
ヘンリーヅタの育て方
特徴として、まずブドウ科、ツタ属であることです。つまりはぶどうの仲間で実もぶどうに似たものをつけます。しかし残念ながら食...
-

-
セントポーリアの育て方
セントポーリアの原産はアフリカです。アフリカに進出していたドイツが、現在のタンザニアあたりを生息地としていた花を見つけた...
-

-
アメリカテマリシモツケの育て方
アメリカテマリシモツケは、北アメリカが原産だと考えられており、現在テマリシモツケ属の生息地はアジア東部や北アメリカ、メキ...
-

-
キングサリの育て方
キングサリの科名は、マメ科 / 属名は、キングサリ属です。キングサリは、ヨーロッパでは古くから知られた植物でした。古代ロ...
-

-
フィットニアの育て方
フィットニアはキツネノマゴ科フィットニア属の植物です。南米、ペルー・コロンビアのアンデス山脈が原産の熱帯性の多年草の観葉...




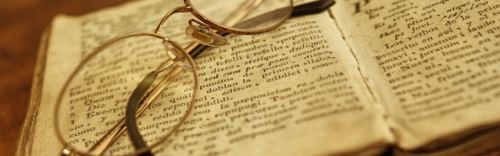





ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くらいかかります。あんなに可愛らしいイエローカラーの実をつけているキュートな実ですが、実は木に近づいてみると、鋭いトゲを持っている木でもあることに気がつきます。