ブライダルベールの育て方

ブライダルベールの育てる環境について
ブライダルベールは日当たりの良い場所を好む植物です。日陰でも育ちますが、日照不足になると葉の色が悪くなり花も咲きにくくなります。そのため栽培する時にはなるべく日当たりの良い明るい場所に置くようにします。ただ直射日光などの強い日差しに当ててしまうと、
葉焼けを起こして茶色く変化してしまう恐れがあるため、日差しが強くなる夏は明るい半日陰に置いたり、レースのカーテンで日差しを遮るようにしてください。ブライダルベールは葉が密集していて、土がなかなか乾かず根腐れを起こす場合もあるので、
蒸れを防ぐためなるべく風通しの良い場所におくようにします。冬が近づき気温が下がってきた時にはできるだけ温度を5度以上に保つようにして、なるべく室内で管理します。窓際などの強い風にさらされる所に置いておくと、茎や葉が傷むことがあるので気をつけましょう。
冬でも暖かい地域では昼間は屋外に置いておくことも可能になりますが、霜が降りる地域では室内で管理します。ブライダルベールは寒さには比較的強く冬には葉が枯れてしまいますが、春になると芽が育ち再び緑の葉が茂ってきます。寒さの影響で葉が枯れてしまっても、
枯れた部分は取り除かずにそのまま越冬させると防寒対策になります。そのため冬になって葉が枯れてもそのまま放置せずに、水やりは忘れずに行うようにして根を育てるようにします。ブライダルベールは日当たりと冬場の温度管理に気をつけることで、美しい葉と花が長く楽しめます。
種付けや水やり、肥料について
ブライダルベールの植付けと植え替えに適している時期は5月です。根の成長が早いので、できれば1年に1度植え替えを行います。鉢の底から根が出てくるなどの、根詰まりを起こしやすい植物なので、植え替えの際には根を刈り込んでおくようにします。
根詰まりを起こすと下葉が枯れてくることもあるので、定期的に行うようにしておくと安心です。植付けや植え替えに使用する土は観葉植物用、または赤玉土と腐葉土など水はけの良い土を使い、吊り下げる場合は、ピートモスやバーミキュライト、パーライトを使って軽量化しておきます。
水やりは通常は土が乾いてから与えるようにしておき、春から夏にかけて水はたっぷりと与えるようにします。特に夏は土が乾燥しないように気を配り、朝と夕方に水やりを行って水切れしないようにしてください。ただし与え過ぎると根腐れの原因にもなるため、
土の状態を確認しながら与えましょう。冬場は乾燥気味にしておくと、耐寒性が高まり根腐れ防止の効果もあるので、鉢の中の土が完全に乾いた状態になってから水やりを行います。ブライダルベールは季節に応じて与える水の量が変わってくるので、注意してください。
肥料は春と秋に置き肥や液肥などの緩効性の物を与えます。肥料が過剰になってしまうと茎が細長く伸びてしまうことがあり、肥料が少なすぎると花つきが悪くなることがあるため、適度な量を与えるようにしましょう。反対に夏や冬は肥料は与えないようにします。
増やし方や害虫について
ブライダルベールの増やし方には、株分けと挿し木があります。株分けをする場合は、5月から7月が最適な時期です。挿し木は5月から9月が適していて、刈り込んだ時の枝などを再利用します。ブライダルベールのボリュームを出すためには、
1本の茎だけを挿すのではなく複数をまとめて挿し木して、だいたい10本程度をひとまとめにして、植付けする鉢の大きさに合わせて挿していきます。直接土に挿す前に、挿し木を水の入ったコップに入れておくと根が出てくるので、それを植えるようにすると手軽に増やすことができます。
直接植える場合には節の部分に生えている葉は取り除くようにして、節が土に埋まるようにして植えます。それを明るい日陰に置いておき、水を切らさないように注意してください。10日位過ぎると根が生えてきてやがて茎がしっかりして新芽が伸びてきます。
その後肥料を与えて新芽が十分伸びてきたら刈り込みをして形を整えて通常の管理を行います。ブライダルベールのがかかりやすい病害虫にハダニと炭疽病があります。ハダニは乾燥した状態になると発生するので、水を与える時には根元だけでなく葉にもまんべんなくかけるようにして、
空気が乾燥している時には霧吹きを使用して時々葉に水をかけるようにします。炭疽病は春から秋にかけて発生し、初期の段階では黒褐色の斑点が見られ、やがて穴があいて葉が先の方から枯れていきます。炭疽病を防ぐには多湿を避けて風通しを良くしておき、発病している葉を見つけた場合は取り除いてから薬剤を散布します。
ブライダルベールの歴史
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライダルベール」になりますが、生息地はタヒチではなくメキシコ原産の植物です。ツユクサ科ギバシス属の多年草で、うまく育てれば毎年白く小さな花を見ることができます。
ブライダルベールはこの白い花が無数に咲く様子がウエディングベールのように見えることが名前の由来となっています。花の開花は5月から10月になりますが、温度や条件などが適していれば年間を通して花が咲きます。ブライダルベールは濃い緑色をした葉が特徴的で、花だけでなく葉も鑑賞に適しています。
葉は濃緑色の他に、黄色の斑が入るバリエガタも存在していますが、模様が目立たないため主に流通しているのは単色の種類です。ブライダルベールの花言葉は幸福や豊かさといった名前に関連したロマンチックなものになっています。葉がこんもりと茂って見栄えが良く、
吊り下げたりスタンドに飾ることができて場所も取らないため、室内のインテリアとしても多く利用されいます。寒さにも耐えるので栽培はそれほど難しくはないのですが、きれいに花を咲かせるためには手間を惜しまず育てることが大切になります。
育て方のポイントとしては、日当たりや肥料などに注意して栽培するようにすると花がたくさん咲くようになり、見栄えが良くなります。また、インテリアとして利用する際には日当たりを考慮して置き場所に注意してください。
ブライダルベールの特徴
ブライダルベールは常緑性の観葉植物であり、栽培は比較的容易に行えます。細長い茎が垂れ下がり、そこから約5~6ミリほどの花がたくさん咲き、花弁は3枚で濃緑色の葉の裏側は赤紫色になっていて、見る角度によっては違った印象を受けます。
草の丈は20~30センチほどになり、成長が早く葉や茎が良く茂るのでボリュームが出てきます。この時葉や茎が伸びたままにしておくと形が悪くなるため、適度にカットして形を整えるようにしてください。剪定には栄養をまんべんなく与えたり、病害虫を防ぐといった効果もあります。
また花が咲き終わると花ガラが落ちてくるので、花枝ごと切っておきましょう。ブライダルベールは蒸れに弱いので、中央部が枯れてきたときには茎を間引いて少なくしたり、短くカットしてしまうといった方法を取ります。こうすることで湿気がこもらなくなって、
新しい芽が伸びやすくなります。カットする際には新芽が育つ節を考慮して切るようにすると、そこから枝が伸びて花がたくさん咲いてきます。ブライダルベールは下に垂れさがる特徴を生かして、ハンギングバスケットや背の高い鉢植えなどに多く利用されています。
それほど置き場所も取らないためリビングや玄関、浴室などさまざまな場所のインテリアとして活用できます。ただし、ブライダルベールを美しく保つには日光が非常に重要になるので、日陰に置く場合には昼間は日当たりの良い場所に移動しておくと、葉の色つやが良くなり、花がたくさん咲くようになります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:プルーンの育て方
-

-
栽培が簡単な植物の育て方
花も植物も育てたことがない人にとっては、花壇いっぱいの花や植物の栽培はとても難しいもののように思われることでしょう。しか...
-

-
サルビア(一年性)の育て方
サルビアの正式名称はサルビア・スプレンデンスであり、ブラジルが原産です。生息地として、日本国内でもよく見られる花です。多...
-

-
シュウカイドウの育て方
シュウカイドウは中国を自然の生息地とする植物で、多年生の植物です。中国名は「秋海棠」と書きます。これをそのまま日本語で音...
-

-
ヒノキの仲間の育て方
ヒノキは原産として日本と台湾にのみ分布する樹木です。アメリカにおいては似ているものとしてアメリカヒノキがあり日本にも輸入...
-

-
芝生の育て方
芝生には様々な特徴があります。原産地によって育つ時期や草丈などにも差があり、どれを選ぶかは自分の住んでいるところどで決め...
-

-
ラディッシュの育て方
ラディッシュとは、ヨーロッパ原産の、アブラナ科ダイコン属に分類される野菜です。ダイコンの中ではもっとも小さく、そして短期...
-

-
ブルークローバーの育て方
ブルークローバーはマメ科パロケツス属の常緑多年草です。原産はヒマラヤやスリランカ、東アフリカなどで、主に高山帯を生息地と...
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
チャノキの育て方
そのように非常に日本でも親しまれているチャノキですが、元々は熱帯地方の植物で、ツバキ科ツバキ属の常緑樹ということですから...
-

-
セイヨウタンポポの育て方
セイヨウタンポポは外国原産でそういうところから持ち込まれたタンポポであり、今では我が国を生息地として生えているタンポポで...




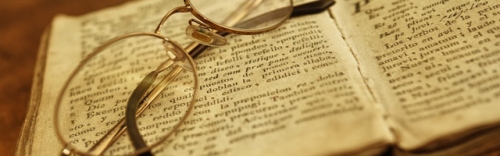





ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライダルベール」になりますが、生息地はタヒチではなくメキシコ原産の植物です。