アイスプラントの育て方

育てる環境について
日本での歴史は始まったばかりだと言っても過言ではない野菜です。段々注目を浴びて家庭栽培されるようになっている野菜ではありますが、前例や情報もあまりない上、日本は生息地でないため、勝手に栽培が難しいと決め込んでしまっている人もいるかもしれません。
原産地のアフリカと日本ではとても環境が異なりますし、同じような環境を家庭で作ってあげるのは不可能だと考える人もいます。しかし、少しの注意するべきことさえ守れば、育て方はそんなに難しいことはありません。日本の気候でも十分に育つ適応性の強い野菜です。春と秋は最適な気候です。
春か秋に気温の変化を確認しながら、最適な時期に種まきをするのが良いです。しかし、関東を基準にした真夏の暑さや真冬の最低気温程度になると枯れてしまう可能性があります。特に夏の暑さと湿気は大敵です。対策は欠かせません。遮光に工夫をするなど対策方法を考えましょう。
また、ほとんどの人が土壌での栽培を考えますし、ほとんどのアイスプラントについての育て方の情報は土壌での栽培が前提とされています。土壌でも十分育てることはできますが、水耕栽培でも育てることができる植物のようです。
ホームセンターなどで多肉植物には水耕栽培は向かないとアドバイスされることもあるかも知れませんが、農家や研究機関においてはすでに実行されて成功しているのでできないことはないはずです。実際に既に家庭において水耕栽培に挑戦している人もいます。
種付けや水やり、肥料について
水耕栽培でも育てられるとはいえ、一般の人にとって一番身近な栽培方法は土壌での栽培です。また、家庭においてはプランターで育てる人も多いでしょう。上記でも述べたように種まきの時期に最適なのは春と秋です。春まきの場合は2月下旬から4月ぐらいを目安に、秋まきは9月から10月を目安にするのが良いです。
この期間のできるだけ早い時期にまく方が良いとも言われています。収穫量にも差が出ますし、収穫時期もずれてくるので野菜が大敵とする時期に重なってしまえば良くありません。また、種からまく人もいますが、現在ではホームセンターなどである程度の大きさまで育てられた苗が販売されていることも多いです。
苗を購入してそのままプランターに植え替える場合、始めは成長が遅く感じられますが、時間が経って周囲の土と馴染むと通常通り大きくなります。プランターには、市販されている土でも良いですし、栄養分を豊富に含んだ山や畑の土を入れるのも良いでしょう。植える時には一緒に肥料をやりましょう。水やりに関しては、少なめにするように注意しましょう。
他の植物のように真水で問題ありませんが、この野菜の最大の特徴は吸塩植物なので、収穫が間近に迫った頃には塩水を与えてやりましょう。塩水を与えることによって、野菜も大きくなりますし、食べた時の塩分も増して美味しくなります。塩分濃度は5パーセント程度が目安です。他の植物の水やりと混同しないようにくれぐれも注意しましょう。
増やし方や害虫について
アイスプラントは成長しますが、夏や冬など苦手とする時期になると成長は止まっているように見えるぐらい鈍ります。もちろんこの時期の収穫は不可能です。しかし、アイスプラントにとって最適な時期の成長は目を見張るものがあります。毎日が楽しみです。放射線状に葉が生い茂って成長するという情報はよく目にするかもしれませんが、
実際に自分の目で確認することもできるでしょう。葉が生い茂っている野菜なので、虫に食われて穴が開いていることもあれば、虫が葉の上を這っていることもあります。すぐに気づかなければなりません。害虫を見つけた場合は、茎を切断しましょう。葉野菜なので、葉を虫に食べられてしまっては、人間が食べる部分が無く、
育てている意味がありません。本来は害虫や病気には強い植物だということで有名です。多くの植物が苦手とする塩分でさえも摂取して育つのですから、この野菜の生命力の強さは想像できます。もしも他の野菜や植物を害虫に侵されてしまって台無しにしてしまったトラウマがある人がいるならば、この点に関しては比較的安心して育てることができます。
元気がなくなっている場合は、害虫を疑うよりも先に他の要因から探してみましょう。害虫が付きにくいということは、農薬も特に必要がないということです。安全性についてもお墨付きの野菜だと言えます。上手に育てることができれば、花を咲かせますし、実を付けます。花を見ても原産地がアフリカだと感じさせられることでしょう。
アイスプラントの歴史
現在近所に買い物に行けば海外から輸入された食品をたくさん目にすることができます。魚介類にしろ、野菜にしろお菓子にしろ、欲しいものは大体揃うはずです。一方で国内産に目を向けると、日本には四季があるため、それぞれの四季の旬の食材は栄養分も豊富で特に重宝されています。
しかし、今となっては野菜や果物は栽培方法が発達して旬がわからなくなってしまうほど一年中店頭に並び、いつでも食べられるようになっています。珍しい名前の海外の野菜を見ることも珍しくありません。新しい物好きな人やお洒落な人は食べたことがあるかもしれません。このような世界中の物が何でも手に入る現代において新野菜として注目されている野菜があります。
アイスプラントという野菜です。名前が可愛いので観賞用の植物だと勘違いしてしまう人もいます。もしくは植物だけ見たら雑草と勘違いする人や外見の奇妙さを気味悪がる人もいるかもしれません。実際に、日本に取り入れられた時の目的は食用ではありませんでした。元々の目的とは別に、後に食べられることが判明したようです。
海外でもフランス料理などに取り入れられています。南アフリカが原産の野菜です。アフリカと聞くと砂漠やサボテンをイメージする人もいますが、この植物もサボテンのように多肉植物に分類されます。日本に取り入れられた元々の目的は塩の被害に合った土壌の塩を抜くための手段とするためです。この植物にしかない特徴を活かそうというアイディアです。
アイスプラントの特徴
元々アイスプラントが日本に取り入れられた理由はこの植物にしかない特徴のためです。その特徴とは塩分、つまりミネラルを吸収することです。普通の植物では、塩分が混ざってしまうと枯れてしまう場合がほとんどです。海の近くで農業をしている人などは、台風による塩害被害を受け農作物が台無しになってしまったという経験をしたこともあるはずです。
アイスプラントには植物は塩分が苦手だという常識が覆されます。この特徴は、外見にまで影響を及ぼしています。葉の表面に塩の結晶のようなキラキラしたものが見られます。霜のようにも見えますし、氷のようにも見えることからアイスプラントと名付けられたことが納得できます。
食べた時にこの表面の舌触りや歯触りが他の野菜にはなくとても不思議な感覚に捉われる人が多いようです。また、味はふんわりと塩味がします。野菜嫌いの子どもも食べてくれるかもしれません。見た目も味も特徴が多い野菜です。しかし、栄養に関しては他の野菜と同様に栄養価が高いです。野菜ですから体に良いことは言うまでもありません。
中性脂肪や血糖値を抑制する成分が多く含まれているので、生活習慣病や中年太りを気にしている人を始め、健康意識の高い人に好まれるでしょう。また、ビタミンやミネラルを始め、ダイエットや美容に大いに貢献する成分も多く含有されているので、女性にとっても嬉しい野菜です。全ての人の悩みを解決し、欲望を満たしてくれる野菜だと言えるでしょう。
-

-
リンドウの育て方
リンドウは、リンドウ科、リンドウ属になります。和名は、リンドウ(竜胆)、その他の名前は、ササリンドウ、疫病草(えやみぐさ...
-

-
観葉植物として人気のシュガーバインの育て方
シュガーバインは可愛らしい5つの葉からなるつる性の植物です。常緑蔓生多年草で育て方も簡単なので初心者の人にもおすすめです...
-

-
さやいんげんの育て方
中南米が最初の生息地であり、中央アメリカが原産といわれています。16世紀末にコロンブスが新大陸を発見した時に、さやいんげ...
-

-
ホリホックの育て方
この花については、アオイ木、アオイ科、ビロードアオイ属になります。見た目からも一般的な葵の花と非常に似ているのがわかりま...
-

-
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)の栽培
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)は、南米原産のノウゼンハレン科のつる性の一年生です。開花時期は5月から10月過ぎる頃ま...
-

-
コルチカムの育て方
コルチカムの科名は、イヌサフラン科で属名は、イヌサフラン属(コルチカム属)となります。和名は、イヌサフランでその他の名前...
-

-
チャービルの育て方
チャービルはロシア南部から西アジアが原産で、特に、コーカサス地方原産のものがローマによってヨーロッパに広く伝えられたと言...
-

-
ガクアジサイの育て方
一般名として、ガクアジサイ(額紫陽花)といい学名はHydrangeamacrophyllaf.normalis。分類名は...
-

-
フキ(フキノトウ)の育て方
植物というのは古来より、食用として育てられてきました。食べ物としてとることによって、人間の栄養になり体を作っていくことが...
-

-
クリダンサスの育て方
クリダンサスの特徴としてはやはり見た目と香りでしょう。鮮やかな黄色の花を咲かせて香りは花のフレグランスとも呼ばれているよ...




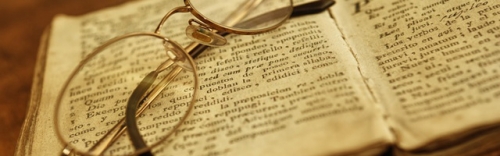





元々アイスプラントが日本に取り入れられた理由はこの植物にしかない特徴のためです。その特徴とは塩分、つまりミネラルを吸収することです。普通の植物では、塩分が混ざってしまうと枯れてしまう場合がほとんどです。