スキミアの育て方

育てる環境について
もともと日光を好む種ではありますが、耐陰性があり多くは必要としないので日当たりの少ないところでも生育が可能です。かといって、あまりに日光が当たらない状態での生育は花つきに影響が出てしまうので可能であればできるだけ明るい日陰に植えることが理想的です。強い日差しには弱いので初夏から初秋にかけての直射日光を避けられる場所に置くことが好ましいです。
日差しの弱くなる秋から初春までは日当たりのよい所に置くとようにします。気温に関しては耐寒性があり冬場の屋外でも生育が可能です。夏場は上述の日光にだけ注意することで屋外での生育が可能です。強い日差しは葉焼けやそれによる株の弱りの原因となってしまうのでとにかく注意が必要です。
以上のような環境を整えるためにも季節に応じて移動が可能な、鉢植えが適しているといえます。尚、十分に成長しきった大きな株の場合は多少の葉焼けで株が弱ってしまうことはほとんどありませんので、庭植えも可能です。ヨーロッパでは大きく成長させた株を街路樹や花壇に植えている姿がよく見られます。またヨーロッパの民家では庭植えをメインとして栽培されています。
庭植えを望む場合は鉢植えで十分に成長させてからの植え替えが無難といえます。強健な生命力をもっているので環境さえ整えることができればみるみるうちに成長します。ツボミから開花まで時間を要したりと少々特質なので初心者には手のつけにくい種と思われがちですが、育て方自体はそう手間のかからない植物ですので基本の環境を整えることで楽に栽培ができます。
種付けや水やり、肥料について
植えつけは3月または9月の下旬から10月頃に行います。一般的に苗で出回っていることがほとんどなので、購入時は苗選びにも気を配るようにします。苗を選ぶときのポイントとしては「葉に艶があり根本付近の幹がしっかりしていること」「変色や枯れがないこと」「虫がついていないこと」を意識できるとよいです。
購入時の鉢は通気性の乏しいビニールもしくはプラスティック製が多く、そのままにしておくと根腐れや根詰まりの原因となってしまうため購入後は出来るだけ早く植えつけを行うようにします。植えつけの際は購入時に植えられている鉢より一回り大きな鉢を用意します。
寄せ植えやプランターに植えつける場合はもともとの鉢より一回り広いスペースを各苗の周りに空けるようにします。成長すると根をぐんぐん伸ばすため、株同士を詰め過ぎると根詰まりを起こしたり養分が十分に行き届かず弱ってしまいますので注意が必要です。用土は小粒の赤玉土と腐葉土を7:3の割合で混ぜると、適度に水はけのよい土壌となりトラブルが起きにくくなります。
プランターや鉢植えの場合は地面に直接置くとダンゴ虫などの害虫がつく場合がありますのでガーデンニング台に置くか、こまめに置き場所を移動させるとよいです。水やりは土の表面が乾いたら十分に行います。庭植えの場合は降雨の水分だけでも十分に育ちますが、晴天が続き地面が干上がってしまいそうな場合は十分に水やりをします。肥料は春と秋に緩効性の肥料を施すことで問題なく元気に成長します。
増やし方や害虫について
挿し木で増やすことができます。剪定自体はあまり必要ありませんが、挿し木をする場合は花が終わった後の5月から6月頃に剪定します。新芽を避けた元気な枝を10から15cmほどに切り下葉がある場合は取り除いておきます。この時ほかに大きな葉がある場合は葉の半分を切り落としておくことで余分な蒸散を防ぎ、次に行う水揚げ処理が幾分楽になります。
水揚げはコップやペットボトルなど、高さの合うものであれば何でも構いません。可能であればメネデールなどの発根促進剤を希釈して使うことが理想的です。最低でも1時間は十水を吸わせ、その間に鉢のセットを行います。用意する土は必ず清潔で肥料分のないものを選んでください(バーミキュライト、鹿沼土、挿し木用の土など)。
養分のある土に挿し木を行うと挿し穂の切り口からでる成分で土が必要以上に汚れ、カビの原因となります。土に4cm程度挿し、十分に水やりをしたら挿し木は完了です。十分に成長するまでは直射日光の当たらない屋内の明るい日陰で管理し、土が乾ききる前に水やりをします。
とくに問題となる病気や害虫はありませんが、初春にアゲハの幼虫やそのほか蝶類の幼虫がつくことがあります。幼虫は葉を食べて成長しますので葉の虫食いを避けたい場合は発見と同時に取り除く必要があります。また、直射日光などにより痛んで枯れ落ちた落ち葉はそのままにしておくとカビの原因となる場合があるのでこまめに取り除くようにします。
スキミアの歴史
「スキミア」はミカン科ミヤマシキミ属、日本を原産とする常緑低木の一種です。学名は「シキミア・ジャポニカ」、英名を「スキミー」といいます。原産国が日本とのこともあり古くから日本人に愛され、一般的に出回る苗ものの中ではやや高価であることで知られています。学名にジャポニカとつけられていることからも親しみの持てる植物です。
生息地は本州全土から九州沖縄と幅広く、様々な気候変化に対応できることも日本の原産ならではといえます。この「スキミア」ですが呼び名が多いことでも知られています。地方の訛りや、原種である「ミヤマシキミ」の名称から「シキミア」と呼ばれることも多く、時には「ミヤマシキミ」と同種として扱われることも少なくありません。
この「ミヤマシキミ」の名称の由来は、シキミ科の「シキミ」と葉の形が似ており「シキミ」同様、山に咲くことからこの名がつけられたといわれています。「ミヤマシキミ」が近年の「スキミア」の美しい姿形に至るまでの背景には、ヨーロッパに渡り長年の品種改良をされてきたという歴史があります。そのためヨーロッパ各国でも親しまれていることで有名です。
上述にもあるように「スキミア」は「ミヤマシキミ」を品種改良した園芸品種であり、雄木と雌木が異なっているため品種改良にも適した植物といえます。代表的な品種として「ルベラ」は絶大な人気を誇ります。深い緑の葉茎と密集した真っ赤なツボミから可愛らしい小花がこれでもかといわんばかりに主張し、上品さの中にも一目見たら印象に残るような大きなインパクトがあります。
スキミアの特徴
生息地は日本をはじめとするアジア地域にまで広がり、成長すると樹高50cmから80㎝程度の低木となります。葉は長い楕円形で少し固めの質感です。開いたばかりの葉はつやつやとしており、ある程度成長してもその質感は大きく変わりません。表裏の濃淡の色合いがはっきりしていますが、全体的に深く落ち着いた緑色が特徴です。
歴史の中でも触れているように雌木、雄木は異株からなり10月頃になるとそれぞれ赤いツボミが目立つようになります。ツボミが付きはじめてから開花までは約3ヶ月から5ヶ月と長い期間を必要とし、早くて翌年の初春には開花姿を見ることが出来ます。ツボミの頃から開花時期までの長い期間を楽しめることも人気の一つです。
ツボミの状態ではマッチ棒が房状に生えているようにも見え、秋入りし涼しくなる頃には日本各地の花壇や民家で見ることができます。上述にもあるようにツボミの状態が長いためその姿ばかりが知られており、開花姿を目にしたことがないという人も少なくありません。大変鮮やかな赤色のツボミに対し、開花時には可愛らしい真っ白い小花を覗かせます。
満開の姿はツボミや花茎を覆い尽くすほどなので開花時は別の花と間違われてしまうこともあります。また、長い期間変化がない特徴を活かし切り花として出回ったりフラワーアレンジに用いられることも多々あります。とくに鮮やかな赤色を活かし、クリスマスには名脇役としてその名をとどろかせています。
-

-
ロシアンセージの育て方
ロシアンセージはハーブの一種です。名前からするとロシア原産のセージと勘違いされる人も多いですが、それは間違いです。原産地...
-

-
ビデンスの育て方
アメリカを主とし世界じゅうを生息地としていて、日本でもセンダングサなど6種類のビデンスが自生しています。世界中での種類は...
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...
-

-
デンドロビウム(キンギアナム系)の育て方
デンドロビウムは、ラン科セッコク属の学名カナ読みでセッコク属に分類される植物の総称のことを言います。デンドロビウムは、原...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
ガザニアの育て方
ガザニアはキク科ガザニア属で勲章菊という別名を持っています。ガザニアという名前はギリシャ人が語源とされており、ラテン語の...
-

-
センペルビウムの育て方
センペルビウムはヨーロッパの中部や南部、コーカサス、中央ロシアの山岳地帯に分布している植物で、ヨーロッパやアメリカでは栽...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
ムラサキツユクサの育て方
ムラサキツユクサは、TradescantiaOhiensisと呼ばれる花になります。アメリカの東部から中西部が原産地にな...
-

-
野菜の栽培野菜の育て方野菜の種まき様々な方法があります
野菜の栽培といえば、日本で一番多く栽培されているのは、主食のコメでしょうか。野菜の育て方で調べてみると、多くの情報には、...




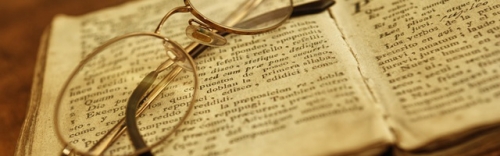





「スキミア」はミカン科ミヤマシキミ属、日本を原産とする常緑低木の一種です。学名は「シキミア・ジャポニカ」、英名を「スキミー」といいます。原産国が日本とのこともあり古くから日本人に愛され、一般的に出回る苗ものの中ではやや高価であることで知られています。