唐辛子の育て方

唐辛子の植え付けの準備
乾燥した環境を好みますので土は水はけのよいものを選ぶ必要があります。このために畑で栽培する場合は、水はけを良くする土壌を作ることから始めます。また植えつける畝は高くする必要があります。まず、水はけを良くするために、たい肥、炭、くん炭などの土壌化良材を用て改良を加えてゆきます。
これらの、土壌改良剤を鍬などで30㎝程掘り起こしたところに加えて混ぜ込んでゆきます。この時、土の状態を確認するために改良成った土の乾いた部分を、手に一握りつかんでみて手を開いた時に殆ど固まらずに崩れ落ちるくらいの状態がベストです。
プランターでの育て方は既製品の培養土を利用してもかまいませんが、この培養土に土壌改良剤である、くん炭を混ぜこんで使います。適量としては、培養土の種類にもよりますが一つのプランターに対して野球ボール2個程の、くん炭を使います。
後は、前述のように手で握ってみて状態を確認します。肥料は多くは必要ありませんが、元肥は、発酵油かすか鶏糞などを入れておいた方がよいでしょう。また、唐辛子は熟すると鮮やかな赤色になるものが多く秋の彩として鑑賞にも耐える品種です。その時の景観も考慮して植え付ける場所を選択するのも楽しいでしょう。
唐辛子の種付け育苗、植え付け
育て方には、畑に直に種を蒔く方法と苗を作って植え替えるという方法がありますが、慣れないうちは苗を作って植え替える育て方のほうが失敗が少なく無難です。
種付けは、育苗箱に4~5センチの間隔で溝を作り、すじまきといわれる種を一列に蒔く方法をとります。その上に1㎝程の厚さに土をかけておきます。
種付けの後、育苗箱の温度は可能であれば29~30度ぐらいに保温します。種付け後の苗の栽培には温度管理が重要で特に夜間は15度以下にならないように注意が必要です。
植え替えの時期は本葉が一枚になった頃に育苗箱から4号ポットに植え替えを行い、その後花が1個か2個くらいになるまで育てます。大苗になったら気温を見ながら畑に植え付けます。この時花は1,2個、本葉は、7~9枚ほどになっていますのでその状態を目安とします。
畑であれば株の間隔を45~50㎝にとって植え付けます。プランターや鉢の場合は、8号鉢に1株65㎝程度のプランターであれば2株ぐらいが目安となります。植え付けの後は十分な水やりをしてください。根が浅いので水切れは厳禁です。
唐辛子の根はあまり深く張らないため風などで倒れやすく、傷んでしまいますので植え付けと同時に添え木として草丈の60㎝以上必要ですから80㎝以上の支柱を立てておきましょう。
唐辛子の育て方と管理方法
ある程度成長したら下の部分から出ている側枝を摘み取ります。中心の枝とその両側の枝の2本で構成される状態で大きくなるよう栽培します。土の水はけがよいことと唐辛子の根が浅いこともあり、水切れしやすい状態になっていますので水やりには注意が必要です。特に夏場の水切れには注意してください。
土の水分が乾いてしまうと株がへこたれて元気がなくなり、そのまま経過すると枯れてしまい全滅となってしまいますので土の状態は常に監視して注意を怠らないようにしましょう。土の乾き具合の目安として、土に指を2㎝程差し込んでみて、乾燥していたら水を与えるという風にする方法があります。
夏場の成長時期の水やりは特に大事で育て方のポイントともいえます。特に夏場の水管理はその後の成長と実りに影響を与えます。これは、唐辛子だけではなく野菜の栽培には共通していえることです。
ただ、一つ注意が必要なのは水を与えればよいというのではなく与えすぎもよくありません。常にふんだんに水がある育て方ですと唐辛子は、あまり根を張ることもなく根腐れしたり、ひ弱な株に育ってしまいます。
ある程度乾いて完全に乾燥する直前に水を与えるというやり方で、株を鍛えることも必要ですので適当な時期に適当な量を与えることで丈夫で夏の暑さや乾燥に負けない唐辛子に育てることが出来ます。
唐辛子の収穫と利用法
花の後に約60日程度で、実が赤く色づきます。この時株ごとにぬいて収穫し、軒下等につるして乾燥させたり、赤く実った実だけを摘み取って収穫するという方法があります。
また、生のまま冷凍庫で冷凍保存しても問題ありません。生の唐辛子と同じような使い方で新鮮な味が楽しめます。?唐辛子の場合は、つくだ煮などにして楽しみます。
乾燥させる場合はなるべく風通しがよく湿気の少ない場所を選びます。場所によっては乾燥する前にカビなどが発生してせっかくの収穫が台無しになってしまいます。
十分に乾燥したものは長期保存が可能で、いわゆる鷹の爪として一年を通じて様々に利用することが出来ます。また、収穫の時期として青い状態で収穫することを推奨する品種がありますが、サイズをよく確認して収穫します。
この品種をあまりに早く収穫すると辛いものとあまり辛くないものなど実の状態にばらつきがあります。様々な品種がありますのでいろいろな品種を試して味の違いを試してみるのもよいでしょう
唐辛子の歴史
中南米が原産地の唐辛子ですが、メキシコでは数千年も前から食用として利用されており栽培も盛んに行われていました。原産地でもあるこの地域が唐辛子の発祥地域でもあり、生息地域でもあります。
この唐辛子が広く世界に知られるようになったのは、もっと後のことで15世紀のコロンブス新大陸を機に始まりました。香辛料に深くかかわるこの航海中に発見された唐辛子は、コロンブスによってコショウとして紹介されることになります。
赤いコショウということで英語ではレッドペッパーという呼び名でコショウと混同されることになってしまいます。また、この時代の船による航海は船員たちには過酷なもので、ビタミン不足による壊血病などに悩まされることが多くありました。
同時代の冒険家バスコ・ダ・ガマの行った航海ににおいても多くの船員たちがこの壊血病によって亡くなったという記録があります。この問題の解決にも唐辛子が一役買うことになります。
なぜなら、唐辛子にはビタミンCが豊富に含まれており乾燥させたものでも100g中100㎎という含有量で、サプリメントの無い当時にはよいビタミン剤となりえたわけです。
その後、世界中に広がることになるのですが、日本に入ってきた時期ははっきりとせず、諸説ある中では16世紀半ばにポルトガルから鉄砲とともに入ってきたとか17世紀初頭に豊臣秀吉が朝鮮出兵の時に持ち帰ったという説もあればその逆説もあり定かではありません。
唐辛子の特徴
茎は多くの枝分かれがあり、?は、互生します。柄が長く、草丈は約40~60㎝ほどに成長します。花は白い色のものが7~9月頃に咲きます。花の後に内部に空洞のある細長い実をつけ、熟すると赤くなります。
これは、品種によって色や形は様々で丸みを帯びたものや黄色や紫に色づく品種もあります。特徴である辛味はカプサイシンといわれるものの含有量によって違いがあり、その量によって辛さが変わってきます。
この辛味成分であるカプサイシンは、水よりも油に溶ける性質があり油を使った料理に使うとその辛味が強調されることから東南アジアや中華料理には油を使った料理に多く用いられています。また、実を細かくすることによっても辛味を際立たせることが出来るため刻み方によってその辛味を調整することもできます。
その、辛さの成分であるカプサイシンが多く含まれる部分は、実の中央部分にある種子を包んでいる綿状のものの中に多く含まれています。多くの方は皮や種に辛さがあると思っていますが、種には殆ど辛味はありません。
香辛料になる植物の育て方は下記も凄く参考になります♪
タイトル:サフランの育て方
タイトル:トウガラシの育て方
-

-
モナルダの育て方
この植物に関しては、被子植物に該当し、シソ目、シソ科、ヤグルマハッカ属になります。非常に見た目がきれいな花が咲くことから...
-

-
シマトネリコの育て方
シマトネリコは、近年シンボルツリーとして非常に人気を集めている樹木です。トネリコと混同している人も多いですが、日本が原産...
-

-
オーストラリアン・ブルーベルの育て方
豪州原産の”オーストラリアン・ブルーベル”。白やピンクや青の花を咲かせるきれいな植物です。名前にオーストラリアンと付いて...
-

-
ミント類の育て方
ミントは丈夫で育てやすいのが特徴です。家庭菜園でも人気があり、少しのスペースさえあれば栽培することが出来ます。ミントには...
-

-
木立ち性シネラリアの育て方
木立ち性シネラリア(木立ち性セネシオ)は、キク科のペリカリス属(セネシオ属)の一年草です。シネラリアという語呂がよくない...
-

-
ゆりの育て方
ゆりは日本国であれば古代の時期から存在していました。有名な古事記には神武天皇がゆりを摘んでいた娘に一目惚れして妻にしたと...
-

-
日本の未来と、植物、食物における無農薬栽培の育て方のあり方。
日本の自給自足率が一向に上がらない今日です。国は農協解体へとメスを入れ始めているようですが、既存の農家からの反対も強く、...
-

-
バラ(ブッシュ・ローズ)の育て方
ブッシュローズは低木として育つものを差します。ヨーロッパにももともとあったそうですが、現在園芸品種として出回っているもの...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...





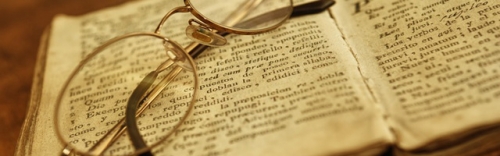





中南米が原産地の唐辛子ですが、メキシコでは数千年も前から食用として利用されており栽培も盛んに行われていました。原産地でもあるこの地域が唐辛子の発祥地域でもあり、生息地域でもあります。