チトニアの育て方

育てる環境について
チト二アの育て方ですが、日当たりのいい場所を選んであげましょう。夏に花を咲かせる植物ですので基本的には暑さには強い性質をもっています。炎天下でも元気に花を咲かせますのでその元気さに驚かされます。暑すぎるのではないか、などいろいろ心配してしまうかもしれませんがそういったことはありませんのでたくさん日光を浴びせてあげるといいでしょう。
ただ背丈が1メートルほどになりますと折れやすくなります。強い風があたるような場所だと折れてしまう可能性がありますので気をつけましょう。あまり直接的に風があたるような場所は避けてあげます。また秋頃になると枯れてしまいます。一年草ですので来年も楽しみたい場合は種を保管しておくといいでしょう。
日常の栽培については先程もいいましたが折れやすいですので支柱などが必要になってくるでしょう。花を少しでもたくさん咲かせたい場合は少し手入れをしてあげるといいでしょう。本葉が7、8枚になったころ芽の先をつんであげます。そうするとわきから3、4本芽がのびてきて、花もそれだけたくさん咲くでしょう。
もしも芽をつまなければそこに花が1つしか咲きませんので、少しでも花をたくさんつけたい場合はそうした作業をしてあげると効果的です。またそうする事で枝の数も増えますので株はりもよくなるでしょう。その他、草丈を少し抑えたい場合は、花が咲いた後に枝を短く切り戻しておくといいようです。それにより低い位置でわき芽がでてきます。
種付けや水やり、肥料について
基本的にチト二アは丈夫な植物ですのでそれほど神経質になる必要もないでしょう。ただそうはいっても水は必要ですのであげなければいけません。だいたい土の表面が乾いてきたらあげるようにします。たっぷりと水を与えるといいでしょう。夏場に花を咲かせますが、そうした時期は特に乾きやすいですので毎日水をあげてもいいでしょう。
鉢植えなどは水分調節がやや難しいのですが、蒸れない程度に水をあげます。また花壇などの場合も乾燥しすぎないようにします。花壇の場合は天候にも左右されますのでそういったことも気をつけるようにしましょう。夏場あまり雨が降らないようなら水を与えます。肥料についてですが、それほど必要ないでしょう。
植物によっては定期的にどうしても必要というものもありますが、これは丈夫ですのであまりいりません。気温が低い時期は成長がゆっくりですので心配になるかもしれませんが、温度が上がってくるとどんどん成長して延びていきます。生育が悪いようなら化成肥料や液体肥料を与えるといいでしょう。様子を見ながらで十分です。
チッソ肥料などはあげ過ぎると葉や枝などが成長し過ぎるようですので気をつけましょう。もともと折れやすく支柱が必要な植物なのですが、肥料により成長し過ぎるとさらにその可能性も高くなってしまいます。また肥料で大きくなりすぎた場合は花つきが悪くなることもあります。チト二アに肥料を与える場合は様子を見ながら少しくらいで大丈夫です。
増やし方や害虫について
チト二アは一年草ですので増やすなら種からとなるでしょう。移植を嫌がりますので栽培したい場所に直に蒔いてあげるのがいいでしょう。庭や花壇、鉢植えなら大きめのものを選びます。種をまくのに適した時期はだいたい4月から5月となりますが、夜の気温なども参考にしながらするといいでしょう。夜間の気温がだいたい10度以上になっていると種まきに適した時期となります。
日中は暖かくても夜に冷え込むようならまだ早いでしょう。気温が低いと芽がでてきてくれません。カレンダーだけを見るのでなく、温度なども気をつけながらタイミングを決めていきましょう。移植は苦手なのですが、その場所に他の植物が植わっている場合などはビニールポットなどに蒔くようにしましょう。
3粒ほどまいて最終的に1つになるように間引きします。葉が4、5枚になったらポットからそのままとりだしてそっと植えてあげます。花壇や庭にまく場合は土を厚めにかけてあげましょう。暑さにはとても強い植物ですが、発芽の際は土を乾かさないように気をつけます。また成長するととても大きくなりますのでそういったことも考え、
株の間は60センチくらいあけて栽培した方がいいでしょう。あまりにも密集し過ぎると窮屈になってしまいます。害虫についてはアブラムシなどがつくことがありますので注意しましょう。大きく成長しますし一度つくと駆除するのは大変です。必要に応じて薬をまいておくといいでしょう。
チトニアの歴史
チトニアはキク科の植物になります。鮮やかなオレンジや黄色などのビタミンカラーが印象的で、美しい花を咲かせるでしょう。キク科ですが、その花はまるで小さなヒマワリの様な形をしており、見ているだけでも元気をもらえるような花となっています。原産はメキシコや中央アフリカなどですが、ヒマワリの様な形をしていることから別名メキシコヒマワリとも呼ばれているそうです。
夏場に花を咲かせますし、見た目などからもそう呼ばれているのかもしれません。とても色がキレイなのでその辺に咲いていてもすぐに目につくのではないでしょうか。古代アステカ王国の国花だったとも言われていますが、そう考えるとかなり昔からある植物なのではないでしょうか。
最近できたような新しい植物ではなく、古代アステカ時代ですからかなり昔になるでしょう。国花になるという事はそれ以前からもたくさんの人から愛されていたのではないでしょうか。チトニアという植物はとても古くからあり、歴史としては長いものだと思われます。国花と言われるだけあり、小さいながらも色が鮮やかで堂々としている花でしょう。
花の種類としては10種類ほどあるようですが、一般によく栽培されているのはチトニア・ロツンディフォリアといわれるもので、園芸で使われる際はこれをチト二アとして扱っています。一年草ですが、8センチほどのヒマワリのような花を咲かせるでしょう。意外と大きくなりますので花壇などで育てた方がいいかもしれません。
チトニアの特徴
チト二アの特徴といえばやはりその色でしょう。生息地はメキシコなどですが、鮮やかなビタミンカラーが目をひきます。緑の中にあるとすぐにわかるのではないでしょうか。朱色や黄色といったどれも美しい色の花をつけますが、とても映える色をしています。また先程もいいましたが、その花の形もヒマワリのようで別名でも使われているほどです。
古代アステカの国花にもなっていましたが、夏らしくとても元気をもらえるのではないでしょうか。草丈は意外と大きく1メートルほどになりそうです。また横幅もあり50センチくらいにまで広がるでしょう。花自体は8センチほどで小さいのですが、草丈などよく成長しますのでそのつもりで育てた方がいいでしょう。葉っぱの部分がかなり多くなりそうです。
鉢植えだと少し窮屈になってくるかもしれませんので花壇に植えるなど状況によっては考えた方がいいでしょう。もしも鉢植えで育てるのなら10号以上の大きなものが必要です。成長後の事も考えそうした鉢を準備しておいた方がいいでしょう。一般的な花だとそれほど背丈は高くならないのですが、
チト二アの場合はとても高くなりますので注意も必要になってきます。1メートルほどにのびるとどうしても茎の部分が弱くなりますので気をつけましょう。できれば支柱などで支えながら栽培するといいでしょう。特に切り花として使用したい場合は支柱で支えてあげるようにします。やはり花首のあたりが折れやすいですし、折れてしまうと切り花としては使えなくなってしまいます。
-

-
育てやすい観葉植物について
観葉植物のある部屋に憧れを持っていたり、お店やオフィスに観葉植物を置きたいと考えている人は多いです。園芸店やホームセンタ...
-

-
観葉植物の上手な育て方
観葉植物の上手な育て方とは、まず定番で簡単なものからチャレンジしてみると栽培しやすいです。場所を選ぶのが大切なポイントで...
-

-
花の栽培を通して喜びを感じる
手作りの物を口にしたり、目の保養をする事ができたら、こんなに素晴らしい事はないと考えている人は多く、実際に実行に移す人の...
-

-
ペトレア・ボルビリスの育て方
ペトレア・ボルビリスは原産地がキューバ・ブラジルといった中南米の常緑蔓性高木です。和名では寡婦蔓(ヤモメカズラ)と呼ばれ...
-

-
チゴユリの育て方
チゴユリはチゴユリ属の多年草で生息地としては、東アジアの日本・中国・朝鮮などが挙げられます。チゴユリ属というのは、イヌサ...
-

-
ニチニチソウの育て方
ニチニチソウに日本に渡来したのは1780年頃のことだといわれています。渡来してからの歴史が浅いので日本の文献などに出てく...
-

-
ハヤトウリの育て方
原産地はメキシコ南部から熱帯アメリカ地域で、アステカ文明やマヤ文明のころから食べられてきたと記録されている野菜です。はじ...
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...
-

-
サトウキビの育て方
サトウキビはイネ科の多年草で、東南アジアや、インド、ニューギニア島などが原産と言います。また、インドの中でもガンジス川流...
-

-
スターチスの育て方
スターチスの花の原産地は、ヨーロッパであり、地中海沿岸地方を生息地としています。いかにも洋風な見た目の花は、日本へ伝わっ...




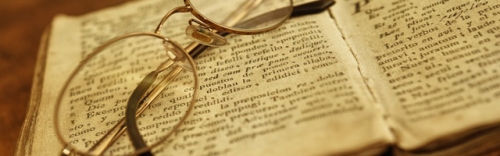





チトニアはキク科の植物になります。鮮やかなオレンジや黄色などのビタミンカラーが印象的で、美しい花を咲かせるでしょう。キク科ですが、その花はまるで小さなヒマワリの様な形をしており、見ているだけでも元気をもらえるような花となっています。