ベニジウムの育て方

育てる環境について
原産地が南アフリカの温暖な地域であることから、やはり環境もそれに近いものが良いことは確かです。しかし、半耐寒性を持っている頑強な性質であることから、日本のほぼ全域を生息地としています。半耐寒性というのは、基準は様々なのですが、園芸における区分においては、大体3度から5度くらいの低温に耐えることができるけれども、
0度を下回ってしまうような環境や、霜が降りてくるような状況においては、枯れてしまうというものと考えられています。ですので、日本全域で栽培が可能であるとは言え、気温が0度を下回ってしまうような場所や、霜が降りてくるような地方において栽培を行う場合には、それなりの寒さ対策を施してあげる必要があります。
防寒対策としては、霜を避けるためのマルチング等の方法が有効です。マルチングというのは、土の表面部分に霜が直接降りてこないようにするために、ワラや水コケ、あるいはバーク等を使って、土の表面を覆い隠すという方法です。これによって、地温が調整できるようになったり、あるいは雑草が生えにくくなるという付随効果を得ることもできるようになります。
鉢植えの場合であれば、地面からの冷たさが直接鉢に伝わってくることがないように、フラワースタンド等を使って、地面から生えれば場所に置くようにする方法もあります。この場合、ある程度の風通しも確保することができるので、病気や害虫を防ぐことができるという効果も得られます。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、種まきの場合、時期としては、大体8月下旬頃から9月上旬が適しています。非常に小さい種子なので、土は細かく砕いてならしておいて、十分に水を含ませてから、なるべく薄くなるように種を播いて行くようにします。この時、覆土する際は、土をかぶせ過ぎないように注意してください。うっすらと種が隠れる程度に土を掛けて行く感じで十分です。
さらにその上に、新聞紙を被せて、さらにその上から寒冷紗で多います。このようにしておくと、おおよそ2、3日で発芽するようになります。この時の注意としては、発芽後から寒冷紗や新聞紙を取り除く間での期間が相手しまうと、ベニジウムが徒長苗になってしまう場合がありますので注意してください。そこから大体1ヶ月程度で、苗が植え付け可能な状態にまで生長します。
植え付けに当たっては、鉢植えの場合には花用の栽培土で十分です。地植えの場合も同じですが、畑などに定植する場合には、有機質堆肥を利用すると良いでしょう。植え付け感覚は株間を25cm程度とるようにします。倒伏を防止するために、株元にある程度土寄せしておくと良いでしょう。
水は土が乾いたのを見届けてからたっぷり与えるようにしますが。花つきがあまりよくないような場合には、定植した後に、摘心をなるべく行って、沢山の側枝を出させるようにすると良いでしょう。基本的に肥料がなくても構いませんが、肥料を与える場合には、チッソ肥料をなるべく控え目にあげてください。
増やし方や害虫について
頑強な植物なので増やすのは簡単です。病気もあまり心配することはないのですが、立枯病が発生することがあります。この病気は連作等を行った場合によく発生する病気で、被害にあってしまうと株全体の生育状況が悪化し、日中であるにも関わらずしおれるようになってしまう病気です。病状が悪化すると、下の方の葉からだんだんと黄色くなってきて、やがて全株が枯れてしまいます。
病気を避けるためには、植え付け前に土壌消毒を行います。鉢植えの場合は、土自体を入れ替えてしまえば済むことなのですが、地植えの場合はなかなか難しい場合もあります。このような場合には、連作をさけて、一旦別の植物を栽培するようにすると良いでしょう。
病気が発生した場合、初期症状であれば薬剤による対処も可能ですが、基本的には葉株ごと抜き取って処分するようにします。害虫については、アブラムシやアオムシが、気温が暖かくなる頃に発生するようになります。特に、密植しているような場合、被害が拡大しやすくなると同時に、蒸れが起こることによって菌核病が出ることもありますので注意してください。
対策としては地植えの場合であれば、株間をしっかりとって風通しを良くすること、鉢植えの場合は、フラワースタンド等を使うことによって、風通しを確保することなどがあげられます。アブラムシや青虫は見つけ次第捕殺していきますが、発生前にあらかじめ予防のための薬剤を撒いておくと良いでしょう。
ベニジウムの歴史
ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英語ではCapedaisyやMonarchoftheveldtという名前で呼ばれています。南アフリカには同じ属の仲間が約20種も存在しています。日本においてはカンザキジャノメギク(寒咲蛇の目菊)と呼ばれることもあります。
南アフリカの気候は地域によって差があるので一概にはいえないのですが、総じて年間を通じて温暖です。基本的には乾燥台地であり、あまり降水量も多くはありません。年間における降水量も極めて少なく、平均で502mmという乾燥地帯でもあります。一部の高い山等における山頂には積雪が見られる場合もあります。
日本に入ってきたのはいつかはわかっていませんが、和名の寒咲蛇の目菊の由来が、寒さの残る季節に咲く花の花弁部分が、蛇目の黒い部分に似ているということから来ていることを考えると、少なくとも最近のことではなさそうです。もし最近だったとしたら、英語名そのままでケープデイジーとなるか、あるいはこれを和訳するような名前になっていたことでしょう。
しかし、蛇の眼というような恐ろしい印象を受けたのは日本人だけではなく英語名の「Monarchoftheveldt」は、「獣ヶ原の王」というような物騒な名前がついていることからも伺いしることができます。その性質の頑強さにおいては、まさにその名前にふさわしいと言えなくはないかもしれません。
ベニジウムの特徴
和名や英語名こそ恐ろしい名前の花ではありますが、見た目には可愛いくて美しい黄色い花でもです。黄色や黄橙色の花弁に黒い蛇の目をつけた花は、なるほど言われてみればなんとなくアフリカの大地に相応しい派手な色合いというように見えなくもありません。実はこの花は、天候の状況によって、多少の開閉運動を行っているそうです。
その明るく華やかな色合いと、特徴ある蛇の眼に見える漆黒色の帯斑のコントラストが色映えすることから、公園等の花壇に利用されることが多く、よくよく注意して見れば、きっと町のどこかで見つけることができるでしょう。頑強さがあるという点も、花壇等で採用されることが多くなるポイントでもあります。
花自体の高さは、30センチ程度から、大きなもので90センチと意外に高くその背丈を伸ばすことがあります。分枝力が強くて、どんどん枝分かれしていくという性質があることと、背丈が以外に高いことから、切り花において利用されることも多く、フラワーアレンジメントでもよく使われてることがあります。
和名と英語名では恐ろしげな名前を持ってはいるのですが、その花言葉は「新しい美、快活」というもので、この花言葉を知ってしまうと、単に明るい色の可愛らしい花にしか見えてこなくなってしまいます。開花する季節は、3月の始めから5月にかけての時期です。半耐寒性を備えているためなのか、早いところでは2月頃には既にさき始める地域もあるようです。
-

-
アリストロキアの育て方
アリストロキアの特徴と致しましては、花の独特な形状があります。数百種類にもなるそれぞれの形状は個々で異なりますが、そのど...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
アロカシアの育て方
アロカシアはサトイモ科に分類される品種であり、学名の「Alocasia」に属する植物の総称になります。原産は東南アジア、...
-

-
シモツケの育て方
シモツケ/学名:Spiraea japonica/和名:シモツケ、下野/バラ科・シモツケ属、シモツケ属は約70種が北半球...
-

-
カラタチの育て方
今から約1300年前に伝来していて、和名の由来はからたちばなという言葉が略されたとする説が実在しています。ただ、からたち...
-

-
コヨバ(エバーフレッシュ)の育て方
マメ科コヨバ属の植物である、コヨバ(エバーフレッシュ)は日本においては、原産地である南アメリカのボリビアから沖縄の生産者...
-

-
アドロミスクスの育て方
アドロミスクスの特徴といえばやはり豊富な形とフォルムでしょう。特に華やかな花が咲くわけではありませんが、肉厚の葉がとても...
-

-
ベンジャミン(Ficus benjamina)の育て方
ベンジャミンの原産地はインドや東南アジアです。クワ科イチジク属に分類されている常食高木で、観葉植物として人気があります。...
-

-
デンドロビウム(キンギアナム系)の育て方
デンドロビウムは、ラン科セッコク属の学名カナ読みでセッコク属に分類される植物の総称のことを言います。デンドロビウムは、原...
-

-
ゼフィランサスの育て方
ゼフィランサスについては、ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物のことをまとめてそう名づけられてい...




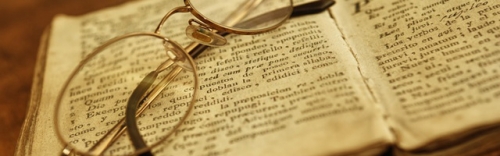





ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英語ではCapedaisyやMonarchoftheveldtという名前で呼ばれています。南アフリカには同じ属の仲間が約20種も存在しています。日本においてはカンザキジャノメギク(寒咲蛇の目菊)と呼ばれることもあります。