きつねのぼたんの育て方

育てる環境について
とにかく有毒なので育て方には充分に注意が必要です。食べると下痢や吐き気を催すことは前述したとおりですが、茎や葉の汁が皮膚につくだけでかぶれたり、炎症を起こすことがあります。誤って傷付けた時にうっかり素手で触らないよう、手袋などを装着することをお勧めします。
基本的に山野で咲いている花なので自生能力は極めて高く、栽培する際にも日当たりと風通しが良い場所にあてがっておけば、枯れる心配はまず、ありません。しかし、適度に多湿な状態を好むので水遣りは欠かさず行うことが必要です。そもそも天然のきつねのぼたんは湿地やあぜ道など水分の多い土地に生育します。
時には川などの浅瀬に生育する場合もあります。同じような場所に自生する草に春の七草で有名な「せり」があります。ちなみに野生のせりを採取する時によく間違われるのが「ドクゼリ」とこの「きつねのぼたん」です。見分け方としてはドクゼリの方は「せり」に比べて地下茎が太くてタケノコのような節があり、
せりの持つ独特の匂いも無いので、それらでもって判別します。同じような方法でキツネノボタンも判別できそうですが、何しろぱっと見はどちらも非常に良く似ているので、素人目には判断がつかないかもしれません。匂いにしても野外で正確に野草の匂いをかぎ取れるのか、そもそも「せり」の匂いはどんな匂いか、など初心者にはハードルが高いので、やはり、疑わしい野草は除外するのが無難でしょう。
種付けや水やり、肥料について
水やりに関しては、先ほども少し触れましたが、乾燥を嫌います。生息地が水辺であることからも明らかですが、頻繁に水やりは必要です。表面の土が乾き気味になっていると感じたらたっぷり水やりしてやると元気になります。その他に管理するポイントとして、植え替えを行う場合は極力、根を傷つけないようにポットから取り出して、大きめの鉢へ植え替えると良いです。
用土は特に指定は無いのですが、有機質の肥料を好むます。ですから土に腐葉土や堆肥などを混合すると、すくすく育ちます。ちなみに、きつねのぼたんに良く似た品種で「タガラシ」という植物があります。なんときつねのぼたんと同じくキンポウゲ科です。
名前の由来は諸説ありますが、あまりに貪欲に土の栄養を吸収するため、田んぼを枯らしてしまうという意味で「田枯らし」と呼ばれるようになったという説。もう一つは田んぼに生えていて、噛むとじんわりと辛みがある(そもそも有毒なのでナンセンスな由来であるが)ため、「田辛し」からきているのだとする説の二つが特に有名です。
ちなみにこの辛味というのは、化学的に根拠がありましてプロトアネモニンという有毒物質の仕業です。なお、キンポウゲ属の植物は全部この成分を含有しています。食べると体内を荒らすのはきつねのぼたんと同じです。
外見上の違いは実の形くらいで、それ以外はほとんど同じに見えます。強いて言えば花の大きさがタガラシのほうが若干小さいのですが、個体差もあるため、はっきりとした違いはありません。
増やし方や害虫について
害虫の代表的なものとして、キツネノボタンハモグリバエがいます。この虫は文字通りハエの一種で、キツネノボタンやタガラシなどの同属の野草に寄生します。きつねのぼたんの葉っぱを食べた幼虫はやがて蛹になって羽化し、そこを発生源として今度はラナンキュラスという同じキンポウゲ科の植物に飛来し、産卵するという生態を持っています。
このハモグリバエという虫は園芸界ではなかなかに悪名が高く、トマトやきゅうりなど家庭菜園でおなじみの野菜の葉にも寄生します。実を食べる種類の野菜ならまだしも、小松菜やチンゲン菜のような葉を食べる野菜に寄生されたら、これはちょっと困ります。しかし実際にそのような被害の報告事例はあります。
ハモグリバエは読んで字の如く、葉に潜るハエの意味で、別名をエカキムシといいます。その心は「絵かき虫」ということで、幼虫が葉の中を潜って食べていった後が白い筋となって残りますので、その様子を指して名づけられたそうです。一枚の葉に数匹なら無視できる範囲ですが、放置するといつの間にか増えていて、葉の裏にびっしりと卵がついていて、
葉が真っ白になったという笑えない話もあります。駆除するには地道に手でつぶすという方法は最も確実かつ低コストですみますがあまりにも数が多い場合は薬剤の使用がお勧めです。白い筋を見つけたら、その周辺に幼虫がいるので、散布してください。ホームセンター等で手に入る薬剤で充分に効き目があります。
きつねのぼたんの歴史
きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は日本と思われますが、はっきりしません。花をつける時期は3月から7月頃にかけてです。可愛い名前とは裏腹に、草全体に毒を持っています。田舎では田んぼの畦など割合に身近な場所の湿ったところに生えます。
名前の由来に関しては諸説あります。毒を持ち、それでいて深い切れ込みのある葉が牡丹によく似ていたため、「狐の牡丹」という名前が付けられたという説が最も有力です。古来より狐は人を化かす存在として恐れられ、狡猾な生き物として周知されてきました。女性には少し心外な言葉かもしれませんが、芝居上手な女性、
人をたぶらかす女性に対して女狐(めぎつね)と呼ぶところからも狐にはどこか怪しい印象を人に与えるようです。手を汚さず、労せずとも人を死に至らしめる毒は狡猾と解釈されたのか、きつねの名を冠する毒草が意外に多いことはあまり知られていないことかもしれません。
きつねのぼたんは正にその典型で黄色いこじんまりした花をつけたその様は一見、見た目にも艶やかで、調理すればさぞかし芳醇な味を届けてくれるようななりをしていますが、実際は煮ても焼いても食えない代物です。ちなみに葉や茎はほとんど無毛ですが、
外見がとてもよく似ていて葉や茎に毛を生やした植物があります。その名もケキツネノボタン(毛狐の牡丹)です。非常に安易ですがわかりやすい名前です。どちらも猛毒ではありませんが口にすれば腹痛、吐き気、下痢、けいれんなどの症状に見舞われます。
きつねのぼたんの特徴
花の色は黄色で茎先の周辺に出た柄に花をつけます。花径はだいたい1センチから2センチくらいが一般的です。花弁の数は5枚で、後ろに萼があるのが特徴です。次に葉の特徴ですが、葉はいわゆる三出複葉という形です。三出複葉というのは1枚の葉が3つの小さな葉に分かれた形という意味でとても特徴的です。
また、根の際から生えている葉には長い柄があります。小葉は2つあるいは3つに裂けており、不規則な鋸歯があります。このぎざぎざした形がいかにも野草という荒々しい感じを印象付けています。茎についている葉は互い違いに生えます。このことを専門用語で互生と言います。続いて実の特徴です。
実は花が咲いた後に、淡緑色の金平糖のような形をした実をつけます。花、葉、実のどれをとっても可愛らしい要素に満ち溢れており、そのまま押し花にでもしたいくらいに可憐に咲き誇ります。やはり、毒を持つ内実と外見があまりに似つかわしくないところから、この和名がつけられたのかもしれません。しかしながら、海外では少し事情が違います。
この花の属名はRanunculusと言ってラテン語のカエル(rana)に由来しています。なぜカエルなのかと言いますと、この属の水生の種が、まるでカエルの生息地のような所に生えていることからその名がつけられたということです。毒の有無など一切、関係が無いところを思うに、名付けというのは本当に植物学者の第一印象で九割以上は決まってしまうと言っても過言ではないでしょう。
-

-
家庭菜園を行う場合の育て方のコツについて
自宅で植物を栽培する場合、その育て方にはいくつかのコツがあります。自宅で植物を栽培する場合、鑑賞用として育てる場合と、食...
-

-
レモンマートルの育て方
レモンマートルはオーストラリア原産のハーブの一種です。ハーブといっても高さ20mと大きく育つため、低木や草花といった一般...
-

-
フリージアの育て方
フリージアは南アフリカ原産のアヤメ科の植物です。ケープ地方に10種類あまりが分布していますが、現在よく栽培されているもの...
-

-
クンシランの育て方
クンシランはヒガンバナ科クンシラン属で、属名はAmaryllidaceae Clivia miniata Regelとい...
-

-
ナイトフロックスの育て方
ナイトフロックス(nightphlox)とは属名に「ザルジアンスキア」という名前を持ったゴマノハグサ科の植物です。原産国...
-

-
アークトチスの育て方
アークトチスはキク科の可愛らしい植物です。とてもかわいらしく可憐な雰囲気のある花ですが、キク科という事もありとても身近に...
-

-
カンヒザクラの育て方
通常の花といいますと太陽の方に向いて咲く、つまりは上向きに咲くことが多いように感じられます。スズランなど例外的な花もあり...
-

-
ディクソニア(Dicksonia antarctica)の育...
ディクソニアは南半球のオーストラリア東部南部、そしてニュージーランドが原産の温帯を中心に生息している木性シダ植物です。こ...
-

-
セアノサスの育て方
セアノサスはカナダ南部や北アメリカにあるメキシコ北部が原産となっています。花の付き方が似ているという理由から、別名をカリ...
-

-
カンパニュラの仲間の育て方
カンパニュラはラテン語で「釣鐘」を意味しています。和名もツリガネソウだったり、英名がベルフラワーだったりすることから、ど...




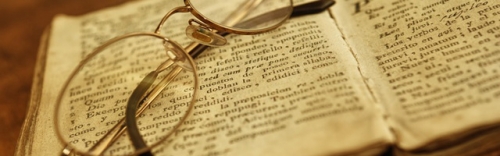





きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は日本と思われますが、はっきりしません。花をつける時期は3月から7月頃にかけてです。可愛い名前とは裏腹に、草全体に毒を持っています。田舎では田んぼの畦など割合に身近な場所の湿ったところに生えます。