オニバスの育て方

育てる環境について
アジア原産で現在では朝鮮半島、中国、インドに分布しており、日本国内においては、本州、四国、九州のやや富栄養化した湖沼、ため池、河川などを生息地としています。昔は普通に見られた植物でしたが、今では全国的にも珍しい植物になってしまいました。かつては宮城県が日本での北限となっていましたが、これは絶滅してしまい、
現在では新潟県新潟市が北限となっています。環境改変にともなう減少が著しい植物です。また1972年以前には霞ヶ浦高浜入に大きな群落がありましたが、これも現在ではまったく見られなくなってしまっています。岡山県の百間川のオニバス群落は、日本でも最大級のものでしたが、現在ではこの場所でも生育が見られなくなってしまっています。
原因は水質が悪化し、トチカガミなどの水草が水面を覆ってしまい、透明度も下がったことから生育が困難になったものと思われます。しかし種子は頑健で長命であることから、種子は生存を期待して水質が改善の取り組みが行われており、再び大群落の復活の可能性に期待が寄せられています。
同じ岡山県赤磐郡山陽町の民潤池では、池に改修工事が行われた際、これらの工事に先立って生物調査が実施されましたが、次の年になってオニバスが大発生したことがありました。これは底ざらえされた土の中にも多数の種子があり、ほとんどは殻だけであり中身がなかったのですが、
中には生きているものもあったようです。記録を調べると50年以上の間隔を置いた大繁茂であったことがわかりました。こうしたことからも種子の生命力の強さを伺うことができます。種子の寿命は最長60年とも言われています。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては種から栽培する方法が一般的です。まず種子を確保する必要があります。毎年春に種子から発芽して大きくなり、秋には開花結実して枯死する1年生植物です。8月から9月頃にとても美しくて小さな花を咲かせますが、大部分は花を開かないで種を作り、水面に多数の種をばらまきます。種はひとつの花の中に沢山できます。
水にプカプカと浮くようにまわりに仮種皮をつけています。これによって気ままに水の上を漂い流れていきます。この仮種皮の中は黒い色の種があります。発芽率が非常に悪く、気長に見守ることが必要です。翌年に芽がでるのは10%ほどと言われています。そのため栽培・増殖のためにはかなり多量の種子を確保する必要があります。
種は50年くらいは泥の中で生きているといわれていますが、まだまだ謎が多いです。大きく成長するためには富栄養な水質が必要です。富栄養な水は透明度が低く、そのため深い場所までは日光が達しないので、浅い場所でなければ初期成長が出来ないということになります。そのために水位変動が問題となってきます。
水位が一定であれば、浅い場所での発芽・成長が可能ですが、ため池においては1メートルを超える水位変動があるのが普通であり、そのためオニバスの生育は難しいものとなっています。基本的には、水質が富栄養であり、年間を通してほとんど水位変動がない池沼が栽培適地であることになります。元来の生育地は、自由に流れを変更する河川の三日月湖ではなかったかと考えています。
増やし方や害虫について
苗でも増やすこともできます。基本的に環境変化に弱いため、種子からの栽培を行うのが最も適しています。花は水中において閉鎖花であることが多く、自家受粉で100個程度の種子を作ります。1つの株から500個以上の種がバラ撒かれるような場合もあります。発芽率は極めて良くないことから、増やすためには根気よく取り組んでいくことが大切です。
種は翌春に全量芽が出るわけではないので注意してください。いつ発芽するか分からないということでもありますので、芽が出ないからとすぐに捨てたりせずに気長に待つようにしましょう。種子は水底に沈めますが、全てが翌年に発芽するとは限らず、数年から数十年休眠してから発芽することが知られています。
また冬場に水が干上がって種子が直接空気にふれる等の刺激が加わることで、発芽が促されることも知られています。そうした事情から自生地の状態によってはオニバスが多数見られる年と見られない年ができることがあります。病害虫については基本的には心配する必要はないでしょう。
あえて言えばネクイハムシの食草であるため、ガガブタネクイハムシに注意する必要があります。オニバスの種子は非常に生命力が強いことから、この種子を食用としている地域もあります。種子を集めて天日で乾燥したものを、生薬名で?実と呼んでおり、インドではMakanaとも呼ばれます。また中国では種子が食材や漢方薬として用いられています。果実を強壮葉とし、葉柄も食用にすることがあります。
オニバスの歴史
本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言います。別名として、ミズブキ、イバラバス、イバラブキ、バリバス、ゲトウ、ジゴクノカナノフタ、英名ではゴルゴンプラントと呼ばれています。類似種に南米原産の「オオオニバス」と「パラグアイオニバス」があります。
植物園などにみるオオオニバス属はオニバス属に似ていますが浮葉の緑が反って「たらい」状になります。日本では天然記念物として保護されていて採取することはできなくなっています。浮水性の水草でもあり、夏になると巨大な葉を水面に広げます。本種のみで属を構成しています。
葉も花も棘だらけのため、見た目が恐ろしく見えることもあり、清少納言は枕草子の一四七段の中で、「おそろしげなるものつるばみのかさ。焼けたるところ。水ふぶき。菱。髪おほかる男の洗ひてほすほど。」と記しています。これは栗のイガイガや火事場の後と同じように、オニバスも恐ろしいという意味です。
中国では種子が食材として使われたり、漢方薬として用いられているようです。日本では、都市開発や公害等による環境の悪化や埋め立てなどによって、全国的に自生地の消滅が相次ぎ絶滅が危惧されています。そのため全国各地で、オニバスを含めた環境保全運動が行われています。
また生育環境となるため池自体が、減反や水事情の改善によって、以前よりも必要性が薄れてきているため、ため池を管理している水利組合等との話し合いによって保全活動が行われています。
オニバスの特徴
特徴的なのは、植物全体に大きなトゲが生えていることでしょう。そのため「鬼」の名が付けられています。特に葉の表裏に生えるトゲは硬く鋭くなっています。ハスと異なり葉が水面から植えに上がることがなく、レンコンもありません。葉の表面には不規則なシワが入っており、ハスやスイレン等と見分けることができます。
春に水底の種が発芽します。その後、矢じり型の葉が水中に現れるてきます。茎部分は塊状で短く、葉は水底の水面へと次々と伸びていくようになります。成長するにつれて葉の形が細長いハート型から円形へ変わっていきます。円形になった葉は、丸くシワだらけの折り畳まれた姿で水面に顔を出して広がっていきます。
円形葉の大きさは直径30センチから2メートル程度の巨大なものになる場合があります。記録によると1911年に、富山県氷見市で直径267センチの葉が見つかっています。しばしば、農家にとってオニバスは排除の対象になることがあります。ジュンサイのような水草を採取したりする場合のように、池で農作業を行うときには、
巨大な葉を持つオニバスは邪魔でしかく、また鋭いトゲが全体に生えているために嫌われています。さらに葉が水面を覆うことによって、水中が酸欠状態になり、魚が死んで異臭を放つようになる場合もあります。また水が少ない地域に作られるため池においては、
では水位の低下は死活問題に直結しますが、巨大な葉が水を蒸散させてしまうとされて歓迎されないこともあります。富山県ではレッドデータブックに記載されていまが、他にも各地の自治体によって天然記念物指定を受ける自生地も多くなっています。環境省レッドリストでは絶滅危惧II類に指定されています。
-

-
アザミの仲間の育て方
アザミの仲間の種類は多く、科属はキク科アザミ属です。生息地で言うと、日本に多く見られるのは、日本が原産国であるためです。...
-

-
サンセベリア(Sansevieria)の育て方
サンセベリアの原産地は、アフリカ、南アジア、マダガスカルなどです。熱帯の乾燥した地域を好んで生息地としており、約60種類...
-

-
サンギナリア・カナデンシスの育て方
サンギナリア・カナデンシスとはケシ科サンギナリア属の多年草の植物です。カナデンシスという名の由来はカナダで発見されたこと...
-

-
ヒペリカムの育て方
ヒペリカムの原産地は中国で、中央アジアや地中海沿岸を主な生息地としています。もともとは中国大陸の草地や山の中に自生してい...
-

-
シュンランの育て方
シュンランはラン科シュンラン属の植物で、洋ランとして馴染みの深いシンビジウムの一種です。原産は東アジアで、日本の森林にも...
-

-
レモンバーベナの育て方
レモンバーベナは、クマツヅラ科イワダレソウ属の落葉低木です。軽く触れるだけでもかぐわしいレモンの香りがします。この香り代...
-

-
ラミウムの育て方
ラミウムは、シソ科、オドリコソウ属(ラミウム属)になります。和名は、オドリコソウ(踊子草) と呼ばれています。ラミウムは...
-

-
タカネビランジの育て方
タカネビランジはナデシコ科マンテマ属に分類される高山植物で、花崗岩帯などが主な生息地と言われています。日本が原産の植物で...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
セージの育て方
セージの基本種、「コモンセージ」は、薬用サルビアの別名通り、古くから薬用に利用されてきました。サルビアは、学名では「Sa...




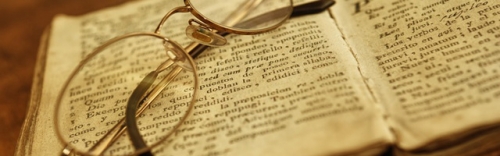





本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言います。別名として、ミズブキ、イバラバス、イバラブキ、バリバス、ゲトウ、ジゴクノカナノフタ、英名ではゴルゴンプラントと呼ばれています。類似種に南米原産の「オオオニバス」と「パラグアイオニバス」があります。