シャクナゲの育て方

シャクナゲの育て方
シャクナゲの植え付けは、3月から4月、10月から11月が植え付けの適期とされています。植え付けや植替えは遅くとも5月中に済ませます。6月に入るとシャクナゲは生育期に入り、この時期にやってしまうと翌年の開花が望めなくなるので注意です。
植え付け方は、まず根鉢を3分の1ほど崩して少し土をはらいます。苗木についている土は、水はけが良すぎるものを使用している場合があるので、土を家庭用の適したものに変えてあげてください。
用土の割合は、玉土小粒4、鹿沼土2、ピートモス3、バーミキュライト1の割合で混合したものがおすすめです。面倒であれば、山野草用土と赤玉土を等量で混合したものを使ってみてください。鹿沼土と腐葉土でもよいですが、ピートモスを使うのには弱酸性が良いといった理由があり、ピートモスが酸性だからです。
庭への植えつけは、水はけがよく、腐植質に富んだ場所を選び、ツツジやシャクナゲといった同じ属科のものを植えてあった場所には植えないようにします。なぜなら、連作障害が起きてしまいうまく育たないからです。
シャクナゲは、根が浅いため、高植えにして植えるようにするのがポイントです。根と土をよくなじませたら、乾燥しないように株元を敷きわらや腐葉土で覆ってください。また庭植え以外にも鉢植えでも育てることもできます。
その場合も用土は一緒でどちらも植え替えたら、水をたっぷりとあげます。肥料は、植え付けの一年目は与えず、花が咲くまえの肥料は入りません。花が咲きはじめたら粒状肥料を与えてください。
剪定は、枝数が少なく、古い枝からは芽が出にくいため必要としません。たくさん枝を出させて、こんもりとした樹形を作るためには芽かきをしてください。芽かきをすることで脇芽がでやすくなり、樹形もこんもりとした形になります。
シャクナゲの置き場所や管理
シャクナゲは日当たりを好むますが、根元に直射日光が当たると、とつぜん生育障害を起こしてしおれてしまうことがあります。そのため、午前中十分に日が当たる場所か、直射日光の当たらない場所を選んで植えるようにしてください。
明るい半日陰といった場所というのが適しています。また、シャクナゲは水をやりすぎると弱るなど多湿にも弱い性質を持ちます。ですが、夏の日照りといった水切れにもダメージを受けやすく枯らすこともあります。
それなので、水は土の表面が乾いたらしっかりとあげるようにしてください。基本的に庭植えの場合は雨水だけでよいとされ、夏場の日照りには少し注意が必要です。とくに、鉢植えは乾きやすいので夏場は注意して管理してください。冬は、寒風が吹きつけない暖かな場所が適しています。鉢なら日当りのよい室内に入れて管理するのがおすすめです。
シャクナゲの増やし方と病害虫
シャクナゲの増やし方は、一般的にさし木と種です。たくさん種付けをすることで増やすことができるのでおすすめです。接ぎ木などもでき、これにはテクニックが必要となるので根が付きやすいさし木がよいです。また、接ぎ木にはシャクナゲの台木というのが必要になりますが、成長が格段に良いというのが利点です。
販売されているシャクナゲには接ぎ木されたものがあり、枝の部分に透明のテープが貼ってあればそれは接ぎ木です。さし木は、新梢が固まり始めた空中湿度が高い6月、または完全に堅くなった9月が適期となっており、もともと根がでにくい性質のため、こういった時期を狙ってやることが成功率を高めるコツでもあります。
まずは、その年に伸びた充実した枝を、長さ7cmから8cmで切ります。枝先の葉を3枚から4枚残して下葉はすべて摘み取り、残した葉も半分くらいにカットしておきます。そして、水揚げを1時間したあとに鹿沼土や赤玉土の細粒の用土に斜めにさします。面倒であれば、さし木用土というのも園芸店などに販売されているのでそれを利用してもかまいません。
成功率を高めるといえば、植物成長調整剤「ルートン」を使うといった工夫も大事です。やり方は、切り口に薄くまぶしてから土にさします。土にさした後は、水をたっぷりとあげて日陰などで管理します。ここでポイントなのが鉢をビニール袋などで覆って乾燥を防ぐようにすることです。
なかなか根がでにくいですが、秋頃には発根するようです。また、種でも栽培することができます。タネの場合は、花が咲くまでにとても時間が掛かってしまうので根気が必要です。うまくいくと4年から5年で花を付けることができるので、成長する様子がみたいというひとは挑戦してみるのもいいです。
シャクナゲには、ハダニという害虫がつきやすいです。葉の裏にある小さく点々とした茶色になっているのが、ハダニの被害です。ハダニが葉の養分を吸った後にできるもので、見た目の悪さだけでなく全体が弱っていくので注意です。一番大きな被害となるのが、「ベニモンアオリンガ」の幼虫による蕾や新芽の食害です。被害が大きいのであれば、殺虫剤を使うなどして対策をするようにしてください。
シャクナゲの歴史
シャクナゲは、ネパール、ブータンを中心にアジア、ヨーロッパ、北米に約300種が分布します。主に、日本や中国が原産となっており、生息地は北半球の亜寒帯から熱帯山地までのきわめて広い範囲とされています。
シャクナゲはツツジ科ツツジ属ですが、自生している日本シャクナゲとヨーロッパで改良された西洋シャクナゲに分けられます。シャクナゲの名前の由来は、「石南花」と書いたものを 「しゃくなんげ」と呼んだのが少しずつ変化して「しゃくなげ」という名前になったとされています。
19世紀にプラントハンターによって、主に中国原産のシャクナゲが、ヨーロッパに導入されて数多くの交配が行なわれました。それらはセイヨウシャクナゲと呼ばれ、明治期に日本に輸入されましたが、日本の暑い気候に合わず普及しなかったといわれています。
その理由としては、夏が涼しいという気候であるイギリスで品種改良が行われたため、日本の暑さに弱いものだったことがわかります。現在では、販売されているシャクナゲのほとんどが、日本の暑い夏に強いことが実証された品種や日本で改良したものなどです。そのため、園芸店で売られているものは栽培が容易でよく育ってくれるものばかりといえます。
シャクナゲの特徴
シャクナゲは、派手で大きな花が咲く常緑広葉樹とされています。ツツジの花を寄せ集めたようなボリュームを持っており、派手なだけでなく気品も兼ね備えた花といえます。また「高嶺の花」という言葉の由来にもなったとされるなど、近寄りがたいほどの美しさに満ちています。またこの高嶺には、ヒマラヤなどの高山にしか咲かない花としての意味もあります。
色は、赤、白、黄、ピンクなどが存在しており、樹高や樹形なども様々なものがあり、いろんなところで植林されているのを見かけます。咲き誇る大輪のシャクナゲを見ると圧倒されるひとも多く、華やかさに魅力を感じるひともいます。色の違ったものでは雰囲気といったものも違ってみえ、そこも魅力の一つだといえます。
多くの品種が存在するなか、日本に自生したものと交配させた「吉野」や「春一番」という品種はとても丈夫といわれています。ほかにも、花びらのフリルがとてもきれいな品種や2色使いのカラフルなものなど多様にあるので選ぶ楽しみもあります。あと、葉にはグラヤノトキシンと呼ばれるけいれん毒が含まれており、漢方薬の「石南」と間違えて摂取するひともいるので注意してください。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セイヨウイワナンテンの育て方
タイトル:サツキの育て方
タイトル:アジサイの育て方
タイトル:クチナシの育て方
タイトル:アザレアの育て方
タイトル:ハギの育て方
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...
-

-
メカルドニアの育て方
メカルドニアはオオバコ科の植物で原産地は北アメリカや南アメリカですので、比較的暖かいところで栽培されていた植物です。だか...
-

-
イチリンソウの育て方
イチリンソウは日本の山などに自生している多年生の野草でキンポウゲ科イチリンソウ属の植物です。元々日本でも自生している植物...
-

-
人参の育て方
原産地はアフガニスタンで、ヒンズークシーという山のふもとで栽培されたのが始まりだといわれています。古代ギリシャでは薬用と...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
ムラサキシキブの育て方
この植物の特徴では、シソ目、シソ科、ムラサキシキブ属となっています。英語の名前はジャパニーズビューティーベリーです。日本...
-

-
ネリネの育て方
ネリネという名前の由来はギリシア神話の海の女神であるネレイデスにちなんだものです。花びらに金粉やラメをちりばめたようなき...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
パンクラチウムの育て方
パンクラチウムはヒガンバナ科パンクラチウム属の植物です。原産はスリランカで、地中海沿岸に生息地が分布しています。17世紀...
-

-
スカビオサの育て方
スカビオサは別名西洋マツムシソウとも呼ばれるもので、同じ系統のマツムシソウは日本を生息地としていて古くから日本人に親しま...




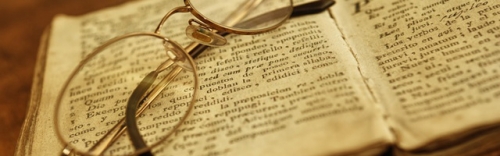




シャクナゲは、ネパール、ブータンを中心にアジア、ヨーロッパ、北米に約300種が分布します。主に、日本や中国が原産となっており、生息地は北半球の亜寒帯から熱帯山地までのきわめて広い範囲とされています。